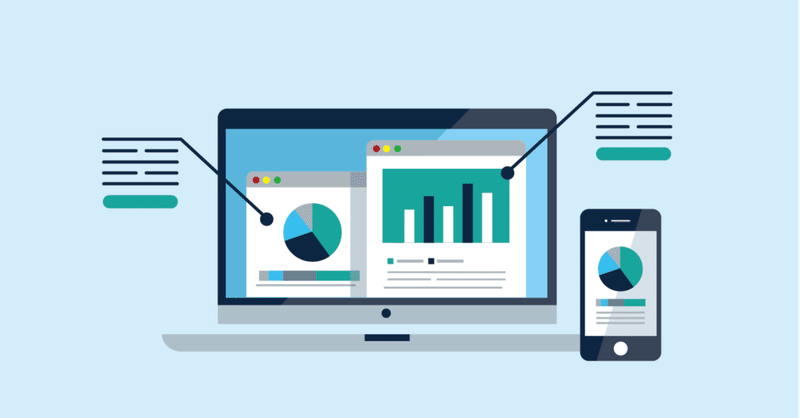
論理的文章と創造的文章:実習レポートの評価の上げ方
文章には大きく分けて3つある。論理的文章、創造的文章、そして日記的文章である。前者2つは他者に読ませるものであって、文章力が問われる。本学の実習レポートで「どう書いていいかわからない」学生さんのために、文章技術について解説する。(小野堅太郎)
![]()
高校の国語では「論説文」と「現代文」という2つのリテラシー課題に分けられていたように、論理的文章と創造的文章には違いがあります。論理的文章では、感情を排した客観的事項を段階的に積み上げる必要があります。一方、創造的文章では、感情を大いに取り込んで他者の心を揺るがす必要があります。科学論文や新聞記事では、論理的文章をベースにスパイスとして創造的文章を織り込みます。優秀な実習レポートとは、このような塩梅になっているものを言います。小説や詩、和歌、歌詞などは、ほぼ創造的文章で形成されます。詩などは韻を踏むことが多いですが、レポートで韻を踏む必要はありません。SF小説は、論理的文章が結構な割合で作家の個性として入ってきます(谷川俊太郎の詩は論理的なところがありますが、今回の話から逸れますので割愛します)。
先に、レポートでの創造的文章について説明します。全体での割合は少ないもののレポート評価を上げる魅惑的スパイスですので、可能な限りレポートに少し入れた方がいいです。ただし、創造的になるためには「教養」というような幅広い知識が必要です。付け焼刃の教養を盛り込んでしまうとちぐはぐな内容になってしまいます。例としては、「本実習では、19世紀ドイツのウェーバーから始まる感覚の定量化を実際体験したことになる。これにより味覚検査法など臨床診断が科学的知見の積み重ねによって成り立っていることを実感できた。」というような内容です。これは、「実験したという事実とその感想」だけです。内容に深く切り込んでいませんが、決して悪い内容ではありません。あくまでもレポートのスパイスです。ここで紹介していますので、九歯大の学生さんは味覚実習のレポートにこの文章を書き込んだらダメですよ。
では、本題のレポートに必要な論理的文章について説明します。論理的というのは、根拠を示して主張することです。「AだからBである」というのは演繹といって「AならBになる」という周知のルールを利用して語られるものです。この周知のルールとは授業で習った内容ということになります。授業や実習を理解していれば、この周知のルールを利用して論理的文章を構築します。もう一つは帰納です。これは周知のルールなしに複数の根拠を示して1つのことを主張するものです。演繹と帰納については、下の過去記事にまとめています。
最も簡単な内容は「自分の経験と実習結果の関連を挙げる」というものです。例えば、「私は子供の頃から煎餅のような固いものを好んで食べていたので耳下腺が発達し、咀嚼刺激唾液が他の被験者よりも多かったのかもしれない。」といった内容です(自分の経験→実習結果)。関連性を示すために演繹法による論理性を含んでいます。周知のルールは「耳下腺が咀嚼刺激唾液の多くを占める」ですね、授業でやっています。「味覚実験での個々の値のバラツキの大きさから、友人たちとの食事のおいしさ評価が合わないことが説明できると感じた。」なんてのもありかと思います(実習結果→自分の経験)。この場合の周知のルールは授業というより常識です。「味の感じ方が人によって大きく異なるなら、食事のおいしさも変わってくるだろう」というものです。授業内容を周知のルールとして持ってくる方が、教員としては嬉しいです。何度も言いますが、九歯大の学生さんは、この記事に例文として紹介した文章をレポートに書き込んだらダメですよ。
演繹と比べて、周知のルール(授業内容や常識)がない帰納法は難しいです。しかし、是非チャレンジしてみてください。帰納法は周知のルールを利用するのではなく、作る方法になります。10年ほど生理学実習の味覚レポート評価に携わりましたが、過去に数人います。文句なしの満点をつけています。もちろん、実習で行っているレベルなので、完璧な証明に至るほどの帰納法的主張にまでは至っていませんが、その科学的精神に感動しました。生理学実習では測定項目の多い「味覚」と「咀嚼」では、帰納法を使った考察が可能かと思います。他の「心電図」「血圧」「唾液」では、実験結果に周知のルールを追加して1つの主張にもっていく展開が考えられます。これについては例文を示しませんので、九歯大の学生さんのチャレンジを心待ちにしています。
下に、九歯大生理学実習に関しての小野のnote記事を挙げておきますので、レポート作成の参考にしてください。コピペしたら剽窃ですのでダメですよ。
全記事を無料で公開しています。面白いと思っていただけた方は、サポートしていただけると嬉しいです。マナビ研究室の活動に使用させていただきます。
