
フィールドワーカーはどんな風に問いを生み出すのか――松村圭一郎『うしろめたさの人類学』レビュー②
(※この記事は2020/02/08に公開されたものを再編集しています。)
今回書評で取り上げるのは、松村圭一郎『うしろめたさの人類学』である。エチオピアでのフィールドワークで収集した観察を手がかりに、日本社会が囚われ、そこから動けないと思い込んでいる様々なルールが、変わりうるものであることを平易な言葉で説く内容だ。
構築人類学はなにを構築するのか
本書を貫くモチーフの一つは、「贈与の関係」と「交換(売買)の関係」である。交換不可能な人間同士のつながりが基礎にある関係のモードと、商品交換のような経済的で代替化可能な関係のモードだと言い換えてもよい。
松村は、その対比を十分吟味した後、こう指摘する。
……モノは「いつでも交換できる商品」と「交換不可能なかけがえのないもの」という、ふたつの両極のあいだを揺れ動いている……。たとえありふれた商品でも、亡くなった家族が愛用していたら、値段をつけられない貴重な形見となる。ぼくらは、こうしたモノの連続的な動きの中に仮の区切りを入れる。これは売られている商品、こっちは大切な贈り物といった感じて。(中略)この仮の輪郭が「世界」をつくりだす。(p.148)
モノに加えられた便宜的な区切りが集積していくことで、「市場」の輪郭ができあがるように、私たちの相互作用が寄り集まることで社会は出来上がっている、というわけだ。
松村は、「構築人類学」を謳っている。ここには、私たちが作り出した、かりそめのルールなのだから、よりよい方へと規則を作り直せばよいという含みがある(こうした立場は、社会構築主義などと呼ばれることがある)。
社会と「慣習の束」
興味深いことに、以前書評した小熊英二の『日本社会のしくみ:雇用・教育・福祉の歴史社会学』も似た見解を述べている(*)。小熊は、社会のあり方を規定する慣習の束を「しくみ」と呼んだ。
慣習とは、人間の行動を規定すると同時に、行動によって形成されるものである。たとえていえば、筆跡や歩き方、ペンの持ち方のようなものだ。これらは、生まれた時から遺伝子で決まっているのではなく、日々の行動の蓄積で定着する。だがいったん定着してしまうと、日々の行動を規定するようになり、変えるのはむずかしい。 人間の社会は、その社会の構成員に共有された慣習の束で規定されている。遺伝子で決まっているわけでなく、古代から存在するものでもないが、人々の日々の行動が蓄積され、暗黙のルールを形成する。それは必ずしも法律などに明文化されていないが、しばしば明文化された規定よりも影響力が大きい。ただしそれは永遠不変ではなく、人々の行動の積み重ねによって変化もする。
私たちが作り、私たちが縛る「慣習の束」は、時に「社会構造」と呼ばれる。個人の努力でどうにもならないほど強固に、変えようとする努力が愚かに見えるほど自然に、諸々の習慣は、私たちの身体に埋め込まれている。

問いは「違和感」から生まれる
ところで、フィールドワーカーは、議論の手がかりになる「疑問」や「問い」をどこから得るのだろうか。とにかく調査地に行って観察すればいいのだろうか。
松村は、自分の居場所と調査地の「往復」が大切だと指摘する。その中で生じた認識のずれや違和感を手がかりに、思考が進められるからだ。
エチオピアにいると、日本とは違う感情の生じ方を経験する。そこから、日本社会の感情をめぐる環境の特殊さに気づくこともできるし、それまで疑問をもたなかった「感情とはなにか?」という根本的な問いにも自覚的になれる。(p.52)
エチオピアと日本のどちらが優れているかという話をしたいわけではない。ここで重要なのは、社会集団をスイッチする中で、それらの「ずれ」を感じることそのものである。違和感をテコにして、今ある規則が「他のものでありえた」ことに気づけるからだ。
エチオピア、食事の風景
一例を挙げておこう。エチオピアでの食事の話だ。
あなたがご飯を食べようとレストランに入る。と、知人が食事している。ここで相手がエチオピア人なら、かならず「一緒に食べろ(インニ・ブラ)!」と言われる。(中略)道を歩いているだけで、見知らぬ人たちから、「食べろ」と声をかけられることも多い。
逆に、あなたがなにかを食べているときに知り合いが通りかかれば、食べないとわかっていても、「一緒に食べましょう」と声をかけるのが礼儀だ。心配しなくても、相手も適切に状況を読んで、(嘘でも)「いま食べたからいいよ」とか言ってくれる。(p.62)
相手が実際に食べるかどうかにかかわらず、なぜ食事に誘うなどという面倒な儀礼をおこなわなければならないのだろうか。
松村によると、お互いが「贈与の関係」にあること、互いの愛着や愛情を、その都度確認するためだ。エチオピア社会は、食事や食欲という親密で共感を呼びやすいタイミングを選び、“惜しまなさ” “気前のよさ”を見せ合うことで、「贈与の関係」を形作る習慣を発達させたのだ。逆に、「食事の時に知人がいるのに、誘いもせず、見知らぬふりをする」ことは、敵対関係の宣言にも等しい振る舞いとなる(p.63)。平たく言えば、贈与とは、あなたと私のあいだに交換できないつながりを作り出そうとする行為なのだ。
同じく、エチオピア社会の発達させた、共同性に関わる習慣として、コーヒーを大量に入れて、近隣の人を誘い、雑談する時間を持つというものがある。話として面白いのだが、紙幅の関係から割愛せざるをえない、ぜひ手に取って読んでいただきたい(pp.78-81)。
余談だが、私はエチオピアの食事の例を読んだとき、関西のアメちゃん文化を思い出した(親戚のおばちゃんがそんな感じだった)。なるほどあれは、一種の「贈与の関係」を構築するための手法だったのか。あと、祖父母が孫に何かとあげたがるのとかも。

ガバナンス強化と改革の行方
少し文脈が外れるが、一点だけどうしても紹介しておきたいエピソードがある。エチオピアの改革をめぐる話だ。
エチオピアは、1974年、「デルグ」と呼ばれる軍事独裁政権が成立した(91年まで続いた)。デルグは、皇帝を廃して、国土の大半を支配していた貴族や大地主から土地を取り上げ、小作農に分配した。この政策は、強烈な中央集権の上に成り立っている。今風に言えば、管理職への権限集中と、強靭なガバナンスによって、組織内リソースの再分配が行われたのだ。
迅速な決定ができる権限集中と、コネにとらわれない公平な、ゼロベースの資源再分配……なんと素敵な! というわけもなく、現実に生じたのは、他者を評価し管理する権限ある人物をめぐる、忖度と賄賂の習慣である。それと並行して、集約的に権限を持つ管理者は、権限を濫用し、迅速に腐敗していく。こうして改革は、支持を失っていく。支持を得られない改革は、当然うまくいかず、従って、ますます強権的に改革へと向かい……と、負のループに入る。
「ガバナンス強化」の名の下に進む改革には覚えがある(佐藤郁哉『大学改革の迷走』)し、いくつかの企業の名前も頭によぎった。いや、最近に限った話でもない。作家の小田実が、ちょっとした権限を持つ人間がお山の大将と化し、こずるい人間へとなり下がるさまを、「きつねうどん大王」と名づけたのは、1970年代のことだ(『世直しの倫理と論理』)。小田は、日本社会のあちこちに、きつねうどん大王がおり、「管理者の権威主義」が見られると指摘した。この状況が変わっていないか、悪化しているのだとすれば、エチオピアの軍事政権の顛末を愚かだと笑える人は、この社会に、そう多くはいない。
松村圭一郎『うしろめたさの人類学』ミシマ社https://www.amazon.co.jp/dp/4903908984/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_858kEbT18P0YD
「どちらの日本になさいますか?」――小熊英二『日本社会のしくみ』レビュー
https://manabitoki.castalia.co.jp/home/bookreview-japanese-construction
小熊英二『日本社会のしくみ:雇用・教育・福祉の歴史社会学』講談社現代新書(Kindle)https://www.amazon.co.jp/dp/B07TYF38B4/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_048kEbQMYKD67
佐藤郁哉『大学改革の迷走』ちくま新書(Kindle)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZJ3TG39/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_718kEbV7PBMCG
小田実『世直しの倫理と論理』講談社(Kindle)https://www.amazon.co.jp/dp/B00KGWB22W/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_p18kEb0C52JSN
(*)本書を読む限り、構築人類学(構築主義)は、「作られているのだから作り直そう」という素朴な発想を採用している。それに対して、小熊の歴史社会学は、作られているが実に変えがたい習慣が形成された経緯を検討して、その歴史的偶然性を明らかにし、今後の日本社会の取りうる選択肢を考えるというスタンスである。このように、両者の視点には大きな違いがある(が、『うしろめたさ』は一般向けの書籍なので、要点を省略している可能性もある)。このように理論には、幾分か複雑な事情があるのだが、書評を読む分には、類似性にのみ注目して「大体似ている」と思ってもらって構わない。
2020/02/08
著者紹介
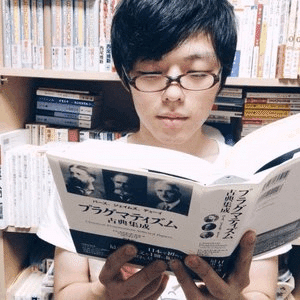
博士(人間・環境学)。1990年生まれ、京都市在住の哲学者。
京都大学大学院人文学連携研究員、京都市立芸術大学特任講師などを経て、現在、京都市立芸術大学デザイン科講師、近畿大学非常勤講師など。 著作に、『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(Discover 21)、『鶴見俊輔の言葉と倫理:想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)など多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
