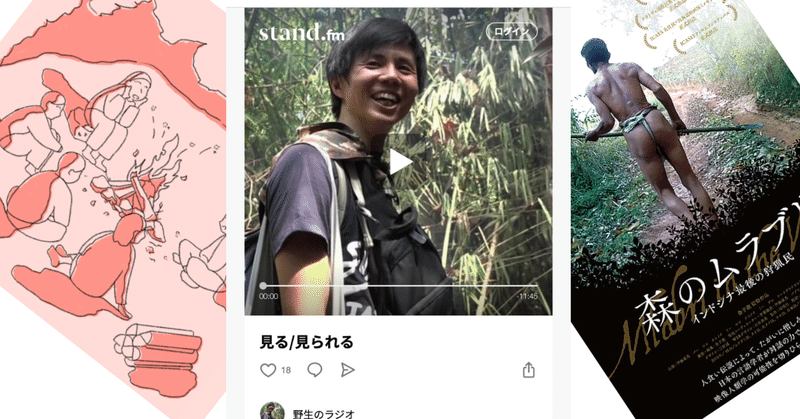
対話と「見る/見られる」とムラブリと
先日、言語学者であり、その枠で括れない自活研究者の伊藤雄馬さんがコーディネーターを務めたドキュメンタリー映画「森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民」の鑑賞&ダイアローグをした。金子監督、雄馬さんにも参加いただき、対話の時間を設けたけれど、その日にこのイベントに出かける前に雄馬さんが取ったらしいStand fmのラジオが面白かった。
ざっと、昨晩1回聞いただけの感覚で書いているので、色々とことばや意味が違ってたらすいません。まあ、コミュニケーションは、誤読の繰り返しであり、意識では測れないエネルギーが通っていればいいと思っているので、ことばの違いは、ご愛嬌ということで。。。
氷水の入ったコップを持っていたとする。そのコップを冷たいと思うのが身体感覚①(見る)、そのコップの存在によって自分の手が温かいと思うのが身体感覚②(見られる)で、それぞれで身体感覚が違うということ。
例えば、いま私は、日差しがたっぷり降り注ぐ部屋でストーブの暖かさを感じながらこれを書いているが、自分が部屋を感じ、このキーボードに向かっているという感覚(身体感覚①)と、部屋の状態によってもたらされる自分の状態や、キーボードの状態によってもたらされるタッチや思考の流れの感覚に意識を向ける(身体感覚②)では、感じ方が違ってくる。後者は、中動態的というか、環境と自分との相互作用の結節点を感じている感覚。自分が能動的にキーボードを叩いてはいるが、キーボードの硬さ・バネによって叩かせてもらっている感じ。環境が自分の拡張した身体であり、自分が拡張した環境であるような感覚。
これと対話が一体なんの関係があるのかというと。
身体感覚①だけで対話をしていると、自分と世界とのつながりがあまり感じられないが、身体感覚②で対話すると、共に場を囲んでいる人や、場そのものから、自分というものの輪郭が立ち上がってくる。世界との結節点としての自分の輪郭が感じられるというか。そして、対話という空間はそれが起こりやすいと思っている。
普段、身体感覚的①が優位にことばを出すことが多いと思うが、対話において、ふと誰かのことばに心を揺さぶられたり、あるいは、もやもやしたり、イライラする自分を発見すると、その環境や他者との出会いによって、自分の存在を意識されるという方向性の身体感覚②が出てくる。とすると、世界によって、中動態的に自分の存在が感じられて、環境や他者の存在によって、自分があるということに気づくのだ。
対話において身体感覚②が立ち上がると、他者との相違によって存在せらるる自分というものに意識が向き、その違いを愛せるようになるのだが、不思議なことに、場合によっては、その違いが意識された方が、その他者が自分に入ってくるようなことも起こる。
で、なぜ、ムラブリかというと。
雄馬さんは、ムラブリ語を研究することによって、ムラブリの身体性を得て、その身体性を身内に抱え込みながら、日本で生活している。おそらく(勝手な想像だが)、身体感覚①的にだけムラブリと出会ったら、観察者と観察対象者にしかならなかったであろうが、身体感覚②的に出会うと、雄馬さん自身の輪郭が明瞭になると共に、ムラブリが雄馬さんの中に入ってくるのではないか。
今回の映画を観てのダイアローグも、いつもの対話会も、その前と後では、私の身体感覚は全く違ってしまっている。身体感覚②で、対話し、他者との違いにおいて自分を感覚すると、かえって他者が自分の中に入ってきて、今度は、その他者を抱き込んだ身体で生きていく感じになる。
そうして、私は、今日も、これまで対話して来た人と環境をこの身体に抱き込みながら、それと共に生きる。私が生きるということは、その全てと共に生きるということだ。
出かける前に、身体の流れのままに書いたので、どんな文章になっているかよくわからないけど、確実に私の身体を通ったことばではあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
