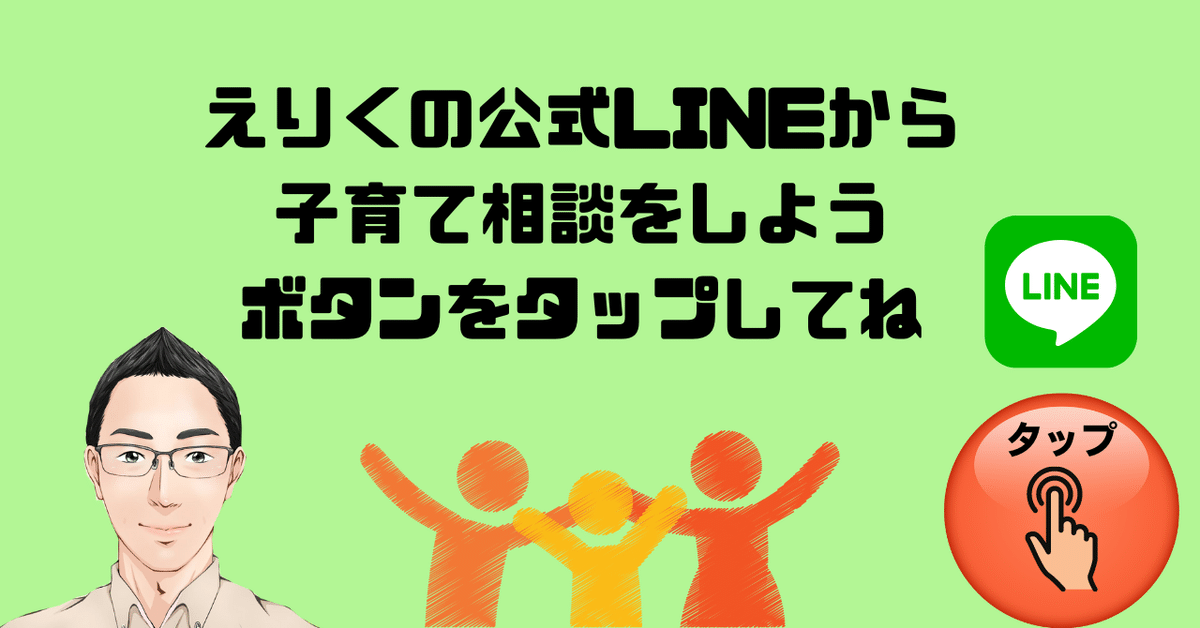年間100件以上の子育て相談を受ける現役園長が教えます。事例と共に学べる子どもへの援助方法。
![]()
こんにちは、えりくです。
今回は年間100件以上受けている
相談の中からピックアップし
解決に導いた事例を
紹介していきますね。
子どもは一人ひとり違いますし
対応方法はその子によって
様々ではありますが
参考になる内容ばかりだと思います。
子育てのヒントになれば嬉しいです。
目次
1.自己紹介
2.ケース①
3.ケース②
4.ケース③
5.ケース④
6.生活習慣をスムーズにする方法
7.終わりに
1.自己紹介
![]()

まずは簡単に私の紹介をしますね。
神奈川の横浜に住んでいます。
保育士歴20年
現在横浜の認可保育園の
園長になり8年目になります。
発達心理学の研究もしております。
家族は妻と息子が一人います。

息子は生まれて5分息をせず
重症仮死症と診断。
新生児スクリーニング検査で
耳が聞こえないことがわかりました。
通常の遺伝子はXYですが
息子はXXXXYという遺伝子異常がみつかり
『クラインフェルター症候群』という
病名がつきました。
10万人に1人と言われています。
簡単に言うと、手足が長くなったり
関節が抜けやすくなったり
無精子症になりやすいんです。
アレルギーもあります。
検査で39品目中38品目が数値として出ました。
さらに斜視もあり眼鏡をかけています。
生まれて1年間様々な告知があり
さあどうすると悩みました。
しかし、妻も保育士なので
路頭に迷うというよりも
どう楽しく生きていけるかを
話し合って考えていきました。
耳が聞こえないことについては
医者に人工内耳を進められました。
手術で埋め込むんです。
こんな小さな子に手術はしたくない。
色々調べて手話という世界を知りました。
そして息子の第一言語は
手話にすることを決めました。
いろいろあるけど
こうして家族で激しく楽しい人生を
歩み出したわけです。
病院・療育通いがあり
大変なこともたくさんありますが
日々の生活を楽しんでいます。
息子は今年小学校1年生になり
歩行はまだ出来ないけど
毎日笑顔で過ごしております。
おかげさまで連携機関との情報を
仕事に生かせているので
一石二鳥なんて思ったりもしています。
園長としては園の保護者や
地域の子育てセンターに呼ばれ
年間100件以上の子育て相談や
講演会を行っています。
子育てで悩んでいる方は
年々増えています。
そんな方たちの力になりたいと思い
毎日全力で活動しています。
それでは事例を見ていきましょう。
2.ケース①
![]()

5歳(年長)男児(定型発達)
2歳の頃から4年間継続面談
2か月に1回相談を受けている
母親がうつでADHD、ASDの診断を受けている
生活習慣が身につかないのが悩み
2歳の頃の悩み
オツムが外れない
食事の時に集中できない
夜寝るのが12時すぎ
母親の話を聞かない
オムツに関しては焦るとよくないので
急がず本人の意思に任せることにしました。
食事に関しては夕飯を少し食べ
飽きて立ち歩いてあそんでしまい
その後、父が帰ってきてから
パンを食べている状態でした。
父親が遅くに帰ってくるため
夜寝ようとしても起きてしまい
興奮状態の毎日でした。
母親の話は全く聞いてくれず
納得いかないことがあると
かんしゃくや母親に当たっていました。
母親が抱え込むことがあったので
全部をやるのを諦めることから始めました。
まずは母親とのコミュニケーションを
強化することを重要視しました。
寝る前に絵本を一緒に読む
一日一回はくすぐりなどのふれあいあそび
保育園に行く時はハイタッチ
この3つを繰り返すことで
1か月でだいぶ母親の話を
だいぶ聞けるようになりました。
オムツは祖母の圧力もありましたが
保育園で焦らなくて良いと言われたと言って
なんとか家庭のペースで進めました。
2か月に1回面談を繰り返しながら
課題を一つづつクリアしていきました。
5歳児になって
オムツ・食事はクリアになった
YouTubeを見て寝るのが朝4時になることも
突然興奮状態になることもある
5歳になると生活習慣が崩れてきて
YouTubeやゲームにはまってました。
母親が見切れずに与えてしまったのです。
バーチャルな表現が多くなり
いきなりスイッチが入った時には
変なテンションになることも
ありました。
大声を出したり叫んだりすることが
多くなってきたのです。
就学前検診では照れ隠しもあり
自分の名前が言えずに
校長面談になりました。
母親はかなり不安になり
気持ちの面で不安定になったので
すぐに面談を実施しました。
YouTubeにはまっているにも関わらず
父がゲーム機を買ってしまったとのこと。
生活習慣は一向に改善されず
むしろ環境的にも悪化していました。
なかなか難しい状況なので
スモールステップで進めることを提案。
①最低0時には寝ること
②ゲーム機は23時で終了
ここを意識することにしました。
友だちとのかかわりは増えてきているので
保育園でも友だちとたくさんあそぶ姿を
見守っていきました。
バーチャルの世界で
表現が間違った方向に行くこともあるので
園でその都度丁寧に知らせるようにしました。
母親に環境の変化があると
不安になりやすいので
就学までは1か月に1回の
面談をやることにしました。
園で出来ることはフォローし
家庭では無理なく出来ることを
少しづつやっていくスタイルで
進めていきました。
母親がしんどくならない
工夫をしながら進めていくことで
12時には寝れるようになりました。
小学校にも連絡を入れておき
状況を話しておくことで
母親の安心にもつながりました。
バーチャルな表現方法は
まだまだありますが
友だちとじっくりあそぶ機会は
増えてきています。

母親がうつを抱えている場合は
無理のないように「これならできる」を
見つけて支援しています。
こちらの要求が強くなることで
総崩れすることもすることもあるので
慎重に進めるようにしています。
子どものフォローはもちろんですが
母親の支援が必要なケースも
多くなってきています。
子どもと母親をバックアップする役割が
保育園にはあるんですよね。
今では小学校2年生になる子の事例でしたが
毎日元気に小学校に通っていて
母親も安定しています。
3.ケース②
![]()

3歳(年少)男児(ASD)
今年度4月より継続面談実施
2か月に1回相談を受けている
今年度他の県から引っ越してきた
支援方法がわからず困っている
入園してからの悩み
朝園に来るときに寄り道が多い
生活の流れがうまくいかない
言葉が出ない
今年度引っ越してきて
診断名はASDとついています。
言葉がほとんど出ないことを
心配していたので
すぐに療育につなぎ
発達支援施設も紹介しました。
すると週5回園に来て
土曜日に発達支援施設に
通うようになりました。
すぐに発達支援施設に私と担任で
あいさつに行き連携を取り始めました。
園では生活表や写真を使い
視覚から支援をするようにし
名詞ははっきり言葉で伝えることを
意識しました。
夏過ぎからはだいぶ発語も見られ
話したい気持ちを表すようになりました。
生活の流れは安定しましたが
母親と園に来るときに道草が多く
手を煩わせていました。
散歩で毎回通るルートに
変更してみてはと担任が提案しました。
するとかなりスムーズになっていきました。
新しい道には発見が多すぎたようです。
集団生活には入れない部分がありますが
本人のやりたいことに集中できる環境を
用意してゆっくり関わるようにしてます。
やりたいことに思いきり取り組むことで
主体性が出てきて
友だちのやっていることにだんだん
興味が湧いてくるようになりました。
療育ともつながっているので
1対1の加配もすぐに取れました。
保育者と1対1でかかわることで
安心して話す経験を積んでいて
生活がだいぶ落ち着くようになりました。
言葉の面でもはっきりは聞き取りづらいけど
話そうとする意志が増えてきたので
言葉を代弁するようにしています。

言葉の遅れに関しては
早めに療育とつないであげることが
重要となります。
STの指導を受けながら
園や家庭とも連携して進めることで
本人も楽になっていきますね。
本人も話したい気持ちはあるので
発語が進んでくると
友だちとのかかわりが深まっていきます。
コミュニケーション能力の獲得のためには
言語習得は重要になってきますね。
4.ケース③
![]()

5歳(年長)女児(ASD)
3歳の頃から3年間継続面談
1か月に1回相談を受けていた
母親がうつの診断を受けていて母子家庭
生活全般の相談を毎回受けていた
悩み
友だちとの関係性について
気持ちの整理がつかない
地域の子育て支援センターから
依頼があって相談を受けました。
母親も心療内科に通っていて
ケアがだいぶ必要でした。
3歳の頃は保育園に入ることが出来ず
友だちに対して手を出してしまうことが多く
支援センターでもトラブルになることが
多々ありました。
4歳になると保育園に
入園することができましたが
月に1度はカウンセリングのように
相談を継続していきました。
母親がいっぱいいっぱいになり
児相や地域の一時預かり施設を
利用することもありました。
友だちとの関係性を気にしていましたが
保育園で友だちができたことで
スキンシップをはかれるようになりました。
しかし自分の思い通りにならないと
癇癪を起したり
友だちに手を出してしまうことが
増えていきました。
まずは行動分析をし事前の配慮と
問題行動を起こした後の対応を
保育園の先生と考えていきました。
園での日頃の様子を見せてもらい
クールダウンの出来る場所を作り
視覚支援もできるようにしていきました。
1か月に1回巡回として入り
行動分析を3か月続けることで
だいぶ落ち着きました。
そこの園の園長からの依頼で
心療内科の先生ともつなぎ
母親の支援もしていきました。
子どもが落ち着くことで
母親も落ち着いていくので
まずは子どもの生活の安定させようと
園での対応を丁寧に行いました。
園の努力もあって生活習慣が安定して
卒園していきました。
小学校に行ってからも
何度も相談に来てくれて
母親の支援を継続していました。
支援級に入ったことで
手厚い支援を受けることが出来て
かなり生活は落ち着き
本人もがんばっているとのことです。
今年小学校4年生になりましたが
安定してきたため
今ではほとんど相談に来ることも
なくなりました。

友だちとのかかわりの中で
手を出したり癇癪を起すことで
困っている保護者は多いです。
こんな時は行動分析をしながら
正しい支援の仕方を
見出していくことが
安定につながっていきます。
ポイントは問題行動の前と後を見て
環境構成と行動に対する支援を
考えていきます。
何のための行動なのかを
しっかり見極めた上で
対応していくことが重要です。
行動分析することで
子どもの内面を探ることにも
つながっていくんですね。
詳しいやり方について
知りたい方はご連絡くださいね。
5.ケース④
![]()

2歳 男児(未診断)
今年度から継続面談開始
2か月に1回相談を受けている
3歳児検診で引っかかり療育とつなぐ
来年度発達検査をやる予定
悩み
友だちとのやりとりがない
友だちと目が合わない
言葉が出ない
2歳児クラスで友だちと
関わる様子がなく
一人あそびばかりでした。
寝っ転がっていることも多く
基本的には自分ペースで
動いています。
言葉が出ていないこともあり
3歳児検診で保健師から
話がありました。
両親と話し合った結果療育に
行くことになりました。
結局今の段階では診断は
出来ないとのことで
年少に上がった時点で発達検査を行い
診断していく方向となりました。
目が合わないので好きなトミカを
保育者の目の所へ持っていき
目を見る訓練は行っています。
トミカを見ながら話すことを
繰り返すことで
だいぶ目を見れるように
なってきました。
言葉は一語文は出るけど
それ以外は出ないので
絵カードを使い、物の名前を
伝えることを丁寧にやってます。
診断が出ていないので
加配がつけられないので試行錯誤ですが
視覚からの情報を入れることで
行動はスムーズになってきました。
パニックになることはほとんどないのですが
好きなトミカがなくなると大騒ぎします。
安心材料になっているので
必ずトミカは持たせるようにしています。

年齢が低いと発達検査を
見送られることも多いです。
そんな時は子どもの特性を把握し
その子に合った支援が必要となります。
療育の巡回を使ったり
専門的知識をもっている人に
見てもらうことが一番です。
スピード感をもって適切な支援を
早めに受けることで子ども自身も
行動が楽になっていきます。
生活の中で不便を感じているのは
子ども自身なので出来ることを
早めにやってあげましょう。
6.生活習慣をスムーズにする方法
![]()

障害をもつお子さんの
相談を受ける中で
一番多い相談は生活習慣の確立です。
なかなか生活習慣が身につかず
困っている方が多いのです。
今回は簡単に生活習慣が
身につく方法を紹介します。
①視覚からの支援

これはうちの息子が実際に使っている
カードになります。
行き先を示しているんですね。
事前に行動を視覚から
入れてあげることで
見通しがもてるようになります。
日々の生活の中で
お風呂の写真やトイレの写真を
見せてあげて促すことも
有効的です。
また、写真ではなく
絵カードやその場で書いて示すことで
行動に移せる子もいます。
お子さんにとって何が一番
入りやすいかを見極めてあげましょう。
②時間を明確にしてあげる
障害をもつお子さんは集中しだしたら
やめ時がわからない子もいます。
携帯のアラームやタイマーを使ったり
時計に表示してあげることで
やめ時がわかるようになっていきます。

音が鳴ったらやめる
時計を見てやめるなど
いろいろな方法を試してみましょう。
③その場ですぐにほめる
障害をもつお子さんは
ほめられる機会が少ないです。
ちょっとしたことで
つまづくこともあります。
自分で挑戦しようとしたり
出来るようになったことは
その場ですぐにほめるように
していきましょう。
否定され続けて
自己肯定感が低くなり
二次障害を起こす子も
少なくありません。
ポイントは大げさにほめること。
人間否定されるより
ほめられる方が嬉しいですよね。
7.終わりに
![]()

今回は私が相談に乗っている事例を
簡単に紹介しました。
通常は1か月~2か月を目途に
定期的に面談したり
子どもの様子を
見させてもらってます。
子どもは一人ひとり違うので
その子に合った適切な
支援方法を一緒に
考えています。
上手くいかないことも
多々あるのが現実です。
そんな時は次の一手を
考えて試してみる。
それが子どもにはまれば
継続していき
生活を安定させていきます。
年齢が低い時から
適切な支援を行うことで
将来の自立へと
つながるのです。
親は子どもが幸せに
生きてくれることを
願っています。
そのために必死です。
そういう方の助けに
少しでもなればと思い
経験を伝えながら相談に
乗っています。
今回このnoteをご覧になって
くださった方には
特別に特典として
子育て相談をプレゼントします。
リモートもしくは電話で
15分~1時間の相談を
受け付けます。
障害をもつお子さんがいると
なかなか相談すらする
時間がない方もいると思うので
電話でも対応します。
この機会に是非ご利用ください。
申し込みは下記の画像をタップし
公式LINEのチャットに
「相談希望」とメッセージをください。
公式LINEでは毎朝7:15に
子育てに役立つ情報を
配信しています。
特典も配っているので
お見逃しなく。
子育ては一人じゃ出来ません。
しんどくなったらすぐに
頼ってくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?