
心理学を使った子育てテクニック10選

こんにちは、えりくです。
私は発達心理学を学んでいるのですが
これがかなり子育てに活用できるんです。
今回は子育てに役立てることができる
心理学を活用したテクニック10選
をお届していきますね。
障害をもつ子の子育てにも活用できるので
意識していくとよいと思います。
今回は特別に解説動画付きです。
目次
序章 自己紹介
第一章 イライラするにはわけがある
第二章 心理テクニック
①「声掛けの工夫」
②「物の扱い方」
③「叱るコツ」
④「プロセス評価」
⑤「けじめ」
⑥「反省」
⑦「やってみせる」
⑧「間違い大歓迎」
⑨「物に命を吹き込む」
⑩「オノマトペ」
第三章 子育ての目標とは
最終章 まとめ
序章 自己紹介


まずは簡単に私の紹介をしますね。
神奈川の横浜に住んでいます。
保育士歴20年
現在横浜の認可保育園の
園長になり8年目になります。
発達心理学の研究もしております。
家族は妻と息子が一人います。
息子は生まれて5分息をせず
重症仮死症と診断されました。
新生児スクリーニング検査で
耳が聞こえないことがわかりました。
通常の遺伝子はXYですが
息子はXXXXYという遺伝子異常がみつかり
『クラインフェルター症候群』という
病名がつきました。
10万人に1人と言われています。
簡単に言うと、手足が長くなったり
関節が抜けやすくなったり
無精子症になりやすいんです。

アレルギーもあります。
検査で39品目中38品目が数値として出ました。
さらに斜視もあり眼鏡をかけています。
生まれて1年間様々な告知があり
さあどうすると悩みました。
しかし、妻も保育士なので
路頭に迷うというよりも
どう楽しく生きていけるかを
話し合って考えていきました。
耳が聞こえないことについては
医者に人工内耳を進められました。
手術で埋め込むんです。
こんな小さな子に手術はしたくない。
色々調べて手話という世界を知りました。
そして息子の第一言語を
「日本手話」にすることを決めました。
いろいろあるけど
こうして家族で激しく楽しい人生を
歩み出したわけです。

病院・療育通いがあり
大変なこともたくさんありますが
日々の生活を楽しんでいます。
息子は今年小学校1年生になり
歩行はまだ出来ないけど
毎日笑顔で過ごしております。
おかげさまで連携機関との情報を
仕事に生かせているので
一石二鳥なんて思ったりもしています。
園長としては園の保護者や
地域の子育てセンターに呼ばれ
年間100件以上の子育て相談や
講演会を行っています。
子育てで悩んでいる方は
年々増えています。
そんな方たちの力になりたいと思い
毎日全力で活動しています。
オープニング動画は ↓ ↓ ↓
第一章 イライラするにはわけがある


私の所には年間100件以上の
子育て相談があるのですが
イライラしてしまうという相談は
多いですね。
イライラのメカニズムは簡単で
欲求が満たされていないことが
原因なのです。
代表的なものを三つ紹介しますね。
その一つが時間です。

考えてみてください。
朝保育園に送る時に
仕事にも遅刻しないようにと
支度を急ぎますよね。
こんな時に限って出る前に
子どもがぐずることありますよね。
完全にイライラの原因となります。
人間は時間に追い詰められた時に
イライラを募らせる生き物なんですよね。
二つ目は空腹です。

例えばご飯の準備をしている時に
子どもはいたずらをしがちです。
ご飯を作っているお母さんも
イライラが倍増するわけです。
お母さんもお腹が空いていますから。
赤ちゃんがミルクがほしくて泣くのも
人間の本能的な部分があるんですよね。
人間は空腹になると不快を感じ
欲求を満たそうとするわけですね。
三つ目は疲労です。

これは言うまでもないですね。
仕事で疲れているのに
家事もこなさなきゃいけない。
子どもも言うことを聞かないという
悪循環を生み出すわけです。
このように私たちは
欲求が満たされなかったり
基本的なものが足りなくなると
イライラしてしまうのです。
逆に言うと
イライラの理由がわかってくれば
気持ちは楽になるということですよね。
疲れてイライラしているのであれば
諦めて子どもと寝てしまうのも
一つの手ですよね。
イライラしてしまうことから
距離を置いてみるというのも
時には必要ですよね。
こうして自己分析をしながら
イライラを解消する工夫ができると
子育てがもっと楽しくなるわけです。
イライラを解消するコツは
資料を載せておきますね。
こちらの資料を参考に
イライラ解消のための
自己コントロールが
できればよいと思います。
解説動画は ↓ ↓ ↓
第二章 心理テクニック

この章からは子どもに関わるための
心理テクニックを紹介していきます。
保育士歴20年の経験と
発達心理学の研究を通じて
得た知識を詰め込んでいます。
子どもとの関わりに
是非活かしていただければと思います。
①「声掛けの工夫」


家事をしながらの毎日だと
どうしても命令口調に
なってしまうことがありますよね。
これを繰り返すことで
子どもの心理としては
行動を切りかえることとセットに
自分が否定されるという認識がつきます。
嫌な感覚がインプットされると
次にやる時には自分から行動を
しなくなりますよね。
こうなることで悪循環が
生まれていくわけです。
これを避けるためには
子どもの近くに歩み寄り
手のひらで身体や頭をさすり
声を掛けてみましょう。
さするという行為は
動物的本能で安心につながります。
安心させた状態で声を掛けることで
子ども自身にもストンと
落ちていくはずです。
もちろん否定ではなく
肯定的な言葉掛けが重要となります。
穏やかな気持ちで接近することと
身体をさすることで
自然とやさしい気持ちで
関われるようになるんですね。
子ども自身に
自分が肯定される感覚が
身についたら主体的に
動けるようになっていくんです。
うちの息子はろうなので
声は届きません。
必ず近くに行って
身体をさすりながら伝えることで
行動がスムーズになりました。
この方法は子どもも親も
穏やかな気持ちになるので
いらないイライラが軽減されます。
②「物の扱い方」


子どもは自分が大切に
されているということを実感できると
何事にも前向きに取り組むようになります。
あなたのことが大好きと
言葉で伝えることも有効ではありますが
もっと良い方法が実はあるんです。
それは子どもが気に入っている玩具を
丁寧に扱うことです。
出しっぱなしになっている玩具を
片づけてあげてください。
その後に
「出しっぱなしの〇〇壊れちゃうので
しまっておいたからね」
とやさしく言ってみてください。
自分が大切にしている玩具を
大切にしてくれるんだという
認識がついていきます。
さらに自分のことも大切に
してくれているんだという
気持ちにもなっていくのです。
物を大事にすることは
それだけ影響力が
あるということなんですね。
実はこれは片づけの習慣にも
つながることなんです。
自分のものくらい
自分で片づけさせたいと
思いますよね。
しかし「片づけなさい」と言っても
簡単に聞くことはないのです。
こんな時は家族みんなのものを
片づけることから始めてみましょう。
うちの息子は食後のお皿を
流しまで持っていくようになりました。
みんなのものを片づけることから
始めていくと片づけ習慣が
次第に身についていくのです。
物を大事にするということは
大人が教え込むことではないのです。
大人がやさしく物を扱うところを見て
大切なものは大切に扱おうと
するようになるのです。
物を大切に扱うようになることで
人にやさしくなっていくようにもなります。
大切な人は誰なのか
その人にどう振舞ったらいいかを
大人の姿を見ながら
覚えていくようになるんです。
子どもは思っている以上に
大人のことをよく見ています。
物の扱い方や人に対する振舞いなど。
だからこそ丁寧に扱うことを
見せていきたいですよね。
➂「叱るコツ」


「あー今日も子どもを叱ってしまいました」
と落ち込むお母さんの相談を受けることが
よくあります。
叱らない子育てをしようと
書いてある育児書は多いですよね。
たしかにほめて伸びることは
たくさんあります。
しかし日々生活している中で
叱らないことなんてありえないですよね。
ほめて伸びるのはわかっているんだけど
そんな簡単に行くもんではありません。
だから落ち込む必要なんてないんです。
例えば自分のことで考えてみてください。
人間関係の中で思いの食い違いから
トラブルになったことはありませんか。
めちゃくちゃ相手を憎いと
思ったことはありませんか。
たぶん誰もが経験のあることだと思います。
それでも修復しようとしていくのが
人間の本能的な部分なんです。
どんなに苦手な人間だって
どんなに憎んだって
必ずいいところは少しでも
あるはずなんです。
沸点がその場でMAXに達したとしても
冷静に考えた時に自分にも非があると
考えていくんですね。
だから子どもを叱るという行為は
すべてが悪いわけではないのです。
叱られた→許されたという経験を
繰り返していけばいいだけなんです。
この経験を積むことで
人間関係は結びなおすことができるんだ
ということを覚えていくわけです。
だからこそ叱る時のコツを
覚えておきましょう。
①感情を出さない
私は保育の場面でも子どもたちと
本気で向き合うことを心掛けています。
時には本気で叱ることもあります。
ある時子どもを真剣に叱っている時に
後ろから他の子が話しかけてきました。
叱っている時は感情が
ヒートアップしてくるもんです。
でもその時は意識していたので
話しかけてきた子には笑顔で
答えました。
感情が入りすぎてしまうと
口調がきつくなったり
暴力的になってしまうので
感情は入れずに叱りましょう。
②真剣さを伝える
いつもは穏やかな人に
突然強い口調で叱られたら
びっくりしますよね。
学生の時にやさしい先生が
キレ出したら場が凍り付く
のと同じ感覚です。
演技も含めて
真剣な場では本気で怒ってると
思わせるようにしましょう。
真剣な場面では
子どもは泣きますよね。
泣いた後は素直になるもんです。
➂説教にならないようにする
話が長いと最終的に
何で叱られているのか
わからなくなりますよね。
端的にわかりやすく
知らせることが一番です。
私は1分以内で伝えることを
意識しています。
説教のように長々と言っても
結局子どもは行動を
繰り返すことになります。
これをしたら不快になる
これをされて嫌だったと
端的に伝えることを意識しましょう。
④最後はアフターフォロー
叱った後は子どもから離れて
クールダウンの時間をもちましょう。
距離を取ることで
お互い頭の整理の時間にもなります。
そして気持ちが回復した時に
わかってくれて嬉しいと
気持ちを伝えていきましょう。
アフターフォローを必ず入れることで
次の行動へつながっていきます。
④「プロセス評価」


うちの園では毎月
アートプログラムというものを
行っています。
その先生がおもしろすぎるんです。
絵を描いていると
「上手だね」という声掛けを
大人はすぐにしますよね。
しかし「上手だね」は禁句なんですよ。
上手だねと言っている時点で
上手い下手の評価をしている
という考え方なんです。
表現とは自由なものです。
その子の表現していることに
口出しする筋合いなんてないのです。
この考えは子育てでも
活きてきます。
大人は結果に目を向けがちです。
子どもの学びには
①やりたい
②やりたいけどできない
➂やったできた
④いつでもどこでもできる
⑤できるようになったことが
まわりに影響を及ぼす
というような段階があります。
ユーリア・エンゲストロームの
学習理論になります。
ここで重要なのが
②のやりたいけどできない
という場面です。
やりたいけどできないという場面では
自分なりに試行錯誤したり
友だちと話し合ったり
試してみたり
失敗してまた挑戦したり
と工夫したり考える場面が
多いわけです。
ここをしっかりと見守り
認めていくことがポイントになります。
大人からすればもしかしたら
どうでも良いことかもしれません。
しかし「なるほど」「そうなんだ」「すごいね」
と共感することで
子どもは認めてもらえたという
意識をもてるようになっていくわけです。
本人が努力していることに対して
着目しようとがんばるではなく
普段していることに興味をもち
そのまま認めてあげればいいだけです。
子どもがしていることに関心をもち始めると
親の心が豊かになっていくはずです。
子ども自身も自分のことを自分で
認めるようになっていき
承認欲求が減りおおらかになります。
ほめるポイント
①やり抜いた・やり切ったこと
②挑戦したこと
➂失敗を乗り越えたこと
④気持ちを切りかえられたこと
⑤相手のことを考えられたこと
⑥試行錯誤したこと
⑦自分で考えて工夫したこと
これらのことに着目して
子どもの行為を全力で
認めてあげましょう。
そうすることで子どもは自信をもって
自分から挑戦していきます。
結果よりもプロセスを大事にしましょう。
⑤「けじめ」

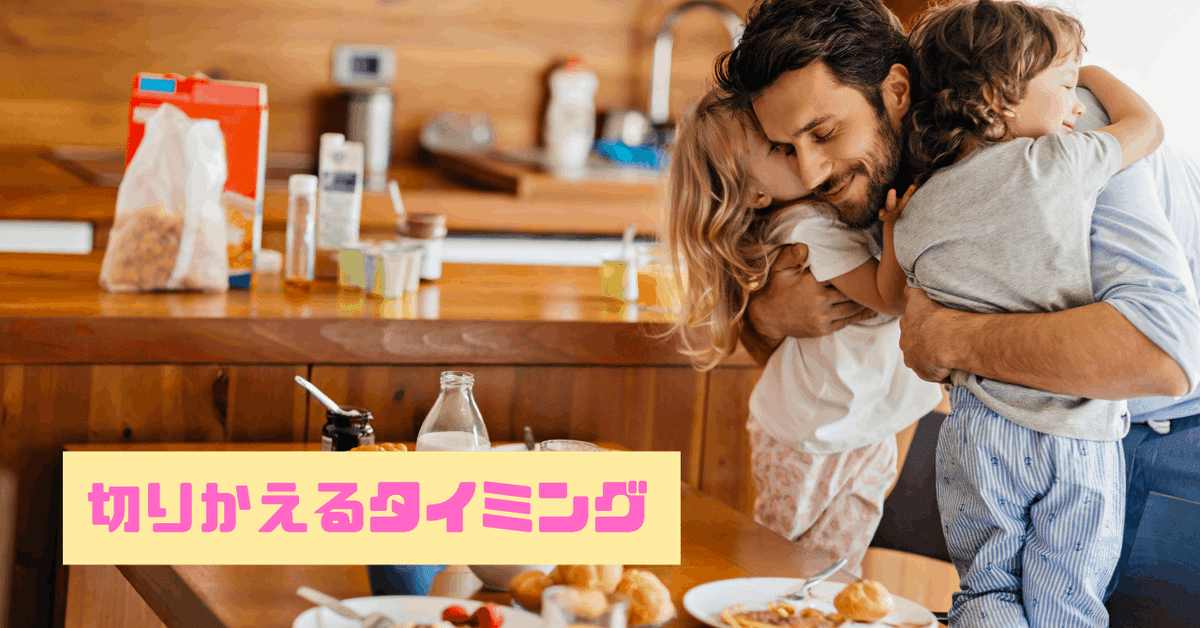
昔の学校は授業が終わるとチャイムが鳴り
日直が号令をかけてあいさつし
休み時間に入っていましたよね。
つまり学習モードからあそびモードへの
切りかえるタイミングがあったわけです。
こういうルーティンを家庭でも
意識していくと子どもの生活が
安定していきます。
そこで意識して取り入れたいのが
「ハグ」です。
子どもが帰宅した時に
①玄関でハグをする
②靴をそろえる
➂荷物を置きに行く
④手洗いうがいをする
というようにハグを挟んで
一連の行動に移すことを
やってみましょう。
ハグには気持ちを整える効果が
あると言われています。
例えばサッカー選手が
ゴールを決めたら抱き合って
喜び合いますよね。
嬉しさの表現でもあるのですが
もう一点取りに行こうぜという
切りかえの合図でもあるんです。
このようにハグを挟むことで
親からの愛も感じることができますし
一石二鳥なんですよね。
私の所に相談に来る方で
小学校4年生くらいまで
続けている人もいるんです。
障害をもっている方ですが
上手くルーティン化できたし
安心材料にもつながっている
とのことでした。
子育ての中での悩みの多くに入る
入眠の際にも効果的です。
①歯磨きトイレを済ませる
②絵本の読み聞かせをする
➂ハグをして横になる
といったように眠りモードへと
促すことで心を落ち着かせて
切りかえられることができます。
動→静の切り替えの時には
特に有効的になりますね。
これを行うことで親自身の
心の安定にもつながり
冷静な子育てができるようになります。
肌と肌のふれあいは
乳児期の「アタッチメント」で
注目されますよね。
年齢を重ねても安心に
つながっていくのです。
第二章前編解説動画 ↓ ↓ ↓
動画を見ることで
さらに深い学びとなります。
⑥「反省」


子どもと生活をしていると
思うようにいかないことって
たくさんありますよね。
だからイライラは増していくばかり。
そんな時に掛けてしまう言葉
①「前も同じこといったよね」
②「何回言ったらわかるの」
➂「もう勝手にしなさい」
④「○○しないと○○はないよ」
⑤「情けないね」
⑥「だらしないんだから」
全部否定語ですが
イライラしてしまうと
使ってしまうことありませんか。
でも実はこの言葉は
子どもに反省を促す
ものなんですよね。
子どものことを嫌いだから
言っているのではなく
改善してほしいから
言っているんですよね。
では反省するとは
どのような心理状態なのでしょうか。
失敗したことに対して
心にとどめておいて
改善しようとすることです。
子どもの場合は
切り替えが早いので
心にとどめておくことが
できないのです。
この時のポイントは
謝る前に許しちゃうことです。
えっ?って思われる方も
いるとは思いますが
先に許すことで
子どもは反省をするのです。
許してもらえないと
子どもは頑なに意地を張ります。
意地を張ると柔軟に物事を
考えられなくなりますよね。
こんな時に先に許されたら
子どもの心理状態は
叱られるはずだったのにと
拍子抜けするんです。
許した後に
「望ましい行動」を
伝えるようにしましょう。
そうすることで子ども自身が
考える力を身につけていきます。
だんだんと望ましい行動へ
変化していくので
否定語もなくなって
いくはずなんです。
子どもの頃を
思い出してみてください。
ガミガミうるさく言われたら
聞く耳持たなくなりますよね。
その原理なんです。
さらにポイントがあります。
①主語を自分にする
②感情を伝える
➂子どもの感情に訴える
どういうことかというと
「お母さん○○ちゃんが
そういうこと言うと
悲しい気持ちになるな」
と親自身の気持ちを
子どもに響かせてみてください。
子どもにとって親は
一番好きな人です。
その好きな人を
悲しませたくないという
心理が働くのです。
逆に「あなたは~すべきだ」
と言われるととムッときますよね。
親の気持ちを感じ取れるような
伝え方をすることで
子どもの行動も
促せるわけです。
⑦「やってみせる」


大人の社会でも口だけ人間って
たくさんいますよね。
私も保育園の園長として
口だけにならないように
気をつけようと意識しています。
管理職と言えば
権威性が目立ってしまいますが
いち保育士として職員たちとも
平等な立場でいたいのです。
親子もこれは一緒で
親は先に生まれているのだけど
偉いわけではないのです。
言葉で言って指示だけ出すのでは
子どもが言うことを
聞くわけないんですよね。
こんな時は先に動くか
一緒に行うことを意識しましょう。
例えば
「○○やってみよう」と声を掛けて
子どもより先にやり始めます。
すると子どもは気分が乗れば
自分でやりだすのです。
自分でやりだしたら
あとは子どもに任せて
いきましょう。
こうすることで
自然に子どもを行動へと
促せるのです。
気分が乗らない場合は
一緒にやることを
繰り返していきましょう。
自信がなかったり
不安なことが多いので
一緒に経験を積むことが
必要になります。
親の雰囲気は子どもに対して
強い影響力をもっています。
親がなにかを始めたら
自分もやりたいという
気持ちになっていくのです。
また、やって見せることで
行動が明確になりますよね。
行動に移せないということは
やり方がわからない
ということもあります。
視覚からやり方を入れることで
真似してやってみるに
つながっていくのです。
そして行動に移せることで
親自身も子どもの姿を
認めやすくなりますよね。
親に認められて自分でできた
という感覚が養えるので
自己イメージが作られていくのです。
イライラしたり
時間に追われている時は
悪循環になりがちです。
しかし、このポイントを
押さえておくことで
子どもの行動は変わります。
無駄なイライラも
なくなっていくわけです。
⑧「間違い大歓迎」


小学校の授業で手をあげて
さされて答えますよね。
でも間違えていた時に
「はい、次わかる人」と
軽く流された経験ないですか。
こんな時は二度と手なんて
あげるもんかと思いませんか。
せっかく勇気を出して手を上げたのに
踏みにじられた感じですよね。
間違いなんて誰もがすることです。
だけどその間違えに
まわりの大人がどう応えるかが
重要になるわけです。
子どもをやる気にさせるか
へそを曲げさせるかは
対応次第ということですね。
ここでのポイントは
子どもの間違いをなぞってあげる
ということです。
具体例を出すと
子どもが投げてはいけない物を
投げてしまったとします。
「それはダメでしょ」と言うのではなく
どういう気持ちでやったのかを
聞いてあげるようにしましょう。
気持ちに共感しながら
行動を振り返ることで
子どもは納得できるようになります。
小学生で言うと
宿題で間違った解答をしているのを
見つけたとしましょう。
こんな時は
「この答えになったということは
○○と思ったんでしょ」
となぞります。
その後に正しい答えを一緒に
導き出していくわけです。
こうすることで
間違えても大丈夫なんだという
意識が芽生え意欲や
挑戦しようとする気持ちが育ちます。
相手に身になって
考えてあげることは
人間が生きる上での
基本的なことです。
親がそういう姿を積極的に
見せていくことで
やさしさというものが
育っていくわけです。
世の中を見ると
自分のことしか考えていない人
多いですよね。
権利は主張するけど
義務を果たさない人も
社会で増えています。
乳幼児期の過ごし方や
学校教育の問題もありますが
間違っても大丈夫という意識が
人を思いやるにつながるのです。
親自身が
間違え大歓迎の気持ちを
子どもに伝えることで
安心して間違ってくれます。
間違ったら考えて正せばいいことを
伝えてあげたいですよね。
失敗は成功のもと
という言葉がありますが
チャレンジもせずに終わるという子も
増えてきています。
諦めなければ必ず
成功につながることを
体験させてあげたいですよね。
そのためには私たち
親自身の意識も強くもって
いきたいものですね。
⑨「物に命を吹き込む」


時代の流れと共にAIなどが進歩し
想像力が乏しくなっていると
言われています。
しかし子どもの世界には
無生物が生きているように
振舞う世界があるんですよね。
これを「アニミズム」と言います。
この独特の世界観は
ごっこあそびでイメージを広げたり
人形に話しかけてみたりと
想像力を養うのです。
日々の生活の中でも
この「アニミズム」を活用すると
驚くほど子どもはその気になります。
私は保育園で担任をもっている頃は
必ずポケットに小さな人形を
忍ばせていました。
例えば2歳児クラスの子で
トイレに行くのを嫌がったら
人形が登場します。
「僕もトイレに行きたいから
ついてきてくれないかい」
と言うとスムーズにトイレに
行くようになるのです。
うちの息子は手にはめる
クマの人形があり
私が手にはめると
手話で話しかけています。
手にはめた瞬間に
命が宿るんですよね。
こうすることで生活の中でも
やらなきゃいけないではなく
あそび感覚で楽しめるようになるのです。
あそび感覚でしていたら
いつのまにかできちゃった
くらいでいればなんだか
楽になりませんか。
こうしなきゃああしなきゃを
考えると苦しくなるのです。
楽しみながら生活習慣を
身につけることで
家庭の笑顔が増えていくことでしょう。
⑩「オノマトペ」


子どもに集中させたかったり
引きつけたい時に効果的な
言葉があります。
「ドキドキする」「ワクワクする」
「ピカピカだね」「パクパク食べよう」
などのオノマトペと言われるものです。
この言葉を意図的に使うことで
子どもも明確なイメージを
もつことができます。
例えば保育園で子どもが
切り替えが難しい時など
「ピピピピピー」といきなり言うだけで
「え?なになに」ってなりますよね。
このように引きつける言葉でも
あるのです。
また行動を促す時にも
効果的です。
例えば
「外に出る時に帽子をパッと被って
靴をスポッとはいていこうね」というと
みんなパッ、スポッと言って行動します。
オノマトペを使うことで
主体的な行動にも
つながっていくわけです。
言葉掛け一つを工夫するだけで
子どもの心をつかめるように
なっていくんですよね。
後編の解説動画です ↓ ↓ ↓
文章を読んでから動画を見ていただければ
理解が深まっていくと思います。
第三章 子育ての目標とは


赤ちゃんの頃から
たっぷり愛情をかけて
時には悩んだりしながら
子育てをしていると思います。
子育てで最終的に目指すところは
どこだと思いますか。
私は「子どもの自立」だと思います。
子どもが成人した時に
自分で生きていく力を
養うために子育てを
しているのです。
動物の赤ちゃんは
生まれてすぐに自立します。
でも人間は歩行するまでに
約1年かかりますし
自分で生活できるまでには
15年~20年かかりますよね。
生物の中でもこれだけ時間が
かかるのは人間だけなんです。
これはいったいなぜなんでしょうか。
すぐれた心とすぐれた脳を
持つからだと私は思います。
自立といってもいろいろな種類が
ありますよね。
一つずつ見ていきましょう。
①身辺的な自立
身の回りに整理ができる
自分のことは自分でできる
考えて行動できる
②精神的な自立
困難にぶち当たった時に解決できる
自分なりに考えて対処する
悩みを解決していく
➂経済的な自立
自分でお金を稼いで生活する
④社会的な自立
家族以外のつきあいで居場所を作る
人との良好なつきあい
自立とは一人でなんとかするという
イメージがありますが
そういうことではないと思います。
自分の苦手なことも含めて理解し
相手の力を借りながら
「自分の意思で生きていく力」
だと思います。
そのために必要なことは
「自己肯定感」を高めていくことが
必要になってくるのです。
先日配布した資料と動画を
載せておきますので
参考にしてみてくださいね。
詳しくはこちら ↓ ↓ ↓
自己肯定感の高い人は
自信のある人が多いですよね。
自信がある人は自分の弱さも
相手に見せることができます。
そしてほどよく相手に依存することが
できるんですよね。
自信がない人は変な殻を被り
なかなか自己開示できなくなります。
こうなってしまうと生きづらさを
感じてしまうのです。
親として他人に依存できていますか。
何度も言いますが
子どもは親の姿をよく見ています。
親が依存できずに誰にも頼らずに
一人で生きていたら
子どもから頼られた時に
受け止めることができません。
だからこそ私のような
子育ての専門家に頼り
打ち明けてほしいと思うんです。
子育ては一人で抱えていても
解決の糸口は見つかりません。
頼れる人にしっかりと頼り
一緒に解決していくことが
社会創りにもつながるし
子どもの自立につながるのです。
最終章 まとめ


心理学の観点から
子育てのテクニックを見ていきました。
私は発達心理学の研究もしているので
子どもの内面を探るためには
心理学は欠かせないと思っています。
特にうちの息子は障害をもっているので
心理学の観点から行動を見ていくことで
理解できることが増えていきました。
子育てや保育の経験を伝え
行動を分析してみたり
様々なことを試しながら
今後も一緒に考えていきましょう。
だって子育てって
本来楽しむべきことなんですから。
年間100件以上の方が
相談に来てくださいますが
年々子育てで悩まれる方が
増加傾向にあります。
本当に一人で苦しまないでほしい
ということが私の願いです。
だからこそ今回のような資料を
どんどん出していき
少しでも心が楽になってほしいのです。
まずは気軽に相談してくださいね。
今回10000文字を越えるnoteになりましたが
お読みいただきありがとうございました。
是非感想をいただければ嬉しいです。
最後に私からプレゼントです。
このnoteをお読みいただいた方限定で
電話orリモートで子育て相談を行います。

子育てをしていると目が離せなかったり
時間がなかったりするので
15分程度でもいいですし
時間がある方は1時間くらいで設定します。
ご希望の方は公式LINEのチャットから
お申し込みください。
今後も多くの子育て情報を
配信していきます。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
最後の動画はこちら ↓ ↓ ↓
noteの感想もお待ちしておりますね。
Twitterでいただければメンション付きで
紹介させていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
