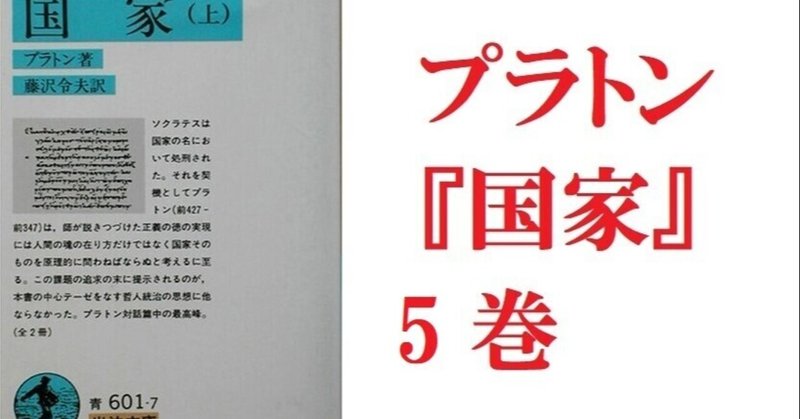
『国家』(プラトン著)5巻
女性や子供の立ち位置について考察された。
男は私有財産を持ってはならない。そこで、女性や子供もそのように扱ってはならない。つまり、プラトンにおいて、現代における核家族の概念は否定されている。誰か一個人の囲い込みによって存在するのではなく、公共の関係性、すなわち、みんなの妻であり、みんなの子供でなければならない。
みんなが家族であれば、他人であることによるいさかいがなくなる。
女性の職場進出、すなわちフェミニズムについても議論された。女性であっても男性と同じく、適材適所に起用されるべきであり、それがたとえ戦場であっても、適任であれば良い。これは、古代ギリシャ社会においても一見変に見える主張だったようだ。
続いて、国家の守護者、ここでは政治に関することだが、それは哲学者に任されるべきだと主張される。これがプラトンの有名な「哲人政治」というものだ。
哲学者は愛知者(フィロソフィア)なのであり、思わくする者ではない。意識には知識と思わくがあり、知識は確固とした存在だが、思わくは真実かどうか分からない不安定な「だろう」とか「かもしれない」とかいったものだ。そこで、思わくする者が王となるのではなく、愛知者=哲学者が政治を司るべきだ、というのである。
さて、上巻の要約が終わったが、まず5巻の感想としては、国民全体が家族という概念は一見理想のように見えるが、悪人に親面されたらたまったものではない。人間には善良な者もいるだろうが、悪人もいっぱいる。それが、「家族だから」とか言って絡んでこられたらどうするのか。
プラトンの説はお花畑理論と言うほかはない。
哲人政治の概念は、ここへきて初めて出てきたが、序章なのであり、まだその詳細は明らかでない。
上巻を通じて、結局臨死体験の話、ひいては霊性進化の哲学は出て来なかった。予想はしていたが…
下巻、果たして?
よろしければサポートお願いします!
