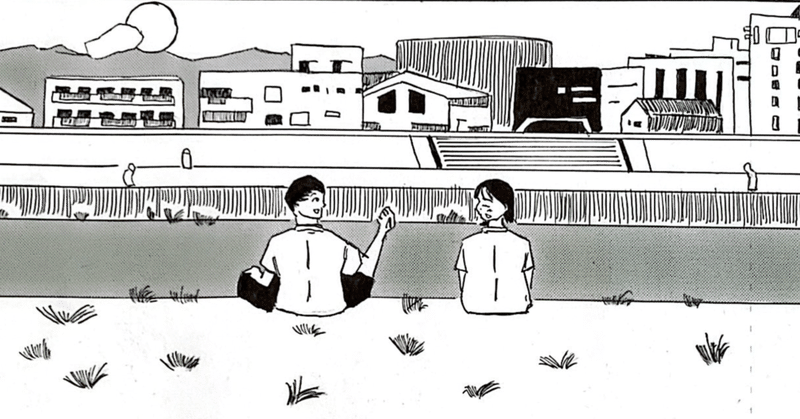
小説 「17歳」
1章
満月の夜。季節は秋。
空は澄み渡っていて静寂に包まれた住宅街の公園のブランコに僕は一人で座っている。
0時を回ったか回っていないかくらいの時間帯。
遊んでいる子供の姿はもちろんなく、
この時間帯に居そうなまるで世界には自分たちしか居ないのだと思っているようなカップルの姿も見えない。
敷地内のすべてを把握できているわけではないが、
おそらく公園内には僕しかいないだろう。
金曜日だからか周りの家々の多くにはまだたくさんの明かりが灯っている。ほとんどの家庭が家族団らんの真っただ中なのかもしれないけれど声はここまでは届かない。
羨ましいなという考えがふと頭を過ってしまったことに対して少し驚いた。暖色系の照明がついたリビングでは今週あった出来事の共有などが行われているのだろうか。
平和だ。
目の前に実在する人間に対して言葉と身体で意思を表現する。
それを生活の一部として取り込んでいくということが地に足をつけて生きていくということなのかもしれない。
目をつぶって考える。
満員電車で視線を外しても広告が目に入る。
逃げようとしても逃げられない。
次々に情報が頭の中に流れ込んでくる。
「多いな。」
自分の欲望や願望の根源に本来の自分というものはどれだけ存在するのだろうか。
純度100%の自分というものはあり得ないのかもしれない。
「そろそろ彼女がやってくる頃かな?」
そう思った時、腹部に激しい衝撃を感じた。
痛く熱く重い。一言では表せない感覚。
思考を長く続けることができず、何が起きたか頭を上げて周囲を確認したかったが体は意思に反して前のめりに傾いていく。
ブランコがきしむ。
17歳男子の体重を支えているのだ。無理もない。
腹に手を持っていこうとするが激しい痛みのせいでうまくいかない。
暖かいような寒いような。
この感覚は秋のせいかと思ったが衣服が濡れているということやブランコの板を伝って液体のようなものが滴っているということから少しずつ状況が分かってきた。
血。
大量の血が腹部から出ている。
ぽたぽたぽたと土に染み込んでいく。
雨天時のグラウンドに染み込ませるスポンジのように徐々に。
その様子を見ていて実にキレイだなと思った。
決して1つの過ちをも犯さずにまっとうに生きてきたという程の自信はないが、そんな自分の内側にもこんなにもきれいで鮮やかなものが流れているということに感動していた。
絵の具よりも鮮やかでおおよその教師が添削で使用するマーカーよりも深みのある赤。
テレビドラマやなんかで見るものよりも美しく、流れる様も現実的だった。
そりゃそうだこれは現実なのだから。
腹から前方に向かって棒状のものが突き立っている。
「あぁ、痛い…。」
ようやく視界に自分以外の存在を認識できるようになってきた。
自分の目の前にあるのは見慣れた頭部だった。
それは「ふぅ、ふぅ」と息を吐きながら上下に揺れていた。
犬みたいだなと思った。
前髪をよく梳いた今どきの髪型。量産的。流行には合わせていかないと。
人口は密集している。
一人だけ違うような恰好をすると無言の圧力でつぶされる。
出る杭は打たれると昔から相場は決まっているのだ。
「あなたのせいなんだからね。」
顔を見ると今付き合っている僕の彼女だ。
涙を流している。
夜の公園で彼女を待っていたのだ。
「泣いている顔もかわいいよ。」
そう言おうと思ったがやめておいた。
というかできなかった。
お腹に刃物が刺さっているのだ。無理だろう。
「あなたのせいで、こんな…こんな…」
血が流れすぎたからかうまく思考が理解に到達できない。
なぜ君が泣いているんだ?
泣きたいのはこっちの方だ。
なんせ好きな女の子に包丁でお腹を刺されて痛い思いをしているのは僕だからだ。
ここには誰もいないがもし第三者が居たら援護してくれるだろう。
そうだ、泣きたいのはこちら側なんだぞ。と。
「なによその顔、自覚ないわけ?」
彼女はまだ泣いている。
こんなに涙って体内で生成できたんだなと思った。それぐらいに泣いている。
表情は怒っているのに顔は涙でぐしゃぐしゃ。かわいい。
本当にかわいい彼女だと思う。
いつか街を走り回っている選挙カーをジャックして彼女の魅力を町中に知らせないといけないなと考える。
叶いもしない公約を騒音でがなり立てるよりかはよっぽどマシな行いだろう。
そこまで考えてやっぱりこの感覚は独り占めにしておきたいという気持ちが出てきて、それが彼女の良さを宣伝しないといけないという義務感を上回った。
人間の心の動きは一瞬で変わってしまうものなんだな。
彼女が口を開いた。まだ彼女の会話のターンは終わっていない。
「優子って子のことよ。とぼけないで。」
じっくりと思いだすということができなかった。
なんせ僕の腹部にはまだ異物が差し込まれているという状況なのだから。
「優子…?」
もちろん優子のことは僕もよく知っている。
僕とも彼女とも違う学校ではあるのだけれど。
だけどそれと今この状況に立たされているということがどうもうまく結びつかない。
そもそもなんで梨香が優子のことを知っているんだ?
血が抜かれすぎてうまく考えることができない。
彼女の眼には明らかな怒りの色が滲んでいる。
「そんな目で見ないでほしい。」
僕を好きだと言ってくれた時の瞳はどこへ行ったのだ。
全然形状が違うじゃないか。
小学校の時に掛けていた形状記憶合金の眼鏡を思い出す。
あれの何が良かったんだ。
もしこのまま死んでしまったら彼女は何かしらの罪に問われるのだろうか。
それだけは避けたい。彼女を犯罪者にはしたくない。
きっと僕は彼女が取り返しのつかないことをするためのトリガーになりうる何かをしたのだろう。
彼女を悲しませるような出来事はなるべく彼女の周りから排除しなければならない。
それは僕がすべきことでもありやりたいことでもある。
その権利は僕にしかないしその事実がとても嬉しい。
「もし、君を何悲しませたのだとしたら…」
「もういいよ。遅すぎる。」
彼女の手が震えながら僕の腹部へと伸びる。
彼女が包丁の柄を握った時、今まで安定していた痛みが一段階鋭くなり体に響いた。
「や..やめ…」
周りの肉を再び引き裂きながら包丁が一気に体から引き抜かれた。
さっきまでぽたぽたと滴り落ちていた血液がぼたぼたと大きな音に変わり、次第にペットボトルの蓋を外したまま倒してしまった時のような勢いで体から血液が抜けていった。
もうその時には自分の血液を綺麗だなと思う余裕もなかった。
霞んでいく視界の中で彼女が走り去っていく姿が見えた。
寂しいなと感じているとふと脳内の回路ががちゃんとつながったようにこの事態が起こってしまった原因に対する一つの仮説が浮上した。
「もしかして…そんな…」
けれどあり得る話ではあった。
「そういうことだったのか…」
やっと理解することができた。
血はまだ腹部から勢いよく流れ出ている。
土は血を吸いきれずブランコの下には水たまりのように血が溜まっていった。
思考する余裕はなく次第に目も見えなくなってきた。
意識が遠のいていく。照明がパチンと消える。ブラックアウト。
もう何かを想うことも何かを考えることもできない。
住宅街に灯っていた明かりは先ほどの半分くらいまでに減っていた。
2章
僕と彼女が付き合ったのは文化祭の頃だった。
毎年僕の学校では各クラスが出し物として劇をやるしきたりがあった。
役者として出演するのはどちらかというと運動部に所属するような活発な人たちで僕はそうではなかった。
運よく僕のクラスの活発な連中たちで役は埋まり自分が役者になることを避けることができた。
なりゆきで大道具係になった。
大道具係は他に9名いた。
僕の彼女の田井中梨香もそのうちの1人だ。
高校生が文化祭でするような劇なので、近所の商店街からいらなくなった段ボールを幾分かもらってきて、ガムテープや画用紙、マジックなどで作成するようなちゃちなものだった。
資材の買い出しは近所のホームセンターで行った。
大道具係にはどちらかというと自己を主張するような者は少なかった。
僕も彼女もその類だった。
地元の進学校としても有名な僕らの学校ではさして目立ったことはせず教室に存在する者はたくさんいる。
多くの者が目立たないように行動しようとするため委員会への立候補や行事ごとはなかなか円滑に進まない。
担任が腹を立てるくらいに委員会の任命もなかなか決まらない。
何か目立った役割を与えられることが嫌なのだ。
2年に上がると国公立を目指すクラスと私立を目指すクラスとで分けられ、国公立を目指すクラスを志望した僕はより一層おとなしい者が多い環境に身を置くようになった。
これといった特徴を出そうともしない集団の中に埋もれていき、時折自分という存在がどこに位置しているのかがわからなくなった。
切っても切っても顔が同じ金太郎飴のうちの1つになったようだった。
そんな自己主張をする者が極端に少ない集団の中でどうやって僕と彼女が距離を縮めていったのか。
ホームセンターへ資材の買い出しに割り当てられたのが僕と彼女だった。
買い出しの組み合わせは男女のグループで分けられた。
仲が良すぎる者同士だと業務を怠る可能性があると判断されたからだ。
大人しすぎる連中ばかりだからそんなに慎重になる必要はないのだが一応これは学校の活動なのだ。
「田井中さんって自分で選んで大道具係にしたの?」
「うん。君は?」
君。
実際にこんな呼び方をされたのは初めてだった。
変わっている子なのかな。
ファーストコンタクトではそう思った。
「流されるままに。気づいたらなってたって感じかな。」
「ふうん。」
少しがっかりした表情をしたように見えた。
自主性を重んじるタイプなのかな。
それともそれは勘違いでただ遠くの山々に想いを馳せようとしていただけなのかもしれない。
「ねぇ。お腹空かない?」
「空いた。たこ焼きでも食べる?」
二人でホームセンターの脇にある小さな屋台の方を見る。
「けど私、財布持ってない。」
「僕持ってる。」
「え!おごってくれるの?」
「そんなわけないじゃん。親からのお小遣いでやりくりしてんだから。貸しだよ貸し。」
「けち。」
なんで今日初めてしゃべった女の子にたこ焼きをおごらないってだけでそんなこと言われないといけないんだよ。
自分で稼いだお金ならともかく。
大体うちの学校は今どきアルバイトすら禁止のお堅い校風なんだ。
ふと彼女の表情がちらと視界の隅に入る。
口を尖らせて拗ねたような顔。あれ。不思議な感じがした。
「たこ焼きを1つください。」
屋台のおじさんに注文する。
「何個入り?6個12個18個。」
「6個入でお願いします。」
昨日は本を買ったので財布には小銭しか入っていなかった。
高校生のお財布事情は苦しいのだ。
「焼きたて一番!!」おじさんはそんな文言が書いてある黒いTシャツに身を包んでいる。
だけど僕が渡されたのは既に焼きあがっていて待機していたたこ焼きたちだった。
木の色をモチーフにした発泡スチロールのパックに入れられて渡される。
「ありがとうございます。」
「食べよう。」
2人でコカ・コーラのロゴが入ったベンチに腰を下ろす。
「わーい。」
棒読み。奢りじゃないのが気に食わないのか。
思えば同世代の女の子と2人きりで肩を並べて座るのは僕にとっては珍しいシチュエーションだった。
意識すると少し緊張する。
はふはふと頬張る横顔。
焼きたてじゃないのかと思ったけど意外と熱いのかな。
自分も口に入れる。ちゃんと熱い。
「熱いね。」
「ありがとうね。」
彼女の方を見ると笑顔で次のたこ焼きをつついて口に持っていくところだった。
さっきの拗ねた顔とは真逆の表情。
可愛い。
そう思ってしまった。
結局彼女はたこ焼きを4つ食べ僕は2つ食べた。
彼女のことを好きになるまではさほど時間はかからなかった。
3章
文化祭をきっかけに僕たちは一緒に行動することが増えていった。
図書館でテスト勉強をしたり、本屋で参考書を探したり、公園でブランコを漕いだりした。
河原で日が暮れるまで話していたこともあった。
学校で異性と一緒にいると目立ってしまい好奇の目にさらされてしまうので、生徒の多くがそうであったように学校にいる間はほとんど一緒に行動しなかった。
会う約束はスマホでしていた。
「あのさ。実は前から田井中さんのことが好きになっていて。よかったら付き合ってくれませんか?」
とあるデートの日、僕から告白をした。
生まれてはじめての告白。
いつものように公園でブランコを漕いでいるときに。
前日は眠れなかったし当日は上の空で何も考えることができなかった。
僕が見ていた景色はいつもの公園とはまた違って見えた。
枝に鳥が止まっている。
「ありがとう。よろしくお願いします。」
照れた笑顔であっさりと承諾をもらった。
こんなことなら前日にしっかりと寝ればよかった。
しっかり考えたつもりのセリフもこれ以上ないくらいありきたりのものだったし。
彼女の笑顔をもっと見たい。もっと一緒に居たいと思った。
正直、付き合うということがどういうことなのかよくわからなかったのだけれど好きになった異性と一緒に居たいと思ったらその旨を相手に伝えることが筋だと自分の中では決まっていた。
自分にも相手にも嘘はつきたくない。
言葉にして外に出したい。
これからはもっと堂々とまっすぐに彼女と向き合っていきたいと思ったから告白をした。
「といってもこれから何をすればいいのかわからないね。割と普段から一緒に居るわけだし。」
「何もしなくていいよ。ちゃんと気持ちを言ってくれたからこれからも一緒に居ていいんだって思う。勇気をだして言ってくれてありがとう。これからもよろしくね。」
「うん、よろしくね。すごく嬉しい。」
こういった会話を交わしても小心者である僕はこれから梨香に嫌われないかが不安だった。
彼氏として何かしなくてはいけないのではないか。
相手に好きになってもらうように。
そう思った僕は幼馴染である小川優子にこのことを相談することになった。
おそらくここからの僕の行動が夜の公園でのあの出来事への引き金となったのであろう。
小川優子とは幼い頃から仲が良かった。
同じマンションに住み同じ幼稚園に通っていた。
彼女はどちらかというと外に出て元気よく遊ぶというよりも室内で物を作ったり絵を描いたりすることが好きなタイプだった。
年齢は僕の1つ上。
優子が自由時間に工作をしていたところに
「なに作ってるの?」
と声をかけたのが初めての交流だったと記憶している。
小中学校は同じ学校に通っていたが高校からは別々のところに通うようになった。
思春期になってもこの年代にありがちな気まずさも感じなかった。
近所に住むお姉さんという感じで接していた。
最近どんな本や音楽が流行っているのかとか、もちろん勉強や進路のことについても相談することは多かった。
女の子との付き合い方について相談する際に進路についても話した。
「優ちゃんは高校卒業したらどうするの?」
「あんまり深くは考えていないんだけどなるべく親の負担にならないように国公立の大学を受けようかなと思っている。」
柔和な笑みを浮かべて答えてくれた。
優ちゃんは名前の通り優しい。
他人の気持ちなんて本当のところでは誰もわからないし、自分の気持ちですら波があったりしてきちんと把握することは難しい。
けど、優ちゃんはそこを諦めない。
今の状況や空気、相手の表情や仕草から自分が今何をすることがベストなのかを自然と読み取って発言しようとするのだ。
幼いころから勉強のことも趣味のこともなんでも話してきた優ちゃんだからというだけでなく、他人のことをきちんと思いやることができる一人の人間として尊敬していたので、初めての彼女である梨香とどうすれば仲良く居続けることができるのかも相談として持ち掛けるようになった。
「ねぇ。梨香。最近付き合ったの?」
「え?」
思ってもみない問いかけに少したじろぐ。
「え?じゃないでしょう。この前本屋で見たよ。言ってくれればよかったのに。」
ほのかが呆れたような笑みを顔に浮かべながら話しかけてくる。
1時間目が終わったばかりの休憩時間。
新しい話題を持ち出すには良いタイミングだったのだろう。
「そんな付き合ったからって『付き合いました!』って堂々と宣言するのも変な話じゃない。それで別れちゃったら周りも気まずいでしょう。」
苦笑いで答える。
「まぁ、確かにね~。」
「梨香、長谷君と付き合ってるの?」
別の子がやってきた。噂好きな栞だ。
「そうだけど。」
「ん-。そうなのかー。」
「栞、まさか長谷君狙ってたの?」
ふざけた調子でほのかが言う。
「狙ってないよ!ていうか彼、他に付き合っている人いなかったっけ?」
栞が場に合った明るい空気のままで答える。
さーっと自分の体から血の気が引いていくのがわかった。
栞は別れたのかなと1人つぶやいている。
「言いにくいんだけど、結構女の子と歩いているところを見かけるからさ。どういう関係なのかはわからないんだけどね。」
「お姉さんとか親戚とかそんな筋じゃないの?結構大げさにするとことあるからね栞は。」
ほのかが助け舟を出してくれた。
「多分うちの学校の生徒ではなかったと思うんだよね。制服が違うし。まぁ確かに一緒に歩いているのを何回か見ただけで浮気しているとかって断定するのは早いよね。ごめんごめん。」
キンコーン。
2時間目が開始するチャイム。
会話の輪は解消され生徒たちは席に戻っていく。
梨香は動揺していた。
長谷君、彼に限ってそんなことはないはずだ。
けれど、栞がよく見かける女性とは一体どんな人物なのだろうか。
それが気になって2時間目以降の授業はあまり頭に入ってこなかった。
4章
長谷圭佑。
付き合っている男の子。
文化祭をきっかけに仲良くなりそのまま付き合いだした。
漫画やドラマにありがちなスタートではあったがいわゆる彼氏彼女の関係。
学校帰りに一緒に帰ったり公園や河原で話したり図書館で勉強したりそんなようなことが私たちのデートの主なものだった。
付き合いだしてから約3か月。
今まではそんなことなかったのに一緒に帰る日が少なくなってきている。
栞が言っていた「よく一緒にいる女」の存在が心に引っかかる。
真面目な彼が浮気するはずはなないとは思うのだが栞も栞で嘘をつくようなタイプではないのだ。
付き合いはじめてから自分の心の変化に驚く。
彼がクラスの女子と話しているところを見ただけで嫉妬のようなものを感じた。
焦りと言った方がいいのかもしれない。
他の子と楽しそうにしている表情が視界に入ると自分と一緒に居る時よりも楽しそうに見えて自分なんかいなくても十分楽しくやっていけるんじゃないかと思う。
そこまで考えたところで今度は自分が彼を楽しませることができるという前提で物事を考えていたことに気づきその自惚れた考えに対して嫌気が刺すという考えれば考えるほど苦しいループに陥ることがよくある。
もっと彼のそばに居たい。
そういう気持ちが強くなってもっともっと必要とされる存在になるように動かないといけないという焦りだかやるいせない怒りだか言葉で表すことの難しい考えが頭をぐるぐる回っていくことがよくある。
そして行動すればするほど思うような結果が出ず考えて行動してを繰り返してどんどん深みにはまっていく。
恋愛して初めて自分が思い悩むタイプなんだなと知った。
はじめてそれを見たのは1人下校しているときだった。
「栞の言う通りだ…。」
とうとう知らない女と一緒にいるところをみてしまった。
女といっても見たところ自分たちと同じような年ごろなので女の子という方が正しいのだろう。
教室で自分以外の女子と話している時のような笑顔ではない。
もっと親密な関係性を感じさせるような顔をしていた。
確かに2人の距離感は何も知らない第三者から見ると付き合っているようにも見える。
ただの知り合いや友達ではないなと周囲に納得させるような空気を生み出していた。
不思議と教室で感じたような嫉妬は出てこなかった。
確定的と思える状況に出くわして諦めのようなものを感じたのだろうか。
そんな気持がなぜふと心を覆ってしまったのか自分でもわからない。
そういう時に自分はあくまで従事しているだけだということが身に染みてわかる。
支配しているのではなく支配されている。自分自身の心のことでさえ。
手綱を握ってコントロールできるものなどほとんどない。
本屋に入っていくところを何気なく目で追っていく。
ほんの数か月前まであそこは私のポジションだった。
私じゃ駄目なのだろうか。
何か気に障ることがあったのであれば言ってくれればいいのに。
自分より好きな人が他にできたとしても。
宙ぶらりんのまま放って置かれるのはつらい。
自分が辛いと思うことを解消するために相手に行動を願うことはおこがましいことなのかもしれないが。
その日の夜に電話をかけた。
「もしもし。元気にしてる?」
パジャマ姿でベッドに寝そべりながら耳にスマホを押し当てる。
「元気だよ。梨香は?」
「まぁまぁかな。なんか久しぶりに会話したって感じだね。」
「そうかもね。最近ちょっと忙しくてさ。またどこか出かけたいね。」
心なし彼が放つ言葉のひとつひとつが中身を伴ったものではないように聞こえる。
ふとした時に口から洩れてしまった空気のように。
「今週末とかはどう?」
「ん、あぁ。今週末ね。どうだろう。」
「どうだろうって…。そんなに会うのが嫌になったの?」
つい、むっとして言ってしまった。
「何か嫌なことがあればはっきりと言えばいいじゃない。そんなに信用ないわけ?」
急な感情の高ぶりを自分でも制御できなかった。
たまにこういうことがある。
普段は大人しく真面目に振舞っているけれどカチンとくると最後まで言ってしまうまで心の収まりがつかない。
「そ、そういうわけじゃないんだけどさ…。さら..。」
がちゃん。
言葉の途中で切った。
こういうところだ。
今週末も会えそうにないというだけで機嫌が悪くなるのを抑えきれない。
もう17歳にもなるのにおもちゃを買ってもらえない子供のようだ。
再来週は自分の誕生日なのに。
もしかするとその日も会えないかもしれない。
初めてできた彼氏と過ごす誕生日。楽しみにしていたのに。
そもそも自分の誕生日を伝えた記憶がないので相手が知らないのも無理はないけれど。
「再来週の…。あ、切られちゃった。」
怒らせてしまったかな。
再来週は梨香の誕生日。
初めてできた彼女の誕生日。
記憶に残るようお祝いをしたいと思っている。
なので当日までこのことは黙っているつもりだ。
「喜んでくれるかな。」
何をするかはまだ決めることができていないけれど精一杯のことはしよう。
「きっと喜んでくれるだろう。」
明日も放課後、本屋に寄って優ちゃんと作戦会議をする。
こういう時に異性の幼馴染の存在は頼もしい。
知識も経験も少ない10代の男子だけでは思いつかないような案がたくさん出てくる。
けれど大切なのは優ちゃんと梨香は全く別の人間だということ。
実際優ちゃんにも
「私とこうやって過ごす時間をもっと彼女に使ってあげたほうが良いと思うよ。喜ばせたいという気持ちももちろん大事だけどまずは二人で一緒に居てお互いを知っていくことが大切なんだから。」
と言われた。
女の子という共通項があったとしてもそれ以前に1人1人の独立した別の人間である。
当たり前だけれど。
女の子という共通項だけで括るには範囲が広すぎて参考になる点は思っているより少ないのかもしれない。
みんなそれぞれ違う気質や考え方、経験を持っているのだ。
付き合い始めてまだ3か月。
一緒に居る時間はもっともっと少ない。
そもそもその期間だけで彼女の好みの傾向や彼女が何に対して良いと思うのかを自分たちだけで考え突き詰めることはあまりしない方がいいのかもしれない。
今僕がすべきことは幼馴染の女の子と一緒に彼女が喜びそうなことを想像するのではなく実際に彼女の傍で同じものを見て何を感じるのかを2人で共有することなのではないかとそう思った。
本屋に入る時、本屋から出る時、優ちゃんの家に入る時、どこからかなんとなく視線を感じたような気がした。
ここ数日何度か感じていたことだった。気のせいかもしれないが。
「見られている?」
一体誰に?
いつもはあまり気にならなかった視線だが今日は違った。
嫌な予感。
来週は遂に梨香の誕生日。
できることだけのことはやった。
喜んでくれるか。
家に帰りベッドで横になっているとスマホが震えだした。
「梨香。どうしたの?」
普段なら電話する際は事前に約束するのだが急な連絡は珍しい。
「明日の夜12時頃に○○公園にきて。」
「ずいぶん遅い時間だね。何かあったの?」
「ちょっと用事があって。」
ちょっとの用事で深夜の公園に呼び出されるのはたまったもんじゃない。
けど最近一緒に居る時間が極端に少なかったため反論はしなかった。
ここは素直に従おう。
「わかった。寒いだろうから風邪はひかないようにね。」
電話が切れた。
感情が読み取れない声だった。無色の声。
ひっかかることなく僕の身体をすーっと抜けていった。
1つの強い意志を持っていた。
強く握った拳の先には銀色に輝く刃物。
そこには自分の顔が映っている。
とても正気には見えないような表情だが集中している自分では気づけない。
「君が私を動かしたんだからね。」
セリフこそは自分の行動を他人のせいにするかのようなものだったが彼女の眼にはもう迷いはなかった。
「大好きなまま。良いイメージのまま。記憶に残しておきたい。」
もうこれ以上大好きな相手を疑って過ごしていくことには耐えられない。
人を疑ってしまう心を持ち続けている自分の醜さに嫌気がさす。
そういうことに耐えて彼とうまく付き合っていくことができなくなった。
人と関係を深く結ぼうとすることに対して向いていなかったのかもしれない。
一人で決断してきたことが多かったから。
家族にも大して愛を注いでもらうことはできなかった。
「もし生まれ変わったら笑顔いっぱいで大切な人に大切だということを伝えることができて、お互いを信じあって、残酷な社会を一緒に支え合って進んでいけるような関係性の人と過ごしたいな。」
拳に力が入る。
休日用で控えめにネイルした爪が手のひらに食い込み赤くなる。
包丁をリュックサックに入れて扉を開ける。
入ってきた光は希望を象徴するようだった。
賃貸マンションの廊下の蛍光灯でしかないのに。
「最後のデートだね。」
1人つぶやきながら。
目を覚ますと自分の体が清潔で真っ白な空間に置かれていた。
ドラマで見るような液体のパックが自分の上にかかっている。
少し動こうとすると腹部が傷んだ。
「・・・。」
目が覚めて自分の状況を認識していく過程で昨夜の公園でのできごとが思い出された。
取り返しのつかないことをしてしまった。
あそこまで梨香を追いこんでしまっていたとは。
もっと2人での会話や触れ合う時間を増やしておけばと後悔したが遅い。
後悔先に立たず。
看護師がきて僕の脈をとる。
「特に異常はないようですね。あと数日療養して血をたくさん作れればすぐ退院できますよ。」
と言った。
年長の看護師のように見えた。
「あの、梨香は?」
看護師は何も知らないというような顔をした。
実際に知らないのだろう。
「あぁ、加害者の方ですか?」
加害者。重い響き。極めて現実的な僕の生活に関与してくるような単語とは思えなかった。
「詳しくはわかりませんが特に大きな事件として処理されていないようですね。」
「よかった。」
身体の力が抜けた。
梨香は僕の目の前から姿を消した。
病室に映るテレビのニュースでもこのことは取り上げられなかった。
警察沙汰にもなっていないことから両親の間で何か話し合いが行われたのかなと想像した。
詳細を聞こうとしてもはぐらかされるだけだった。
退院後学校に行くとそこにはもう梨香の姿はなかった。
当たり前のように日常に戻され、社会のシステムの頑丈さと人間一人単位の脆弱さを思い知ったような気がした。
梨香はこの街から去ったのだ。もちろん僕の目の前からも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
