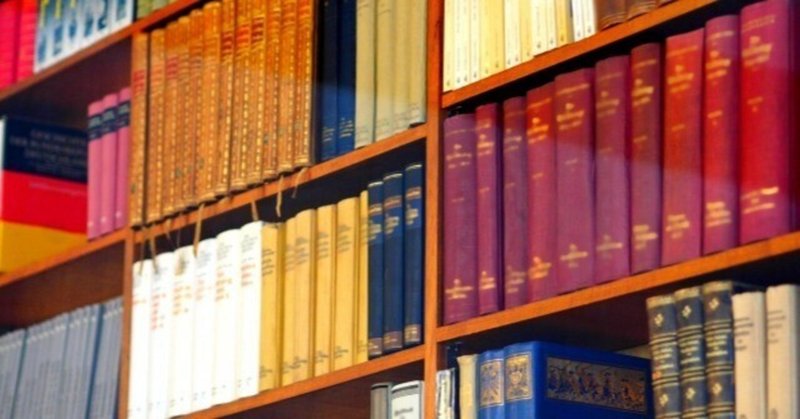
問いかける状況によって、意味を異にする問いがある
最近、「考える」から遠ざかり、少々上滑りをしている感覚の脳みその深いところを刺すような刺激が久しぶりにあった。
問いかける状況によって、意味を異にする問いがある?!
これは、「いかに生きるべきか」という問いに対する小泉仰先生の指摘である。この問いは、経済的に苦しんでいる人にとっては、つくべき職業や金銭のやりくりをどうするかという問いになり、政治家ならば政治的決断についての問いになるという。
私がなぜ突然に「いかに生きるべきか」という問いについて思いをはせることになったかというと、母校の文学部の科目履修生として『倫理学』の教科書を読み始めたからである。さぞかし勉強しているだろうと思って頂ければ嬉しいが、まだ序論である。せっかく受験票を出して登録してお金も払ったのに、5月が終わってしまうので渋々読み始めた。
が、これは、最近「考えてみたいけど、どうやって考えるか全く入り口さえ見つからなかった」自分のテーマの答えが書いてある本なのではないかとワクワクしている。
身近な人が亡くなり、私自身はこれからどうやって生きていくのだろう、とたまに漠然と考えようにったが、私の生活の中に「いかに生きるべきか」という問いを開口一番しゃべってくるような人はいないし、話し相手になってくれそうな人もあまり思い付かない(相談すれば答えてはくれると思うけど)。
何より、日々目の前のことに手いっぱいで、そんな<悠長なこと>を考えている時間が一瞬もない(と思っていた)。しかし、それは学問として成立していた。しかも「序論」!
なお、この問いではまだ不完全であり、全ての人に共通に問うている一つの問いは「正しく生きるには私はいかに生きるべきか」とか、「より善く生きるには、いかに生きるべきか」というもので、これこそが倫理的な問いかけということのようである。
さて、私の仕事は弁護士である。最近は業務の幅が広がり(私が勝手に広げている)、ちょっと資格を持っている起業家ではないかとからかわれることもあるが、取引先が金を返してくれないとか、会社を買いたいとか、はたまた娘婿が不貞しているとか、そんな話に何かしら区切りをつけ、解決することがやはり仕事の一つである。契約書の作成や修正の仕事も多いが、それらも「最終版」、「締結版」がある。
しかし、「より善く生きる」には多分、解決がない。もしかすると、「解決らしきもの」はあるかもしれないが、それは法的解決とは全く違うレベルのことだと思う。
こんなテーマをずっと考えている人が世の中には一定数いて、それが学問になっているというのが新鮮で、別の時空間に入ったような、異国に旅行に来たような気分になった(学生時代に、文学部との共通講義を聞いて、とても面白いと思いつつ、この先に続く現実社会が分からないと思った記憶も蘇った)。
「序論」であるため難解すぎるわけではないけれど、流し読みでは意味が入らない。ひとまとまりを2回くらい読んで、先まで進んでもう1回読むと、何かまた違う発見がある。「こんなこと考えて意味あります?」という素朴な疑問も含め、いちいち面白い。
これから先は、ユダヤ・キリスト教の倫理追究、アリストテレスの倫理追究…と進んでいく。理解できるのかできないのか、納得するのかしないのか、全然わからないけれど、いつでもいけるディズニーランドというか、そんな別世界を見つけたような予感。現実社会で吐きそうになっている大人は、こういう時間が必要なのでは。
問いに対する答えが見つかるのか、ご期待ください!
小泉仰著『倫理学』〔慶應義塾大学通信教育部教材〕より
記事をお読みいただきありがとうございます。少しでもお役に立てたり、楽しんでいただけると幸いです。皆さんからの応援が励みになりますので、是非サポートお願い致します!!頂いたサポートは、活動費に使わせていただきます^^。
