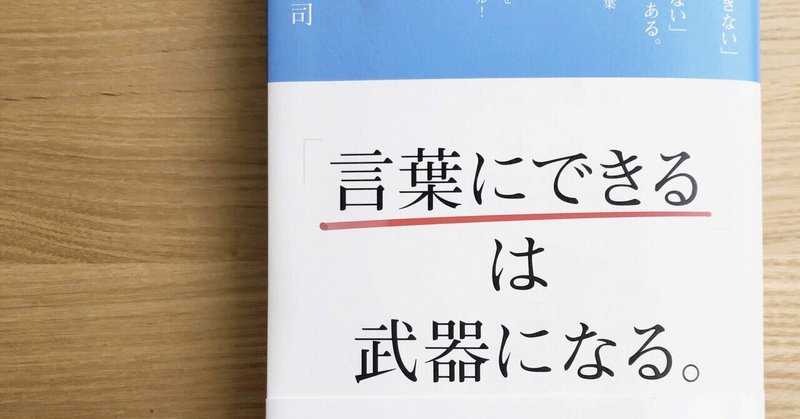
内なる言葉 解像度を高める
【言葉の解像度を高めることは自分という生き物の理解につながる】
レゾナンスで読もうと思ったけど、通読せずにはいられなかった案件ならぬ案本。

『「言葉にできる」は武器になる。』
内なる言葉の解像度を高める。
思考がグルグルしてしまうのは、脳内(記憶域)で回遊しているから。答えは簡単、一旦外に出す。
気持ちを整理し、さらけ出す。
動詞にこだわる。
文末に動詞が来る日本語は、動詞選びがカギ。
「走った」→「疾走した」「ひた走った」「かっ飛ばした」
________________
内なる言葉を磨くための具体的な思考法が満載でした。
こんなことまで教えてくれるんだ!と。
読後感は、電通のコピーライターである著者の文章講座を受講したかのよう。
「言葉は、思考の上澄みに過ぎない。」の一文など、私としては「たしかに!」のつぶやきオンパレード状態(笑)
言葉の解像度を高めようとすると、自分の感情にもっと絞り込んでフォーカスしなくちゃできないから、結果、感情の解像度が高まる。
文章にするということは、自分という生き物の理解にもつながるんだな。
具体的な思考法がたくさん書かれている本ですが、その中からひとつご紹介。
~内なる言葉を磨く思考法~
①頭にあることをとにかく書き出す。
一単語、一文で、紙や付箋などに一枚ずつどんどんアウトプット。
②T字型思考法
本当に?←内なる言葉→それで?
↓
なぜ?
なぜを繰り返すことで抽象度が高くなり、本質的な課題について考えられる。
③グルーピング
書き出した紙・付箋を机に並べ、グルーピング。
横軸~方向性の幅、縦軸~深さ
横に広げて、縦に深める。
④俯瞰して足りない箇所を埋める
(実は同じことばかり考えている、狭い範囲しか見えていない)
⑤時間を置いて寝かせる
(その場から離れる効力。セレンディピティ)
⑥真逆を考える
自分の常識は単なる先入観
(否定としての真逆、意味としての真逆、人称としての真逆)
⑦違う人の視点
「あの人だったら、どう考えるだろうか?」
________________
「解像度は高まった?」
「もっとしっくりくる動詞はない?」
「なぜ?」
「立場が私と逆だったら?」
「あの人だったらどう考える?」
そんな質問を自分に投げかける機能を
インストールしたい。
自分というものを閉じ込めているのは
いつだって自分なんだ。
読んだ本のアウトプット
@makana_suzume_books にて発信中♡
着物、風呂敷、日常については @makarin_o にて発信中♡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
