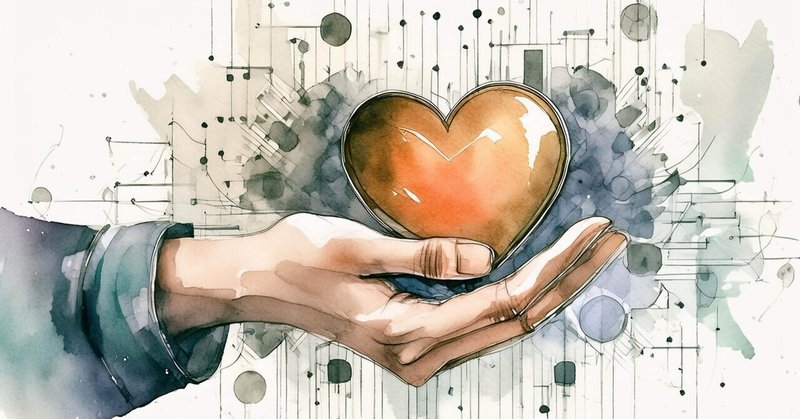
承認欲求 #3/10
次の日、遼圭は学校を休んだ。
体の調子は悪くない。ただ、気分がのらなかった。どんな顔をして聡太と話せばいいか分からなかった。
改めて昨日の自分の投稿を読み返してみると、空虚で薄ら寒いとさえ感じた。大事なものが抜けている。原因は分かりきっている。やはり、その世界は『シンゲキ』の模倣により成り立っていて、意図的に遠ざけたことで、抜け殻のようになった。作品の熱とは、外から与えるものではなく、内側から発せられるものなんだ、と遼圭は思った。
それでも、スキはついた。分かっている。あいさつのようにつけるスキもある。
平日の日中に自室にいると、世界に自分だけが存在して呼吸をしていると思うほど静かだった。こんなときこそnoteに投稿する物語の作成を進めたかったが、全く捗らなかった。
時間だけが過ぎ、外が暗くなりかけた頃に、母親が仕事から帰宅してきた。遼圭は、「夕飯は済ませたからいらないよ」と伝え、再び自室にこもった。
聡太の『顔のない男の子』を何度も読んだ。今はまだ一話しか投稿がないが、連載もののようだ。続きを読みたい。それを素直に〝スキ〟で伝えればいいのだろうが、押せるわけがない。今まで、聡太はどんな気持ちでリークの作品を読んで、どんな気持ちで遼圭の話を聞いていたのだろうか。
顔のない男の子は、鏡の市場で醜い顔の女の子と出会う。女の子は、自身の顔に劣等感を抱いていた。男の子もまた、自分の顔がないことにコンプレックスを感じているが、女の子はそれすら羨んだ。こんな醜い顔なら、なければいいのに、と。
男の子は、その世界の創造主で、なんでも創ることができる。ただひとつ、自分の顔をのぞいて。
男の子は、女の子を美しい顔にすることも可能なはずだ。それなのに、なぜそうしないのか。
なんて自由で罪深い世界だろうか。誰に許される必要も媚びる必要もない。その世界に誘い、怒りや悦び、絶望やあるいは希望を差し出すだけでいい。創作とは、そうあるべきだ。
遼圭のスマートフォンが鳴った。鳴っている。花凛からのラインの着信だ。
切れるまで待つつもりだったが、いつまで経っても着信は鳴り続けた。仕方なく通話のボタンをタップする。
「もしもし、遼圭、具合は大丈夫?」
「ああ、うん。だいぶいいよ」欠席理由は、体調不良ということにしていた。
「今日、寂しかったよ。二人とも休みなんだもん」
「二人? もしかして、聡太も?」
「うん。私を除け者にして二人で遊びに行ってるのかもって思ったけど、違うみたいだね」
「そんなことするかよ」
そうは言ったが、前科がある。中学生のときに二人で学校に行かず、隣町までアニメかなにかのグッズを買いに行った。その帰り道で、あえなく補導された。
「最近、遼圭、ちょっと変だよ。noteもいいけどさ。私にもかまってほしいな。なんて」
「noteは関係ないだろ」
大ありだ。プライベートな時間の大半をそれに費やしている。ただ、そんな生活をいつまでも続けるつもりはない。どこかで区切りをつけるつもりだった。どこで? 満足してこれで終わり、という瞬間はくるのだろうか。スキがいくつついたら? フォロワーが何人になったら? 数字に終わりはない。
「ねえ、遼圭。ビデオ通話できる? 顔が見たいの」
「……いいけど」
顔を見て話したい心理は何だろう、と遼圭は考えた。noteで交流のある人たちの顔をほとんど知らないが、それでも「この人は特別だ」と思える人の顔は知りたいと思う。もし会話をする機会があれば、顔を見て話がしたい。顔のない男の子は……、きっと寂しかっただろう。誰とも〝特別〟になることができないのだから。
「えへへ、やっほー」
スマートフォンの画面の向こうで花凛が手を振った。
「相変わらずかわいいよ」遼圭は、軽口をたたいた。余裕がないときほど、それが出る。
「そうだ。私、かわいい水着買ったんだよ」
「へえ、どんなの?」
「見たい? 実はこの下に着てるんだよ」
「マジで? 見たい見たい」予定調和。意外でもなんでもなかった。
花凛は、ボタンをひとつずつ外して、「ジャーン」と言いながらシャツを脱ぎ、水着を披露した。花柄の黄色い水着だ。
――顔のない男の子は、女の子を美しい顔にしなかった。それは、なぜか。
推測一、予定調和はつまらないから。
「ねえ、花凛。おっぱい見せてよ」
いつもなら、そんなことは思っても言わない。少し困らせたかった。要するに八つ当たりだ。
「だから今見せて……って、え、中ってこと?」
「そうだよ。いつも見せたがってただろ。見せてよ。見たいんだ」
「そんなこと……、やっぱり変だよ、遼圭」
「そうだよ、変なんだよ、俺は」溜まっていたものが吹き出す。「くそ、聡太のやつ。黙って小説書いてやがった。花凛も、いつもいつも……」遼圭は、スマートフォンの画面を見て言葉を失った。
花凛が、水着のビキニトップを外していた。インナーも着けていない。
画面のノイズ越しでも分かる透明感。膨らみのその先端は完全に陥没している。それは、花凛の小さい頃からのコンプレックスだった。花凛が心配していたのは、自分が子供を産んだときに、ちゃんと授乳できるかどうかだった。
「これで満足? 明日はちゃんと学校に来てよね」顔はフレームアウトしている。
「花凛、ごめん」通話を切った。花凛が切ったのかもしれない。
――顔のない男の子は、女の子を美しい顔にしなかった。それは、なぜか。
推測二、自分の気持ちの理解者が欲しかったから。推測三、四……。
自分は今、どんな顔をしているだろうか。花凛には、どう見えていただろうか。
「くそ、なんであんな話が書けるんだよ」
しばらく眠っていた。
カッと目を覚まして飛び起きた。書かなくては。noteを更新しなくては。脂汗をかいていた。夢の中で白けた目を向けられていた気がする。それなら、まだマシだ。そのうち、目も向けられなくなる。
日付が変わってしまう。あんなに時間があったのに。なにも思いつかない。なにも書けない。
遼圭は、すがるようにソータのページを開く。続きが更新されていた。やっぱりあいつ、学校を休んでまで……。
この話なら、この設定なら自分でも書けるのに。そう思って疑わなかった。なぜならそれは、顔のない男の子は、遼圭そのものだったからだ。
チョコレートの包み紙が、ゴミ箱に溢れるほど溜まっていた。どれだけ食べても糖分が足りない。
アナログ時計の秒針の進む音が、徐々に大きくなっていく。まだか、まだか、まだか、まだか。
顔のない男の子。
この話なら自分だって書けるのに。自分だって書けるのに!
――オマージュっていうんだよ。
それは昨日、聡太に言った言葉だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

