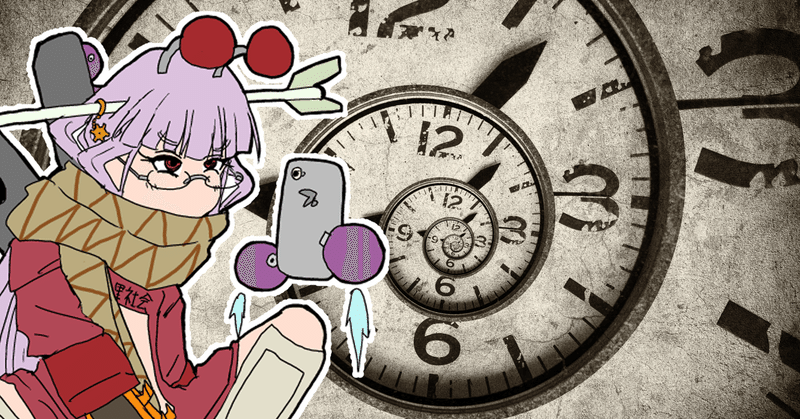
マシーナリーとも子EX ~知る能力篇~
ネットリテラシーたか子はめまいに襲われ、力無く腰掛けた。ファンネル2個が気を利かせブランケットをその膝にかける。なんでこうなるのか?
目の前には知らない少女と、それを連れてきたアークドライブ田辺……かつての部下であり、今は敵対する組織の幹部……がキラキラと目を輝かせている。
少女はたか子をキッと睨みつけている。だがその心の奥底には不安があるのだろう。目尻がピクピクと動いており。膝も少し震えているようだった。チェーンソーに怯えているようだ。珍しいことではない。
「それで……その……女の子、が超能力者だと」
「はい! でもよくわからない能力なんですよ! 本人も困ってるようで……あーちゃん、なにか試してみせてくれますか?」
「ん……じゃそれ、貸して」
あーちゃんと呼ばれた少女は田辺と繋いでいた手を離すと、田辺が肘から下げていたレジ袋に向けて手を向けた。田辺はレジ袋から飲み終わった紙パックのコーヒーを取り出すとあーちゃんに渡す。
あーちゃんはグッと左手に力を込める……。するとみるみるうちに紙パックはボロボロに崩れていき、やがて砂のように風化した。
「ふむ……」
「このように、触れたものを破壊してしまう能力なんです……。私の腕は大丈夫のようなんですが」
「なぜ田辺の腕は大丈夫なのかしら?」
「それがサッパリ。本人も苦労してるそうなのでこの能力の正体を知りたいんですが……。そこでたか子さんのネットリテラシーを知りたいんですよ」
「今のままではなんとも言えないわね。色々試してみないと……。あーちゃんと言いましたね」
「うん……」
「これまで触ってきて壊れなかったものはどれだけあるのですか?」
「そんなもの、無いよ。私が触ったものはなんでも壊れちゃうの……。このお姉ちゃんの手以外は」
「田辺の手以外の部分は試しましたか? 頭とか胸とか」
「触って壊れちゃったら怖いから試して無いよ」
「ふぅーむ……。もう少し様子を見てみましょうか」
たか子はファンネルに指示をすると台所からニンジンを持って来させ、あーちゃんに持たせた。ニンジンは見る見る前に腐敗し、だが悪臭を発するよりも早く乾燥し、やがて風化した。
「有機物と無機物の区別はしないようね」
「そうですね」
「じゃあこれはどうかしら」
たか子はファンネルに指示を飛ばすとあーちゃんの手に収めさせた。
「わわ……」
「ヒィーっ!」
ファンネルは怯えた声を出す。1秒……2秒。ファンネルは壊れる様子がない。
「あれれ?」
「なるほど……。田辺の手と同じですね」
ファンネルはホッとしながらふよふよとたか子の背中に戻っていった。
「田辺、なぜだかわかりますか?」
「はいっ?!」
たか子は我関せずといった雰囲気でボーッと中空を眺めていた田辺に水を向ける。だが田辺はいかにも見てなかった聞いてなかったという様子で目をぐるぐる回していた。こいつは……。仕方なくたか子は田辺を聞き役とし、自分で理論を展開することにした。
「あなたの腕と私のファンネルは、彼女の手で触れても崩壊しなかった……。つまり2045年のものについては壊れないのではないか、と推測できますね。サンプル数は2ですが……」
「あっ、あ……! なるほど! 確かにそうですね!」
「2045年……?」
少女は不思議そうな顔をしている。無理もない。
「と、なると今度はなぜ2045年のものが大丈夫なのかを突き止めなければなりませんね」
「うーん、技術が進んでるからじゃあないですか? 私たち丈夫ですし」
「本当にそれだけが理由かしら? 考えてもみなさい。私達とくらべてリモコンの構造が弱く、壊れやすいというのはまあわかります。でも紙パックやにんじんも壊れるんですよ。紙パックやにんじんの丈夫さは2022年でも2045年でも対して変わりません」
「いや、でも絶対的丈夫さは私達のほうが上じゃないですか。所詮は紙や野菜なんですから」
「ファンネル」
たか子は田辺に返事する代わりにファンネルを飛ばす。2分ほど後、ファンネルは包丁を持ってきた。
「この包丁はプロの料理人が使う鋼でできたものです。青紙という、とくに硬いタイプのものですね。もちろん私達の身体とは比べ物になりませんが、これがある程度丈夫であり、また単純な物質であるということは田辺、あなたにもわかるでしょう」
「それで試してみると?」
「あーちゃんとやら、これを持ってみてくれる?」
「うん……」
少女は少し怯えながらファンネルから包丁を受け取る。少し力を込めると、やはり包丁は錆びていき、最後はボロリと風化していった。
「あ……!」
「風化するスピードはニンジンとあまり変わらない……丈夫さはあまり関係ないようね」
たか子はふぅっと息を吐いた。ほかに考えられる要因は……。
「そうね……。ファンネル。あれを取って頂戴」
「え……? あれですか?」
ファンネルは上に目線(彼に目はないがとにかく目線だ)を向けると戸惑いながら支持された物を運んできた……。
「時計?」
田辺はなんで、と声を上げた。それはリビングの壁にかけられていた時計だったのだ。たか子は田辺に返事はせず、あーちゃんに時計を持たせた。あーちゃんもまた戸惑いながらその手に力を込める。当然、時計は破壊された。
「……で、なんなんです?」
田辺は答えを求めてたか子の表情を伺う。が、そこで田辺はおややと思った。予想外にたか子の目がクワと見開かれていたのだ。
「たか子さん……?」
「……見た? 田辺」
「何をです?」
「いま、非常に興味深い現象が起こっていました。彼女の能力の正体がわかるかもしれません」
「現象お?」
田辺にはさっぱりだった。これまで壊してきたニンジンやら包丁やらと何が違うというんだ?
たか子はファンネルにボロボロになった時計を持ち上げさせる。
「時計が崩れるまでのわずかな間……。時計の針が高速で回転していたのよ」
「針が……回転んん?」
そら不思議だ。回っているようには見えなかった。
「これがどういうことかわかる? 田辺」
「はあ……私には全然見えませんでしたけどあーちゃんの手はすごい勢いで回ってたんですか?」
「え……してない……」
あーちゃんは納得いかないように首を横に振る。たか子はハア、とため息をついた。
「そうじゃなくてね田辺……。……いや、待てよ? 言いようによってはそうとも言えるわね……」
「えーと……たか子さん? 結局どういうことなんです?」
「……つまりあーちゃんの能力は物質を破壊する能力ではなく……手で触れたものの時を加速する能力なのではないか、と推測できるのです」
「時を加速???」
なんのこっちゃ。
「つまり高速で時間が過ぎていく結果……耐用年数が過ぎて壊れてしまうのです。未来の技術である私たちの身体は……おそらくそこに"追いつくことができない"のでしょう。いま、ここにあるはずのないものをいくら加速しても未来には追いつきませんから」
「わかるようなわからんような……」
「そして……"時が加速する"というのはどういうことなのかわかる? 田辺」
「何にもわかりません」
「よろしい。全然偉くないが自分の非を認めるのは徳が高いわよ。時間という概念には様々な意味が含まれていますが……。この能力の場合、司っているのは"時が今から未来に向かう"ということです」
「はあ(わからないけどわかったふりをしておこう)」
「例えばですよ? ニンジンが風化するのに……そうですね、3年くらいでしょうか? 風化するまでほっといたことはないからさっぱりわからないけどね。それくらいかかるとして、その3年が経つ……ということはつまりこの我々の世界にはなにが起きたと考えられますか?」
「全然わかりません」
「よろしい。答えには期待してなかったわ。つまり3年が経つ、ということは……1096日が経過したということ。これはさらに言えば……地球が1096回、太陽の周囲を公転したと言い換えられるのよ」
「公転……」
「つまり彼女の能力は……触れたものを擬似的に超高速公転させている、惑星的に回転させているのではないか、と考えられるわ」
「ええ……。すいません、ちょっと言われてもよくわからないんですが……。だって公転ってのはその場で回ることじゃなくて地球がぐるぐる回ることなんでしょう? 私たちの時間に丸ごと加速するならわかりますけど、触れたものだけが公転って……ええ?」
田辺はしばらく考えてみようと試みたがすぐに諦めて首を捻った。何が何やらわからないのだ。
「つまりそこが"特殊"ということよ。彼女は時を部分的に……無意識に切り取ることができるのよ。おそらく、いつのまにか"触れたものが壊れる"と認識するようになったのね。だからいまの彼女は自分の能力をコントロールできていないとも言えるし、抑えられているとも言えるのよ」
「えっと、つまり……どういうことなの?」
これまで捲し立てられる一方だったあーちゃんはようやく口を挟んだ。時を加速する……というのは、よくわからないが、わかった。自分の力は物を壊す能力ではなかったのか……。しかし、だからといってどうすればいいのだろう?
「そうね……。最初はどーでもよかったけど少しあなたのことに興味が湧きましたよあーちゃん。時間のコントロールと回転については我々も常に意識しなくてはいけないことですから……。そして国連のよからぬ者があなたを確保しようとした理由もわかってきたわ。仮に今のままの制御力だとしても恐ろしい能力には変わりがないもの」
「私、ものに触れるようになるの? 自分の手でなにかを持ったり操作したりできるようになる?」
「訓練すればね。それこそ、こういう領域はトルーの方がノウハウがあるでしょうが」
「そーかもしれませんね」
「でも一朝一夕でできるようなものでもなちわよ、お嬢ちゃん。まずはしばらく手が使えない状態で、ほかの人類に頼らなくても生活できるようになるのを目指しましょうか」
「そんなこと……できるのかな?」
「あら……」
たか子はクイっと両腕を掲げ、あーちゃんに示した。そのダブルチェーンソーを。
「幸い、手を使わずに生活することには慣れていますよ」
***
読んだ人は気が向いたら「100円くらいの価値はあったな」「この1000円で昼飯でも食いな」てきにおひねりをくれるとよろこびます
