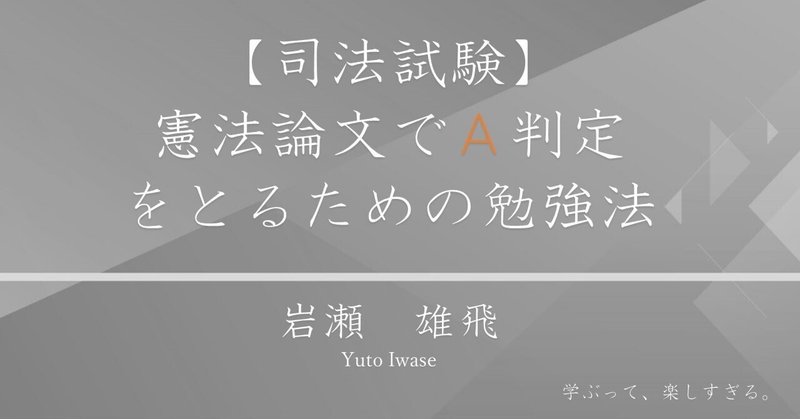
【司法試験】憲法論文でA判定をとるための勉強法
「学ぶって、楽しすぎる。」-弁護士の岩瀬雄飛です。
本noteでは学ぶことの面白さや学習のノウハウ等を発信するとともに、自分が学んだことの記録を発信しています。
今日のテーマは「司法試験 憲法論文試験の分析と対策」。
私が受験したのは平成28年司法試験である。その際の評価は公法系145.09点/200点(憲法A・行政法A)。公法系の論文は比較的得意であった。
しかし、当然ながら現在までに毎年新たな出題がされており、当時の得意が今も通用するとは限らない。。そこで、最近の出題傾向等を分析するため、令和元年以降の司法試験の憲法の問題を確認した。
なお、具体的な内容(例えば●年は表現の自由が出題された、等)には踏み込んでおらず、いわゆる「ネタバレ」にはならないため、まだ過去問を解いていない人も安心して読み進めてほしい。
①基本的なスタイルは変わっていない
問い方にはバリエーションがあるが、基本的には、ある仮定の法令が合憲か違憲かについて①X(当事者。法令により権利が侵害されたと主張する者)の意見をまとめ、②反論を踏まえつつ、③「あなた」の意見を問うものである。
ここで重要となるのは答案の構成である。例えば、何に対する反論なのかが不明確であったり、Xとあなたの意見がまったく同じであったりする答案は、設問の要求に応えたことにはならない。
以下のような構成が一例である。問題に応じて、例えば反論を「営業の自由として保障されるにすぎない」として「あなた」で憲法の何条で保障されるかを論じることもできる。

②判例の重要性が高まっている
私が令和5年~令和元年の「設問」だけを遡って見ていった際に違和感を覚えたことがある。それは、設問中に「判例を踏まえて」という指定が追加されたことである。確認したところ、この指定は平成30年司法試験以降常に入っている。おそらく従前判例を軽視した答案が続出したため、このような「指定」が入ったものだと思われる。

もちろん判例を踏まえない答案は従前から高い点数を与えられなかったと推察される。しかし、「判例を踏まえて」との指定が入ったことで、「あなた」(場合によってはXや反論)の中に判例を盛り込むことが明示的に求められるようになり、これを無視した答案はかなり低い点数をつけられることであろう。
それでは、「判例を踏まえる」とはどのような趣旨であろうか。私見となるが、大きく①定義と②論理構成の2つに分けられると思う。昭和女子大事件(最高裁昭和49年7月19日)を例に考察してみたい。昭和女子大事件を一言で言うと、大学が政治的活動を行った学生を退学処分した事件である。
①定義(判例の言い回し)
昭和女子大事件の中で大学と退学処分はそれぞれ以下のとおり定義されている。このような定義を答案中に使用できると判例を踏まえたことになろう。
大学:国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の目的とする公共的な施設
退学処分:学生の身分を剥奪する重大な措置
②論理構成
より重要なのが論理構成である。昭和女子大事件では大学と退学処分についてそれぞれ以下のような論理構成がとられている。
大学:特に私立学校においては、建学の精神に基づく独自の伝統ないし校風と教育方針とによって社会的存在が認められ、学生もそのような伝統ないし校風と教育方針のもとで教育を受けることを希望して当該大学に入学するものと考えられる
★問題の設定が私立大学にもかかわらず、国公立と私立の違いに言及しない答案や、私立で基準を緩めることに関し言及していない答案は、判例を踏まえたことにならない
退学処分:学生の身分を剥奪する重大な措置→当該学生に改善の見込みがなく、これを学外に排除することが教育上やむをえないと認められる場合に限って選択されるべき
★退学処分であるにもかかわらず、「あなた」が権利侵害の程度が弱いと認定する答案や、合理性があれば許容されると基準設定したりする答案は、判例を踏まえたことにならない
③終わりに
今回の内容が司法試験・予備試験受験者の憲法の学習の一助となれば幸いである。また、憲法の深堀りや他の科目についても今後Noteを作成していく予定である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
