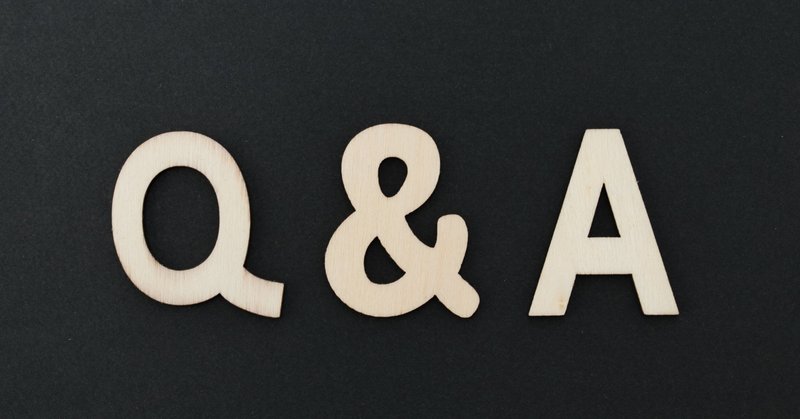
[ビジネス小説]未来へのプレゼン 第20話 質疑応答
前回のあらすじ
SDGsの下調べを各チームがそれぞれ行いながら、プレゼンテーションの形にした。
限られた時間で伝えるためには伝えたい内容を絞り込んでキャッチーに尖らせる必要がある。
しかし、実際に重要なのはそこではなくてそのあとの工程であることを今回のプレゼンではみんなが学ぶことになった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「・・・以上でプレゼンを終わります。」
慎吾のチームのプレゼンが終わった。
リカレント教育プレゼンであったが丸山から矢継ぎ早に質問が飛んできた。
「ありがとう。質問です。」
慎吾は唾を飲み込みながらも想定していた質問であるように祈った。
「今回のこのアプリのリリースタイミングは2022年を想定しているようですが、遅すぎないですか?なぜそんなに準備に時間がかかるのですか?」
「実際に先方の担当セクションに事前ヒアリングを取りました。今回のこのタイミングで弊社から仮にオファーした場合のリードタイムおよびプロモーションを考えると2022年が妥当であるとの見解です。」
「なるほど。その間に別の企業が実施した場合はどうしますか?」
「それは。。。想定しておりませんでした。」
「わかりました。次の質問です。」
慎吾は汗が止まらなかった。
「SDGsのお題ですが、これは単にシニア層をターゲットにしたリカレント教育のビジネスの新規事業提案のように思います。
2019年 6月のG20 大阪首脳宣言の中に、人的資本に投資し、全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を推進するというコミットメントが盛り込まれましたが、今回の提案でこのコミットメントに合致することはありますか?」
「・・・。はい。少子高齢化の日本において、シニア層も働き手として重要な人的リソースとなります。テクノロジーの進展はめざましいため、AIをはじめとしたテクノロジーを用いたサービスにおいて、基礎的な知識やスキルを身につけることは経済成長においても重要な役割を担うと考えます。
その中で、一握りの層の方だけを対象にするのではなく、これまでに十分な教育を受けられなかった方々にも人的リソースとして活躍いただけるベースとしてこちらのコンテンツを提供したいと考えます。」
「なるほど。わかりました。では、最後の質問です。
この事業を当社がやらなければならない理由は何ですか?
他の企業でも良いのではないでしょうか?」
「・・・。はい・・・。確かに、当社が必ず実施する必然性はないかもしれません。他の企業でも実現可能かと思います。しかし、私は、このフロンティアワールドでやりたいと思っています。
『未来への扉を開く』という理念の下に・・・。
私は・・・。
私はリカレント教育で未来への扉を私が開きたい。
そう思っています・・・。」
慎吾は、一つ一つの言葉を自分の中からたぐり出すようにゆっくりと紡ぎ出した。
「わかりました。ありがとう。
慎吾くん。
気持ちは十分伝わります。
だけど。
ビジネスはそれだけでは相手を説得できませんよ。
前回よりはファクトを抑えてロジカルに一見なっているように思います。
ですが・・・。」
丸山は目を閉じながら息を深く吸い込んでから続けた。
「ですが・・・。このレベルの検討では不十分です。
まず、SDGsであることを前提とした場合、2030年というタイムスケジュールをどう捉えるか。
次に、2030年までのマイルストーンをどこに設定するのかが不明確でした。
さらに、持続可能にするための事業の構築として循環するという観点では、あまり魅力的に感じられるものがありませんでした。
そして、当社が実施するよりもこの事業をスケールさせたり、上手にスムーズに回していくことができる企業は当社ではないでしょう。
私は賛同できません。」
慎吾は痛感した。
プレゼンはプレゼン資料でなく、その後のこのやりとりこそが重要なことを。
聞かれたことに対してどう答えるのかの準備が最も大切であることを。
このことが今回の1番の気づきであった。
これは内藤と土屋のチームも同様だった。
メインで話をした土屋は吉田に対する丸山部長の質疑応答を見て意気消沈。
何を聞かれても答えられる自信はなくなっていた。
「土屋さん。今回鯖江市にターゲットを絞りましたが、なぜ他県、他市でなく鯖江市を選定したのでしょうか?」
丸山はまずはターゲットから聞いてきた。
土屋は動揺が隠せない。
「はい。あの。それは・・・。私の幼少期を過ごしたところでして。
ですから、よく事情がわかっているので何とかしたいという故郷への思いもありまして。それで、今回は何とかその故郷の・・・。」
「わかりました。それは縁がある土地の説明であって、鯖江市をビジネス的に選定した理由ではありません。他にも多くの地方都市では取り組むべきところがあるはずです。その中でなぜ鯖江市を選択したのか。
それと、このアクションが成功すれば横展開が可能とありましたが、本当に横展開は可能でしょうか?
都市のサイズや資産、リソース、産業などは異なります。横展開すれば最初に行った鯖江市の差別化要素はなくなってしまいます。
この点についてはどう考えてますか?」
「はい。・・・。あの・・・。・・・。」
土屋はすでに答えられるような状態ではなかった。
「すみません。今回は鯖江市についてのターゲット設定は土屋さんの強い思いがあり、実行に移す際にはその思いが重要であると考えてターゲット設定を行いました。
したがって、他県と比較をしてその優位性からターゲット設定したわけではありません。
また、横展開ですが、もちろんスケルトン化などをそのまま実施することが有効ではないと考えています。差別化要素も薄れてしまいますので、あくまで地方都市のブランディング手法の一つとして実行し、その後そのノウハウをコンサルティングとして横展開することを想定してまいります。」
内藤はすかさず土屋の代わりに答えた。
「では、次の質問です。今回の提案ですが、このタイミングで2030年に間に合いますか?難しいと思いますが、本当に移動手段を新たに構築して実用化に持っていくことが可能ですか?
つまり、あなたたちがコントロールできるものでなく他者の進捗に依存しているため、圧倒的に実現可能性が低いと考えますが、そのリスクヘッジはどうしますか?」
「はい。想定よりも遅れる可能性は十分想定しています。遅れる場合はそのまま事業が後ろ倒しになります。その場合は現行事業を持続させてドローンによる交通手段を待つことになります。」
「内藤課長。それはリスクヘッジではなく、遅れていることを放置しているだけです。それは事業計画を進める意味では無策と一緒です。
では、最後に。」
内藤は先ほどの吉田のチームとのやり取りで想定をしていた。
「では、最後に、この事業を当社がやらなければならない理由は何ですか?
他の企業でも良いのではないでしょうか?」
丸山部長の質問は先ほどと同様であった。
土屋は内藤を見て自分が話すことを目で訴えた。
「あの。。。当社の『未来への扉を開く』という理念ですが・・・。
私は・・・。
・・・誰の未来への扉なのかをいつも考えていました。
それは、私自身のことであり、誰かのためであり、人類全体のことであると思うのです。
そして、揺るぎないものとして、未来というものは誰にでも訪れるものです。
だからこそ、その扉は全ての人に開かれるべきだと考えています。
今回の提案は、たくさんある扉の一つです。
私がこの会社で開けることができる扉はそんなにたくさんの扉ではないと思います。
私にしかできない扉の一つが今回の提案です。
そして、企業がやるべきかどうかですが、その会社の企業理念に基づいた、やりたいと思う社員の念いを実現するのが企業であるべきだと考えています。
企業がやるべきことを限定するのではなく、社員がやるべきことを広げるべきだと私は考えます。
以上です。」
内藤は安堵した。
このことは、二人でチームの中で十分に確認したことだった。
なぜこの提案を私たちがこの会社でやるべきであると考えるのかは重要な出発点だった。
「土屋さん。ありがとう。その会社を動かす気持ちは十分伝わりました。
その念いは素晴らしいです。
ですが、さらに実現可能性を高めること、ステークホルダーの妥当性など検討すべきことはまだまだあります。」
丸山は続けた。
「今回、みなさんがチームで検討したことで、よりその精度、アイデアの柔軟性などレベルアップが見て取れました。その点は十分評価すべきところです。
さらに、この質疑応答にどこまで準備をするか。
準備ができていたか。
みなさんの提案をより良いものにするには、この質疑応答が十分対応できているかどうかが成否を分けることを念頭においてもらいたいと思います。
聞かれたことに対して、的確に答える。
聞かれそうなことを事前に予測する。
プレゼンは発表して終わりじゃない。
その後こそ重要なのだということを理解しておいてください。」
その場にいる全員が深く心に刻んだ。
考えるということは、プレゼンのその先にあるということを。
サポート大歓迎です。!!明日、明後日と 未来へ紡ぎます。
