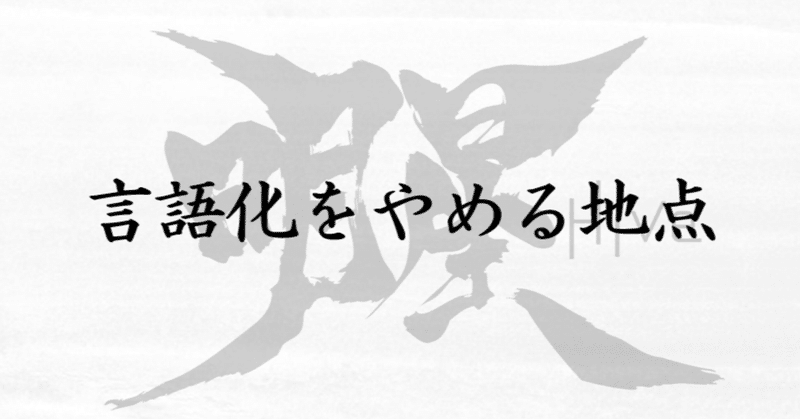
言語化をやめる地点
先週、競技TCG界隈で言語化というツールが過大評価されているが、言語化は完全な唯一無二の方法ではないということについて書いた。
ただ言語化能力とTCGの強さに相関性があることについては同意するところである。では相関ではなく、因果関係として「言語化によってTCGを上達する」とはどういうことか考察してみたい。
はじめに言語化によりプレイヤーはどのような内容の成長をしているのか、次にその地点からどのような試みが可能であるか、最後にどのような目的意識で言語化をするのかについて述べる。
言語化β
既存の概念に対し新しい見解を述べるコンテンツで、「2.0」とつける流行りがある。だが言語化について目的が曖昧なまま、「したほうがいいと強い人が言うから」「強い人がしているから」と漠然と実践されていることが多い。1.0になる前のベータ版と言うのが相応しい。
きっかけとしての言語化
なぜ目的が不明瞭に「言語化したほうがいい」と勧められそれにより上達を実感する人がいるのか?
「何もわからない」というレベルの人が言語化により上達する理由は二つ考えられる。
一つ目は、すごい初心者なので慣れて上達しただけということ。別に言語化せずにやっていてもうまくなっていただろう。身もふたもない。
二つ目は言語化により考えるきっかけを与えられたことにより上達したということ。現実に起こっていることを言葉として表現し直すには一定の思考プロセスを伴う。そのため自分の誤った選択に気付く機会が増え、改善され上達するというもの。
デッキ選択、カードの選択、プレイなどについて、なぜそれをしたか説明してみるというのは、より深く考えるきっかけになる。
あくまできっかけなので、この段階の人は「ゲームが終わったらスクショを撮ってくれ。それでそこに写っているカードの名前でダジャレを考えて欲しい」と言ってもうまくなる可能性がある。最終盤面を繰り返し見るようになればそこに至るまでの過程について考える機会が増えるかもしれないからだ。
誤り検出のための言語化
そこから少し進んだ段階にある言語化による成長として、一貫性の実現が考えられる。各々の言語化された事柄を命題として見てみる。ある命題と別の命題が矛盾するのであれば、いずれかの命題は誤りということだ。
あるとき、「デッキAでは土地枚数は24より多くすべき」という命題を立てたとしよう。また別の時「デッキAでは土地枚数は22枚以下であるべき」という命題を立てたとする。これらは矛盾するので、いずれか(あるいは両方)が誤っていることがわかる。
人の認知は劇的なことをより起こった数が多いかのように認識したり、利得と損失で損失を過剰に認識する。
矛盾する二つの命題を立てたことに気付くことで、そのどちらかあるいは両方の命題を立てた際の認識が歪んでいたことに気付くことができる。こうしてずれた認識を修正し、よりよい判断を下すことができるようになる。
あるいはそれを意識せずとも、矛盾する二つ以上の命題を立てる前にその矛盾を避けて命題を立てる、あるいは既にあるものを修正することで一貫性のある理論体系を構成できる。
プレイングや細部のカード選択にも同じことが言えるだろう。あるところでリソースを理由にテンポを犠牲にする選択をした。そしてまたあるところでテンポを理由にリソースを犠牲にする選択をした。何らかの理由により立場が逆転したのか?だったらよいが、そうでないなら認識が歪んでいるせいでプレイングの一貫性が実現できていないということだ。
負の側面
誤り検出が可能になるのは誤った命題を立てたとき、それと矛盾する命題を既に立てている場合である。矛盾する命題を立てることができていなければ検出できないし、矛盾しない誤った複数の命題を立てている場合もある。論理の妥当性(推論過程が正しいか)と議論の健全性(前提の真偽を含めた全体の真偽)は別のものであるが混合されやすい。
誤った命題を立てた上でそれに矛盾しないように新たな誤った命題を立て理論を構成しているときなんかは最悪である。
人は雄弁な主張を信じてしまうし、一度信じたことの誤りを認めることは難しい。説得力のある論理的(であるように見える)主張を聞いてその穴に気付かずに信じ込んでしまったこと、周りの人がそのようになっているのを見た経験があるだろう。
誤り検出のための言語化の欠陥として人は雄弁な言論に導かれその不完全さや対立する事柄を見落とす傾向にあるものだからだ。一度誤った命題のうえに構築してしまった理論体系を修正することは困難極まる。
人は現状維持バイアスを持っていて現在の主張をそう簡単に変えない。それどころか確証バイアスから現在の考えをより強固にする根拠を優先して集め続ける。誤った認識を持つことはゼロではなくマイナスである。
情報を捨てること
なぜこのような負の側面が存在するかというと、言語化は情報を捨てることであるからだ。
言語化は抽象化である。本来膨大な組み合わせにより一つ一つを記述しきることができない事象の集合を広がりのある単語に写像することで記述するのだ。より一般的な事象についての記述のために例外的な事象に関する情報を捨てるのが言語化である。
存在するカードの全てから起こりうるすべての状況を想定せよと言われても無理な話だ。だから想定するカードをよく使われるものに絞ったり、使用率の高いカードが唱えられるようになるターンに起こりうる事象に想定する内容を絞る。
複雑すぎて論理的な手続きができない対象から情報をそぎ落として論理的なフレームワークに当てはめることができるようにするのだ。

《時を解す者、テフェリー》がスタンダードでリーガルだったときを例にする。このとき、「先攻テフェリーをカウンターできる《神秘の論争》や《否認》を使うべきで、それに間に合わない《イオン化》は使うべきではない。」という記述に同意するプレイヤーは多かっただろう。


ここには《時を解す者、テフェリー》が着地すればその後カウンターは使えなくなるため、3ターン目の着地そのものを妨害することが重要であるという前提がある。起こりうる状況を列挙していけば、3マナが余った状態で対象を唱えられても打ち消すことができる、2点のダメージを与えることができるという《イオン化》の長所が活きることはある。これらが、神秘の論争が優れているという記述の際に重要度の低いものとして捨てられている情報である。
言語化をする者は既知の概念を抽象化し記述可能な形式に写像している。この過程は新たな情報を得ることそのものではなく、新たな情報を得るために情報を捨てて思考領域を限定するものである。言語化そのものによる新たな発見はなく、現実的な時間とリソース内で試行をするために領域を絞る取捨選択がある。
この際に捨てられた情報は過小評価されがちである。それらしい理由付けがされるとそれが真であるように思えるし、確証バイアスがこれを助長する。言語化を通じて理解が深まったと感じることがある。だがそれは本当に理解が深まったのか、それっぽい理由付けにより確証バイアスから都合のいい情報を集めて認識を歪めただけなのか疑う余地があるだろう。
反証と新たな発見
ここまで自分が言語化の主体となる場合について考えてきた。では他人の言語化した情報についてはどうだろうか?
一番初めの言語化の目的は情報伝達のため他者に理解できるような形式に思考を写像することだ。それを受け取るとき我々には何ができるか?
まず目的がその言語化した主体に追いつくことであれば言語の後ろにある概念を想像し理解して自分のものにする必要がある。これは写真に写った二次元の画像から、被写体の三次元の形状を推測することに似ている。写真が三次元から情報の少ない二次元への写像であるように、多くの言語化は記述しきれない複雑な概念を短い文へ写像したものである。ここで、言語化されたことについて追加の説明を求めることは、対象を別の方向から撮影した写真を求めることに似ている。
次にその言語化の主体を超えた新たな発見をするにはどうしたらよいか。まずは自らによる言語化と同じように、その上に立って新たな概念の発見を試みることだ。そしてもう一つが矛盾の導出による反証である。言語化とは情報を捨てることなのだから、捨てられた情報の中から捨てていいほど小さくない重要性を持つ情報こそが新たな情報である。「Aという理由でBである」という定石が出来上がっているとき、Aである場合が十分に大きくなるような理論を組むことができれば新たな発見だろう。
前者より後者の種類の発見の方が刷新の余地がある。言語化する主体は大抵練度が高くその先の考察もしているのでその先へ行く難しさに加え伸びしろは狭い。だが既存の概念の反証については、心理学的要因から他者のほうが容易であることが多い。既存の概念を疑うことが発見の本質である。
余談だが私は《イオン化》が大好きでスタンダードリーガルな間ずっと使っていた。
言語化をやめる地点
自らが主体となり言語化をすることへと話題を戻したい。
言語化は複雑な対象から情報をそぎおとすことだ。ではそれが向かう地点はどこだろうか。
言語化を重ねてより事実を詳細に記述することであるという考えがあるかもしれない。「某というカードはしかじかの状況でああ強い」という記述に対し、「ただしあのカードを相手が使う場合はこうこうという理由で例外的に弱い」という記述を加えたとしよう。これにより現実の事象をより詳細に記述できただろう。ではこれを永遠に続けて起こりえる全ての事象を記述すべきかといえば否だ。第一にそんなことはパターンが多すぎて不可能である。加えてこれは情報を捨てて対象を思考可能な領域にもってくるという目的と反している。永遠に情報を増やして複雑にして行けば本末転倒である。
複雑な対象に対する判断の過程は数行の文に落とし込むことができる範疇の外にある。この複雑さの人に認識可能な情報量からの乖離は、囲碁や将棋の人のプロに勝ったプログラムの話からもわかる。ブラックボックスである深層学習を使用しているため、その判断を過程を人にわかる形で言語化することができない。人のプレイヤーでもそうだろう。なぜその判断をしたかと聞けば何か理由を聞けるかもしれない。だがそこに全くの例外がなく、それに該当する選択が他に何もないことは稀である。その判断の根拠にはなんとなくこうすべきであるという漠然としたものが含まれているだろう。
複雑な対象へのよい判断とは論理と感覚のハイブリッドに他ならない。単純な記述よりは詳細な記述のほうが良いことが多いが、詳細ならば詳細なほどよいというわけではない。言葉による説明をより詳細にしていくことで、記述をよりそれがそうあるように近づけていくことができる。しかしそれを永遠に続ければよいというわけではないということは、どこかにそれをやめるべき点があるということである。これは判断の根拠に占める論理と感覚の割合のトレードオフである。その最適になる点に漸近することが言語化の目的である。その地点ではさらに詳細な記述はせずに感覚に判断を任せるべきなのだ。それは感覚的判断と抽象化し論理に落とし込むことによる検討をいったりきたりしながら漸近する地点で実際に到達はしないだろう。だがこの地点をゴールとした試行として言語化をとらえるならば、言語化の目的は言語化をやめることだと言える。
おもろいこと書くやんけ、ちょっと金投げたるわというあなたの気持ちが最大の報酬 今日という日に彩りをくれてありがとう
