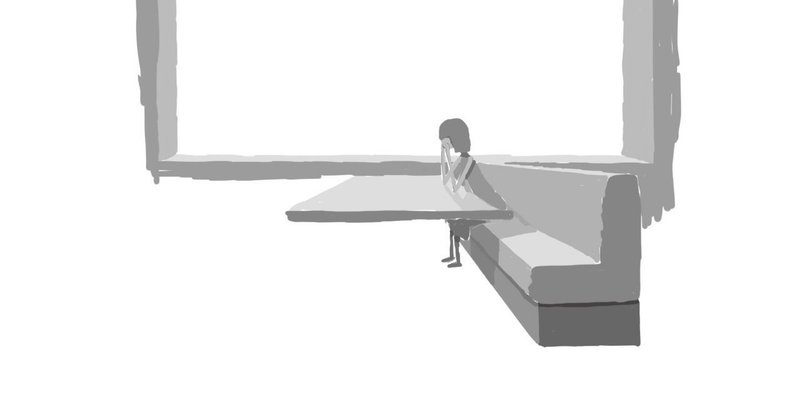
掌編 「もっと好きになっていい」
「直江くん、お金もーけに興味ない?」
と水瀬さんに聞かれたぼくは、絶対に怪しい話だと心の中で確信しながらも、水瀬さんに興味がありますなんて下心を打ち明けられないまま、ほいほいと後ろを付いていくことになった。。
「頑張れば頑張っただけ、沢山お金がもらえるの!」
水瀬さんはそういう人特有の輝ききった瞳でぼくに訴える訳で、一生懸命に見つめられると照れてしまう。見つめないでくださいよ、と口にしつつ、本当はやめないでほしいというのも本心。揺れるのは、繊細な男心なのだが、水瀬さんがそれに気付くはずもない。というか、気付かないでほしい。と言うと嘘になるが。
「だから、直江くんもいっぱい頑張って、お金もーけしようね!」
水瀬さんの説明を聞けば聞くほど、ぼくの確信は深まっていく。彼女の中のぼくが、つまりはそういう存在、カモなのだと。そう気付かされるのは実に苦しい。
「それって、ぼくが頑張ったら、水瀬さんも……うれしいですか?」
言葉を選んだら、変な感じになった。水瀬さんも驚いて、止まってしまっている。
ああ、もう、と心の中であたまをくしゃくしゃする。これじゃあ、水瀬さんだって答えにくいだろ!
「すいません、変なこと言って……」
とそこまで口にして、止まった。
彼女は満面の笑みでぼくを見ていた。
「うん! 直江くんが頑張ってくれたら、私もうれしいよ」
ああ、もうダメだと思った。何をどうやっても、この人には勝てないのだ。水瀬さんのことを好きすぎて、ぼくはもう死ぬしかない。
世界中の不幸や憎悪を集めても、ぼくの好きには勝てないと思う。だって、ぼくの絶望の方が深いに決まっているのだ。何がどうあっても、ぼくは水瀬さんを愛したくて、それなのに絶対に愛されないことだけは決まっていて、核戦争が起こって、人類が滅んで、もう一度地球の生命がアメーバからやり直したとしても、この愛と運命だけは交わらない。
ぼくの好きは深すぎるので、水瀬さんを愛するあまり、水瀬さんへの愛は彼女を突き抜けて、人類愛迄到達してしまう。だからぼくは、彼女を愛しているのに、彼女を愛していないというパラドックスに陥る訳で、それはつまりどういうことかというと、ぼくの愛は誰にも届かない。
そんな訳だから、水瀬さんに誘われたマルチ商法なようなものでも、彼女の養分になることをぼくは厭わない。というよりむしろ、彼女の音に絡め取られて、からからになるまで搾り取られるという想像は、ぼくにとってあまりに甘美だ。
誰からも愛されず、誰にも届かない無価値な僕が、それでも他人の役に立てるとしたら、このくらいの道筋しかボクには立てられない。
ぬるい吐息を感じながら、頭からむしゃむしゃと食べられる。そんな想像は、ぼくの一つのハッピーエンドなのだ。
話しかける口実がほしかった。彼ならきっと、いい働き手になる、そう信じていた。
誰とも仲良くなれて、みんなに等しくやさしい直江くんだからこそ、この役割にぴったりじゃないかなって。
私は自分のことばかりで、いつも話をする人に飽きられたり、怒らせたりしてしまうから、直江くんの気遣いとか優しい所にはすぐ気が付いた。
全部、私にないものばかり。
うらやましいと嘆く私もいた。あんまりうらやましくて、悔しいから、無視しようと思ったこともある。でも、ここで直江くんを誘わなかったら、私はいつまでもダメなままなんだろうなって……。
自分のためじゃなくて、みんなのために。それに気付かせてくれたのは、やっぱり直江くんだった。
少しずつ麻薬を飲ませるようなものだ。誰にでも傷や痛み、弱点はあるもので、ぼくは人に近付いてはそれを暴き、助けるような振りをしては毒を混ぜる。それをやさしさと誤解させたまま、関係を長く続かせるのが、この仕事で業績を上げる一番の方法だった。
いつか中毒を起こしても、痛みが消えた分、それは幸せなのだ、と自分をごまかしながら……。
「お疲れさま、直江くん」
本部に戻ると、水瀬さんが出迎えてくれた。彼女はぼくを勧誘したことで、外へ売り込みにいかなくなった。元々、多くなかった彼女の友人も、ぼくが引き継いで面倒を見ている。最近では、幹部入りも噂されているとか。
「今日の調子はどうだった?」
ぼくは水瀬さんの淹れてくれたお茶を受け取る。
「まあまあですよ」
「直江くんのまあまあは信用できないからなぁ」
うれしそうなによによ顔の水瀬さんに、今日の数字を伝えると、彼女は飛び上がった。
「すごいよ! 直江くん」
顔を綻ばせ、本当にうれしそうにする姿を見て、いい気分になってしまうぼくは、まだ彼女を好きなのだろう。そして、それを知ることができて、やっぱりぼくはうれしい。
他人から吸い上げた不幸でも、水瀬さんが幸せになるのなら、それでいいと考えるぼくは、これでようやく本当に彼女を愛せるようになったのだと思う。
「私が褒めてあげる!」
いつものようにぼくが頭を下げて、水瀬さんの前へもっていくと、彼女はぼくの頭を撫でた。
あたたかな手の平と、神の間を抜ける指の感触が心地いい。
「直江くんの髪はいつ触っても、もふもふだね」
その口ぶりは、本部で扱っているシャンプーを褒めているのだ、と分かっていても、まるで自分が褒められたみたいにうれしくなる。
「今日も直江くんは、沢山の人を幸せにしたんだね」
この人の側にいると、その物語の強い香りにぼくまで酔ってしまいそうになる。水瀬さんは本部と、本部の祀っている神や神話を信じ切っている。だから、こんなに真剣に誰かを救おうと、やっきになるのだ。
そして、ぼくが水瀬さんに忠実でいることで、多くの人を教団に誘い込み、彼らはその救いをお金で贖う。それが幸せなのか、はたまた不幸せなのかはぼくには分からない。
ただ、こうすることでぼくは水瀬さんの側にいられて、幸せを感じているということは確かだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
