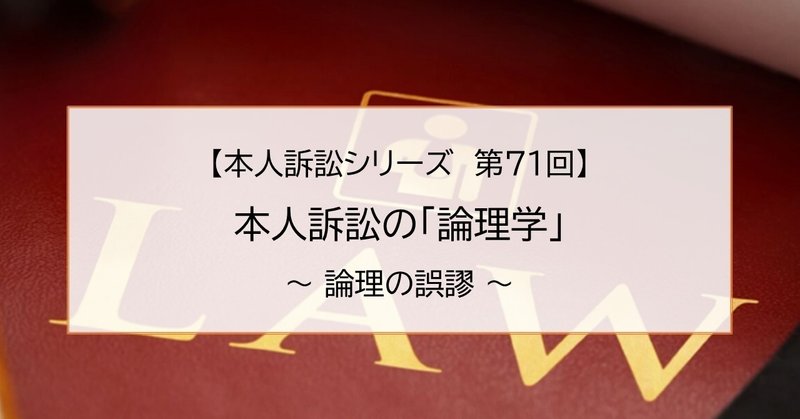
論理の誤謬に要注意!!
今回のnoteでは第67回noteの「三段論法」に続いて、本人訴訟の「論理学」をお届けします。テーマは論理の誤謬(ごびゅう)です。
誤謬とは「妥当でない」「間違っている」といった意味です。論理の誤謬には、以下のようにいくつかのパターンがあります。それぞれ簡単な説明とカッコ内に誤謬の例を示しますので、労働審判手続申立書や訴状、準備書面での文章作成に使用しないように気を付けてください。
論点先取
結論を前提のなかに先に取り入れてしまうこと。「社長はウソツキなんだから、本当のことを言うはずがない」「彼は管理能力があるんだから、部下をちゃんと管理するはずだ」
論点すり替え
本来の論点への答えにはならない論証をすること。「残業代なんか期待するな。誰しもサービス残業をやってるんだ、君だけじゃない。」「給与を勝手に減らされたことで不満を言うな。支給されるだけありがたいことだ。」
標本の偏り
偏った例(標本)だけから結論を導くこと。「俺の周りにはサービス残業をいとわない者しかいない。だから、会社の全従業員はサービス残業を受け入れるはずだ。」
例外の撲滅
一切の例外を無視した一般化をして結論を導くこと。「上司が部下を注意するのはパワハラだ。昨日部下がミスをしたので課長が再発防止について指導した。よって、課長は部下にパワハラをしたことになる。」
早まった一般化
十分な論拠がないにもかかわらず一般化すること。「社長は今月前半は毎日8時には出社したから、月の後半も8時には出社するはずだ。」
誤った二分法
提示した選択肢以外には選択肢がないという前提。「仕事が嫌なら、会社を辞めてしまえ。」「サービス残業をどんどんやって出世するか、いっさい残業しないでずっと平社員でいるかだ。」
合成の誤り
部分の特性を全体の特性として捉えること。「W大学出身の彼は優秀だ。だから同じW大学の学生を採用するようにしよう。」
分割の誤り
全体の特性を部分の特性と捉えること。「喫煙者は仕事が遅いという研究結果がでている。彼は喫煙者だから仕事が遅いはずだ。」
相関関係と因果関係の混同(擬似相関)
相関関係とは、1つが変わった時、その変化に応じてもう1つも変わるという関係です。因果関係とは、相関関係が認められる2つのうち一方が原因、他方が結果という関係です。因果関係には、原因が結果よりも先に発生すること、原因が結果に直接影響するという特徴があります。その点、相関関係は、発生の順番は問われず、また2つには互いに影響がない可能性もあります。
相関関係と因果関係を混同するとは、2つに相関関係が認められることから、それら2つに因果関係もあるかのように錯覚してしまうこと、相関関係があるものを因果関係もあるものと捉えること。
例えば、「朝出社する時間が早い従業員ほど、営業成績が良い」という相関関係があるとします。そうした従業員は、始業前の時間を使って、マーケット情報を再確認しながら顧客への営業トークを練ったりして、入念な準備を行う人が多いでしょう。他方、営業成績が良い社員ほど、顧客の業界を研究したり、個人的にもスキル向上にお金を惜しまないなど、日頃から営業成績アップに結びつく努力をしているでしょう。
つまり、「朝出社する時間が早い」と「営業成績が良い」には、「仕事に対する真摯な態度」という共通の原因が考えられるのです。この「仕事に対する真摯な態度」という第3因子が、相関関係と因果関係を混同させてしまうのです。要するに、「朝出社する時間が早い」と「営業成績が良い」の2つには相関関係がありますが、因果関係はないということです。
因果関係の逆転
原因と結果を反対にして主張すること。「そのプロジェクトに入る従業員が多いほど、そのプロジェクトはより重要ということ。よって、プロジェクトに入る従業員が多くなることが、プロジェクトの重要性が上がる原因となる。」
類推の誤り
重大な相違点の存在を考慮せず類似点をもとに推しはかること。「部下へのパワハラと部下の育成は、上司が部下に対して行うという点で似かよっている。パワハラは違法だ。だから、育成も違法のはずだ。」
統計の誤謬
平均値にだけに注目してデータの分布を考慮しないこと。「うちの会社の従業員の平均年収は700万円もあるんだ。だから、君も新卒で入社すると余裕のある生活ができるよ。」
伝統に訴える論証
これまでの伝統、しきたり、流儀などを根拠に論証すること。「うちの会社は長年トップダウンでやってきて業績を伸ばしてきたんだ。下があれこれ言わず、社長の指示に従ってさえいれば、今後もうまくいくよ。」
権威に訴える論証
権威を根拠に論証すること。「今回の戦略は間違っていない。社長が正しいと言ってるんだから。」
衆人に訴える論証
多くの人々が支持していることを根拠に論証すること。「会社の従業員のほとんどが今年の事業目標は達成できると言ってるんだから、今年も業績アップ間違いなしだ。」
個人攻撃
論点について発言するのではなく発言者個人を批判すること。「君はもっともらしい反論をするが、そもそも先輩に対する言葉使いが失礼過ぎる。」
知性への脅し
反対意見をいう者がいかにも「劣っている」といったマイナスイメージを与えるような言い方をすること。「君はえらそうに反対しているが、ポーターの著書数冊くらいは原書で読んだ上で反対してるんだよね。」
以上、論理の誤謬のうち主なものでした。引き続き、本人訴訟の「論理学」を続けていきます。次回のテーマは「ベン図」です。お楽しみに。
街中利公
PS. 拙著も是非手にお取りください。
免責事項: noteの内容は、私の実体験や実体験からの知識や個人的見解を読者の皆さまが本人訴訟を提起する際に役立つように提供させていただくものです。内容には誤りがないように注意を払っていますが、法律の専門家ではない私の実体験にもとづく限り、誤った情報は一切含まれていない、私の知識はすべて正しい、私の見解はすべて適切である、とまでは言い切ることができません。ゆえに、本コラムで知り得た情報を使用した方がいかなる損害を被ったとしても、私には一切の責任はなく、その責任は使用者にあるものとさせていただきます。ご了承願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
