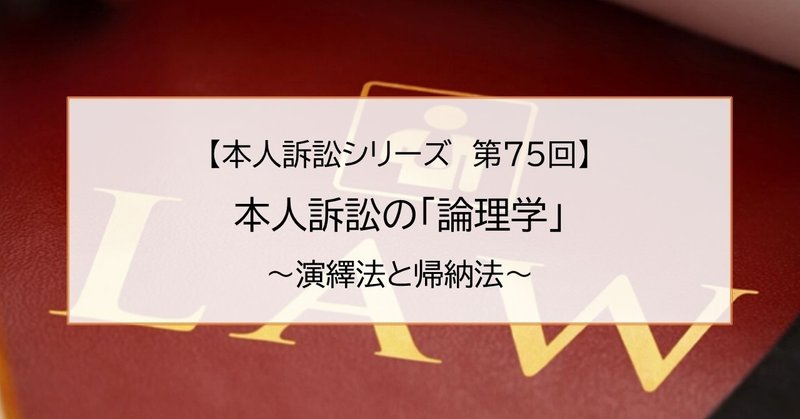
「一般から個別具体へ」の演繹法、「個別具体から一般へ」の帰納法
今回の本人訴訟の「論理学」は、推論の手法である「演繹法と帰納法」を取り上げます。
演繹法とは、観察された事柄をすでに知っているルール(一般論)に照らし合わせて、その観察された事柄がルールに整合しているかどうかで結論を導く推論の仕方です。第67回noteの三段論法も演繹法の一つで、観察された事柄が小前提(A→B)、すでに知っているルールが大前提(B→C)、そしてそこから導かれる結論(A→C)ということになります。一方、帰納法とは、いくつかの観察された事柄の共通点に着目してルール(一般論)を導く推論の仕方です。
帰納法が「個別具体から一般へ」という流れであるのに対して、演繹法は「一般から個別具体へ」という流れとなります。また、演繹法では自動的に結論が導き出されますが、帰納法では結論を導き出すために想像力が必要となってきます。例えば、次のようなケースです。
事柄1: 朝早く出勤する従業員 → 営業成績が良い
事柄2:夜遅くまで残業する従業員 →営業成績が良い
結論:長い時間仕事をする従業員 →営業成績が良い
このケースでは、朝早く出勤して夜遅くまで長い時間仕事をしていますので、その仕事時間の多さが営業成績に結び付いたと想像したわけです。確かに、その可能性は高いかもしれません。
しかし、仕事時間が営業成績に完全に比例するとは限りません。もしかすると、このケースでは、朝早く出勤する従業員と夜遅くまで残業をする従業員の共通点としての仕事に対する真摯な気持ちや熱心さから、休日の空き時間を使って商品知識や顧客業界について研究を重ねているのかもしれません。それが、仕事時間には関係なく、営業成績に結び付いたのかもしれません。
つまり、帰納法では、導き出される結論は一つには限らないことに注意する必要があるのです。
労働審判手続申立書や準備書面といった書面では、帰納法よりも演繹法や三段論法の使用を心掛けた方がいいのではないかと思います。それは、帰納法では、共通点の理解や想像の部分が当事者間の争点になってしまって、結論や立証へ結び付きにくいと思われるからです。ただ、演繹法でも、すでに知っているルール(一般論)が誤っていた場合や観察された事柄が見誤ったものであった場合、たとえ論証の仕方が正しかったとしても、当然に導き出される結論は正しくないものとなってしまいます。
次は、労働審判や民事訴訟で未払い残業代を請求された相手方/被告の会社が持ち出す反論手法の一つ、演繹法の代表である三段論法です。
小前提: 営業課長は、管理監督者にあたります(A→B)
大前提: 管理監督者には、普通残業代は支給されません(B→C)
結論: 営業課長には、普通残業代は支給されません(A→C)
「営業課長は、管理監督者にあたります」という小前提を、会社の役職規程や権限規程、管理職規程などをもとに事実認定する。そして、「管理監督者には、普通残業代は支給されません」という大前提を、労働基準法をもとに法解釈する。そうして、「営業課長には、普通残業代は支給されません」という結論を導き出す。
労働審判や民事訴訟の当事者は、自分の主張が正しいこと、各命題が真であることを証拠と法律を以って明らかにしていって、結論の命題が真であることを立証して、自分の主張が法的に適正であることを論証することになります。優れた労働審判手続申立書や訴状、答弁書や準備書面では、「裏付け→事実→主張」のプロセスにこの三段論法がしっかりと組み込まれている場合が多いのです。
今回は以上です。次回にもご期待ください。
街中利公
PS.拙著も是非手にお取りください。
免責事項:noteの内容は、私の実体験や実体験からの知識や個人的見解を読者の皆さまが本人訴訟を提起する際に役立つように提供させていただくものです。内容には誤りがないように注意を払っていますが、法律の専門家ではない私の実体験にもとづく限り、誤った情報は一切含まれていない、私の知識はすべて正しい、私の見解はすべて適切である、とまでは言い切ることができません。ゆえに、本noteで知り得た情報を使用した方がいかなる損害を被ったとしても、私には一切の責任はなく、その責任は使用者にあるものとさせていただきます。ご了承願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
