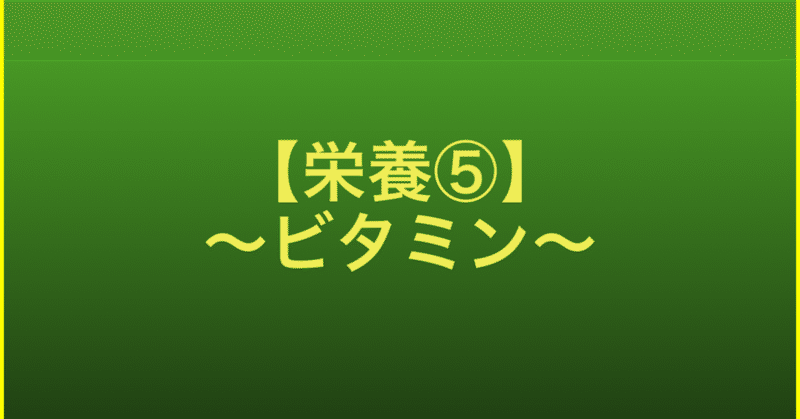
【栄養⑤】〜ビタミン(軽視しがちだが実は大事)〜
埼玉県では、夏の大会の抽選会まで2週間を切りました。
高校球児にとっては、この時期はベンチ入りをかけた勝負の時期であり、またここから夏の大会までケガなどで今までの努力が水の泡にならないように、細心の注意を払わなければいけません。
トレーニング過多などによるケガや、コンディショング不良によるパフォーマンスの低下といったことが起きないよう、1人のアスリートとして栄養面にも気を配ってもらいたいものです。
これまでに「スポーツフードスペシャリスト」と「スポーツフードアドバイザー」の資格取得の中で得た知識や、その他各種セミナーや講演会、野球指導専門誌の特集や連載記事、書籍の中で学んだことを参考に、私自身の頭の中のアウトプット・整理整頓・アップデートも兼ねて簡単にまとめてみました。
少しでもご参考になれば幸いです。
前回までは「たんぱく質」「炭水化物(糖質)」「脂質」について書きましたが、今回はたんぱく質・糖質・脂質とともに五大栄養素の1つである「ビタミン」について取り扱おうと思います。
ビタミンは大きく分けると2種類
ビタミンはたんぱく質や炭水化物に比べると軽視しがちな栄養素ですが、体の調子を整える“潤滑油”のような働きをするため、重要な栄養素です。
ビタミンは、大きく分けると2つの種類に分けることができます。
「脂溶性ビタミン」と「水溶性ビタミン」です。
脂溶性ビタミン
脂溶性ビタミンにあたるのは、
① ビタミンA
② ビタミンD
③ ビタミンE
④ ビタミンK
の4つのビタミンです。
脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は、体内に蓄積することが可能なため、不足しにくいことが特徴です。
水溶性ビタミン
一方の水溶性ビタミンは、
① ビタミンB1
② ビタミンB2
③ ビタミンB6
④ ビタミンB12
⑤ ビタミンC
⑥ 葉酸
⑦ ナイアシン
⑧ パントテン酸
⑨ ビオチン
の9つのビタミンです。
水溶性ビタミンは、漢字で書くと“水に溶ける性質”というように、脂溶性ビタミンとは対照的に、水に溶けて排泄されてしまうことが特徴です。
つまり、ビタミンB群やビタミンCなどの水溶性ビタミンは、毎日の食事の中で意識的に摂取しなければならない、ということです。
ビタミンB群&C
それでは、毎日摂らなければならない水溶性ビタミンの中の、特に主要なビタミンB群とビタミンCの働きを個々で取り上げていこうと思います。
ビタミンB1
まずは、ビタミンB1です。
ビタミンB1は、糖質からエネルギーを作りだすのに必要になります。
特に疲労回復に必要です。
ビタミンB1が不足すると、糖質の代謝がうまくいかなくなり、長時間の練習に耐えられなかったり、疲労の回復が遅れたりしてしまいます。
豚肉や大豆製品、緑黄色野菜に多く含まれています。
他に多く含まれる食材には、うなぎやさつまいも、たらこ、カシューナッツなどがあります。
ビタミンB2
次に、ビタミンB2です。
ビタミンB2は、脂質の代謝を助けます。
豚レバーや卵、納豆などに多く含まれています。
ビタミンB6
そして、ビタミンB6です。
ビタミンB6は、たんぱく質の吸収を高めます。
鶏肉、マグロ、サケ、カツオ、バナナなどに多く含まれています。
鶏肉やマグロ、サケなどを食べるということは、たんぱく質だけでなく、その吸収を高めるビタミンB6も摂取するということなので、非常に効率的に感じます。
ビタミンC
最後に、ビタミンCです。
ビタミンCは、コンディショング維持や風邪予防に効果があり、コラーゲンの合成や鉄分の吸収を助けます。
また、たんぱく質の吸収も高めます。
柑橘系の果物や、レバー、貝類、ほうれん草、小松菜などに多く含まれています。

アリシン
アリシンとは、にんにくや玉ねぎ、にら、ねぎなどに含まれる辛みや匂いの成分です。
このアリシンは、ビタミンB1と一緒に摂ることで、ビタミンB1の吸収を助け、さらにビタミンB1の効果を持続させる働きがあります。

ビタミンB1を多く含む豚肉や大豆製品(豆腐・味噌など)、緑黄色野菜と、にんにく、玉ねぎ、にら、ねぎを一緒に使って作られる料理はたくさんあります。
豚の生姜焼きなどがそうですね。
中華料理などに多いのではないでしょうか。
そのような料理は、栄養面において非常に理にかなっているということです。
抗酸化ビタミン
最後に、「抗酸化ビタミン」について記して終わりにします。
「抗酸化ビタミン」とは、抗酸化作用をもつビタミンで、ビタミンA・ビタミンC・ビタミンEがこれにあたります。
ビタミンA・ビタミンC・ビタミンEを合わせて「ACE(エース)」と呼ばれたりもします。
抗酸化作用とは、運動したときに体内に発生する活性酸素を除去する働きのことです。
この活性酸素の増加が疲労の原因にもなります。
つまり、ビタミンA・ビタミンC・ビタミンEなどを摂取することで、活性酸素を減らし、疲労回復の効果が期待できます。

まとめとして
このように、さまざまなビタミンについてまとめてみると、すべてのビタミンにそれぞれの役割があり、それぞれが大切な栄養素であることがわかります。
「体づくりのためにとにかくプロテイン!」だとか「エネルギー補給のためにとにかくタッパ飯!」というふうに、偏った食事(食トレ)をしてしまいがちですが、一番大切なのは、日頃の3食の食事の中で、さまざまな食材を食べて、たんぱく質・糖質・脂質だけでなく、多くのビタミンなどもしっかりと摂取することです。
その方が、せっかく摂取したたんぱく質や糖質もしっかりと体に吸収され、疲労も回復してコンディショングの維持やパフォーマンスの向上につながっていくことと思います。
選手よりも、サポートする保護者の方の協力が不可欠ですが、毎食1品おかず(小鉢)を増やすことから始めてみるのが良いのかもしれません。
ビタミンは、車で例えると“潤滑油(オイル)”にあたります。
車の“ボディー”や“エンジン”、“ハンドル”が錆びついて動かないといったことがおきないように、しっかりと意識して日頃から摂取していきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
