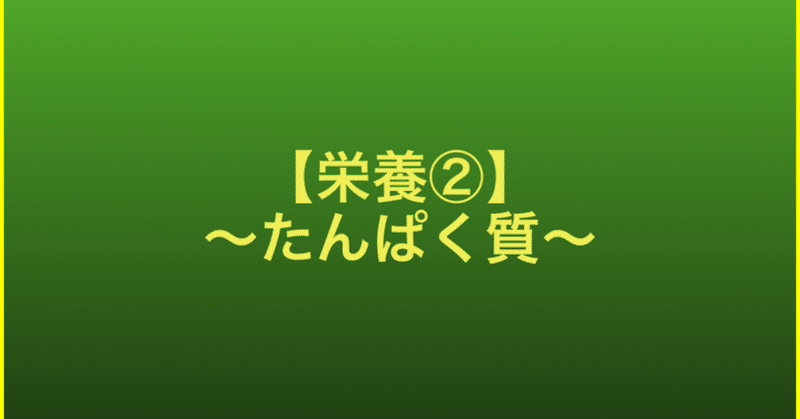
【栄養②】〜たんぱく質(こまめに摂取する)〜
埼玉県では、夏の大会の抽選会まであと2週間ほどになりました。
高校球児にとっては、この時期はベンチ入りをかけた勝負の時期であり、またここから夏の大会までケガなどで今までの努力が水の泡にならないように、細心の注意を払わなければいけません。
トレーニング過多などによるケガや、コンディショング不良によるパフォーマンスの低下といったことが起きないよう、1人のアスリートとして栄養面にも気を配ってもらいたいものです。
これまでに「スポーツフードスペシャリスト」と「スポーツフードアドバイザー」の資格取得の中で得た知識や、その他各種セミナーや講演会、野球指導専門誌の特集や連載記事、書籍の中で学んだことを参考に、私自身の頭の中のアウトプット・整理整頓・アップデートも兼ねて簡単にまとめてみました。
少しでもご参考になれば幸いです。
前回に引き続き今回も、五大栄養素の1つである「たんぱく質」について取り扱おうと思います。
1日に必要な摂取量
筋肉や骨、血液といった、体の材料となるたんぱく質を、スポーツ選手は普通の人より多く摂取する必要があります。
1日の摂取量の目安としては、体重1kgあたり、約1.5〜2gのたんぱく質を摂取する必要があります。
野球は持久力系というよりは瞬発系のスポーツであるため、体重1kgあたり約2gのたんぱく質を摂取するのが良いです。
「体重の数字の2倍(g)」摂る!
ということです。

例として、体重70kgの選手であれば、70×2=140なので、1日に140gのたんぱく質摂るということです。
70kgの選手を例に続けますが、実際に140gのたんぱく質を摂取するにはどうすれば良いのでしょうか?
ここで主な食材のたんぱく質の含有量(100gあたり)をまとめてみると、以下のようになります。
◯ 豚モモ 約21g
◯ 豚ロース 約19g
◯ 豚ヒレ 約23g
◯ 鶏胸肉 約20g
◯ 鶏モモ 約17g
◯ 鶏ササミ 約25g
◯ 牛モモ 約19g
◯ 牛バラ肉 約11g
◯ マグロ 約23g
◯ サンマ 約19g
◯ サケ 約22g
◯ アジ 約21g
◯ カツオ 約26g
◯ ウナギ 約17g
◯ 卵 約12g
◯ 納豆 約17g
◯ 木綿豆腐 約7g
◯ 牛乳 約3g(約100ml弱あたり)

お肉だと、ざっくり計算でおよそ700g食べなければいけません。
ステーキで考えたら、結構な量ですよね。

納豆だけで考えると、だいたい1パック50g程度ですから、20パックになります。
毎日の食事で食べるということは、親御さんがスーパーで食材を調達することになるわけですが、家計のことも考慮すると、鶏胸肉が比較的安価に購入できて手軽に摂取することができます。
また、朝・昼・晩の食事の中だけですべてを賄おうとすると限界があるので、プロテインをうまく活用して液体で摂取することが効率的だとわかります。
一度にすべて吸収されない!
ここで、もう1点押さえておくべきことがあります。
それは、1回の食事の中で摂ったたんぱく質が吸収されるのは“40g程度”であるということです。
夕飯だけでドカ食いなどといった食べ方では、どんなに食べても40g程度までしか摂取されないということです。
つまり、1度の食事で摂取できる量が限られているので、食事を何回かに分けて摂取することが大事になります。
では実際に、先ほどに引き続き70kgの選手が1日に140gのたんぱく質を摂取することを例として考えてみます。
1度に摂取できる量は40g程度なので、1日3食に分けて摂取しようとすると、
朝食40g+昼食40g+夕食40g=計120g
になります。
ですが、これでは1日に必要な摂取量140gまで、あと20g足りません。
この不足分は、朝食と昼食の間や、昼食と夕食の間に、摂取するしかありません。
高校球児なら、学校の休み時間や部活前、練習中の休憩時間、部活終了後に、たんぱく質をしっかり含んだ具いっぱいのおにぎりを食べたり、プロテインを飲んだりして摂取すれば、この不足分を補うことができます。
朝食を抜いたり、軽食で済ませたり、疲れて夕食を食べずに寝てしまったりするのは、言語道断です。
体づくりどころか、体にはダメージを与えたまま、回復するのに必要な栄養すら与えない状態になってしまうので、故障の原因になります。
さいごに
今回は、
◯ 1日に必要なたんぱく質の摂取量は「体重の数字の2倍(g)」。
◯ 1度の食事で摂取されるたんぱく質は40g程度。3食以外にも分けて摂取する。
という2点について書きました。
この投稿を読んでいただいた高校球児たちには、自分の体重をもとに、自分が1日にどのくらいのたんぱく質の量を摂取しなければいけないのかを計算してみたり、その量を摂取するにはどのくらいの食材を食べなければいけないか、3食以外に補食やプロテインを摂る時間をつくれないか、などなどを考えたりするきっかけにしてもらえたら嬉しく思います。
次回は「炭水化物」について書こうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
