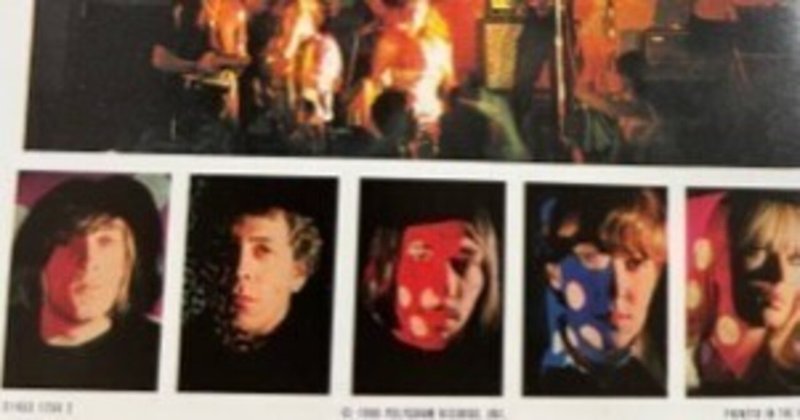
『Sunday Morning』vol.3 【小説】
−東京 1974年−
「三か月、ですって」
佳代が、助手席でうつむいて言う。
こんなふうに恥ずかしそうな表情は、めずらしい。
僕は吸っていた金ピースを、思わず灰皿に擦りつけた。
高校を卒業すると、僕は東京の大学に進学した。
親友の古川が、
「オレは、京都のボンらしく、同志社や
八木、どうや、同志社で一緒にまた、テニス
やらんか」
と誘ったが、姉も母もいなくなり、男ばかりになった京都の家は寂しかった。なにより、姉の不在と、母の死の真相を、ひた隠しにする父と兄を、どうしても許せなかった。
体育会庭球部に入り、八幡山の合宿所で四年間。就職してからも、近くの下宿に移り、週末は後輩と、テニスに汗を流した。合宿所のおじさんおばさんの料理を食べ、今では、ふたりが、僕の東京の両親みたいなものだ。
就職は、体育会の先輩の紹介で、自動車会社に入り、夢中で売っていたら、営業セールストップになっていた。
自分がこんなに、クルマ好きとは思わなかった。
いつも社の新車に乗ることになるので、社内でも派手な人間だと思われているようだが、実は、女性を助手席に乗せたことは、一度もない。
ある日、いつもと同じように、合宿所で学生に混じって飯を食っていて、おばさんに、
「八木くん、紹介したい人がいるんだけど、会
ってみない?
なかなかの美人よ」
と言われ、渡された紙どおりに、その週末、愛車で迎えに行った。
乗り慣れているのか、その人は、当たり前のようにサニーのドアを開け、僕のとなりに滑り込んだ。
「八木さんですか
初めまして、佳代です」
挨拶もそこそこに、
「良かったら、大丸へ行きませんか
今、ちょうど見たい美術展があるんです」
と言う。
「ダイマルって、あの大丸デパートですか?」
「ほかに大丸って、あって?」
ぶしつけな女だ、と思った。
めったにデパートなんか行かないが、大丸といえば、京都の本店だ。子どものころ母親や姉に連れられて、行ったことがある。
オレは、本店のことを言ったんだよ、と胸の内で毒づきながら、車を東京駅八重洲口にまわして、駐車した。
すると佳代が、さっきまでの不愛想とは打って変わり、手を叩いて喜んだ。
「ありがとう
ほんとに、来たかったんです」
弾けるような笑顔だった。
佳代に連れられ、催事場までエレベーターで上がると、得体のしれない、大きな牛の顔が並べられたポスターに、仰々しい文字が躍っている。
―――今世紀最大のスーパースター
アンディ・ウォーホル展―――
美術展など、小学生のころ行ったかも、定かではない。
だが、知らぬ間に、引き込まれていた。
どういうわけか、マリリン・モンローや、ジャクリーン・ケネディなど、僕でも知っている有名人の顔が、何枚も何枚も、並べられている。入口の牛の顔とおんなじだ。そういや、モンローも、ケネディ大統領も死んだんだったな…
佳代は先に立って歩きながら、ときどき僕を振り返り、子どものように目を見開いては、何も言わずにクシャっと笑った。
感想を聞かれたらどうしよう、と思っていたが、そんなことは求めていないようだった。
二人ともひと言もしゃべらずに、すべての展示を見終わると、小一時間が過ぎていた。なんだか、懐かしい感覚だった。
だれかと、黙々と、一緒にいられるなんて、いつ以来だろう。しかも相手は、初対面の女性だ。
そんなこともあるものか…
ふと、古川を思い出した。
喉が渇いたので、大食堂へ行って、ビールを注文した。
佳代と初めて、正面から話すかたちになり、改めて挨拶をと、座り直したが、相手はまったく意に介していないようで、
「美術展、今日でおしまいだったの
明日から神戸に行ってしまうから、慌ててし
まって」
突然、急がせてしまってごめんなさいね、と謝った。
「・・・もしかしたら、昔、京都に来たかもし
れない」
ビールが運ばれ、佳代のために、もう一つグラスをもらい、注いでいると、さっきから、頭の隅に引っかかっていたことが、口から滑り出た。
「僕の姉が、通訳をしていたんです
そのとき写真を見せてもらいました
年は取ってますが、たしかあんな顔のアメリ
カ人だった
・・・そうか、有名になったんですね」
佳代は、およそ詮索をしない女だった。
姉のことを聞かれたら、と一瞬身構えたが、佳代は、旨そうにグラスを干してしまうと、
「枝豆も、食べませんか。
あと、ビーフシチュー」
僕は、ビールも一本追加して、食券を買い、席に戻った。料理を待つあいだも、佳代は口を開かなかった。といって、緊張しているふうでもない。
気づけば、話しているのは、僕だった。
「姉はずっと、入院してるんです。
京都の家を出て、静岡の精神病院にいると
か。
僕の下宿の近くにもある、気のふれた者の病
院と、一緒です」
「そんなふうに、言うもんじゃないわ」
そのとき、初めて佳代が、自分から口を開いた。
「病院の外にいる、私たちの方が、よっぽど気
がふれているのじゃなくて?」
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
