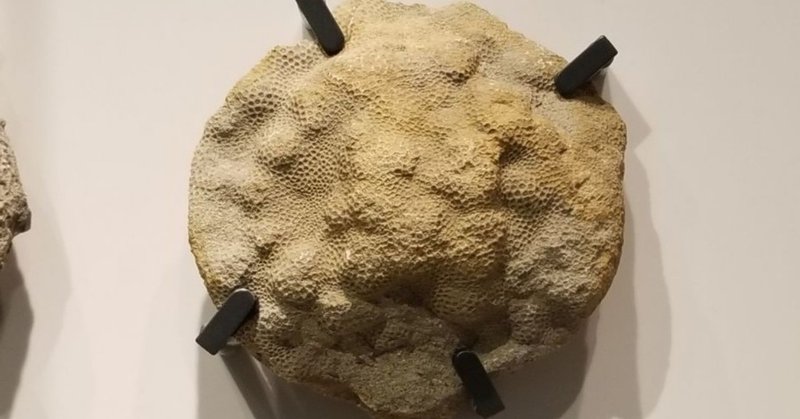
ポケモンソード・シールドはポケモンによる古生物表現の革命である
ポケモンファンの皆さん、アローラ。じゃない。えー、ガァラ~ル~~(ない挨拶)。いきなり新年関係ない記事です。
ポケモンソード・シールドでは、古生物に関する表現の大きな革新が2つもありました。
第4~5世代の頃に「ティラノサウルスのポケモンが出てほしいがトリデプスのようにけっこうひねった姿で出るのでは?」と思ったのがきっかけで、ポケモンのデザインに生き物・古生物のファンとして注目してきました。
そして第6世代で王道とひねりの共存した恐竜のポケモンであるガチゴラスとアマルルガが登場し、ポケモンによる古生物の表現は一度頂点に達したかに見えました。
第7世代では、舞台のモデルが古い地層のないハワイだったためか化石ポケモンは追加されませんでした。
頂点を経て一旦休んだ後の第8世代での古生物の表現は、古生物のポケモンとはこういうものだという今までの思い込みを完全にひっくりかえすものでした。ポケモンと古生物はやはり我々を驚かせる存在です。
今回はその2つの革新について解説してみたいと思います。
化石ポケモンの革新
あまりにも大胆な今回の化石ポケモンはかなり物議を醸しました。
化石ポケモンの元となる化石は4種類も手に入るものの、「カセキのトリ」、「サカナ」は前半身、「リュウ」、「クビナガ」は後半身のみで、前半身と後半身を選んで組み合わせ、1匹のポケモンとして蘇らせてしまうというものです。
蘇った4種族の姿と図鑑説明は明らかに不自然で、一見グロテスクですらあります。一見して、こういう姿と生態のポケモンではなかったはずだと思わせるものです。
とどめに、化石を蘇らせる技術者も名を「ウカッツ」といい、ちゃんとした研究所を構えておらず、白々しい言葉や挑発的なセリフを繰り返すのです。
これはポケモンの生命を弄ぶ描写だとして一部のプレイヤー(または聞きかじっただけの人)の怒りを買ったもようです。
ただし、後述するように、これはポケモンを通じて古生物を表現すること、化石ポケモンとは何なのかを真摯に考えた結果ではないかと私は思い立ち、きちんと確認することにしました。
確認といってもデザインの意図をデザイナーやスタッフのかたに直接聞けるわけではありません。
ポケモンを理解するには触れ合うこと、つまり、ゲームで手持ちに入れることです。
私はストーリー攻略中にワイルドエリアの岩場をさまよい、高レベルポケモンにおびえながらも「カセキのクビナガ」を手に入れることに成功しました。
ポケモンセンターでもらった「トリ」と合わせてウカッツに……あのしゃくに触る胡散臭いマッドサイエンティストに……渡し、パッチルドンを蘇らせました。
細いでんきタイプの「トリ」の前半身が、どっしりしたこおりタイプの「クビナガ」の後半身に冷却され、常に凍えながら鰭の後肢でぎこちなく歩くという、見るからに不憫なポケモンです。
その血色悪くあり続ける頬を見て自らの罪悪の重みを感じながらも、他のポケモンと同じように古生物の名前の一部から取ったニックネームをつけました。
「ルカラス」、アルカエオラプトルとエラスモサウルスから一部分ずつ取った名前です。この2種についてはまた後で述べます。
このような個体を生み出してしまったからには少しでも生きる喜びを感じさせねばなりません。私はルカラスを手持ちから外さず、キャンプで遊ばせ、カレーを食べさせ、ルカラスの嬉しそうな姿を引き出しました。
そしてもちろんバトルです。ポケモンの主人公とはバトルで自己実現を目指す人物であり、おそらくそれだからこそ手持ちは主人公についていくのです。ルカラスも私の手持ちである以上バトルの中で少しずつ輝いていきます。
ルカラス、というかパッチルドンは素早さはやや低いものの耐久面は悪くなく、「ゆきなだれ」という後攻で出せば威力が上がる技を覚えます。つまり相手の攻撃を受けつつゆきなだれで反撃するのが得意ということです。(後に、ゆきなだれとは逆に先に出すと威力が上がる「でんげきくちばし」を覚え、相手との素早さの違いを見極めるのが重要になります。)
同じでんきタイプで初期から手持ちにいたストリンダーの「ルギニ」(エルギニアが由来)とも競合せず、ルカラスは面白みのある活躍を見せてくれました。
そしてムゲンダイナとの戦いでも相手の弱点であるこおり技で押してくれて、そのままチャンピオンとも戦い殿堂入りを果たしました。
ルカラスは自身の冷気に凍えたまま、一体のポケモンとしての栄誉を勝ち取ったのです。
こうして私は、化石キメラたちがまぎれもなく立派な一体のポケモンであると認めるに至りました。
さらに、突飛な化石キメラとの旅を通じて、私は今までの人間に振り回されてきたポケモンについて振り返りました。
まず初代からして、人工的に作り上げられギャンブルの景品にされたポリゴンがいました。ミュウツーやタイプ:ヌルをはじめ、人工的な要素があるポケモンは皆際どい存在でした。
そして、初代で化石からポケモンを蘇らせた技術者はウカッツ以上に胡散臭い人物として描かれていたように思います。
化石から蘇らされてすぐ、知らない生き物であるはずの主人公の手持ちとして戦う化石ポケモンとは一体何なのでしょうか。
ゲノセクトに至ってはプラズマ団に蘇らされて改造を施され、元の姿(おそらくゴキブリ?)が分からなくなっています。
メガプテラの描写からも、化石ポケモンが本当に元のとおりの姿とは限らないことが分かります。
ガチゴラスもおそらく、図鑑説明どおりの剛力無双の実力をポケモンバトルのルールでは発揮できていません。
元々化石ポケモンとは、いやポケモンとは、我々が大なり小なり罪を背負うことで仲間になってくれる存在なのです。
これからも彼らへの愛情といたわりを各々表現していこうではありませんか。
さて、従来の化石ポケモンも本当に元の姿が分かっていると言い切れないのですが、今回の化石ポケモンはまさに元の姿がなかなか分からないという、古生物の復元の悩みどころをモチーフにしています。
すでに指摘されていますが、前半身・後半身のモチーフは下記のとおりと考えられます。
トリ:アルカエオラプトル(鳥類の前半身と非鳥類恐竜の後半身をつなげて作られた偽りの種)
サカナ:ダンクレオステウス(巨大な魚類。前半身は固い骨の板で覆われていましたが、後半身の骨格は軟骨だったようで化石が見付かっていません)
クビナガ:エラスモサウルス(首長竜。脊椎の前後を間違えた骨格図が描かれたことがあり、これが「化石戦争」と呼ばれる熾烈な発掘競争の引き金になりました)
リュウ:ステゴサウルス(背中の骨板の配置がなかなか判明しませんでした)またはダケントルルス(ステゴサウルスと同じ剣竜類でイギリスから腰の部分のみ発見されています)
また「復元の間違え方」のモチーフとして、前後上下が誤解されていたハルキゲニアなどもあります。
姿のモチーフに無関係なハルキゲニアの「間違え方」をウオチルドンに与えることや、尾に頭を付けるというクビナガの姿のモチーフが持っているはずの「間違え方」をクビナガを用いないウオノラゴンに与えることなど、モチーフをそのまま用いない撹乱が施されています。
また図鑑説明も、もし本当にそうだったら生き物として成り立たないので化石も残らないだろうと思わせる、古い図鑑の生き物としての現実味に欠ける解説を連想させます。
このように「間違え方」も現実から丁寧に範を取ることで、「我々は化石ポケモンについて本当は何も知らないのだ」と気付かせるようになっているのです。
しかも、ただ本当の姿が分からないだけではありません。各化石が半身しか見付からないことや、今までの化石ポケモンも断片的だったのに整合性のある全身が再生できていたこと、無理のある姿に見えるのに一応個体として成立してしまうことから、もしかしたら本当に生息当時も妙な体のつながり方をしたポケモンだったのかもしれないという可能性を残し、ますます化石ポケモンの謎を深めています。
全く化石ポケモンとは、いつも我々を驚かせてくれる可能性の塊なのです。
絶滅種の地縛霊のポケモン
化石ポケモンが大胆な表現を行っている一方で、ストレートに古生物を表現したポケモンも現れました。サニーゴ(ガラルの姿)とドラメシヤ系列です。
どちらも太古の海に暮らしていたものの、今は陸上に現れるようになったといいます。そしてどちらもゴーストタイプを持っています。
これらは、住処を失った古生物の地縛霊なのです。「もしもこれまでに地球上に現れた古生物の亡霊が現れたら」という空想を表現したポケモンといえます。
ポケモンでは化石に関連したいわタイプのポケモンを主軸にして古生物が表現されてきましたが、それとは全く別に設定されたゴーストタイプによっても古生物、つまり死滅した生物を表現できるという発想から生まれたようです。
しかも地縛霊ポケモン達は明らかにゴーストポケモンとして独自の特徴を持った種族に変化しています。
「死に絶えているのが特徴の生き物」とでも言ったらよいでしょうか、死んでしまってもゴーストポケモンとしてならそういう種族として存続してしまうという、ゴーストタイプのポケモンの表現がこれまで練られてきたからこその新しい表現なのです。
もしかしたら今までに登場したゴーストポケモンの中にも種族全体が滅んでゴーストタイプに変質してしまったものが含まれているのかもしれません。系列全体がゴーストで生き物っぽいプルリル・ボクレー・バケッチャの各系列あたりが怪しいですね。
サニーゴは人為的な環境変化で絶滅したのだと誤解するかたもいらっしゃるようですが、太古のものと図鑑に載っています。
ドラメシヤともどもワイルドエリアに現れるので、ワイルドエリアの広大な盆地にはかつて海で堆積した地層があると分かります。おそらく「カセキのウオ」か「カセキのクビナガ」と同じ時代のものでしょう。
陸生の「リュウ」「トリ」(これらはモチーフの生息年代が異なります)と合わせると、ワイルドエリアには様々な年代の地層が含まれていることになります。こうした幅広い年代の地層を含む土地として、国内でもいわき市などがあります。
こちらの考察ツイートによると、ガラルサニーゴの詳細なモチーフはハチノスサンゴ、つまりファボシテスではないかとのことです。(冒頭の写真はファビアという別のサンゴですがちょっと似ています。)
https://twitter.com/Sarcopbyton/status/1198341346135658497?s=09
丸い体を持つファボシテスは枝サンゴのような他の地方のサニーゴとは異なりますが、ガラルサニーゴの本体部分とよく似ています。蜂の巣模様がガラルサニーゴの本体にある水玉模様と符号します。
他の地方のサニーゴにとっては生前のガラルサニーゴが祖先に当たるのかもしれません。その一方では、ゴーストタイプになったことでサニゴーンに進化するという新たな生態を得ています。
これぞ「死んでいるのが特徴の生き物」というゴーストポケモンであり古生物であるといえます。
ドラメシヤ系列のモチーフとなった古生物は両生類のディプロカウルスです。ブーメラン型の頭部やサンショウウオ的な胴体を忠実に再現しています。
ディプロカウルスは淡水に生息していたとされていますが、ドラメシヤ系列は海に暮らしていたポケモンがゴーストポケモンとして蘇ったものだとのことです。モチーフそのままになりすぎないようひねってあるようです。
ディプロカウルスの首から後ろの化石は乏しく、体型はあまりはっきりしていないのですが、これが幽霊然とした尾に符号します。またドラパルトでは尾をとても長く大きくすることで、ややもすると凡庸になりかねないトカゲ的体型を個性的なものにしています。
頭部が固いことと、ドロンチやドラパルトがドラメシヤを育てることは、子育てをしていた甲冑魚マテルピスキスをも連想させます。ゴースト、つまり死んでいるのに子育てをするという倒錯があります。
ドラメシヤ系列の重要なもう一つのモチーフが、ステルス機をはじめとする航空兵器です。
ディプロカウルスの頭とB2爆撃機がどちらもブーメラン型をしていることと、「幽霊」と「ステルス」どちらもゴーストタイプにつながることが綺麗に組み合わさった見事なデザインです。しかもB2爆撃機の愛称は「スピリット」、霊魂です。
細部を見ていくと、ドラメシヤはドラパルトに「ドラゴンアロー」で発射される前提でミサイルに似せてあります。両生類の中には幼生の段階で肢がないものも多いことと噛み合っています。
ドロンチの切り詰めたような頭部は小型の固定翼式ドローンが元のようです。
ドラパルトはドラメシヤを収める部分をジェットエンジンの吸入口に見立てています。体の模様もステルス戦闘機の排気口に似せてあります。
ディプロカウルスを元々知って比較的好きな古生物に挙げていた者としては、ドラパルトの強さも感慨深いです。まさかディプロカウルスのポケモンがカイリューやメタグロス、バンギラスと同格の能力値を持つようになるとは思ってもみませんでした。
化石ポケモンと地縛霊ポケモンどちらも驚きでしたが、おそらく次世代で連発はしてこないでしょう。今回これだけ新しいことをしてきたのですから、今後もますますポケモンの古生物表現に目が離せません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
