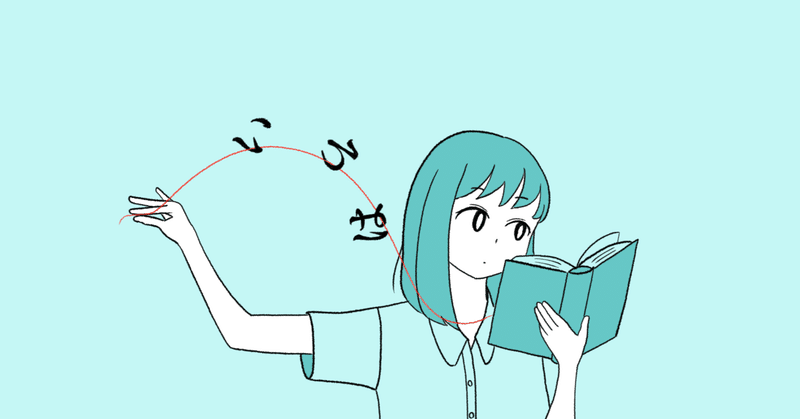
昨日の続き:児童福祉法を読んでみる
【 自己紹介 】
プロフィールページはこちら
このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、600日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。
法律に関する記事は既にたくさん書いていますので、興味のある方は、こちらにテーマ別で整理していますので、興味のあるテーマを選んでご覧ください。
【 今日のトピック:児童福祉法 】
昨日の続きです(昨日のブログは↓)
昨日は、「法律の読み方」について、児童福祉法の27条1項2号を例に出して、いろいろと説明していました。
改めて、その条文を書いときます↓
第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
で、この条文は、↓の①~⑤に分解できることも昨日書きました。
①児童又はその保護者を
②児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、
③又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、
④児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、
⑤又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
昨日は、②の途中で終わっていました。
②及び③は、④の「指導させ」、そして、⑤の「委託して指導させる」、それぞれの実施場所を確定させています。
場所を確定することを示すのが、最後の「において」です。
②及び③は、それぞれ「において」で終わっていますが、それはつまり、場所を確定させていることを意味します。
②は、途中に、「通わせ」とありますが、この「通わせ」前後で2つに分かれます。
昨日は、「通わせ」まで解説したので、今日はその続きです。
で、「通わせ」の後には、「当該事業所若しくは事務所において」と書かれています。
昨日の復習ですが、「通わせ」の前に書かれている「関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所」は、↓の4つをいっぺんに表現しています。
・関係機関の事業所
・関係機関の事務所
・関係団体の事業所
・関係団体の事務所
そこに「通わせ」るわけですから、④の「指導」又は⑤の「委託して指導させる」を実施する場所は、↑の4つのいずれかです。こんなの、わざわざ書かなくてもわかることではあるんですが、②の部分で、わざわざ書いています。
「通わせ当該事業所若しくは事務所において」というのは、こういうことです。
↑4つのどれかに通わせて、その上で、通わせている事業所又は事務所で、④の「指導」又は⑤の「委託して指導」をさせる、というのが、②で書かれているのです。
めちゃくちゃに難しい言い回しだと思われるかもしれませんが、法律って、わかりやすさよりも、一定のルールに基づいて、他の解釈の余地がないように(複数の解釈ができないように)書くべきなんです。
で、なおかつ、文字数も少ないほうがいいんです。
・他の解釈の余地をなるべく無くす
・文字数をできるだけ減らす
この2つを追求しているので、わかりやすさは後回しです。
というか、きちんとルールに従って読み解いていけば、「こういう風にしか読めないよね」という感じで、意味が1つに決まるので、その意味で「わかりやすい」んだと思います。
法律を作っている官僚たちに言わせるとですが(笑)
さて、こんな風に脱線していると、もう終わらないので次に進みます。
次の③は簡単です。②と「又は」でつながっていて、②と同じように、④の「指導」又は⑤の「委託して指導」を実施する場所を特定しています。
②
又は
③
という感じです。②と③は並列です。
②は、「通わせ」と書かれているように、通わせた上で、その通わせた先の事務所や事業所で、④の「指導」又は「委託して指導」をさせることになるのですが、③は違います。
③には、「当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において」と書かれていますが、これも更に分解すると、
a 当該児童又は保護者
b の
c 住所又は居所
d において
に分かれます。aとcが「の」でつながっているので、この場合も、↓の4つを言い表しています。
・当該児童の住所
・当該児童の居所
・その保護者の住所
・その保護者の居所
そして、「において」は、↑の4つ全部の最後に付け加えられるので、結局、
・当該児童の住所において
・当該児童の居所において
・その保護者の住所において
・その保護者の居所において
この4つを、③は言い表しています。③は、このうちのどれか(複数可)を、場所として確定させているわけです。
結局、②と③は、②が「通わせ(通所)」、③は家庭訪問なんです。
通所又は家庭訪問、という形で場所を確定させているのが②と③の役割です。
そして、④と⑤ですが、④と⑤は、指導の方法について定めています。
④は、指導する職員本人に対して指導を命じます。
⑤は、関係機関に指導を委託します。
そういう大きな違いが、④と⑤にはあります。
この大きな視点を踏まえた上で、④をよくよく見ていきます。
④は結構難問です。「若しくは」が2回も入っていて、どれがどう「若しくは」なのか、よくわかりません。
結論から言うと、
ⅰ児童福祉司
ⅱ知的障害者福祉司
ⅲ社会福祉主事
ⅳ児童委員
ⅴ-ⅰ当該都道府県の設置する児童家庭支援センター職員
ⅴ-ⅱ当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員
→に指導させ、
と読みます。最後に「指導させ」が、全部にかかっていくことになるんですが、じゃあ、指導する主体(誰が指導するか)は、↑に書いたとおり、ⅰ~ⅴに分かれていて、なおかつ、ⅴが2つに区分されています。
ⅴの中で、「当該都道府県の設置する児童家庭支援センター」と「当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る」が「若しくは」でつながっていて、最後の「職員」が、双方にかかっています。
だから、
・当該都道府県の設置する児童家庭支援センター職員
若しくは
・当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員
という感じでつながります。条文に「職員」が2回書かれていないのは、1回目の職員は書かなくても書いたことになるからです。
先ほど書いたとおり、条文は、
・文字数減らす
を目的としているので、「職員」という2文字でさえ、書かなくて済む方法があるのなら、その2文字を削ります。
削ってわかりにくなったとしても、ルールに従って読めば意味が通るのなら、それでいいんです。
で、最後に⑤ですが、⑤は、「委託して指導」を定めると同時に、委託相手を確定させています。
委託相手は、↓の4つです。
ⅰ市町村
ⅱ当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター
ⅲ当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者
ⅳ前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者
このⅰ~ⅳを相手に、委託して指導させることを⑤は定めています。
さて、解説はこの辺にします。
今回は、単に、法律の書き方ルールに基づいて、読み方を解説しただけですが、本当は、こういった「読み方」に加えて、各単語の意味も確定する必要があります。
例えば、先ほど、「住所」と「居所」が別の概念として用いられていましたが、それぞれの意味を調べる必要がありますし、「厚生労働省令で定める者」と書かれていれば、当然、「厚生労働省令」を読みます。
とても大変な作業に思われるかもしれませんが、まあ、僕らの業界では、普通です。
こうやって、ひとつひとつ読み方を確定させ、同時に、使われているひとつひとつの言葉の意味を確定させる。
それが、「法律を読む」という作業で、ここに精通しているのも、弁護士の大きな強みなのです。
それではまた明日!・・・↓
*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*
TwitterとFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。
昨日のブログはこちら↓
僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。
━━━━━━━━━━━━
※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。
毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。
サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!
