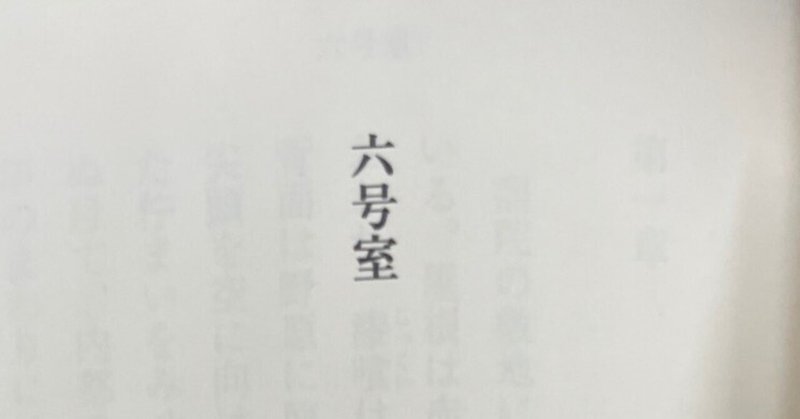
六号室 チェーホフの偉大さ
”偉大さ”とは、何も全知全能であるとか、誰にも真似できないことを成し遂げたとか、そういうことを指しているのではない。少なくとも、私の中では。
では私の中で偉大さとは何を表すか、それは自分とは全く種類を別にする他者を知ろうとする試みのできること、または実際に知ってその他者の気持ちを汲み取ることができること、である。
チェーホフの六号室を読んだ際、私が彼に見出した偉大さとは、まさにこの点にあり、彼は知性と大衆性、鈍さと鋭さ、生と死、両極にある二つの概念をきっちりと理解し、それを一つの物語にして(私に共感まで覚えさせ)、叙述している。少なくとも、私はそう感じる。
以下、六号室を読んでから、見た前。
この本はいわばラーギンとイワン・ドミートリチという、前述したような正反対の概念、環境を抱える二人の人物が、『物を考える』という点において(少なくともラーギンの側からは)、認め、話すというところに、さわりがある。(さわりというのは、冒頭部分、という意味ではなく物語の核、聞かせどころ、という意味であることは、あまりにも有名な話である。)
ラーギンは、いわゆる”生活”というものを知らない、比較的苦労を知らずに、学問を追求してきた者だ。
対してイワン・ドミートリチは、”生活”を知っている。環境的、精神的にも苦しむだけ苦しみ(これは一応は彼の主観であるが、読んでいてもその苦労は客観的にも保証される苦労である)、それでも学問を追求してきた。学問を追求してきた、というのは、つまりありとあらゆる本を読んで、思案する、と言うことをここでは指す。
そんな二人は題名にある六号室という精神病棟のような離れにて出会う。この病棟は腐敗していて、孤独であり、凄惨だ。最初ラーギンは医者、イワンは患者という立場だが、やがて二人とも患者となってその六号室に眠る。勘違いしないよう言及しておくが、彼らは決して友達などではない。再度書くが、『物を考える』という点のみにおいて繋がっている二人である。
彼らの思想を端的に表すと、まずラーギンの方は「安らぎと充足は人間の外にあるのではなく、その人の内部にある。」というものだ。私は高校生の時分、林修氏に現代文を習っていたが、彼はよくこういっていた。「優秀な人間は、環境に文句を言わない。」
つまりラーギンは、知を一点高尚なものとし、それ以外のものは些末なことに過ぎない、としているのだ。その知は、外部ではなく、それを伴っている人の内部に存在する、だから知を備えている者は、痛みや苦しみにも鈍い。シベリアの極寒であろうと、悪臭垂れる劣悪な”病棟”であろうと、自らで安息を生み出すことができる。こんな具合であろう。そしてそんな人物を、林修は優秀であると形容している。
ここで私は、何だかショーペンハウアーの幸福論を思い出すのだ。詳述はしないが、彼も本当の幸せはその人の内部にあると述べていた、”出来事”というのは取るに足らないことだと。
一方、イワンの方は、我々人間は有機体である以上、あらゆる刺激に反応するのは当たり前で、それが「生きる」ということだ、と述べている。感覚の鈍いのは、有機体の中で下等なものである、鋭さこそが生だ、ラーギンの言うような知は生活を知らない、生きると言うことを知らない机上の空論だ、と。
物語では、ラーギンは結局「六号室」と言う隔離された離れにおいて、自らの考えを実践することができずに、つまり環境に耐えられず、自ら安息を生み出せずに、死んでいく。イワンの言う通りであったわけだ。
もしかすると彼ら二人は対ではないのかもしれない。人間という生き物を考えた時に、やはり根を辿ればどれも同じなのかもしれない。では何が重要なのか、何が私たちを規定するのだろうか。
私の話をすれば、私はラーギンとイワンのどちらの要素も持った人間であると言える。ラーギン側に立つと、確かに私は何不自由なく暮らしてきた。あるいは本を買える金もあった。これは客観的であり、相対的な話だ。イワン側に立つと、確かに私は精神を参らせるほどの絶望に近い、近いと言うのが重要であるが、経験をしたことがないとも言えない。生活の苦しさだって、一人暮らしを始めてからは、大体わかる。これは主観的であり、(私の中で)絶対的な話だ。
であるから、どちらの肩を持つこともできる(賢明な読者であれば気がついたであろう、確かに私は自らの中に”偉大さ”を多少なりとも見出している。それがナルシシズムと言われれば、そうなのかもしれない。)。敬虔に生きることは難しいし、理想はいつだって高く立ちそびえる。
そんな私に(我々に)、チェーホフは六号室と言う物語の締めくくりとして、こんなささやかなものをプレゼントしてくれた。
先ほど述べたラーギン、病棟で死んでいったラーギン。彼の葬式には、一人の友人(友人とここではしているが、決して仲睦まじい気の置けない仲ではない。一方的な厚意を元にした関係であり、ラーギンの方からは時にいい迷惑な存在である)と、一人の女(物語中では恋愛描写はないが、恋人、としても過不足はないであろう)の計二名がやってくる。
これが答えではないだろうか。随分とシンプルな答えだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
