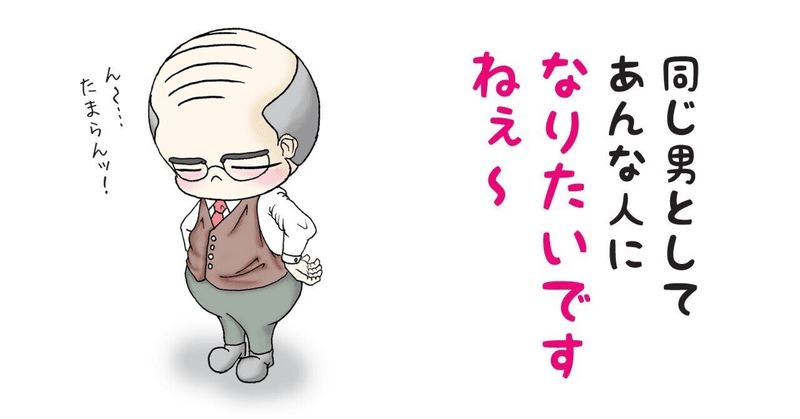
期間限定の公開になるかもです。
まずは、独立おめでとうございます。
サラリーマンを続けた人生に、感謝とお礼を申し上げます。
そして、新たな歩みを始める前に、これを贈ります。
会社員からフリーランスを始めるために必要な情報です。
会社に在籍している間なら、舵を切り替えることが容易なことも、
退職後は難しくなる(年数がかかる)こともあります。
これからの、予定を組むための情報としてお使いくださいね。
出勤最終日までに、退職受付窓口へ、次のことを手配します。
●退職届けの提出
●離職票の依頼
●任意継続の意思表示と手続きの説明を依頼する(任意継続の場合)
有休休暇、ゆっくり何もしない時間を満喫して、
ぼーっとする時間を楽しんでください。
楽しみつつ、会社名が肩書の間に次のことを計画、算段してください。
● クレジット申請、賃貸契約、ローン購入は済ませる
● 社会保険と比較して、健康保険の持ち方を決める
● 失業給付は必須で申請する
退職後は、計画・算段を実行します。
● 失業給付金の手続き
● 初の確定申告の後、開業の手続きは収入と相談
● 税金の種類を知っておく
●その他
● クレジット申請、賃貸契約、ローン購入は済ませる
社会は、個人の名前で信用を得るのは難しい。
会社名や、給与を収入保証の肩書として信用している。
クレジットカード、賃貸契約、ローンの購入は、
肩書があるうちに済ませる。
● 社会保険と比較して、健康保険の持ち方を決める
退職後は、会社の健康保険と比較し、
健康保険を4つのパターンで選択する。
※ 会社の健康保険:会社と従業員で50%の折半で保険料を払う。
扶養家族、傷病手当金、出産手当金の補助が付いた健康保険。
保険料は収入額で決まる。
パターン1:国民健康保険(手続きに離職票が必須)
退職月の翌月から国民年金と共に役所で手続きする。
扶養家族の概念はなく、100%個人負担x家族人数=保険料になる。
(保険料は世帯単位で納付)
また、保険料は、前年の確定申告からの算出金額+世帯負担額(固定)で
決まる。
パターン2:任意継続
会社の保険を100%個人負担で2年継続する。
手続きは、対処日以降20日以内。
ただし、昨年の収入>今年の収入の場合は、確定申告後、4月納付分より
国民健康保険に切り替える。(保険料を低額納付にするため)
パターン3:健康保険組合
開業届けを出して、職種系の組合に登録して、被保険者となる。
保険料は一律。
パターン4:短期就労
4時間/日に仕事を切り替えて、健康保険と厚生年金を確保する。
独立の仕事が安定するまで2足のわらじになる。
その他:扶養家族
可能ならの家族の扶養になるのもひとつ。
収入に制限がつくので要注意。
自分の健康保険に、扶養家族を入れる場合も、収入の制限は同じ。
所得税の範囲:103万〜201万円までが控除対象(満額控除は150万円)
※106万円が勤務先の社会保険加入義務発生額(毎月の働き方で、
常時この106万円を保つ見込みがあると判断された時点で加入となる)
扶養家族の範囲:年間の収入が130万円を安定的に超えそうと判断されると注意。
年金の範囲:所得が48万円以下(65歳以上の場合:年金収入158万円、
65歳未満の場合:年金収入108万円)
● 失業給付は必須で申請する
必要、不要に関わらず、離職票は申請する。
※国民健康保険の手続きに必須のため。
● 失業給付金の手続き
国民健康保険手続き後に、失業給付金の手続きをする。
(失業給付金は非課税)
失業給付金の申請期間は、退職日から1年は有効。
収入と相談しつつ、手続きのタイミングを図るといい。
資金調達や、期間待機のために会社員やパートをした場合、
短期でも離職票を作成してもらうこと。
※離職票の有効申請期間内なら、給付に必要な期間を合算できる。(離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月が6ヶ月以上)
● 初の確定申告の後、開業の手続きは収入と相談
開業の手続きは、収入が安定してからでいい。
事業税の納付義務が発生するのは、所得が290万円以上。
所得税が発生するのは、年間所得が48万円以上。
所得=収入−必要経費
● 税金の種類を知っておく
開業届→税務署(国税の所得税、消費税)
法定事業に該当する場合で、所得が290万円以上に納付が発生する。
一年未満の事業主は、290万円/月割になる。
事業税→物品販売:税率5%
※事業税は、作家、ライターは0%だが、記事を請け負って書く場合は、請負業扱いになり、5%の納付対象になる可能性が出てくるかも?と職種の扱いや、状況により変わってしまうあやふやな税金。
しっかりと、自分の業種を見極める必要がある。
事業開始等申告書→自治体の税事務所(都道府県税の個人事業税)
個人→住民税、健康保険、年金
収入のより納付額が変動する。
納付が不要になる場合あり。
フリーランスになると、収入は不安定を伴い、
とても大切なものになります。
納付の税金は、「待った」をするにも手続きが必要ですし、
遅れれば、遅延金が発生して、収入にダメージを与えます。
しかし、税金は、確定申告の経費としての顔も持っています。
納付のタイミングをしっかりと、見定めること、
どの税金が経費に該当するのかを知っておきます。(領収書は保管が必須)
納付のタイミング
※例:2024年7月31日退職、国民健康保険加入の59歳の男性、扶養家族1名。
所得税、住民税、事業税、消費税、健康保険、年金を支払うタイミング
●毎月の支払い:国民健康保険・国民年金
8月1日の健康保険、年金保険の加入先に納付になる。
なお、誕生日で、国民年金の納付期間は、満了となる。
●6月8月10月翌年1月の支払い:住民税
2024年7月の対象まで給与で、その後は個人納付に切り替えになる。
2023年の年末調整で、2024年6月から2025年5月までの
納付額が確定している。(2024年度の納付額)
●8月11月の支払い:県に収める事業税(事業税に該当しない職種や利益が290万円以下は非課税)
事業開始等申告書は、その仕事で、安定した収入を得て、
生計を営んでいると認識できてから。
●毎翌年3月15日までに支払い:所得税
確定申告で申請する。
基礎控除、社会保険料、経費など、控除金額で、所得税が決まる。
●2026年3月31日までに支払い:消費税
2024年(法人の場合は2024事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているか、2025年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、2026年に課税対象者。インボイスの申請が必要となる。
免税事業者:上記の条件を満たしていない事業者のこと。
特例:給与から生命保険料天引きの人は、銀行振替に移行することを
保険会社に連絡する必要がある。(在籍中に)
保険料が、5%〜10%の増額がある。(団体扱いの割引適用が外れるため)
給与天引きや、自動引き落としに慣れていると、納付を忘れがちです。
毎月支払い以外は、しっかりと予定を立て、
支払い月を意識している必要があります。
特に消費税は、課税対象者かどうかを自分の認識に頼ります。
能動的に動くことで、忘れた後の、怖い追徴税を回避しましょう。
その他
自宅で仕事をするあなたに。
私生活と仕事を時間の線引きしましょう。
1日24時間の1/3を仕事に割り振りします。
自宅に仕事場を作った場合、会社に在籍しているときより、
値上がりするものがあります。
そう!
水道光熱費と言われるものや、消耗品にあたるものです。
勤め人の時間帯は、会社使用だった、自宅のものです。
当然、購入金額や支払い料金は、在宅時間が増えた分、増額になります。
増額は、仕事に関係した金額ですから、経費になるのです。
経費は、家事按分とします。
?となるなら、いくつか例を出してみます。
通信費:インターネットの回線代とか、プロバイダーの料金
月額9,000円だったとして、1ヶ月の日数で割る。(30日として)
9,000/30=300 1日300円を8時間労働で計算して1/3日分を計算。
300/3=100円 100×30=3,000
月額9,000円の内、3,000円は、家事按分で経費に計上する。
ガソリン代:買い出し、仕入れたをした場合のガソリン代
月額の30〜40%を家事按分で経費に計上する。
水道料金:増えるのは、トイレの回数ぐらいの差分金額。
ガス代:社員食堂の支度が、自宅に変わった差分金額。
灯油代:冬の暖房の味方も家に居ると必要なわけだから、
代金の1/3は、家事按分で経費に入れる。
電気代:パソコン、ミシン、電灯、アイロン、空調など、
必要なものを使った時間の差分金額。
備品・消耗品の一部:1/3の金額を家事按分する。
会社で使っていたもので、家でも使うものが該当。
忘れがちなのが、トイレットペーパー。
昼休みに歯磨きしていた人なら、歯磨き粉とはぶらし代金もOK。
福利厚生:昼食のコンビニ弁当、休憩の飲み物や、お菓子代
自分で決めた仕事時間とか、8/24時間で飲んだり食べたりしたもの。
レシートにアンダーラインなどを引いて、分かるようにしておく。
1ヶ月毎に集計する。
そして、必要なことの最大が、「経費は、遠慮せず計上してみる」こと。
決めるのは、税務署側ですから。
自分で決めて、計上するのはNGってことです。
全部通すつもりでいいのです。
家事按分の部分も、経費として、しっかりと説明できればOKです。
判断は、「しない」を心がけていきましょう。
独立、フリーランスの仕事を始めるまでに、気になる、つまずくところを、
書き上げてみました。
あなたに、必要な情報として伝えられたら、幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
