
アリーナを中心とした、よりよいまちづくりを目指して(パネルディスカッション編)
オンラインイベント「まちづくりとデータ利活用 ~多目的アリーナ・プロスポーツを軸としたスマートシティ~」、各登壇者によるプレゼンテーションのあとは、パネルディスカッションを行いました。
参加者:
岩本 健太郎 氏(株式会社スマートバリュー)
田代 正雄 氏(シナジーマーケティング株式会社)
貝野 宏至 氏(西日本電信電話株式会社)
渋谷 順 氏(株式会社スマートバリュー)
及部 一堯 氏(西日本電信電話株式会社)
池内 勇太 氏(株式会社千葉ジェッツふなばし)
内田 真由美 (ヤフー株式会社)
中川 雅史(ヤフー株式会社)
※パネル参加された方の発言を、順序不同で要約し記載しています。
(詳しくは動画をご視聴ください。)
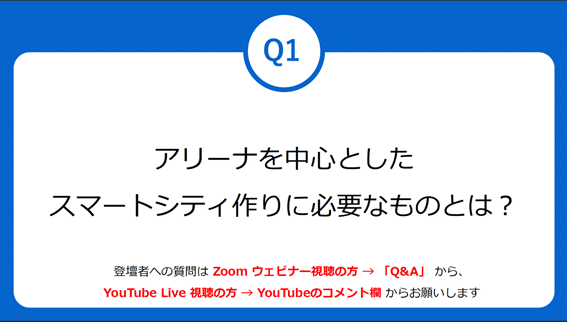
岩本さん:
(Q1のテーマについて)環境面であったり、データを用いて新産業を生み出す「まちづくり」という観点で、アリーナを中心としたスマートシティづくりは他にないと思う。人々が動くことによって生じるデータというところが必要だと思う。
「スマートシティ」化していく上で重要なこと
及部さん:
スマートートシティの本質は、市民の生活の質を高めることであると。多様化する市民のニーズに関してはどのように情報収集していくと良いと思われますか?
貝野さん:
ペルソナを設定し、街にどうなってほしいのかというのをシミュレーションし、実際の生活に即して真のニーズを深堀りしていく。実証実験とヒアリングを繰り返す。
逆に、多様性であればあればあるほど、意外と皆さんに共通する大胆な一つを目指すというのも大事かも。アリーナ周辺に住む人に何が一番共通項目なのかというのを取り出すと、実はものすごくヒットする可能性があるんじゃないかなと思う。
「応援消費」の真意について
及部さん:
応援消費が大きなマーケットになるとのことでしたが、今回アリーナとして取り組むときに、神戸が好きとか、ストークスが好き以外に、この応援される地域とか、応援されるアリーナになっていくために必要なことは何でしょう?
田代さん :
(プレゼンで事例紹介した)しょっちゅう美瑛町に来る、そういうコアな人たちをいかに育てるかだと思う。神戸好きとかストークスの大ファンの方とか、今すでにコアな方々って間違いなくいらっしゃるので、そういう人たちをちゃんと見つけ、デジタル上でもリアルの場所でもコミュニケーションを取っておく、一緒になって一体感を持たせるというのがすごく重要なポイント。
また、インフルエンサーを使って情報を拡散させるより、本当に好きな人(相手から見てもわかるくらいの人)が「推奨」するという流れが本当に最も効くと思う。
渋谷さん:
(美瑛町の例であった)デジタルとアナログの融合した分野というのは、そこに入り込んだ特徴的な人が地域に根づいて、現実的な活動をされたということですが、その人は具体的にどんなことをやったのでしょうか?
田代さん:
いろいろなコミュニティをつくって、自ら参加し、活動をSNSで拡散、外部からいろいろな人を連れてきて巻き込んでいく(体験させる)ということを、ハブとしてコツコツやっていらして、実は(美瑛には)これだけの価値があるんだよということをいろいろな角度で見せていく、という活動を、地元の人たちと行っていた。
渋谷さん:
ビジョナリーであることと、愛と、その両方かもしれないですね。
千葉ジェッツではどうしている?
及部さん:
ファンをつくっていくために、千葉ジェッツで一番大切にされていることは何でしょうか?
池内さん:
(千葉ジェッツでも)ファンの声というのはしっかり取り入れようとしている。例えばクラブへの問い合わせメールや、SNSを通じてメッセージをいただくので、例えばブースターのクラブ、来場マイルなど、いただいたご意見をアレンジしながら、ファンが求めるものをクラブの運営に反映できるようにしている。そこはけっこう受けは良く、リピーター施策につながったかなとは思う。
及部さん(Q1まとめ):
その地域の市民や、それ以外の人も含め、どれだけ巻き込みファンを増やしていけるか。そのために重要な情報をどれだけ収集できるか。アリーナがファン化していくことによって市民が参画し、収集された情報からまた次の施策を考えていくことができそうですね。
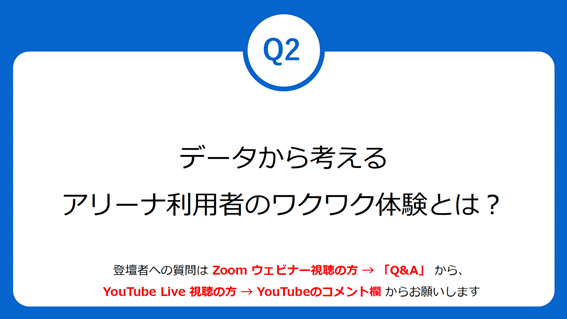
データの「定点観測」から見えること
渋谷さん:
データをもとに何かを施策実施した際、ずっと観測し続けることで効果がすごく見えやすくなるなと思って、今まで感覚的にやっていたことがこうやって定量的にデータで見ることができるというのは大事ですね。
内田さん:
三遠ネオフェニックスさんの検索数が伸びたことに対する疑問や、逆になぜ(このクラブは)こんなに検索少ないのだろうという疑問から、プロモーションをもっと頑張らないといけないね、みたいな両方で気付きと打ち手というのが考えられると思う。
岩本さん:
(共起ネットワークの解説を見て)ストークスは地域密着型か。でもエンターテインメントで千葉ジェッツみたいにやれたらこうなるな、みたいな感じに思えましたので、このデータは非常に興味深い。
渋谷さん:
今回はヤフーさんの検索データですが、もっと他にもいろいろなデータがありますから、そういったものをうまくマージしながら分析していく、街が良くなるために使うべきなのだろうなと思う。
及部さん:
人が何を検索しているかというのは、たぶんそれがニーズであり、お客さまの生の声。アリーナに近づいた人が、どういう検索をしているのかということを分析することによって、施策に生かし街をつくっていく(ハードとソフトが一体型になっている)ことができるなら、逆にヤフー検索するとそれで願いがかなうらしいよと、今までにないようなマーケティングの仕方みたいなのもあるかなとも思う。
他にも登壇者から下記のようなワードが飛び交い、白熱しました
・ 「潜在的なファン」から「顕在的なファン」へ移行
・ 人をいかに巻き込むか
・ アリーナの”聖地化”
・ 人の心の中で(アリーナに対する心象が)生まれていく
・ ハードとソフトをいかにうまく両肩並べてやっていくか
(詳しくは動画をご視聴ください。)

イベント全体まとめ(スマートバリュー:渋谷さんより)
本当にソフトとハードが両方が大事です。
内田さんの話の中にあった、共感、愛着、信頼。ステークホルダーとの協業バランスにおいても重要です。
田代さんの言った、明確なパーミッションという表現。これは共感性とか愛着とか信頼があるから実現できることだと思います。
貝野さんの資料にあった共創型のスマートシティは、市民と協働してつくっていく、まさに我々が目指す民主的なモデルです。
今、社会の変化とともに、大きく転換できるタイミングに私たちは生きています。これを私たちが構築していくということに本当にワクワクするし、Bリーグのようなソフトコンテンツも含めつつ、アリーナ、そして地域に根ざしていくということが実現できたら本当にいいなと感じました。
また、このプロジェクトは僕らなりの言葉を使うと「共感」をつくっているんだと思っています。その共感性の先に、街や社会自体もあると思っているので、そこまでをつくり上げていくくらいの30年、50年かけてでもやりきっていくような気概を持ち、大局観とかビジョナリーであることを大切にしながら実現できたらと思っています。
今日お聞きの皆さまも含めて、面白そう、一緒にやろう、みたいなお話があれば、ぜひご連絡いただきたいですし、今日ご登壇いただいた皆さんともやれることを一緒にやっていきたいなと思います。
長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。
動画アーカイブ
パネルディスカッションは 1:22:10 ~ 2:10:30の部分です。是非ご覧ください!
