
地域ビジネスは世界のどこよりも先進事例になれる 森山奈美×糀屋総一朗対談3
ローカルツーリズム株式会社代表取締役糀屋総一朗と、石川県七尾市の民間まちづくり会社・御祓川株式会社代表取締役の森山奈美さんの対談。対談の最終回は、これからの地域ビジネスの可能性についてです。
変えていくもの、変わらないもの
糀屋:僕も地方には、そういうザ・昭和的なところは感じているんですけどね。それを変えていくのはなかなか大変ではありますよね。価値観を変えていくっていう事も、地域でやらなきゃいけない重要なことなのかなと感じているんですけれど……。
森山:でもね……価値観って変わらないのよ。そこは「そうじゃないところも受け入れてく」って考えた方が良い。例えば、会社での価値観を変えていこうとすると、代替わりのタイミングしかないんですよ。あとはよっぽど悔い改めるか(笑)。でも、固定している価値観ってなかなか崩せないよね。
糀屋:特にオーナー企業とかはまず無理ですね。
森山:会社とは違う話なんだけど、例えば5月1日から『青柏祭』って祭りがあったんですけど、うちの町内に関しては女人禁制なんです。どこまでをグローバルスタンダードにしていくか? って言う問題はあるんだけど、その女人禁制であるということが、もう価値だから。そこが固有性だから。そこは保守だから(笑)。
糀屋:大島でもそうですね。世界遺産になった沖ノ島も、未だに女性は入れないんですよね。
森山:だから「駄目なものは駄目」っていう部分もあっていいと思うんですよ。全部が全部「変えていかなきゃ」みたいなのは、逆に息苦しいっちゅうか……そっちに合わせるのに疲れちゃう(笑)。
地域の依存体質を変えるには
糀屋:でもやっぱり変えていくべき価値観ってものもあるのかなと思って……。僕が変えていきたいと思っているのは、地域の依存体質なんですよ。日本の地域というのは、歴史的に非常に甘やかされて、依存体質に陥っているんじゃないかと個人的に思っていて。「依存せずに自分たちでやっていくんだ」っていう空気をちょっとずつ醸成させていくっていうのが、地域にとって非常に重要なんじゃないかなって思うんですよ。大島で、そのための戦略を今いろいろ考えている所です。
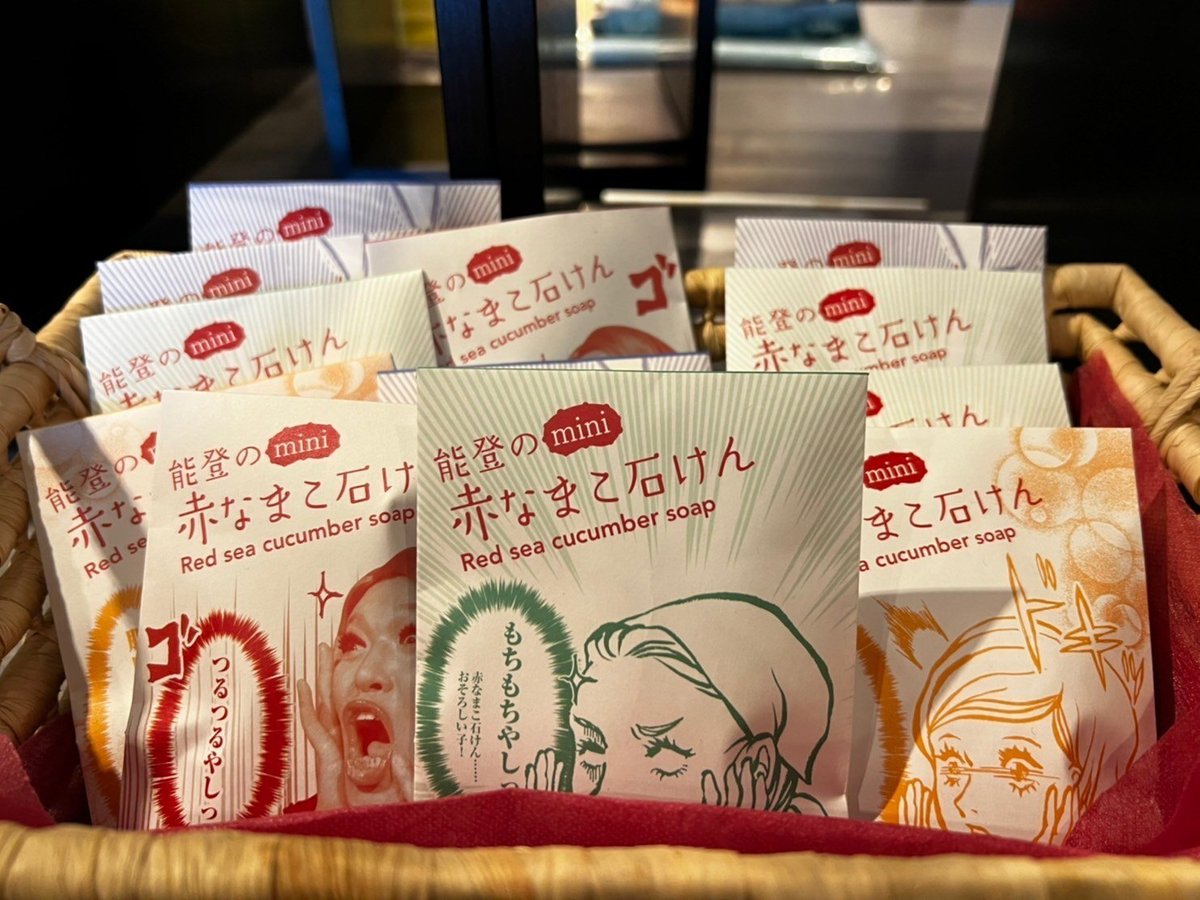
森山:それはなるべく補助金に頼らないことじゃないですかね(笑)。それこそ「一切補助金を使わずに、やれる事業、小さい事業をたくさん積み重ねていく」っていう木下斉くんの戦略しかないと思いますよ。その先にしかないじゃないですか。うちも御祓川を立て直すのに自分たちで金払ってやっとるわけで、補助金をもらったわけでもないし。やりたいことを継続するためにはいろいろもらいましたけど(笑)。
糀屋:何か自分たちで「商売を作れる人たち」の頭数を増やすしかないんじゃないかなと思っているんですけれど……。
森山:本当そうだと思います。例えば、今うちがやってる「TANOMOSHI」(民間互助組織)をお勧めします。お互いに出資をし合うとか、お互いに挑戦資金を出し合うっていう経営者の互助システム。それが学び合いのコミュニティにもなるので相当強くなりますよ。孤独に戦う1個1個の経営者に、ティールで言うところの、助言プロセスをインストールすることができるので、強くなる。
糀屋:非常に有効な方策ですね。
森山:連帯するってことですよね。その中でお金を出し合ったりとか、その配当で次を産んでいく。糀屋さんも「投資をして次を育てていくための原資にしていく」ってやっていますけど、そういう考えしかないんじゃないかな。
糀屋:それは共感します。僕は地方で活躍する人たちをある意図を持ってローカルエリートって呼んでるんですけど、そういう人たちにどんどん投資をしていこうと思っています。投資をするだけじゃなくて僕らの意見も提供しつつバックアップする。僕らもフィーはもらいますけど、それを再投資に回していく。そういう形で「自立して地域で稼げる商売」を実際作れるっていうことを見せていこうと考えているんです。その文脈と、今日の森山さんのお話はリンクしているなと思いました。
森山:発展的にやってほしいことって言えば、「TANOMOSHI」がやりやすくなるWebシステムとか作って欲しいんですよね。ってか、作りたい。かつて、CAMPFIREがやっていた「共同財布」っていうサービスがあったでしょ? でも今、サービス停止しているんですよ。使おうと思ってたのに……。今、うちはシェアハウスだけど、シェアハウスの「PayPay財布」がほしい。みんなが毎月PayPayでそこに送金して、それをみんなが使えるっていうふうにしたいんですけど、ないんですよ。
糀屋:今は無くなってますね。
森山:ちょっと早すぎたんかな。ああいうのを作るのにちゃんと投資してほしいんですよ。早いもん勝ちだと思うんですけどね。
糀屋:今だとベンチャーキャピタルも含め企業の会社の社長とかもお金出すんじゃないですかね。そんなに難しくなさそうですからね。

森山:現にこの前まであったんだから。
糀屋:そういう仕組みは、ちょっとインスピレーション受けますね。地域の中でうまくお金を融通しあって、新しい事業が生まれて行って、適度な競争が生まれるところもあるし。
森山:ちょうどいいと思う。
地域でビジネスをすることの面白さ
ーー地域のビジネスと、大企業のビジネスの違いをどのように考えていますか?
森山:うちの会社にも、この4月から企業から出向で1人来ているんですけど、急に大手企業がローカルの方を向き出してるのが気になっていて……大企業も新規事業が生まれない的なことで悩んでいて、どうもその種を探しに来ているっぽいんですよ。そこに一種の危機感みたいなものを感じているんです。
人材を送り込んでくれるのはウェルカムだし、人材育成のフィールドとして、うちにコーディネートフィーが入るのは歓迎するんですけれども……逆に、ローカルを市場としてそこまで吸い尽くすなよ!とは感じています。大企業は大企業のやるべきフィールドがあるでしょ?って思う時があるの(笑)。大企業はこんなことはやらなくていいです! ここはうちがやりますから! って。
糀屋:この前、熱海の市来広一郎さん(民間まちづくり会社・株式会社machimori創設者)と話してたときも、大企業から熱海にも人がやってきてると聞きました。交流が生まれてるということは言ってましたけど。
森山:大企業がローカルに興味を持つ動きってのは悪くはないけど、短絡的にならない方がいいだろうねって思うの。本気でプロジェクトを作ろうってことであれば、こっちがお世話するのはおかしな話なんですよ。
私は地域の中と外を繋ぐみたいな立ち位置にいるじゃないですか。そうすると外からのものをある程度スクリーニングする機能も果たさなきゃいけないなと思っていて。その水際のところで相手の本気度を見極めなくちゃいけないわけですよね。大企業って体が大きいから、ちょっと振り向いただけでこっち吹き飛ばされちゃいかねないんですよ。
ーーベンチャーはベンチャー、大企業は大企業で、その役割っていうのが全く違う、ということでしょうか?
森山:目指したいのは、共創なんですよ。大企業の役割はあると思うんですよ。でも、資本主義の論理だけでは動かない、ローカルの矜持もある。小さなところが豊かになることで、見えてくる世界観もある。そこの全体としてのその生態系のあり方みたいなのが、共有できるといいのかなあとか思っています。
ーー森山さんにとって地域でビジネスを作っていく面白さってどの辺にあると思います?
森山:地域のビジネスが向き合ってる課題って、世界的に見ても先進的なんですよ。そういう自負があります。経済成長しなくなっちゃったこの国全体の何十年先の姿を、前もってやっていくってことなんですよ。この小さいエリアで解決できなかったら、この後そういう状況を迎える東京や、より早いスピードで高齢化が進む台湾や韓国に応用ができないんですよ。
なので、今この小さいコミュニティの中で、今必要とされるものをどうやって供給し続けるか? どうやって循環の仕組みを作るか? って考えることは最先端だって思ってるんです。
ーー仕事の縮図みたいなものが地域にはあるというイメージですか。
森山:民主主義もでかくなり過ぎるとわからなくなる。この範囲の人たちでこの範囲のことを決めるっていう構造もそう。民主主義がドライブしやすい範囲ってあると思うんすよね。コミュニティに「関わりを持てる」範囲。それが結果、住んでる人たちが、自分なりの幸せだなって思えるような状態を実現できやすい環境になると思うんです。それが私にとっては、ある意味、わかりやすいし、面白い所ですね。
糀屋:さっき言った「自治」の話と繋がりますよね。自治っていうのは、やっぱり顔の見える範囲でのコミュニティと言うものがあって、そこで感じられる「幸せ」って目標を持つことができる。それが人と人が繋がる一つの仕組みなのかなって感じますね。
森山:だからそこで「祭り」を守っていけるんですよ。「祭り」というのはみんなが平等に参加できる、一つの象徴的なものなんです。「祭り」を続けているということを健全な形で作り直さなきゃいけないなと思っています。「祭りのために仕事を休む」とかってあるんですよ。市役所の職員でさえ「これから祭の準備なんで」って言ったら「じゃ、しゃあないね」って言って帰してもらえるんですよ。

それぞれの地域にその地域を自治していくためのシステムとして「祭り」は重要なところ。「祭り」って人材育成機能を持っていたり、コミュニティを維持する役目を持っていたり、経済を回す仕組みになっていたり、いろんな部分を包含してるんですよ。
ーー「祭り」の役割を、いわゆる神事ではなくて例えばフェスだとか、そういうイベントがになっていくという可能性はあるんでしょうか?
森山:イベントって神なき祭だと思うんですよね。神に祈るとか、願うとか。祭りには「神聖性」があるんですね。だからイベントとは分けて使っています。神社の宮司さんがその点を論文にまとめてらっしゃいましたけど、祭りには「神聖性」と「遊技性」の両方がないと駄目なんだと。片方だけでは「祭り」にならない。コロナ禍で「祭り」は休んでいたって言われるんですけれども「神事」は続けてるんですよ。「神聖性」のところだけは継続していたけど、なんとか「遊技性」の部分を確保しなきゃっていうので、この2年はオンラインでおうちで祭りしようとかって取り組みをやっていました。
一方で、人口が減りすぎて「祭り」が出来ないっていうところいっぱいあるんですよ。でもこの「祭り」をやめるか続けるかっていう議論をするところも「祭り」ですから。それこそ最も自治の話です。儲かるからやってることじゃないじゃない。世の中が色々と合理化されてきて、あと10年ぐらいでさらにみんなの意識って変わると思うんです。そしたら人間に残されてるのは「合理的じゃないところ」なのかもしれない。人は非効率で不合理なことをやるみたいな存在です。そういうのを感じられるのもローカルのいいところじゃないですか。
糀屋:確かに。
森山:ほら「合理的じゃないと駄目」みたいなコミュニティだと人間が記号化していくって言うか……。ティール組織的に言うと、そういうところから全体性を取り戻すっていうか。なので、人間らしく生きるために、ローカルでビジネスをやるのはとても良いと思います。
(構成・斎藤貴義)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
