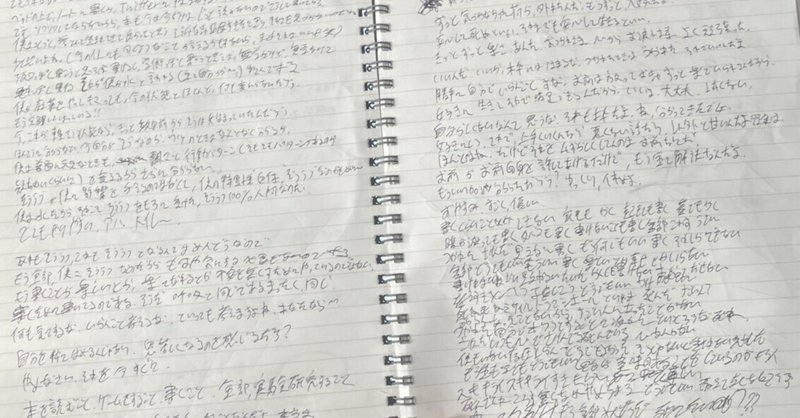
「書く」ということについて
ずっと「書く」ということを書きたかった。きっとまた長文になる。楽しみなんだけど、それが読まれるかは分からない。最近では僕も、「読まれたい」と思うようになってきているのだと気づいた。でもこのアカウントでは自分が思うようにそのまま文章にしていきたい。このことについての詳細も全て余すことなくこの記事で伝えていきたい。
書けるから、書く
まず、僕にとって「書く」というのにそれほど”こだわり”がない。好きだから書いているわけでもない、楽しくて書いているわけでもない。ただ、何故か書けるので書いている。この「書ける」ことに気づいたのも最近のことである。最近になっていろいろ気づくことがあるのは、きっと醸成期間が終わったからであろう。分からないことを、分からないまま置いておいて、たまに引き出して悶々としたりして、ずっと自分の中に蓄積していった。それが最近になって萌芽してきているのを感じる。何がトリガーか、今回は「書く」というのが主題なので簡単に言うと、一生懸命やっているからだと思う。何をするにもやると決めたらプロになったつもりでやってみる。そこに自分が要らないので、点と点が、新しい視点によって線でつながっていっているのを感じる。話を戻す。自分が「書ける」というのに気づいたのは友人と電話していた時である。それまでは僕、「みんな書けばいいのに」と思っていた。それにTwitterでも「うるさい」と言われミュートされるほどに書き込んでいた訳だが、なぜみんな書かずに済んでいるのだろうと思っていた。それくらい僕にとって書くという行為は呼吸同然なのだが、友人に「一日原稿2,30枚は書くんじゃないかな~」と言ったら驚かれた。僕はみんながみんな、僕と同じくらい、僕の見えないところで書いているか、それとも「書く」ということを知らないだけで書き始めれば(例えばnoteとか)、スラスラかけるものだと思っていたわけだが、友人に驚かれて自分も驚いた。どうやら僕が「書ける」のは、嫌な言い方をすると「才能」になるのだと思った。ただ、才能とは認識したくない。みんな天狗になって汚らしくなるのを知っている。僕は泥まみれなのは好きだけど汚いのは嫌いである。おんぼろ、泥まみれ、たまに美しいくらいがいい。
書くこと以外どうでもいい、精神疾患者
僕はずっと「自分にできること」を探していたんだと思う。でも探しても探しても見つからないから、もうないものだと思って淡々と日課をこなしてきたわけだが(その日課に書くというものがあった…。灯台下暗しとはこのことか)、「自分にできること」が無いというのはそのまま、アイデンティティの喪失とつながる。僕は無い自分を取り繕おうとして何かの真似をしたりり、変にこだわりを持ったりしてきた。そしてそれが自分では気づかないというのがまた難しい。一度、離れてみないと分からないのである。僕はずっと追ってきた作家に呆れて心酔がさめて、ようやく僕は心酔していたことに気づくわけだ。それまで無意識に文体が、精神が、生き方がその作家に依存していて、僕はもうその人になっているので、僕自身が疲れていてもそれに気づかないのである。酔いがさめて晴れて自由の身かと思えば僕は虚無に陥った。今まで自己かと思っていたものが全てその作家の真似事だったのである。僕はずっと真似をしてきたんじゃないか。僕なんて最初からいなかったんじゃないか。確かに、人は人の再現をしていて、その連続だというのも分かる。当然のことだ。しかし人にはやはり特異性があって、そのことを知ると自己アイデンティティの喪失と受け取るものがいれば、自分は真似事の天才だと思う人もいるわけで、僕はその前者だっただけだ。もとより自己が強すぎるのである。精神疾患者は感受性が高い傾向にある。不安に人一倍気づく。僕も躁鬱だからわかる。考えすぎと言われるが、僕たちにとってそれは仕方のないことだ。それらが先に述べた前者になる。しかし、ここで僕は偶然にもその虚無から脱却する方法をすでに行っていた。それが「自分にできること」だ。そして大抵の精神疾患者は同じように、それが書くことにならないだろうか。感受性が高ければ、不安も高揚も、書くには困らないほど与えられる。それが考えすぎの妄想だって構わない。元来僕たちは現実に興味なんてなかろう。僕は「自分にできること」それはつまり「書くこと」であるが、それをやっとの思いで見出して、非常にうれしく思った。もう自己のひねくれに、喪失に、こだわりに、困らなくていいのだと思った。書いてさえいれば自分であることを確認できる。それ以外はもうどうだっていいのである。
「読まれるための努力をしていい」ことに気付く
読まれたいと思った、と最初に綴ったが、これも僕のこだわりが剝がれたためであろう。僕が傾倒心酔するのはいつだって嫌儲の人で、評価されないのも厭わない方たちであったが、結局は読まれているし、読まれるための努力もしてきたであろう。そうでなければ出版なんてできない。つまり僕の思い込みであったわけだ。この思い込みも全てこだわりから発生する。こだわりを捨てて素直になることが大事なのかもしれない。ここで言っておきたいのは、素直とは、相手の言うことに素直になるのではなく、自分の気持ちに素直になることである。「読まれるための努力をしていい」、と気づくのに随分と時間がかかった。これはあくまで個人的な意見だが、努力をするのは、その基盤が「自分にできること」である場合に限定している。それは好きなことでも、才能でも当てはまる。なぜなら、僕がなぜ書くかというと、自分ができるというほかにも、生き延びるためであるからだ。生き延びるのに辛い努力をするのは勘弁である。やるのなら、自分にできることでの努力をしたい。そうであれば他人から見て努力と思われるのも自分にとっては当然のことである。僕は気が早いとこがあって、書くことが自分のできることだと気づくと、すぐそれを職にしようと思ってしまう。つまりそれで生計を立てようとする。それはとても野心的で素晴らしいことなのだが、もう少し待ってからでいいと思う。病み上がりなのだから。また自分を醸成してからでいい。僕は文字を書けるだけで、まだ自分がどんなジャンルを書くのかとか、そういったものが見えない。それも少しづつ、やっていこうと思う。毎日書くことはできるのだから、何もしないでも見つけていくだろう。
始めて現実的に考えることが可能になったかもしれない
このように、僕にとって書くという行為は自己保全の核になる。「種種雑多で無鉄砲なこだわり」の開放であり、アイデンティティの帰る家であり、将来の可能性にもなった。書くということを主軸に僕はこれから初めて、理想ではなく現実的に生活を構築することが可能になった。やっとである。本当に長かった。僕はこれから、そのために働くかもしれないし、そのために書くことを訓練するかもしれないし、そうして出版をして、また見えてくる何かに期待することができる。僕は表面ではその行為を否定しておきながら、生き方というのをずっと模索していたように思える。(これとは主旨がずれるが「本当の自分探し」みたいなのが大嫌いなのである。)自分の身を守るので精一杯だった。だが、書くことに気づいたらもうそれも克服したように思える。それでやっと動けるのではないかと、思い始めている。気が早いことも自覚しているので、今は興奮だけで押さえておいて、病み上がりを終えたらゆっくり考えるとしよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
