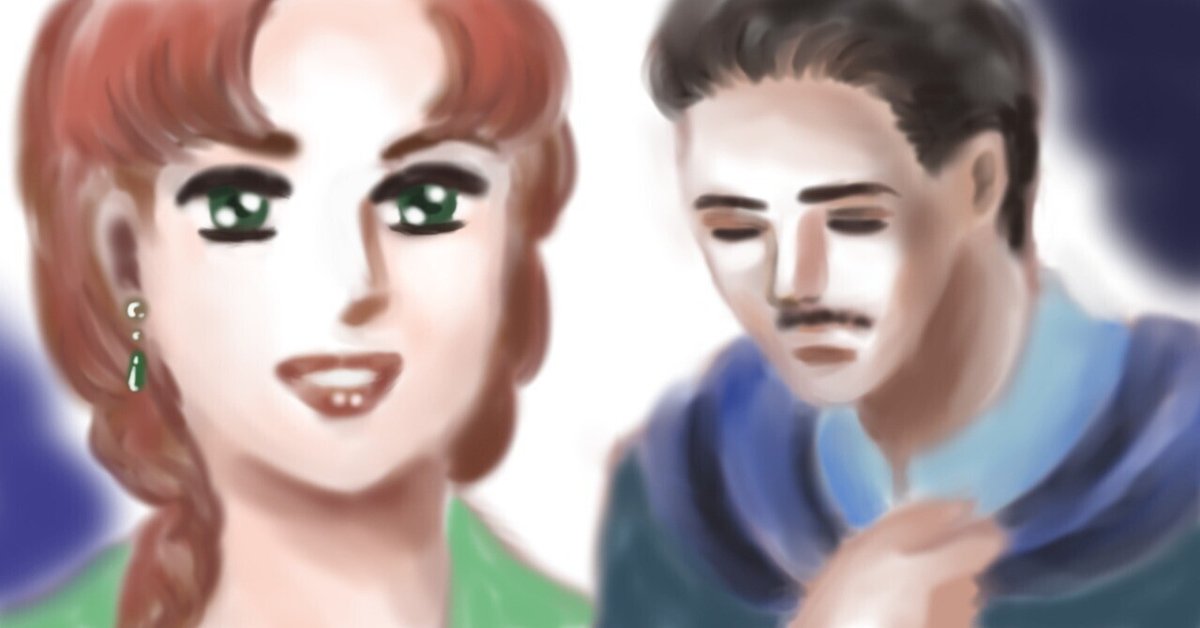
『ペルシアン・ブルー3』
4 パリュサティスの章
気がついた時は、蛇と向き合っていた。ほっそりとしていながら強靭で、凶悪な力を秘めていることがわかる。
廊下を素足で駆けてきて、寝台に飛び乗ったパリュサティスに驚いて、寝具の下から這い出してきたのだ。脇の台に置かれた油皿の、ささやかな灯火の元であるが、毒蛇なのは間違いない。
この屋敷の女たちや召使たちが用意し、親衛隊の兵士がきちんと点検した寝台に蛇が潜んでいる理由は、それしかない。
アルタクシャスラ王子の暗殺。
兄がまだまだ宴席にいて、幸いだったと真っ先に思った。パリュサティスが自分用に用意された寝室に行かず、野営の時のように、兄の寝台に潜ろうとしたことも。
(兄さまだったら、ぼんやりしているうちに、噛まれていたわ)
蛇は寝具の上で鎌首をもたげ、パリュサティスを注視している。目の前で膝をついている赤毛の少女が大きく動いたら、あるいは人を呼んだら、その瞬間に噛みつくだろう。
追ってきた侍女のミラナが、戸口ではっと凍りつき、そろそろと下がって消えたのがわかった。警護の兵を呼びに行ったのだろうが、余計な動きは危険だ。兵の足音だけで、蛇が動くかもしれない。
パリュサティスは呼吸を乱さないようにしながら、腰に手をやった。そこには、帯から下げた剣がある。柄には幾つもの宝石が埋め込まれ、鞘は黄金造りでずっしり重いが、刀身は鋭利な鉄だ。
次の瞬間、蛇と剣が交錯した。
首元の骨を砕かれた蛇は、牙を剥いてもがき、暴れまくる。おぞましい尻尾がのたうち、膝を打つ。けれど、その牙はぎりぎりで、少女の肌に届かない。
(短剣でよかった)
もしこれが長剣だったら、抜くのも突き刺すのも間に合わず、噛まれていただろう。
蛇はじきに力を失い、ぐったりと伸びた。長い戦いに思えたが、実際には、ほんのわずかな対峙だったのだろう。ようやく、青と緑の制服を着た親衛隊の兵たちが駆け込んできた。
「姫さま、お怪我は!!」
「我らの見落としです、申し訳ございません!!」
「平気、何ともないわ。これを片付けて」
兵たちが親衛隊全体に警告を発し、改めて松明の明かりで寝室の安全を確認する中、ミラナがパリュサティスに抱きついてきた。
「姫さま、お一人で動き回らないで下さいと、あれほど申し上げましたのに!!」
恐怖の反動だろう、ミラナは震えが止まらないようだ。こっそり抜け出して心配をかけたのは悪いと思うが、ミラナはそもそも、パリュサティスが兄の寝室で寝ることに反対したのだ。どうか別室でお休み下さい、さもないと悪い噂になりますと。
外聞が悪いということが、パリュサティスには納得いかなかった。
これまで野営の陣を張る都度、自分は兄の天幕で、兄の懐に潜るようにして寝てきたのではないか。それが一番安全だし、温かい。
ミラナだって、自分を間にはさんで、兄と同じ天幕で寝ていた。十五歳という年頃になったミラナのほうが、よほど、嫁入りに差し支えるというものだ。
いや、〝王子のお手付き〟という噂がある方が、ミラナの身の安全には役に立つというものだが。
それでも、ミラナが命の縮む思いをしたのはわかるので、パリュサティスは、四つ年上の侍女の背中をさすって慰めた。
「大丈夫に決まっているでしょ。あたしは、アナーヒター女神に守られているんだから」
半分は冗談だが、半分は本気だ。少なくとも王家の者は、神から地上の統治を任された責任を負っている……はずなのだ。
「もう、姫さま」
ミラナは泣きべそだった。パリュサティスの度胸や才覚は認めているが、だからといって、常に無事で済むとは限らないではないか。
もちろんパリュサティスとて、神の姿を見たこともなければ、声を聞いたこともない。予言の力もないし、霊感を受けたこともない。
それでも、周囲にはそう言うべきなのだ。ハカマニシュ王家は、至高神アフラマズダの代理人として、世界に君臨しているのだと。
太陽神ミスラ、水の女神アナーヒターもまた、王家の守り神だ。
そしてパリュサティスは、アナーヒターを自分の女神だと勝手に決めていた。アナーヒターは命を育む女神だが、戦士の守り神でもある。それならば、自分に相応しい。
「パリュサティス!!」
ようやく兄が駆け込んできた。薄明かりでも、端正な顔が強張っているのがわかる。
「そなたは、どうして、自分に用意された寝室にいないのだ!!」
(あら、お小言なんて)
兄を救ったと思っているパリュサティスには、心外である。
「だって、兄さまを一人で寝かせるなんて、心配だもの。あたしが、寝室の点検をしてあげたのよ」
パリュサティスがにっこりしてみせると、兄王子は絶句した。ついてきたアルシャーマも、とっさには言葉が出ない。
「とにかく、今夜は天幕でお休みを……」
この屋敷にはまだ、何らかの仕掛けがあるかもしれない。過去に幾度も王族が滞在している豪族の屋敷だが、敵の手が回っていたものとみえる。
「それがいいだろうな。二人とも、休みなさい。我々は下手人の捜索をする」
妹と侍女を兵の囲みの中へ託し、アルタクシャスラは年上の従兄弟にささやいた。
「どうせ、とうに逃げているな」
「生きたまま捕えられれば、背景がわかるのですが」
これまでの刺客たちも、生かしたまま捕えることはできなかった。この親衛隊の中にも、敵の回し者は紛れているだろう。お互い様というものだった。アルタクシャスラもまた、実の兄の陣営に、自分の配下を送り込んでいる。
王子同士の争いは、王家の宿痾。
たとえアルタクシャスラに野心がなくとも、存在するだけで、兄の側からは脅威と映るのだ。
(しかし、今夜は危なかった。パリュサティスが死ぬところだった……)
毒蛇と聞いた時には、心臓が止まるかと思った。まだ、胸の中が波立っている。
(この子は本当に、性懲りもなく、わたしの胆を冷やしてくれる……)
そもそも、もう無理なのだ。妹を旅に連れ歩くなど。
幼いうちはともかく、パリュサティスも、じきに十二歳になる。いつまでも、少年兵と同じ格好でうろつかせるわけにはいくまい。
(十三か十四で婚約し、十五で嫁ぐ……)
それが、王女の当たり前の人生だ。いくら本人が、嫁ぐ気などないと言い張っていても。
パリュサティスの母のリタストゥナ妃からも、長旅に連れ歩くことは、もうやめてほしいと懇願されている。
(少なくとも、寝所は別にしなければ……)
これからもまた、自分を狙った罠の巻き添えにしてしまうかもしれない。
(あの子の縁談にも、差し支えるだろう)
本人には聞かせないようにしているが、よくない噂も耳にするようになっていた。アルタクシャスラ王子は、幼い妹を連れ歩いて〝ご寵愛〟だというのだ。
(馬鹿な……あんな小さな子を)
王家には確かに、実の姉妹を娶った王もいるが、自分にはそんな趣味はない。パリュサティスは異母の妹だから、結婚しようと思えば認められるだろうが、近親婚というものは、他民族の間では忌避されている。
王家の者は、積極的に外の血を入れるべきなのだ。それでこそ国交も広がり、他国の富も流入する。
自分もまた、遠からず、妻を迎えなければならない。それはわかっていた。ただ、窮屈な王宮暮らしよりも、こういう旅の方が好きで、縁談も右から左に聞き流してきただけのこと。
娘を差し上げたいという声は、何人もの貴族から聞いているのだ。
(いつまでも、先延ばしはできないか)
繰り返しやってくる刺客のことも、いつまでかわせるか、わからない。色々なことに、決着をつけなければならないのだ。
***
翌朝、パリュサティスの元に、ゾルタスがやってきた。中背で痩せ型の三十男で、鼻の下に黒い髭をたくわえている。盗賊暮らしをしていた頃の名残は、こけた頬と油断のない目つきに残っているが、元が貴族なので、裕福な商人に化けても違和感はない。
親衛隊の制服を着ないのは、二十人ほどの別働隊を率いるようになっているからだ。
「姫、申し訳ありません。こちらの手抜かりでした」
彼は床に片膝をつき、深く頭を垂れた。彼の小部隊は旅人や雇われ兵士のなりをして、正規の親衛隊に先行したり、離れて後方を警戒したりする。
必要ならば、他の王子の部隊に潜入したり、問題のある総督を暗殺したりもしてきた。この屋敷の様子も、部下が事前に探っていたのだ。
「気にしなくていいわ」
パリュサティスは簡単に答えた。ゾルタスにこういう役目を負わせたのは、彼女の考えである。甘やかされて育った貴族の子弟では、こういう日陰の任務は務まらない。
事実、ゾルタスはうまく陰部隊を育て、指揮してくれている。税の二重取りをしたり、身内の犯罪をかばったりする総督は、王に知らせる手間をかけるより、アルタクシャスラ王子の判断で〝事故死〟してもらった方がよいのだ。
「外からちょっと見たくらいでは、買収された者を見分けるのは無理よ。それより、あなたに相談があるの」
「は、何でしょうか」
「蛇の毒を、たとえば、この針に塗ることはできるかしら」
パリュサティスは、自分の髪飾りを外してゾルタスに見せた。これは母方の祖母からの贈り物だが、もしもの場合に備え、隠し針が仕込んである。急所を狙えば、人を殺せるだろう。祖母は若い頃、戦乱に巻き込まれて恐ろしい経験をし、そこから自衛の知恵を備えるようになったのだ。
「それは、できないことはありませんが……」
横にいたミラナが、すかさず反対した。
「おやめください。危険すぎます。間違ってご自分を刺したりしたら、どうなさいます」
パリュサティスは軽く笑った。
「そうなったら、それまでの運命だったということよ」
ミラナは額を押さえたが、あきらめた。パリュサティスは、そういう工夫が大好きなのだ。馬に乗るための足掛かりも、以前に発案している。鞍から左右に、革製の幅広の輪を吊り下げたものだ。そこに足をかければ、乗り降りに便利だし、騎射の精度も上がる。
ミラナもその恩恵にあずかっているので、優れた発明だとわかっているが、親衛隊の男たちは女子供の補助具と見て、笑っていた。だが、いずれは女子供の世界に広まり、男たちもやがて、その便利さを認めるのではないだろうか。
ゾルタスは王女の強運を信じているので、黄金の髪飾りを預かって一礼した。
「職人を探して、手配します」
口の堅い職人でなければならないことは、もちろんだ。他にしゃべるような素振りがあれば、始末する。
殺しは好きではないが、王女のためならば、ゾルタスは自分にも部下たちにも、それを神聖な義務だと言い聞かせていた。
この世界は残酷な場所だが、今は希望の光が射している。
(王家にこのような方が生まれたのは、奇跡だ)
王女がいつか女王になることを、ゾルタスは密かな夢として抱いていた。
そのための障害は、可能な限り、自分が排除する。たとえ、それが皇太子であろうとも。
午後になると、屋敷から姿を消していた下男が、村はずれの森で死んでいるのが発見された。刃物で首を斬られていたが、目撃者はなく、犯人はわからない。
厳しく詮議しても、豪族の一家は何も知らないようだったので、それ以上咎めることはせず、王子の一行は村を離れた。暗殺未遂は初めてではないし、これからもあるだろう。余計な恨みを残すことはない。
夏の都に向けて街道をたどり、その夜の野営場所に着くと、兵たちが焚火を熾すうちに、アルタクシャスラは妹を呼んで宣言した。
「今夜から、そなたとミラナには別の天幕を用意する。もう二度と、わたしの寝所に入ってはならない」
パリュサティスは仰天した。兄はきっと、昨夜のことを重く考えすぎているのだ。
「兄さま、でも……」
「これ以上、わたしに恥をかかせたいのか」
思いもよらない言葉に、パリュサティスは息を呑んだ。兄の黒い瞳には、笑いのかけらもない。
「そなたに退治できた蛇なら、わたしでも退治できただろう。わたしはそなたがいなければ、自分の面倒も見られないというわけか?」
パリュサティスは唖然とした。
(兄さま、変だわ)
兄の部隊が崖の間の細道を通る時、伏兵がいることに最初に気付いたのは自分だし、狩り場の樹上に暗殺者が潜んでいた時、それを発見して射落としたのも自分ではないか。料理の碗に毒が入っていることを、給仕する召使のわずかなぎこちなさから見抜いたのも、自分だ。
兄もアルシャーマも、これまでは、自分の活躍を喜んでくれたはずだ。たとえ、心配混じりであっても。
横からミラナが素早く、パリュサティスを抱きとるようにした。
「姫さま、兄上さまのおっしゃる通りです。年頃になられる方が、いつまでも殿方と一緒にお休みになるなど、よくありません」
その後はアルシャーマに隔てられてしまい、女二人は別の焚火の側に追いやられた。
(兄さまはもう、食事すら、一緒にしてくれないつもりなの)
パリュサティスは目の前が暗くなる思いだったが、横にいるミラナが切々と語りかけてくる。
「姫さま、兵たちの前で、兄上さまに逆らってはなりません。それでは、アルタクシャスラさまの威厳が損なわれてしまいます」
わかっている……わかっている。男たちが、何より面子というものを重んじることを。
しかしこれまで、この兄だけは、自分の願いを苦笑で聞き入れてくれていたのに。
「姫さま、旅をお続けになりたければ、兄上さまのお考えに従わなくてはなりませんわ」
ミラナにそう言われた時、パリュサティスはぞっとした。
(まさか兄さま、次の旅では、あたしを置いていくつもりじゃないでしょうね!!)
パリュサティスにとって、王宮とは、贅沢な牢獄にすぎない。本来、王女がいてよい場所は、母や侍女たちに監督される後宮だけである。許される気晴らしは、楽器の演奏や、刺繍などの女らしい手仕事くらいのもの。
異母の姉たちは、後宮からほとんど出ないまま、十五になった順に嫁がされていった。顔も知らない相手の元へ。
パリュサティス自身、正妃の王女とはいえ、王子たちのような自由はなかった。強い決意で父王に直訴しなければ、学問所への出入りも認められなかったのだ。
母のリタストゥナもまた、王に見初められて五番目の妃になったが、夫婦らしい情愛があるかといえば、疑問である。母は未だに王の機嫌を恐れ、他の妃たちを警戒して、びくびくしながら暮らしている。
(あたしは違う。あたしは戦えるし、知恵もある。他所へ嫁ぐ必要なんてない)
そう思っていたが、それも、兄の庇護があればこそ。
(兄さまは、わかってくれている、と思っていたのに)
王宮の書庫でも、めぼしい書物は、あらかた読み尽くしてしまった。教師たちや学者たちに疑問点を尋ねても、満足のいく説明は得られなかった。
それならば、じかに外の世界を見たい。世界の真実を、この目で確かめたい。
神はたくさんいるのか。それとも、ただ一人の神が、違う相を見せているだけなのか。
あるいは神も魔物も、人間の空想の産物にすぎないのか。
世界の果てでは、海が滝となって流れ落ちているのか。
それとも、世界は球体であり、一周して元の地点に戻ってこられるのか。
はるかな北の大地では、夜空に光の滝が乱舞するというのは本当か。
高い山の上では、昼でも星が見えるのか。
謎は限りなくある。だから、心配する母を泣かせても、無理を通して兄の部隊に同行させてもらっているのだ。
隊の兵士たちからは故郷の風俗を聞き、彼らの言葉を覚えた。川や湖に行き合えば泳ぎを習い、森では獣を狩った。村では農地や飼育動物を調べ、町に着けば路地に紛れ込み、庶民の暮らしを垣間見た。王宮にいては得られない知恵を、山ほど身につけたのだ。
何より、
(兄さまのことは、あたしが守ってあげなくちゃ)
と以前から心に決めている。
王子には危険がつきものだが、この兄は武勇自慢ではない。パルサ人の男子として、馬術も弓術も叩き込まれてはいるが、決して、それらに夢中になっているわけではない。
兄が愛しているのは、書物を紐解いたり、学者と議論したり、各地の古老を訪ね、歴史や風俗を記録したりすることだ。この巡察の間にもきちんと日誌をつけ、同行の学者たちに植物や昆虫を採集させたり、古代の石碑の碑文を記録させたりしている。
暗殺の危険にさらされても、こちらから反撃しようとか、有力者をもっと味方に引き込もうとかいう、政治向きの知恵は湧いてこないらしい。だったら、その方面は、自分が補ってやらねばならないだろうと思っていたのだ。
(いいわ。明日になったら、兄さまの考えを変えてやる。あたしには、アナーヒターさまがついているんだから)
ミラナと共に新たな天幕に押し込まれると、パリュサティスは毛皮と毛布にくるまって横になった。
(そうですよね、アナーヒターさま。あたしはこの地上で、したいことがたくさんあるんだから)
アフラマズダやミスラは、自分の神という気がしない。
(男の神なんて……女子供が味わう苦痛や屈辱なんか、本当にはわかりはしないわ)
戦乱があれば男は殺され、女子供は奴隷にされる。男の神は、勝った男だけを祝福するのだ。
女が肌に焼き印を押されるのも酷いが、男の子が去勢されるのも残酷だ。生き残って宦官になれた者はまだ幸運で、出血と高熱で苦しみ、死ぬ者も多い。
成長して宦官になった者が、協力し合って去勢の制度を止めればいいのに、それをせずに保身や蓄財に走る愚かしさ。
更に逃げ道がないのは、女だ。平和な時でも売春宿に売られたり、好きでもない相手と結婚させられたりする。
王宮でも、下級の侍女が何人も、望まぬ妊娠で泣いていた。父の側室が、出産で死んだこともある。
(あたしは結婚なんかしない。そうしたら、出産しなくて済むし。そもそも、月のものなんか、来なくて構わないし)
それがどれほど厄介なものか、パリュサティスは、年上の侍女たちを見て知っている。ミラナもまた、旅の途中で、男たちには言えない苦労を重ねていた。
男ばかりの部隊に同行させて申し訳ないが、さすがに、王女が侍女もなしで旅はできないのだ。
そもそも他には、きつい日差しにさらされ、嵐に襲われる長い旅路に、喜んで付き従ってくれる侍女はいなかった。貴族出身の上級の侍女ならば、王宮での贅沢な暮らしを望むのが当然である。
だが、ミラナは煮炊きの手伝いも、馬での移動も、野営の天幕で寝ることも、別に辛いとは感じていないようで、助かっていた。下級貴族の、それも妾の娘だったので、実家には居辛かったらしいのだ。
(旅が辛いなんて、パルサ人としてありえないわ)
とパリュサティスは思っている。帝国の始祖、偉大なるクルシュ大王は何と言っていたか。
『高地に住んで、低地の民族を支配せよ』
すなわち、厳しい砂漠気候の高地で自らを鍛えよ、という意味だ。
元来、パルサ人は遊牧民族であり、王族も貴族も、五つある帝都の間を移動して暮らしてきた。行政の都スーシャ、大河のほとりの古都バビロン、夏の都ハグマターナ、クルシュ大王の墓所があるパスラガータ、そして高地の聖都。
各地に王宮を構え、屋敷を持ってはいても、老人や病人でない限り、隊列を組んで移動することは当然なのだ。
アルタクシャスラ王子の親衛隊の場合、馬車は用意してもらえず、馬にまたがるしかないので、月のものの間は、ミラナもさすがに大変そうだが……
王子かアルシャーマに配慮を求めれば、宿を確保してくれたり、休憩時間を長く取ったりしてくれる。自分だって、これからもずっと、旅に同行できるはずなのだ……
パリュサティスが眠りに落ちるのを確認して、ミラナもゆったり仰向けになった。
(よかったわ……これからは、もっと楽に眠れる)
いくら王女を間にはさんでいても、男性と同じ天幕では、緊張を解ききれなかったのだ。
(今が一番、幸せ)
女連れの旅は面倒なはずだが、アルタクシャスラ王子は可能な限り親切にしてくれたと、ミラナは感謝している。パリュサティスのお守りに苦労する点で、二人は同志といえるかもしれない。
(お母さまは不幸だったけれど、それは、男の持ち物だったからよ。わたしには、侍女が向いているわ……結婚などせず、ずっと姫さまに仕えていられれば、それでいい)
実家では妾の娘として、肩身の狭い暮らしをしてきたのだ。病弱な母の死後は、更にひどかった。異母の兄たちにからかわれ、あるいは追い回され、陵辱されそうになったこともある。
それに比べれば、ここでは姫の第一の侍女として振る舞っていられるし、兵たちに守ってもらえるのだから。
(それも、アルタクシャスラさまが〝お手付き〟のふりをして下さるから……)
時折り、兵たちの前でミラナの肩を抱いてみたり、ちょっとした品を贈ってみたり、という芝居をしてくれるのだ。
二人の間にそんな関係がないことを知るのは、王子の側近数名のみ。全ては、王子がパリュサティスの願いに弱いからだ。パリュサティスを連れ歩くならば、不平を言わない侍女は貴重である。
(どうかいつまでも、アルタクシャスラさまが、姫さまを庇護して下さいますように……暗殺などされず、長生きして下さいますように……)
政治のことは、よくわからない。今の王が亡くなって、皇太子が即位しても、まだ刺客はやってくるのだろうか。
不安はあるとしても、ミラナはただ、パリュサティスの後についていくだけである。難しいことは、王子や王女の領分なのだ。
(姫さまのお考えは、アルタクシャスラさまにも理解しがたいのかもしれないけれど……)
いつしかミラナも、深い眠りに落ちていた。
ペルシアン・ブルー4に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
