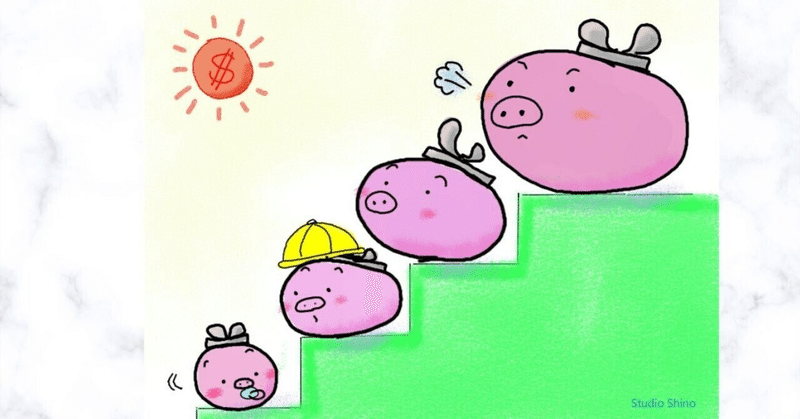
日本株の歴史的株高
日経でとても興味深い記事があったので取り上げる。歴史を振り返りつつ、現状の株高を分析している良い記事だと思う。
要約文
この記事では、日経平均株価が約34年ぶりに高水準に達し、1989年のバブル期の最高値に近づいている状況を分析しています。世界的な金融環境の改善や日本企業の変革が株価上昇の背景にあると指摘しています。具体的には、グローバルな「ゴルディロックス」市場の影響、日本企業の1株利益の大幅な成長、企業統治改革の進展などが挙げられています。さらに、株主還元の期待が続いており、企業と投資家との関係性の変化も触れられています。これは、日本の「失われた30年」からの脱却を示唆する内容です。
ゴルディロックス市場とは?
ゴルディロックス市場は、経済が過熱も冷え込みもせず、インフレ率が低く成長が続く状態を指します。この用語は、経済が「ちょうど良い」状態にあることを、ゴルディロックスと三匹のくまの童話にちなんで表現したものです。株式や債券が安定して成長する環境を指し、投資家にとって好ましい条件が揃っていることを意味します。
企業統治改革
企業統治改革は、会社の経営構造や運営方法を改善し、経営の透明性を高めるための改革です。これには、取締役会の機能強化、監査体制の充実、株主とのコミュニケーション向上などが含まれます。目的は、企業価値の向上と持続可能な成長を実現することにあり、株主の利益を最大化するとともに、企業の社会的責任を果たすことです。日本では、2015年に企業統治コードが導入され、上場企業に対し良好な企業統治の実践が求められています。
補足
安倍政権下で企業統治改革は大きく推進されました。2013年に第二次安倍晋三内閣が発足して以降、日本経済の再生と成長戦略の一環として、企業統治の強化が重要視されました。2015年には日本版企業統治コードが導入され、上場企業に対してより透明性の高い経営や株主との健全な関係構築などが求められるようになりました。これらの改革は、日本企業の国際競争力を高めることを目指しています。
この動画でも安倍政権の企業統治改革の取り組みを再評価していた。
歴史的株高

史上最高値(1989年)
1989年の日本株価が最高値を記録した要因には、バブル経済が大きく関わっています。この時期には、土地や株の価格が異常に高騰しました。要因としては、過剰な流動性(金融緩和政策による大量の資金供給)、投機的な投資の増加、そして土地を担保にした融資の拡大などが挙げられます。これらが相まって、資産価格を不自然に押し上げ、最終的にバブルが崩壊する結果となりました。
プラザ合意は、1985年にアメリカ、日本、西ドイツ(現ドイツ)、フランス、イギリスの5カ国がニューヨークのプラザホテルで合意した通貨政策の調整です。主な目的は、当時高騰していたドルの価値を下げ、経常赤字が膨大になっていたアメリカ経済の負担を軽減することでした。ドルの価値が下がることで、日本やヨーロッパの通貨価値が相対的に上昇し、これが日本の株価上昇につながりました。結果として、日本では資産価格のバブルが発生し、後に経済に大きな影響を与えることになります。
山一證券破綻
山一證券の破綻は、1997年11月に起こった日本の証券会社の倒産事件です。バブル経済崩壊後の不良債権問題が深刻化し、金融機関の経営状況が悪化する中、山一證券も巨額の損失を抱えていました。経営再建が困難になり、最終的には自主廃業を選択しました。この事件は、日本の金融システムの脆弱性を露呈し、金融危機の象徴的な出来事となりました。
リーマンショック
リーマンショックは、2008年にアメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻したことをきっかけに世界的な金融危機が発生した事件です。これは、過剰な住宅ローン貸出とその後の不動産価格の急落、それに伴う不良資産の増大が原因で、金融市場の信頼が失墜し、世界中の銀行や企業に大きな打撃を与えました。結果として、多くの企業が倒産し、世界経済は深刻な不況に陥りました。
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
