
たまたま読んだ本19:「ごまかさないクラシック音楽」 なぜ、古い西洋音楽を現代の日本で聴くのか? バッハからモーツアルト、ベートーベン、ワーグナー、時代を映した人間臭い音楽世界
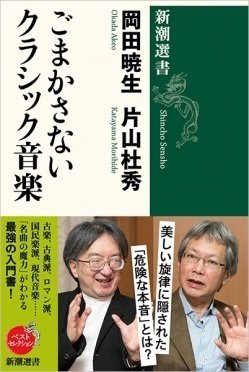
日本でクラシック音楽は、もはやオタク文化らしい。
ジャズもあまり聴かれなくなった。、
今若者に一番人気は世界的にK-POPかも。
栄枯盛衰。ともあれ、クラシックは根強く聴かれている。
映画、広告、BGMなどにもよく使われ、コンサートも開かれる。
同書はそんなクラシックの秘密を音楽学者の岡田暁生氏と音楽評論家の片山杜秀氏が対談を通じて明らかにしていく。
音楽だけにとどまらず、世界歴史などの豊富な知識に裏打ちされた中身の濃い対話は、レベルの高い知的世界へ導いてくれる。
また同書では、曲の解説などはないが、9世紀ごろの西洋音楽の本格化から、古楽(クラシック以前)、クラシック(古典)、現代音楽(クラシック以降)へと変遷していく中で、バッハ以降のクラシック(古典)だけが「価値」を持ち続けている、その歴史を解き明かす。
まず、クラシック音楽とは、18世紀から20世紀初頭の西洋音楽で、時空を超えた特権的な地位が与えられており、音楽とイデオロギーは不可分であり、一つの社会思想として捉えることが重要だと説く。
19世紀にヨーロッパ発のクラシック音楽が世界中の音楽を標準化し、征服したのは、キリスト教の価値観が、資本主義経済発展とともに帝国主義の植民地支配を通じて拡散していった当然の帰結であろう。
バッハの前段、バロックまでは「教会のための音楽」から、表現の自由を取り入れていくプロセスを経て、ルネッサンスで決定的になり、「古代ギリシア神話」から聖書ネタだとやりにくいエロチックな表現を美術史と同じように取り込んで来た。音楽というのは本質的に大変エロティックな芸術で、徐々に「人間が楽しむ」ものになり始めたと論じる。
なるほど、現代でもK-POPを見ると、エロチックなダンスを見せる曲もある。
「音楽の父」バッハの背景には強烈なプロテスタント倫理があり、その音楽は徹底的に組み立てられ、ある意味、近代的な平等性、市民社会的な平等性を、音楽の中で実現しているようにも見える。
すごく科学的数学的であると同時に、すごく神学的である何かを感じるという。
だが、ルター派のプロテスタントは鉄の規律みたいな世界になっていき、ナチズムにも社会主義にも適応してしまうとその危うさを指摘する。
「バッハがすごく好きだ」という学生は、ほとんど例外なくは頭がいいらしい。数学的に構成されたような音楽に魅力を感じているわけだ。
当然、音楽も他の芸術と同様に経済や社会発展ともに変化する。
パッハは18世紀の前半、つまり人がまだ神を信じていた時代の人で、フランス革命や産業革命より前の「前近代の人」。それに対してべートーヴェンは市民革命と産業革命より後、つまり「近代の人」だと指摘する。
産業革命後のロンドンでのハイドンの演奏会は、チケットを買ってホールで音楽を聴く「コンサート」の誕生となり、「商品」として書いた12曲の交響曲は、弟子のベートーヴェンへつながった。
ハイドンまでは地位と収人が何とか見合う面があったが、けれど、少しだけ下がってモーツァルトになると、もう「教会専属」「宮廷音楽家」の肩書を得ても、十分な収人が伴わない。そうなると、やっばり「市民」を相手にして、一番お金をくれる「予約演奏会」、いまでいう「定期演奏会」をやるとか、楽譜の出版に向かうしかない。そこでビジネス先進国で大陸の文化教養に憧れを持つイギリスの役が突出してくるわけだと論を広げる。
モーツァルトになると現代にも通じる物語が見えてくる。
モーツァルトは、音楽史で最初の「根無し草」だと言い、大家族の時代に珍しく、モーツァルトがパパとママとお姉ちゃんと僕の四人だけの「核家族」の出身。自分の子どもを天才少年として売り出そうとするステージ・パパという現象は音楽やスポーツによって一発逆転で社会的に上昇することが可能になる時代になってから出てくるもので、「神童」として親によって売り出されたモーツァルトは近代的だったという。
ベートーヴェンは掛け算もできなかった。ガサツな田舎者で、天才だけど、どこかとんでもなくパカなところがある。
それに比べ、モーツァルトは、ものすごく頭の回転の速い人。教養があるというタイプじゃないけれども、当意即妙の言葉で端的にパッと表現できるという。
びらめきでなく労作というところがべートーヴェンで、<第九>は結局、西側民主主義のンンポルとなり、世界中の人類が手を取り合って幸せになろうという、西側イデオロギーをあらわす。ベートーヴェンの音楽は、フランス革命以降の近代西洋社会における宗教音楽という側面があるという。
べートーヴェンの音楽が熱く語りかけるのは、「頑張れば頑張った分だけより良い明日が待っているという、右肩上がりの時代のモデル。
彼の音楽はしつこい。<第九>のコンセプトから、編成から、音量から、和音から、楽式まで、とにかくべートーヴェンはしつこい。圧力そのものだから。と、称賛しているのか、けなしているのか、分からない。
人と人が肩を組んで一致団結しなければいけない社会の変革期にビッタリ合うとすれば、すごく司馬遼太郎的だという。「坂の上の雲を目指せ!」みたいな時代に、ベートーヴェンほどはまる音楽はなかった。だからこそ明治後期の洋楽の導入において神格化されたのは、誰よりベートーヴェンだった。
ベートーヴェンはただの「いい音楽」じゃない、ひとつの「世界観」で、べートヴエン・コンプレックスがそのまま19世紀のクラシック音楽史になっていると喝破する。
同書では、この他、ロマン派や3分間の短いショパンとか、ヒトラーが愛し、現代のアニメや映画に影響を与えた3時間文化のワーグナー、そしてウクライナや東欧ユダヤ系移民が作ったアメリカ音楽など、時代の流れとともに変遷していく音楽の世界を万華鏡のように見せてくれる。
中でもショパンのノクターン(夜想曲)は、実はショパンでなく、ロシアに移民したアイルランド人がロシアの夜が長いなあと思って発明した音楽であり、イギリスとロシアの結びつきなども興味深い。
結局ところ、クラシック(古典)が特別扱いされるのは、キリスト教の束縛から逃れ、人間の感性に訴えかけるものへと変わることができたためかもしれない。それが現代音楽になると一般的な人間の感性を越えてしまう。ジャズも古いジャズは分かりやすく楽しみやすいが、現代ジャズになると騒音にしか聞こえない、難解どころか耳障りなものとなっているものもある。奇をてらいすぎるのだ。もう一度、芸術の人間回帰、ルネッサンスが必要な時期になったのかもしれない。
音楽だけでなくすべてに言えることだが、専門を突き詰めると一般から遊離しすぎ、専門バカに陥ることがよくある。ほどほどのところでちょっと先を行っている感じが良い。一般の感性が後から追いついてくることはよくあることだ。
しかしクラシックが古くならないのも不思議だ。民謡と同じく、歌い、演奏され続けるものは古くならなく、歌われなくなり、演奏されなくなると古く感じるようになるのかもしれない。
出版社 : 新潮社
発売日 : 2023/5/25
単行本 : 360ページ
定 価 : 2,090円
著者プロフィール
岡田暁生(おかだ・あけお)
1960年、京都市生まれ。音楽学者。大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。京都大学人文科学研究所教授。『オペラの運命』でサントリー学芸賞、『ピアニストになりたい!』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、『音楽の聴き方』で吉田秀和賞、『音楽の危機』で小林秀雄賞受賞。著書に『オペラの終焉』、『西洋音楽史』、『モーツァルトのオペラ 「愛」の発見』など多数。
片山杜秀(かたやま・もりひで)
1963年、仙台市生まれ。政治思想史研究者、音楽評論家。慶應義塾大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。慶應義塾大学法学部教授。『音盤考現学』および『音盤博物誌』で吉田秀和賞、サントリー学芸賞を受賞。『未完のファシズム』で司馬遼太郎賞受賞。著書に『近代日本の右翼思想』『国の死に方』『尊皇攘夷』『革命と戦争のクラシック音楽史』など多数。
トップ写真:ユーパトリウム
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
