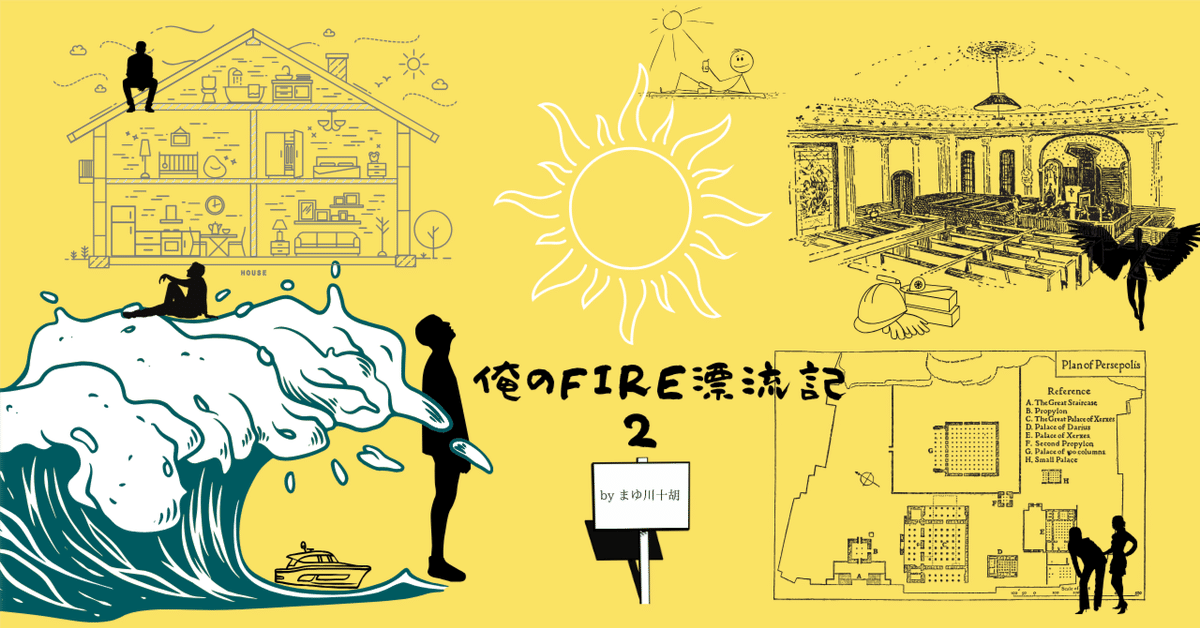
俺のFIRE漂流記②(お仕事小説)
工程2 仕事の意義と生きる意味は同義語か?
1、バリキャリ凛々子
外でエンジン音が鳴っている。あのちょっと耳障りなツーストロークの回転音は聞き慣れている。会うつもりはまったくなかったのに、音を聞きつけた途端、足は一目散に玄関へと向かっていた。
外へ出ると、オレンジのジムニーがぶるぶると身体を震わせて停まっていた。ちょうど、息子の柔道が山のような荷物を抱えて降りてきたところだった。身長の半分はある、岩かと見紛うような、デカいリュックを背負い、パンパンに膨らんだスポーツバッグに埋もれた小柄な姿は、以前テレビで見た映像を彷彿とさせた。戦後の混乱期に、大人と一緒に大きな荷物を抱えて街をあてどもなく彷徨う子供。現代の日本ではありえない、あの胸が塞がれる姿。
おかえり、と声をかけると、疲れ切った顔でただいまと呟き、よたよたと玄関へ吸い込まれるように入っていった。まだ中2だというのに、あのくたびれよう。この若さがまるで感じられない中年男のような後姿を、俺は眉を顰めて見送った。
「結構ヘロヘロだよ、あの子。もっと気にしてあげてね」
エンジン音に負けじと張り上げられた声に、俺は振り返る。オレンジ色のルーフに片手を突き、寄りかかる女。ウルフカットのショートヘアに白のパンツスーツという、自分の魅力をよくわかっている自己表現に長けた女。
俺の元妻、眞島凛々子。元妻……最近やっとそう言えるようになった。
「柔道をありがとうな。俺の代わりに色々してくれて。おまえも忙しいのにな」
そのまま運転席に乗り込んで去っていきそうな気配を感じて、俺は慌てて声をかけた。
凛々子は何か感じるところがあったのか、俺の顔にじっと目を添え、やがて思い直したかのようにエンジンを切り、運転席のドアを閉めた。夜更けの住宅街ではちょっとはた迷惑な稼働音がようやく鎮まった。
「目、ゾンビになってるぞ。ゴロちゃん」
凛々子は笑いながら俺をからかってきた。この横に長く伸びる細い目は、良くも悪くもかなり特徴的らしく、昔からことあるごとに、いろんな相手からからかわれ続けてきた。
……急いでいるだろうに。エンジンを停めて少し付き合ってくれるそぶりの元妻に、甘えのような安心感を抱いた。
「あたしは時間の融通が効くからね。それにさ、親の1人なのよ、あたしも」
あんただけが親じゃないという目で軽く睨まれた。
「中学生はね、中学校というちょっと特殊で狭い箱の中で生きている、あたしたちとは別次元の生き物なんだよ。こっちから理解しようと歩み寄らないと、どんどん訳のわからない相手になっちゃうぞ。最近、会話してないでしょ」
昔から変わらない独特な話し方だが、注意を受けていることはわかる。
「繁忙期で忙しくて…。あまり話してなかった」
話してないどころか、ろくに顔を見てもいなかったような気がする。指摘されて、ひやりとした。凛々子はそんな俺に軽くため息をついたようだった。
「あの子にもっと意識を向けて。こっちを見てくれている、気にしてくれてると感じるだけで相当安心するものだよ。それと、いつも以上にちゃんとコミュ取って。これ、今週の課題」
わかったと頷き、言葉を発しかけたが、伝えたい……いや、訴えたい思いが形にならず、結局口をつぐんでしまった。凛々子は再び車に乗り込み、エンジンをかける。運転席側へ回り込んだ俺に、「じゃあ」と声をかけ、キコキコと手動でウィンドウ硝子が閉められる。あがりきる寸前、やっと口から言葉が飛び出した。
「あのよ、義理を守ることと間違いを正すこと、どっちに重きをおくべきなんだろうな」
凛々子はアーモンド形の大きな眼を丸くしながらも、気のせいかニヤリと笑ったようだった。
「さあ? 一緒に並べるのは矛盾してると思うけど」
「そうだよな、ごめん、引きとめたな」
衝動的に何を言ってんだ、俺は。頭を掻きながら後ろに下がったが、凛々子はまだ留まってくれていた。
「……ゴロちゃんさあ、何を悩んでいるのか知らないけど、相手にとってとか、相手のためとかを考えるより先に、自分がどうしたいのかを最初の判断基準にしたら? それを押さえておかないと、ずっと振り回されっぱなしだと思うよ。人にも環境にも自分自身にも」
凛々子の言葉はいつも俺の核心をぐさーっと刺してくる。それがどうにも我慢ならない時もあるが、今日は刺さり加減が痛みのツボに若干届いたような癒しを感じた。
黙って頷く俺に、凛々子の声はいつになく優しかった。
「不条理って、会社勤めをしていると付き物だよね。あたしはそれが嫌で辞めたけど」
じゃあね、とひと言残して凛々子は去っていった。1986年式の2サイクルエンジン車がいまだに快適に走り回っている姿に驚きながらも、そのオレンジの車体が角を曲がって見えなくなるまで見送り続けた。
凛々子は同い年だが、俺より遥かに達観していて、完全に自立した人間だ。工業高校の同級生で、その頃からすでに思考回路が他の誰とも違って、俺たちには見えない回路をたくさん持っている、風変わりで早熟した奴だった。とはいっても、そんな凛々子から言わせると、俺も相当変わっている部類に入るらしい。
高校卒業後は、凛々子は建築科のある大学へ進学し、途中でアメリカの大学へ建築を学びに留学して、卒業後はそのまま向こうの建築事務所で数年働いた。二十六で帰国し、大手ゼネコンへ就職。在職中に俺と再会し、どういうわけか結婚した。そんな、ハイパーバリキャリの凛々子がなぜ俺を選んだのか。とうとう理由を教えてくれないまま、別れてしまった。それが俺の未練がましい、数多い心残りのひとつである。
結婚して息子を産んで、職場復帰をして間もなく、凛々子は将来が約束された好待遇の会社を辞めた。俺には理解できない選択を、凛々子は己が思うままに選び、突き進んでいった。俺の意見などひとつも聞き入れてはくれなかった。知らないうちに取得していった数多くの資格と経験を活かして、凛々子は建築家兼インテリアデザイナーとして頭角を現し、今や売れっ子となって、全国を飛び回っている。
大袈裟でも何でもない。この間は、地元のTVに「あなたの住まいを大変身」というコーナーで出演していたので、息子と二人で緊張しながら視聴したばかりだ。
考え方も、人生に対する姿勢も、生活スタイルもここまで乖離してくると当然うまくいかなくなる。まだフリーのインテリアデザイナーとして軌道に乗る前から、俺たち夫婦の歯車は嚙み合わず、ギクシャクしだした。決定的にお互いが嫌いになりきってしまう前にと、2年前に離婚をした。夫婦として心が通い合っていないのに、未練がましくしがみつく俺をすっぱりと断ち、決断をくだしたのはやはり凛々子だった。いつでも決定権は凛々子にあった。
「あら? 凛々子帰っちゃったの?」
背後から、サンダルを引きずる音を引きつれて、残念そうな声があがった。俺は笑顔を作って振り返り、義母に挨拶をした。
「柔道を送ってくれたんですよ。俺の代わりに塾に迎えに行ってくれて、そのままご飯も食べさせてくれて」
「ご飯なら、うちに寄って一緒に食べればいいのに。まったくあの子ったら」
シーズー犬を腕に抱きながら、今年70歳になる義母、眞島こよりは口を尖らせて文句を言った。実は俺の家のお隣さんは、元妻の実家なのだ。凛々子の姉家族との二世帯住宅で、両親が犬と一緒に暮らしている。大抵の人間は、この家庭環境と関係に驚く。まあ、事情を話すとひとつのドラマくらいになってしまうので、そこは適当に流しておいている。
「吾郎ちゃんも大変だったら、こっちへいつでも気兼ねなく来なさいね。柔道にも言っておいてね」
「はい。いつも本当にありがとうございます」
義母へ丁寧に頭を下げて、わが家へと戻った。
柔道が帰ってきただけで、家の暗さが消し飛んだ。俺は息子の存在に救われている。一人でいると昼間の黒い渦に巻き込まれたまま、夜通し過ごしてしまいそうだった。気持ちを逸らしてくれる、自分が守らなければと思える存在がいるのはありがたかった。浴室、トイレ、リビングと探し回って、ようやく子供部屋のベッドに潜りこんでいる姿を見つけた。床には、脱いだジャージやリュック、部活の練習着が散らばっていた。
「風呂入らないのか?」
真っ暗な室内へ声をかけると、間をおいてからのそりと掛け布団の山が動いた。
「……入りたくない。もう寝る」
とりあえず言葉を返してきた。俺は心の中でほっとひと息ついた。そのままドアを閉めて話は明日にしてもよかったのだが、今夜はそうしない方がよさそうな気がした。部屋の中へ入って、背中を丸めて寝ている息子の傍らに腰かけた。ぴくりと柔道は反応し、驚いたようだった。
「最近ずっと迎えに行ってやれなくてごめんな」
背を向けて眠る布団の山に話しかけた。
「飯も一緒に食べられてないし」
返事はないが、聞いてはいるようだった。
「ろくに話もきいてやれていない。ごめんな」
いくら忙しいとはいえ、あまりにも自分本位だったな、と話しながら自覚した。話を聞く余裕のない親には、子供はいつでも簡単に心を閉ざしてしまう。かつて自分が経験したことなのに、なんでいとも簡単にそんな大事な教訓を俺は忘れてしまうんだ?
「さすがにお母さんには言えないことだってあっただろうにな」
「それはない」
速攻で返してきやがった。ここはちょっと傷つくな。やはり子にとって、父より母の存在の方がでかいのか。わかってはいるが。
「忙しかったんだからいいよ、それは。そういう仕事だってわかってるから」
一瞬黙った俺に気遣ったのか、小さな声で呟いてきた。自分も何かに煮詰まって、いっぱいいっぱいだろうに。親の都合に合わせて気遣おうとする優しさに、いじらしくなってしまった。思わず、掛け布団からほんの少しだけ覗いているヒヨコみたいな頭をワシワシと撫ででしまった。
「お父さん、今日なにかあったの?」
俺にされるがままだった柔道の突然の不意打ちに、ドキリとした。思わず、しつこく撫でていた手が止まる。
「なんでそう思うんだ?」
「だって、死んだような目になってたから」
……3回目だな。今日言われた数。
「俺の目って、そんなにわかりやすいのか?」
「うん。最近ずっとだったけど、今日特にひどい。元気な時はギラギラしてるから」
「ギラギラ……」
「うん。圧が強い」
知らなかった。だから女性や若手から怖いと言われるのか。だからどうってこともないけど、軽くショックを受けた。
「柔道はママ似でよかったな」
瞬時で気持ちを立て直し、心からそう思って息子を褒めた。だが、本人は意外にもそう思わないようだった。
「俺はお父さんのほうがよかった」
嬉しいが、引っ掛かる言葉だ。こいつの悩みはこの辺にあるのか? なにせ、不安定な年頃だ。悩みや気の迷いなんて沢山あるだろうが、どれもひとつひとつが本人には深刻なことだってある。だが俺はあえて言った。
「俺はな、おまえがお母さんに似てくれていて嬉しいよ」
本心からだ。どう受け止めてくれているかはわからないが、伝えてみると気持ちが少しすっきりした。もう言葉は帰ってこない。背中を向けたまま身じろぎもせず、眠ったふりをしている。邪魔にされてもいないので、俺はずっと息子の体温を背中に感じながらいつまでもそこに留まった。やがて寝息が立ち上がる。規則正しい静かな寝息を聞きながら、俺はまずひとつの選択をした。
2、まさかの〇〇〇〇カット……
「亘君、ちょっといいかしら」
夕方、社内の給湯室でコーヒーを淹れているところを、業務課課長の牛込ひかりに声をかけられた。俺より8つ上だから、確か50歳と記憶している。俺と同じひとり親で大学生の娘がいて、このノマドランドが設立された当初から在籍している初期メンバーだ。決して狎れあわない仕事の仕方を好む信念の人なので、俺は密かに『サッチャー』と呼んでいる。昭和の時代に活躍したイギリス初の女性首相で、『鉄の女』という異名はあまりにも有名だ。俺の中では信念の人といえばサッチャーであり、牛込さんだ。風貌がどことなく似ているという理由も、なんとなくある。
「どうしたんすか?」
珍しく勤務中にフロア外で声をかけられ、更に「ちょっと」と給湯室の奥にある休憩コーナーへ誘導された。首を捻りながら、その日本人離れした体格の(つまりすげえバディ)いい、牛込さんの後を追った。
休憩コーナーには、都合よく誰もいなかった。終業間際だからな。
アメリカ西海岸風にコーディネートされた、白とベージュの色彩と光に溢れる空間に、大きな窓を背にして佇む牛込さんの姿に俺はいたく感心する。背景はアメリカだが、さすがサッチャーだな。
「亘君はここ3日間、現場に詰めてたから知らないだろうけど、実はちょっと問題が起きてね」
少しドキリとした。まさかおやっさんが被った秘密の過失が明るみに出たのか?
「来月のボーナスが半分カットされることになったのよ。私と亘君の分が」
「……はい?」
何か過失をしただろうか? まったく身に覚えがないのだが。
「実は、マルトク興業が不払いで飛んだのよ。先々月から兆候が出てて、これは怪しい、と社長も部長も先回りをして、直接資金回収先へ回ったりしてたんだけど、マルトクの社長の方が先に動いてたらしくて。うちが請け負っていた工事が終わるより先に……というか、契約した時点で前払いでお客さんから全額受け取ってたらしいのね。どうやら計画的だったみたいね」
「いくらでした?」
「500万よ」
……でかい。でかすぎる損失だ。おやっさんの(彼の責任ではないが)100万どころの話ではない。
「マルカク……。たしか部長の客でしたよね」
「そうね。私たちの前ではさすがに見せないけど、社長からの叱責は凄まじかったようでね。部長は勿論のこと、斉木課長も責められたそうよ。補佐すべき立場なのにそれを怠ったとして。それで、二人とも今季のボーナスは支給なしとなったわ」
もしかして、それがあったからおやっさんは俺に借金を申し入れたのか? 二重の失態を重ねた部長を、おやっさんなりに守ろうとしたのか?
「亘君も知っているだろうけど、コロナ回復後からうちは売り上げが低迷しているでしょう。昇給も見送っているくらいなのに、今回の損失は大きすぎてね。それで、役職のついている私と亘君もその煽りを食らっちゃったというわけよ」
「じゃあ、心介たちは大丈夫ということなんですね」
「ええ、さすがにそれは常識的に考えて支給されるわね。彼らにはなんの非もないし」
それは俺たちもだけどな。それがまかり通らない世界はこうして確かに存在する。
「サッ……」
少し頭に血が上りかけたせいで、思わず口走りかけたところを何とか踏みとどまった。一瞬怪訝な顔をされたが、俺は気にせず続けた。
「牛込さんはそれでいいんですか? 納得できるんですか?」
「……」
珍しく、牛込さんは沈黙した。いつもはっきり意見を言うサッチャーらしくない。
「らしくないんじゃないすか?」
「私一人なら、どうにでも思うように振舞えるでしょうね。亘君ならわかるでしょう?」
ハスキーに呟く牛込さんは、ぐっと奥歯を噛みしめたようだった。数日前のおやっさんと同じ表情だった。
「こんな一蓮托生、嫌ですね」
「そうね」
今や、牛込さんと肩を並べて一緒にふかふかのソファへ沈み込んでいた。しばらく二人でぼんやりと窓の外の景色を眺めていた。もうそろ初夏になる頃の、澄んだ青空に綺麗な赤い夕焼けが混ざり始めている。こんなにも美しい空。なのに、この間からなぜこうも心はどんより汚く曇ったままなのか。
「不動産の方から援助はしてくれないんですかね」
「それは人の褌で相撲を取るってやつよ、亘君」
俺の軽口に、牛込さんは乾いた笑い声を立てながら窘めた。
さすがサッチャーだ。わかってはいるが、言ってみたかったんだよね。グループ会社とはいえ、自社の損失を別会社の資金で穴埋めするなど、経営の基本として禁じ手である。
「正式に部長から話があると思うけど、個人的に亘君には話しておきたかったのよ。時間を取らせちゃったわね」
牛込さんが腕時計を見やりながら立ち上がった。ゆさりと大きな胸が揺れるてるな。それを眺めながら、俺も腰を上げた。ひどく身動きが億劫に感じた。
「いえ、先に話してくれてよかったです。お陰で冷静に部長には対処できるので。ところで、このことを心介たちは知っているんですか?」
「いえ、まだ知らないはずよ。社長と部長、斉木課長、それと私の4人だけで話していることだから。多分、今回の件は内密にするでしょうね」
その方がいいだろうと俺も同意した。恐らく、これで当面俺たち全員の昇給は見込めないだろう。そんなことはこの出来事を聞かされた時点ですぐに想像がつく。あいつらがそんな暗い話を聞かされたら、絶望しか感じない。頑張っても見返りがもたらされない職場に、誰がずっと働いていたいと思うだろうか。確実に勤労意欲を削ぐことになるのは目に見えている。
俺もサッチャーも、そこは結束を固くして口をつぐんだ。
3、虚無という名の病
今日は塾の日なので、柔道を迎えに行く時間にあわせて、事務仕事をする予定でいた。が、とてもじゃないがその気持ちは失せた。
席に戻った俺は部長と目が合いそうになり、ことさらそれを躱す。躱したついでに自分のノートパソコンを引っ掴み、現場に行くふりをして一目散に外へ出た。今日はさすがに勘弁してほしい。俺だって気持ちの整理は必要なのだ。
スマホで最寄りのコワーキングスペースを検索してそこへ向かう。カーオーディオには陽水の《氷の世界》が流れている。我ながら、偶然の選曲で感心する。吹雪も吹雪、いっとき凪いだと思った心象風景がまた白く荒れ狂い出した。
昨日、現場でおやっさんに100万円を耳をそろえて手渡した。産まれてこの方、札束なんて掴んだことはなかったから、その厚みと重みをこういうものなのかと味わった。
すぐに渡さなかったのは貸し渋ったわけではなく、俺がコツコツと投資をし続けていたFXを売却して、現金化するのに時間がかかったからだ。恥ずかしながら、薄給の俺は人並みの貯金があまりない。何とか、息子の進学のために積み立てている学資保険と塾の授業料、十年前に建てた住宅ローンでかなり生活費が圧迫されている。毎月僅かな額で貯金をするのがやっとという有様で、将来の貯蓄に悩んでいた。
そんな中、大手キャリアの携帯会社が宣伝しているFX投資を目にし、子供のお小遣い程度の金額で細々と始めた。ここまでやっと大きく育てた俺の唯一の資産だった。それを売却するのはかなりの覚悟を要した。あの、全てを売り払ったあとの、未練のようなもの。希望の残りかす。喪失感ていうほど大袈裟なものではないが、なにか虚しい。あの札束が、何か俺の大事なものまで持っていってしまったのかもしれない。
おやっさんは俺には親にも等しい存在だ。
このノマドランドに入社したのは、おやっさんの口利きのお陰だった。本来なら俺はとてもノマドランドに採用されるような人間ではないのだ。高卒で大学を出ているわけでもなく、何の資格も経験もない、定職にもついていない半チンピラのような生活を送っていた。
仕事といえるのは、夜の繫華街で客引きや風俗店で裏方のアルバイトをして食いつないでいた。暴力団関係の運び屋などにも手を出して、捕まりかけたこともある。おやっさんと出会ったのは、そんな生活を送って5年目の頃だった。
水商売関係の住人が多い一角にあるアパートに当時俺は住んでいた。6帖一間で、トイレと風呂が一つの空間にある三点ユニットバスの、築35年のボロアパート。川べりにあるからネズミもよく出た。ある夏の日、隣りの部屋から機械音が聞こえてきた。俺は朝帰りだったので、昼過ぎまで眠りこけていたのだが、耳障りな音に起こされて不機嫌になった。しばらくじっと我慢をしたが一向に音が止まないので、文句を言ってやろうと起き上がり、玄関へと向かった。いつの間にか機械音は止んでいた。俺が土間のサンダルへ足を入れようとしたと同時に、壊れて閉まらない玄関ドアの隙間から人の顔が見えた。ばっちり目が合った。いかつい顔をしたオヤジだ。やべえ。その筋にも見える風体だ。俺はとりあえず剥き出しの敵意を少し引っ込めた。
「ドアが壊れているのかい?」
無言でそっと閉めようとドアノブに手をかけると、いきなり話しかけられた。風貌に似合わない静かな口調だった。俺はなぜかその時、そのまま無視ができず、返事をした。
「ああ。別に大して困ってない」
するとそのオヤジは笑うでもなく、こう言った。
「壊れているのなら直した方がいい。ちょっとみさせてもらってもいいか?」
当時の俺は、周りの人間はすべて敵という精神状態で生きていた。なのに、すんなりこの申し出を受け入れる気になったのはどうしてだろう。
無言でドアを開き、そこで相手の全貌を目にした。角刈りの頭に、頑固そうな厳めしい角ばった強面。筋肉質で大柄な体格をベージュの作業着がさらに際立たせている。手に持ったごついドリルが似合いすぎて、それを向けられた時の恐怖を相手に想像させるような緊張感を感じてしまった。
「吾郎ちゃん、この人とっても腕がいいのよ。なんでもみてもらったらいいよ」
小柄すぎて見えなかったが、オヤジの背後には隣に住む婆さんがくっついていたらしい。相変わらず俺をなれなれしく名前で呼ぶので、俺は嫌な顔をした。オヤジは肩から下げていた工具箱を置き、ドリルを使って丁番やドアノブを次々と外していった。バールや丁番起こしという工具を使いながら、10分と掛からず、建付けの悪さをあっという間に直してしまった。俺はその一連の作業を玄関の脇にあるキッチンに半分腰掛けながら見守っていた。
「応急処置程度だから、開け閉めしているうちにまた建付けが悪くなるだろう。ドアごと交換した方がいい。俺から管理会社へ報告しておくよ」
オヤジは俺に丁寧に説明をした。
「金は出さねえぞ。頼んでねえし」
「別にいらんよ。今日来た工事のついででみたことだから」
「吾郎ちゃん、トイレも見てもらったら? 水が止まりにくいって、この間ぼやいてたでしょ」
婆さん、余計なことを言うなやと目を三角にした俺を、オヤジは見つめた。見ていいか? とその目は尋ねている。仕方なく俺は頷いた。オヤジは案内するまでもなく玄関横の風呂場へ大きな体を押し込めた。トイレタンクの蓋を開けて何やら触りながら、携帯で写真を数枚撮っている。水も数回流して確認していた。やがて、狭い開口枠に肩をぶつけながら出てきて言った。
「ボールタップ交換だな。タンクの中に水をためて流す装置が壊れている。これも管理会社へ報告するから、許可が下りたらまた来るよ。担当者から連絡がいくからね」
それだけではすまなかった。オヤジは他の水回りも一通りすべて点検し、他2か所の不備を見つけて帰っていった。
その風変わりなオヤジと再会したのはそれから一週間後だ。そんな出来事をすっかり忘れていた矢先、玄関チャイムが鳴って外から呼び声がした。
「斉木設備です」
誰だ? と訝しみ、声に聞き覚えがあって俺は即座にドアを開けた。ドア枠いっぱいに先週のいかついオヤジが立っていた。
「管理会社の担当者から連絡が来ているはずだけど、トイレの部品を交換しに来たよ」
「……今日って約束してねえけど」
「水がもったいないから早く直した方がいい。お隣でまた作業があったから、ついでに寄らせてもらった」
「ついでって……」
「水漏れを放置してると、その分水道料金も嵩むだろう?」
言われるがままに、その日はトイレの水漏れを直してもらった。そんな修理がこの後3回続いた。俺の部屋だけではなく、このアパートの他の部屋にも足しげく通うオヤジに、俺はよっぽど暇なんだなという印象を抱いた。実態は真逆であったが、当時の俺は何の知識もなかったので実情を見抜く洞察力もなかった。俺はいつしかオヤジが訪れてくるのが楽しみになっていた。
玄関ドアから始まって4回目の時、居間のドアの建付けを直しながらオヤジが静かに話しかけてきた。
「興味があるのか?」
背を向けたまま、唐突に話しかけられて俺は面食らった。ひどく無口な人間で、作業している間も一切会話したことがなかったからなおさらだった。俺が黙っていると、どうしたことかオヤジの方からまた話しかけてきた。
「毎回、俺が作業している手元をじっと見ているな。さっき給湯器の給水栓を交換している時もだし、最初の玄関ドアを直しているときもそうだった」
「他に行き場がねえんだから、そりゃ見るだろ。こんな狭い部屋」
気づかれたのかという図星で、俺は気恥ずかしかった。咄嗟にごまかしたが、オヤジはわかっていたのだろう。
「やってみるか?」
いきなり、立ち上がって俺に鉋を渡してきた。びっくりしている俺に、場所を空け、作業しやすいように場を整えだした。
「丸ノコを使ってもいいんだが、たぶん鉋でちょっと削るくらいで充分なはずだ。ここからこう当てて、ここまで引く。力は均一に。使ったことあるか?」
俺は頷き、つい鉋を受け取ってしまった。オヤジはあまりにも自然体で、構えることも抵抗する必要もなかった。教えられたとおりに体勢を構え、腕を動かす。時間は少しかかったが、鉋で木製のドアを削り、丁番の位置を変えてドアを設置しなおし、建付けを整えた。
「筋がいいな。経験があるのか?」
オヤジが目を細めて俺を褒めた。
「……工業高校を出てるから。ひと通り授業で教わったし」
「だとしても器用だな。いいものを持ってるぞ」
そのひと言と目を細めた笑顔が、その時の俺の中の何かを変えた。自分の手で壊れたものを一つ直した。些細なことだが、忘れていた達成感を思い出した。その後、最後に修理で部屋を訪れたオヤジに、作業のアルバイトをしないかと誘われた。俺は気楽にその誘いに乗り、二年間オヤジの元で働き、リフォームや住宅設備全般の修理の修行を積んだ。オヤジなりに、俺に手に職をつけさせようとしてくれたのだろう。そして2年後、25歳になった年にそのオヤジはノマドランドへ転職し、俺もやや遅れて呼ばれ、正式な社員となったのだ。
俺はおやっさんから仕事の技術を学んだ。おやっさんから、物を直し、造り出して、生き返らせる楽しさを知った。自分の手で仕事を生み出していく喜びを見つけた。自分の生きる世界を見つけたと思った。だから凛々子ともまた再会できたのだ。
おやっさんから仕事を学び続けていくのは楽しかったし、全てがとてもやり甲斐があり充実していた。なのにその充実感がどんどんなくなってきていることに、あえて目を背けていた。
おやっさんはここ数年でどんどん変わっていった。今のおやっさんは、俺が23の頃に出会った時のオヤジではなくなってしまっている。
あの真っ直ぐな目をした、静かに確固たる自分をどっしりと持った、俺の好きだったオヤジ。変わってしまったおやっさんと、そんなおやっさんを変えてしまった組織という名の会社、そして部長や社長という人種を憎んだ。
またひと昔前の、人嫌いの自分が発動しそうな気配に俺は怯えた。
次作、「工程3 これ、蜘蛛の糸か?」 へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
