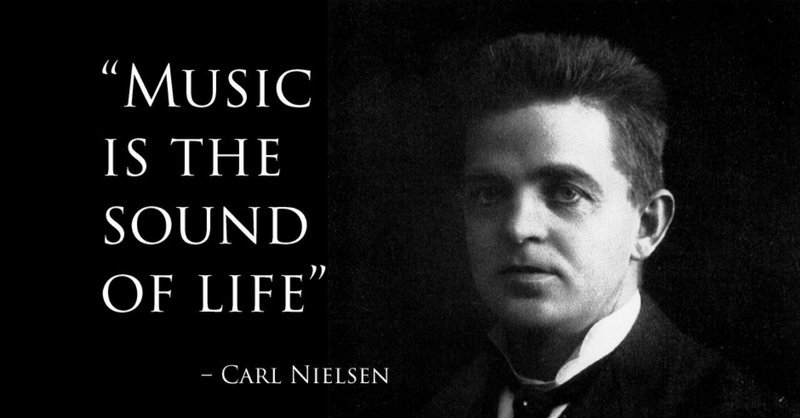
独創性はエゴを父とし生活を母とする...カール・アウグスト・ニルセン “交響曲第三番 Sinfonia Espansiva”
カール・アウグスト・ニルセン(1865-1931)はデンマークの音楽家。彼の生まれた頃のデンマークは、プロイセンとの国境に接するシュレースヴィヒ=ホルシュタイン公国の独立紛争とその敗北という危機に直面している時代にありました。
ナショナリズムの隆盛と帝国主義の衝突による世界大戦の危機という時代の流れの中で、ニルセンは本家本元のドイツ(オーストラリア)に比肩するクオリティと独創性を持つ交響曲を作り続け(6曲作っています)、世界の度肝を抜くことになりました。今風に言うとM-1で吉本じゃないけど毎年決勝に出てくるし超おもしろくてネタの完成度もスゴいみたいな感じだったようです。その功績によってデンマークでお札になってたりする。
ニルセンの曲を聴いてみると、大先輩のドヴォルザークや同級生のシベリウスのように朴訥とした「土地の訛り」が前面に出るという感じでもなく、俺だぜ!という熱さがバンバン前に出ているところが特徴的。ヴァイキング的な土地柄ということもあるかもしれませんが、何よりもニルセン自身が快活でスパッとした自信家だったようです。
ニルセンのもっとも有名なものは4番目の交響曲(これが一番熱い)ですが、今回は個人的に好きなので第3番(1911年)です。外連味の溢れる作風がよくでたニルセン円熟期の出世作です。
前置きが長くなってしまいました。ようやくの音源。地元デンマークのオーケストラによるものです。
“広がる”ニルセンの宇宙
この曲には"Sinfonia Espansiva"という愛称がつけられています。楽譜の最初の指示が"espansivo"とあることに由来しますが、「広がって」「おおらかに」というような意味であるようです。曲を聞く感じだとおそらく意味が二重になっていて、「爆発」と「包容」といったニュアンスを感じます。
起承転結の「起」となる第一楽章はのっけから何のてらいもない同音の連打。「つかみ」のパターンが出尽くした感のある20世紀の交響曲でこの入りは度胸がありすぎる。この”ハッタリ”で一気に加速すると、代名詞となる猛スピードの3拍子で主題が展開されますが、これがもうしびれるほどカッコいいし個性的。そしてこの最初のテンションが冷めることなく最後まで駆け抜けてしまいます。
第二楽章は第一楽章の爆発を「承」、優しく受け止める田園調の緩徐楽章。ソプラノとバリトンの声を楽器として用いて(言葉を発さないで音だけを歌います)天から降りるような調べを実現しています。本来は舞台裏から歌うようにと指示があるので、「天の声」という表現をしたかったんじゃないかなと思いますし、実際その効果が出ています。
「転」となる第三楽章はダブルリードの2楽器がミステリアスなパッセージに対してホルンの咆哮と重ね合わされるトリルが緊張感を引き立てるスケルツォ。そして、フィナーレ、「結」となる第四楽章は威風堂々、大地が歌うように「おおらか」で包容力のあるテーマで大団円。デンマーク、というよりはニルセン自身の森羅万象が余すところなく表現されています。
ワーグナーとブラームスの狭間で
ニルセン青年期の楽壇はワーグナーとブラームスという二大巨頭の派閥論争の最中。いずれもベートーヴェン以降の大家としての地位を確立したのですが、すごーくおおざっぱな理解に基づくと、ワーグナーは音楽を「音を使った大いなるものの表現」と見て大規模な劇場装置やオペラを導入した総合的な芸術をめざし、ブラームスは音楽を「音そのものの美を表現する建造物」と見て緻密な構築美を追求していました。(彼ら自身はお互いの作品を研究し、時には賞賛さえしており、単なる取り巻きのポジショントークにすぎなかったようですが)
ニルセンもまたコペンハーゲンの音楽院時代やドイツへの留学と演奏旅行のなかでこの両巨頭に魅了されます。ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指輪』の上演に接すると「脱帽!」と昂奮を日記に残していたり、ブラームスの論理的な作曲法を尊敬し自作の交響曲を共通の知人を通じてこの大家に見て貰ったりしていたようです。
しかし、ニルセンはフォロワーではなく根っからのクリエイターでした。ベルリンの音楽院でブラームスの親友にして当代きってのヴァイオリンの名手ヨーゼフ・ヨアヒムに卒業制作の弦楽四重奏曲を提出した際の一幕。「比類なき独創性」を認められながらも、「常識外れだ」と指摘された箇所について
「それを直したら自分の作品ではなくなる。それが自分の作品の魅力となっているところなのに」
「そう、君の思う通りに書きなさい。親愛なるニルセン君。私は古い人間なのだよ」
と鋭い切り返しで大御所の温かい激励を得たという逸話が残っています。
デンマークという小国の、それも田舎のペンキ職人の子で8歳から働きに出ていたという貧しい生まれでありながら、堂々たる音楽で歴史に名を残したニルセン。その秘訣は揺るがぬ自信とエゴ。そして、それを堅持するに足る奨学金制度の存在も抜きにできないでしょう。1900年代を象徴するクリエイターの一人です。
*参考
森田ユリ『ポホヨラの調べ 指揮者がいざなう北欧音楽の森 《シベリウス&ニルセン生誕150年》』
カール・ニールセン協会HP
