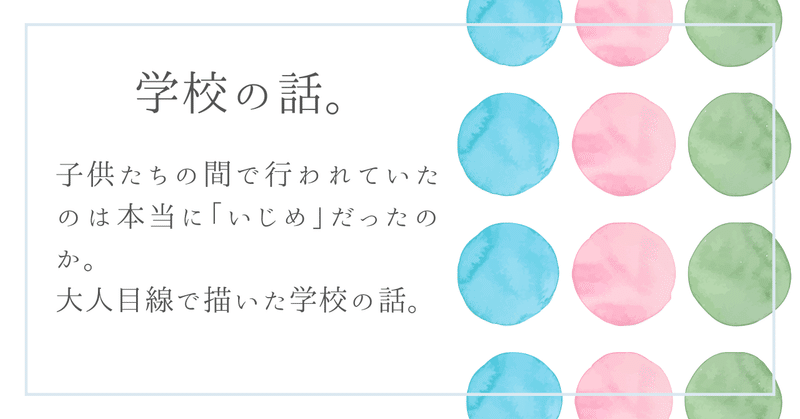
【小説】学校の話。<起>
1)
小渕沢 丈二は、教員生活二十二年目となる今年度、とある町の小学校に赴任した。
児童や同僚たちは、彼を「丈二先生」と呼ぶ。
三学期現在、3年3組の雰囲気はかなり砕けたものになっている。
「ウチ、あの子キライ」
漢字の書き取りノートの山に目を通しているとき、その声を聞いた。
(やれやれ)
赤ペンを走らせながら、小渕沢は嘆息した。
金縁眼鏡のブリッジを押さえて声の方向を見遣ると、廊下側の席に三人の女子児童が固まっている。
本人たちに気づかれないよう、すぐ手元に視線を戻す。
ちょっとしたことで陰口を叩いてみたり、仲間外れにしてみたり。
(女の子は難しい)
こういった兆候は、2年生頃から徐々に現れ始める。
女子三人という状態はただでさえバランスが難しい。
普段の結びつきは強いが、ひとたび何か起これば──。
廊下側に固まる子らは、そこに輪をかけて心配な三人組であった。
たった今「キライ」と発言したのが笹木 凛音。
家庭環境がやや複雑である。
目を丸くして「何で?」と聞いているのが中嶋 千乃。
三人の中ではリーダー格だ。
教師の前では大人しく問題ないように見えるが、彼女に二面性があることを小渕沢は知っている。
そして。
何も言わず、ただそこに居るだけの児童が伊藤 葵である。
とにかく大人しい子で、発言を求められても蚊よりも小さな声を発するか、黙り込むかで終わってしまう。
そんな彼女の唯一の友達が、千乃と凛音だ。
二人について回っているだけで、振り回されているようにも見える。
(何も起こらなきゃ良いがな)
小渕沢は、最後のノートにチェックを入れる。
考え事をして時間を食ってしまった。
テストの採点は会議後にするしかない。
「さあ、帰りの会の時間だよ。日直さーん」
小渕沢が立ち上がると、子供たちは蜘蛛の子を散らすように自席へ戻っていく。
教師という仕事は嫌いではないが忙しい。
効率化しなければやっていられない──。
2)
「瀬尾先生、そんなものまで作るんですか?」
会議後の職員室。
小渕沢が声をかけると、向かいのデスクで作業している女性教師が顔を上げた。
瀬尾 実咲。まだ2年目の若い教師で、3年2組を受け持っている。
彼女は、算数の授業で使うための小道具を作成しているのだった。
画用紙に大きくホールケーキを描き、何等分かにできるようにハサミを入れている。
「昼休みなんかを使ったらいいのに」
「その時間は子供たちと遊んでいるので」
瀬尾が、長い休み時間の度に子供たちと鬼ごっこやドッジボールに興じていることは小渕沢も知っていた。
若いな。
だが、そのうち潰れる。
「瀬尾先生。
熱心なのも結構ですが、もっと効率的にやらないと身体を壊しますよ」
「私が楽しくてやってるんですよ。
一緒にいると、子供たちのことがよく分かります」
いつまで続くかね。
小渕沢は鼻白んだ。
「子供の様子なんて、日頃からちょっと気を配っていれば分かりますよ」
「私はまだまだ丈二先生の域には行けないなぁ。
時間をかけなきゃ分かりません」
瀬尾が笑顔を見せる。
世辞も入っているのだろうが、若い女性に持ち上げられたことで小渕沢は少々気を良くした。
と、職員室の入り口がにわかに騒がしくなる。
「殿山先生、また会議サボったでしょう!?」
キンキン声を発したのは及川というベテランの女性教師だ。
3年1組担任。学年主任である。
「おー、忘れてたわ」
「確信犯ね!」
「俺ぁ、職員室って場所が嫌いなんだよ。
会議だって、どうせしょーもない内容だろ」
及川に捕まった殿山という教師は、面倒くさそうに胡麻塩の頭髪を掻いている。
小渕沢は辟易した。
殿山は苦手な部類だ。
シャツをだらしなくジャージの外に出し、三学期の現在は防寒のためか派手なスカジャンを羽織っていたりする。
教師にあるまじき姿だ。
何故か1〜3年生の低い学年ばかり受け持っており、今年度は1年生の担任である。
厳しい指導は有名で、低学年相手でも手加減しない。彼の教室では毎日一人は児童が泣いているという噂だ。
「あんな不良教師になってはいけませんよ」
小渕沢は眉間にしわを寄せ、小声で瀬尾に忠告した。
瀬尾は微笑を返したのみで、先程のケーキの裏にシート状のマグネットを貼り付けていく。
「ああ、小渕沢先生」
殿山が呼びかけてくる。
彼は、他の教員のように「丈二先生」とは絶対に言わない。
誰からも慕われる自分を妬んでいるのだろうと、小渕沢は考えている。
以前教頭に聞いたところによると、彼は小渕沢と同年に教員免許を取得しているということだった。
「伊藤 葵の母親が来てます」
殿山が3年生のシマに歩み寄ってくる。
小渕沢は不快感を隠せない。
「こんな時間に非常識な。
どうして断ってくれなかったんですか」
「今時は母親だって仕事してるでしょ。
心配じゃないんですか、自分のクラスの児童が」
「……」
「隣の会議室ですよ」
こんな嫌がらせまでされるのかと、小渕沢は憤慨した。
「小渕沢先生、赴任の挨拶でおっしゃってましたよね?
”よく聞く”のがモットーだと」
「線引きは必要です。
こんな対応したら、保護者が増長するだけでしょう」
「今さら追い返すんですか?」
小渕沢は仕方なく立ち上がった。
(会議はサボる癖に余計なことを!)
苛々と職員室を後にする。
殿山の声を背中で聞いた。
「どうもお疲れ様です。小渕沢先生」
3)
口角を上げつつドアをノックすると、ややあって「はい」と小さな声が返ってきた。
「どうも、お母さん」
小渕沢は、平身低頭する伊藤 葵の母親に席を勧める。
「ほ、本当に申し訳ありません、こんな時間に……」
「いえいえ。今日はどうされました?」
葵の母親は、ハンカチで小鼻の辺りを押さえた。
「そのぉ、お友達関係のことで」
「ほほお」
「なかなか、お友達の間に入っていけないようで」
「葵さんと一緒にいるのは、千乃さんと凛音さんですね」
葵の母親は頷くと、心配そうに声を震わせる。
「仲良くできることもあるんです。
ただ、大勢のグループになると、あーちゃんは入れてもらえないと」
公の場で自分の子を”あーちゃん”などと呼称することに、小渕沢は呆れ返った。
葵はもう小学3年生なのだ。
「それは、具体的にいつ頃のことで?」
「ええと、最近では先週……」
何だ、それは。
小渕沢は、自分の頬が引きつるのを感じた。
これでは何のために時間を取ったか分からない。
「……あのですねぇ、お母さん」
小渕沢は何とか微笑を保つ。
「そういったことは、その日に言っていただけると。
時間が経ってしまうと対応しようがありませんのでね」
「はあ、す、すみません……」
葵の母親は、怯えた小動物のように目まぐるしく黒目を揺らした。
(まったく。この親にして、あの子ありって感じだな)
とはいえ、葵を含めた三人組については以前から懸念があった。
いよいよ問題が顕在化してきたか。
「まあ、心配ではあります。
子供たちの間には力関係が存在しますから」
「は、はあ……」
「こちらでも様子を見ておきましょう。
お母さんも、遠慮されずにいつでもご連絡くださいね」
いじめの端緒を掴んだ。
小渕沢は、そう考えた。
ただでさえ忙しいのだ。
早めに手を打たなければ──。
「もう終わったんですか?」
会議室を出てすぐ、書類の束を抱えた殿山に出くわしてギョッとした。
廊下は既に薄暗い。
「伊藤の母親、あまりスッキリした顔つきではなかったようですが」
「ポイントを絞れば、面談なんてすぐ終わりますよ。
立ち聞きはやめてください」
小渕沢は目を三角に尖らせた。
「教室に戻る途中だったんですよ。
俺ぁ、効率的な人間じゃないんでね」
殿山は、立ち聞きなどしていないと言外に匂わせてくる。
小渕沢は、構わず殿山の横をすり抜けた。
「何が”遠慮なく連絡しろ”だ。
先週、忙しいからってお前が応じなかったんだろうが。
及川が言ってたぞ」
聞いていたんじゃないか──!
憤然として振り向いた時には、殿山は既に暗い廊下の角を曲がっていた。
小渕沢が殿山とまともな会話をしたのは、これが初めてだった。
▼次話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
