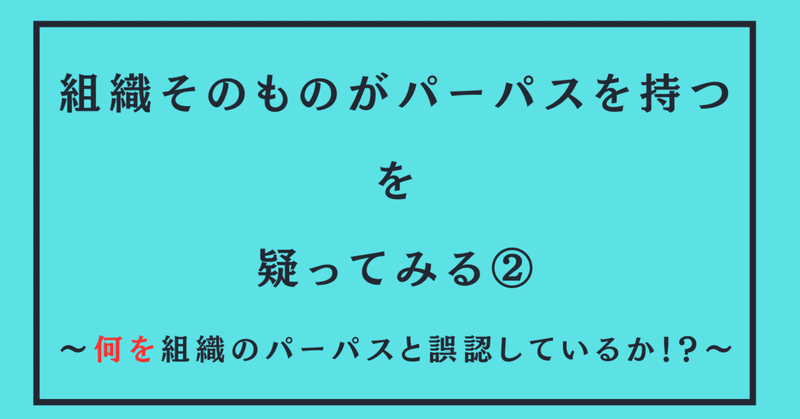
「組織そのものがパーパスを持つ」を疑ってみた②
はじめに
書籍『Reinventing Organizations(組織の再考案)(邦訳:ティール組織)』で示唆されている「組織そのものがパーパスを持つ」ということについて、そもそもソースプリンシプルのレンズで観ると「ない」となります。私も個人的にはそう感じるのですが、「以上終わり」と済ませるのではなく、ソースのレンズを用いたとしても「組織にパーパスがある(ように思える)」という世界について理解を深めてみたいと思い、記事を書き始めました。
前回は、個人の内面にフォーカスを当てましたが、記事で紹介した投影の状態にある個人は、「何」を「組織のパーパス」と誤認しているのか、について仮説を書きたいと思います。
誤認その1「クリエイティブフィールド−グローバルソース=組織のパーパスと観ている」
ソースプリンシプルのレンズではクリエイティブフィールドというものがあります。
クリエイティブフィールド (Creative field)とは?
ソースが「心の中にある、世の中にある何かを創造したりや変化をもたらすようなアイデア(ビジョン)」を実現する際に、必要となる人達やその他のリソースが引き寄せられて、集まってくる、つまり、みんなを魅了するようなフィールドのことを、クリエイティブフィールドと呼んでいる。
クリエイティブフィールドは、ソースがイニシアチブを始める時に生み出される。お互いに活動を共にし、力(エネルギー)を合わせることで、繋がりや一体感からくる一貫性を生み出す場でもある。
このクリエイティブフィールドは、必ずそのイニシアチブにおけるグローバルソースと紐づいているものになります。
ですが、前回の記事でも扱った、「組織のパーパスがある」と観る人の中に、階層型ヒエラルキー及びトップへの抵抗感・否定感を持っている場合においては人(ここでいえばグローバルソース)をないことにし、フィールド(場)としての側面だけにフォーカスが当たり、そのフォーカスが組織のパーパスという誤認を生み出しているのではないか、という仮説を持っています。
誤認その2「クリエイティブフィールドの健全性・一貫性を保つという企業文化=組織のパーパス」
グローバルソースの役割として、クリエイティブフィールドの健全性を保つことが挙げられます。これは言い換えれば、何がクリエイティブフィールドの中なのか外なのか境界(エッジ)を明確にすることと言えます。
とはいえ、これは動的なプロセスであり、実際にフィールド内でコトが起こってみないと、グローバルソース自身もまだ分かっていないことが多いのです。
また、健全性だけではなく一貫性を保つことも重要なことになります。
書籍『すべては1人から始まる――ビッグアイデアに向かって人と組織が動き出す「ソース原理」の力』
著者のTom Nixonは
企業文化とはクリエイティブ・ヒエラルキー内で誰に責任を委ね、影響力を発揮させるか
と書いています。
ここからは私の解釈ですが、この健全性・一貫性を保とうとし続ける人(エッジを守る人)がより多くフィールド内にいられるようにすることもグローバルソースの役割だと思えます。
そして、この「エッジを守る」ということ自体は企業文化と言えそうですが、この意味での企業文化そのものを組織のパーパスと見做してしまうのが2つ目の誤認だと思っています。
クリエイティブフィールドも企業文化も土壌のようなもの!?
書いてみて思ったのは、クリエイティブフィールドと企業文化はどのような関係にあるのだろう、ということです。
Tom Nixonは文化について以下のように書いています。
●文化とは?
・相互交流によって生まれる動的な「現象」
・直接的に変えることはできない
・文化を牽引するものはクリエイティブ・ヒエラルキー
・あるシステムにいる人たちの考え方や感じた方の動的な相互交流であり、絶えず進化するものーエリック・リンー
ソースプリンシプル提唱者のピーターカーニックに文化をどう捉えているのか聴いたことがないため、上記はあくまでTomの見解となります。
また、これは著者とディスカッションしたり、関連する発言があるか英語記事などに当たっているわけではないので、あくまで私の独自の考察になりますが、
クリエイティブフィールドも企業文化も土壌のようなものであると捉えることはできないでしょうか。そして、種は、そこで働く1人1人と言えないでしょうか。
クリエイティブフィールドは別にして、私は企業文化とは『(あくまでも)土壌であり、そもそも人が持つアイデア(種)が芽吹きやすいかどうかに影響のある要因であり、どんな種が芽吹き無事に育っていくかを決めるもの』と捉えたいと思います。
また、グローバルソースを否定している場合、この種から出てくるものの中で、土壌の健全性・一貫性を保つための新しいアイデアは育まれるかもしれませんが、この土壌自体を含む全体の方向性(未来)については雲がかかったままとなり、徐々にクリエイティブフィールドは枯渇していくでしょう。言い換えれば、グローバルソースが未来を創造する直接的な根源ということですね。
文化は「目に見えない形」であり、クリエイティブフィールドは「流れ」と区別することができるのかもしれません。これは引き続き考察していきたいと思います。
さいごに
気になってしまったので、とてもマニアックなテーマでありながら考察記事を書いてみました。一晩寝かせて読み直してみたら、こんなニッチなネタ誰が読むんじゃ!?というツッコミが湧きましたww
書籍『ティール組織』の内容に慣れ親しんでいる方以外では、そもそも「組織そのものがパーパスを持つ」ということ自体がイメージが湧かないのに、さらにその先について考察しようと思ってしまったという・・・汗
ただ、書いたことで分かっていないこともたくさん出てきましたので、ソースのレンズを通した世界への解像度を高めるためにも、著者や提唱者に機会があれば尋ねることを通じて探究を続けたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
