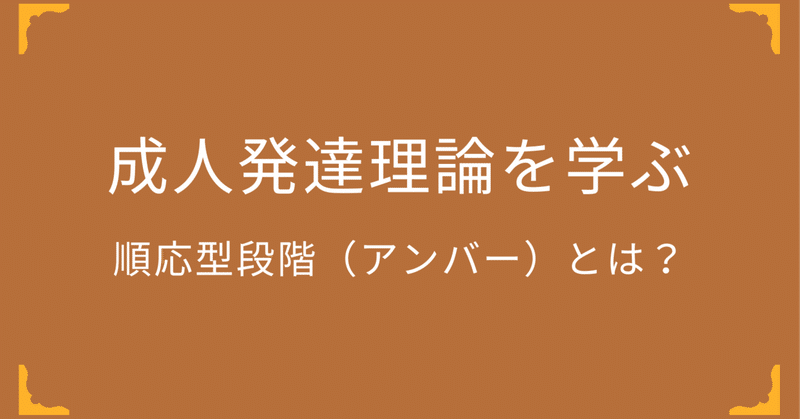
順応型段階(アンバー)とはどんな段階なのか?基礎について学んでみる
はじめに
先日こちらの記事にも書いたのですが、書籍「ティール組織」が出版されて以降、成人発達理論にも注目が集まる一方で、ティールという段階への美化に伴い、それ以前の段階の陰陽でいう「陰の部分」にフォーカスが当たりやすくなっている状況があるように思えます。
それによってティール以前の段階が軽視されるとしたら、それはある種の不健全さをもたらすと思えます。(厳密に言えば、その軽視やそれによって生じる課題自体はその人自身の発達の重要なプロセスと言えるので良い悪いはないのですが)
私自身、2018年にティール組織の書籍に出会い惹かれて、実践探究を続けていますが、最近、各段階への理解を深めていきたいという気持ちが高まってきたので気持ちが続く限りは記事にしていきたいと思います(笑)
まず、今回はアンバーという発達段階を扱います。参照書籍は、鈴木規夫さん著『人が成長するとは、どういうことか ーー発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ』です。
成人発達理論を学ぶ上で重要なこと
書籍の中でも繰り返し提示されているので引用します。
『発達理論というものが「諸刃の剣」になり得るということである。』
『活用の仕方を誤ると、この理論を容易に、人間を順番付けするための道具に堕してしまうことにもなる。そして、最悪の場合には、「発達段階は高ければ高いほど望ましい」というような優生学的な発想に道を開いてしまうことにもなる(その結果、発達段階の低い人々を侮辱・差別したり、あるいは、高次の発達段階に向けて効率的に成長や発達をするように他者に強制・強要したりする発想に陥ることになってしまう)。』
『発達理論とは、何らかの意図に基づいて、人間を操作するためのものとして利用されるべきものではない』
『そうした意味では、発達志向型支援の文脈においてはー他の対人支援と同じようにー支援者には倫理的な意識が求められることになる』
順応型段階(アンバー)の位置づけについて理解する
外向のフェーズ
ケン・ウィルバーは人間の発達のプロセスを大きく2つのフェーズに分けています。前半期のことを外向のフェーズと形容しており、少なくともアンバーからオレンジまでの段階がこのフェーズに該当しそうです。
特徴はこちら。
●外向フェーズの特徴
・一人の社会的存在として自我を確立する前半期。この段階における発達上の課題は、自らの生きる社会や時代の中で共有されている価値観や世界観を習得(内面化)し、それらを素材として独自の生き方を確立していくこと
・自らが生まれた時代や社会に与えられた脚本に基づいて生きることに集中する段階
・死の拒絶という自己を衝き動かす根源的な衝動に無意識なまま、そうした衝動に支えられてさまざまな活動や事業に取り組んでいく
また、なぜ外向という名称かというと、「メインテーマが時代や社会という外的な文脈の中で自己を確立することにあるから」だそうです。
慣習的段階
順応的段階(アンバー)は発達段階を3つの大別するレンズを用いた時の2番目、慣習的段階に位置する段階です。この段階には他に、アンバー・オレンジ段階が属しています。(鈴木規夫さんの書籍では、アンバー/オレンジという間の段階も紹介しています)
この慣習的段階の重要な目標は、「個としてのアイデンティティを確立する」ことです。言い換えれば、以下の問いに対する答えを見出していくといいうこと。
この社会において私はいかなる存在として生きていくのか?いかなる価値を生み出して貢献をしていくのか?
なお、ここでいうアイデンティティの確立とは、「複数のペルソナを確立し、それらを統合するプロセスを通じて達成される」ことだとされています。(組織人、職業人といった特定の役割に紐づいた限定的なアイデンティティではない)
この確立に至る段階は後期合理性段階(オレンジ)だそうなので、順応的段階(アンバー)はそこまでのプロセスに位置しているとも言えます。
いかにして順応型段階(アンバー)に発達していくのか?
こちらでは書籍の中から順応型段階に発達していくためのポイントだと思われる箇所を引用します。
共同体の中で共有されているそれらの規則や規範を基本的に無批判に受容
自身が生まれた共同体の中で共有されている言語や作法や物語や価値観や世界観を学び、それを内面化することを通して、真の意味でその共同体の一員になっていく
思ったこと
ここに書かれているプロセスは、この記事を読まれているような方であれば少なくとも2回通っているように思える。1回目は、自我が芽生える前、2回目は(日本の場合)小中高大いずれかの学歴から働き始めてから慣れるまで。
順応型段階(アンバー)の伸び代とは?
ここでは、順応型段階の傾向(表裏一体としての伸び代)について紹介します。
外部より与えられた役割や規則を基本的に無批判に受容し、それらに立脚して行動する
この意識は、また、共同体の中で共有されているそれらの規則や規範を基本的に無批判に受容するために、実質的にその支配の下に生きることになる。たとえそれが歴史的に継承されてきた大切な価値観であるとしても、「果たしてそれが今もなお真実として信頼に値するのか?」という問いを発しようとしないのである。
人は自己の所属する共同体の価値観や世界観に呪縛され、それを共有しない他者を拒絶したり、否定したり、排除したりする傾向にある
自身の拠り所となっている価値観や世界観を対象化して内省・検証するために必要とされる基本的な心理能力が育まれていない
この発達があることで可能になることとは?
ケン・ウィルバーはこの段階の意識を「他者に与えられた期待や規範や規則に従って自らの思考や行動を律する意識」と形容されていうそうです。また、この段階の成果・可能になることについて書籍ではこのように紹介されています。
こうした意識は、われわれに自らの中に息づく利己的な衝動や欲求を制御することを可能にする真に特筆するべき発達上の成果と言えるものである。(例:「今日は疲れているので運動部の練習は休みたいところだが、部長としてはそんな弱音を言うことは許されない」
つまり、この発達段階に到達すると、人々は、物理的に監視されていなくても、内面化された規則や規範に基づいて、自己を監視することができるようになるのである。また、こうした意識が共同体に生きる人々の中にひろく共有されることで、はじめてその共同体は文明としての基本的な条件を満たすことができるとさえ言えるのである。
また、他にも可能になることとしてこんなことが紹介されています。
この発達段階で涵養されるとりわけ重要な「能力」は、共同体をともにする他者を同胞や同士として受容し、彼らとともに共同体の将来に向けて叡智を結集して協働していこうとする意志である。すなわち、自己に執着するのではなく、自己を「超えた」ものに対して自己を捧げることを学ぶのである。
この発達段階における学びは、その後、われわれが後慣習的段階(グリーン〜ティール〜ターコイズ)に向けて歩みを進めていくうえで、非常に重要になる。中でも特に重要になるのが、「他者」との関係性のなかで自己の探求を深めていく能力である。
アンバーとは、共同体の一員としてのアイデンティティに基づいて生きることを学ぶ発達段階である、そして、この発達段階を十全に経験し、そこで必要な学びを得ることを通して、われわれははじめて自己に対する執着と対峙して、それを超えたものとの関係の中で生きるための方法を会得するのである。もちろん、そうした能力は、後慣習的段階に向けた深化の過程の中で洗練され、時代や社会に与えられた価値観や世界観を超えたところにある、より高次の現実に基づいて生きる能力に昇華されていく必要はある。しかし、その基礎は、このアンバーにおいて確立されるのである。
さいごに
書籍では、この段階からどういう取り組みをしていくと次の段階へ発達していけるのか?についても書かれていましたが、さらに長くなってしまいますので別の機会に回します。
また、書籍「インテグラル理論を体感する 統合的成長のためのマインドフルネス論」によると、ケン・ウィルバーはそれぞれの発達段階には、「前の段階を超えて含む」性質があると言っています。「新たな発達段階は前の段階を包み込んでいるのと同時に、前の段階には全く存在していなかった新たな内容を付け加えている」という意味だそうです。
そして、この普遍的なプロセスにおいて、超えると含むのいずれかがまずい方向に進むことがあるとのこと。
「超える」の面に失敗すると、前の段階から抜け出せず、その段階に「固着」し続ける。そのため、固着している部分に対するさまざまな「中毒」が発達する。
「含む」の面に失敗すると、新たな段階が以前の段階を包含すること、統合することをせず、その段階を否定し、新たな段階から切り離してしまうとーー新たな段階において、そうした認めてもらえていない側面、望まれていない側面に対する「アレルギー」が発達する
今回は表層的にしか紹介できませんが、この2つの観点は秀逸だなぁと感じました。安易なセルフチェックはよくないと思いますが、あえてこの観点で私自身のアンバー段階、とりわけ「規範・ルール」ということに対する感覚でいうならば、頑なさを感じる(中毒と捉えています)領域と、避けたい感覚を感じる(アレルギーと捉えています)領域のどちらも感じるのが正直なところ。
今の人生のタイミングもありますので、改めて学び、解像度をあげる&プラクティスをしてみたいなぁ。
気になる方はぜひ書籍「インテグラル理論を体感する 統合的成長のためのマインドフルネス論」を読んでみてくださいね。(濃ゆい本なので読み手を選ぶと思いますが)
おまけ
成人発達理論とは?発達段階とは?について入門的な内容を知りたい方は、私が学び始めた頃に書いたこちらの記事がオススメです!ぜひご覧ください(今回引用している鈴木規夫さんの書籍からの引用はありません)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
