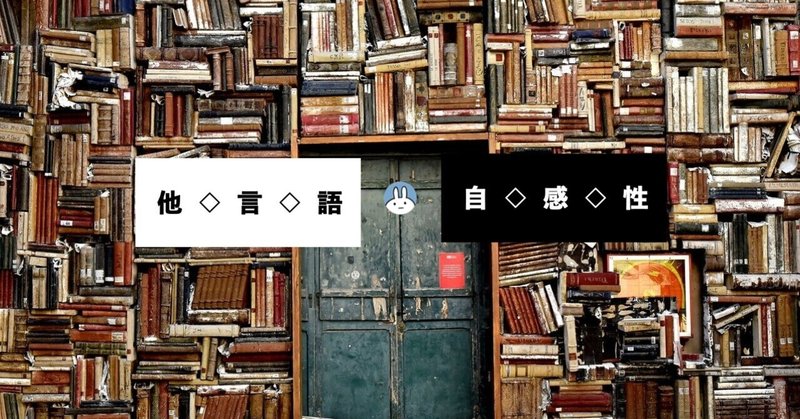
他 ◇ 言 ◇ 語 ・ 自 ◆ 感 ◆ 性
感情はものすごく多様で、人によって、そして環境によって微細に揺れ動く。言葉はその雲をつかむような心の動きを「捉える」働きをする。
だから、語彙力が覚束ないと引きずられて感情も乏しくなってしまうのではないか(持論)。
もちろん、感情を音で表現したり、絵で表現したり、笑いで表現したり、物語で表現したり、表現の仕方はそれぞれなので一概に語彙力といっても簡単に万人を測ることはできないかもしれない。
言葉が感情を作っている
言葉によって感情が豊かにも乏しくもなる、そう思うようになったきっかけは、苦手な外国語を使って生活していたときだった。あるとき、ふっと自分の感情がとても淡白になっていると感じた。大学のレポートを書いていたときだったかもしれない。感じたことを感想として書いていたのだけれど、少しアイデアを足したくて日本語に翻訳しなおしてみるとなんだかとても薄っぺらかった。あれ?これは本当にわたしの感情なのだろうか?なんとも不思議な心持ちだった。
映画をみて面白かった!と言う時、"面白い" にもいろんなニュアンスがある。ゲラゲラ笑ったとか、ハラハラドキドキしたとか。恐怖映画ですら、面白いと感じるには恐怖の背景になにか愛しさやくすぶっていた感情や微細な心の動きがあったはず。感動に涙したことも同じ面白いという言葉で表現できてしまう。その涙にも、悲しみ、同情、悔しさ、悲惨さ、憧れ、さまざまな感情が入り混じっている。
それらをぜんぶ "面白い"という言葉に集約できてしまう。当たり前だけれどもよく考えるととても不思議。そして、興味深いことに面白かったと表現すると、「オモシロカッタ」としか感じなくなる。言葉というのは自分がどう感じているかを表現するものであると同時に、自分の雲を掴むような感情に言葉という「カタチ」を与える行為でもある。つまり、あるレベルでは言葉が感情を決めている、そんな側面がある。
だから、外国語の苦手なわたしが語彙力の低い言語を使って生活すると、感情そのものの表現の幅が狭まり、ひいては感情の「カタチ」が淡白に収まってしまったのではないか。
中学時代の恩師の今と昔
先日、中学校時代の恩師に会った。これと似たようなことをおっしゃっていたのが興味深かった。ゆとりだなんだと言われるけれども、今の中学生も昔の中学生も本質は変わらない。同じように一生懸命で、同じように悩んでいる。ただ、最近の子供達は語彙が少ないかもしれない。例えば、なんでもかんでも「ヤバい」で片付けてしまう。こないだのテストがヤバかった、お母さんとの関係がヤバい、○○くんがカッコよすぎてヤバい、あそこのクレープがまじヤバい。そいう友達内でしか伝わらない言葉遊びは昔からあったから悪いことでは決してないと前置きした上で、でも「ヤバい」という表現しか知らないような節がある。生活指導をしていて、彼らを見ていると多感な時期に、自らの悩みを「ヤバい」としか表現できないことで返って苦しんでいるように見える、とおっしゃっていた。
人は言葉によって感情を自覚していて、その言葉にどうしても収まりのつかない感情がでてくると溢れてしまう。国語の勉強が重要なのはまさにそのためだとわたしは思う。別に漢字が書けなくても、小説が嫌いでもなんでもいい。でも、少なくとも自分が表現したい心を言語化できる能力を持っておくこと、これが「私は何者か?」の問に対する答えを見つける近道なのではないか。
幼少期の多言語教育について
そう考えると、日本語もおぼつかない幼少期から、グローバル人材を育てるといって英語やら多言語を学ばせることは、親の意図に反して実はリクスの高い選択なのではないかとわたしはほんのりと思っている。
もちろん、言語に対してとても柔軟な適応能力をもっていて、返って多言語を学ぶことで言語野が活性化しているような子もいる。わたしの友人でも言語が得意な子は、英語にロシア語にスペイン語を学び、今ではポルトガル語を話してブラジルに在住している。○○な表現をするのは日本語だけなんだとかよく語っていたが、わたしにはほぼ理解不能だった。ただ、そういった人材は希だと思う。むしろそれは特技だ。
逆に、別の友人の子は幼少期から日本語と英語の英才で育てていたのだけれども、小学生に上る前に自己表現がうまくできずにコミュニケーション障害を起こしてしまった。以来、家庭では1つの言語のみに絞ってコミュニケーションをとっているのだそうだ。これは先程の恩師の話にも通じるところがある。
英語とグローバル人材
グローバル社会で有用な人材を育てるために、英語を学ばせるという目的は少し的を外しているような気がする。英語などの母国語以外の言語ができたらグローバルな人材にほんとうになれるんだろうか?
海外で活躍したいとか英語がしゃべれるようになりたいって大人でも言う人がたくさんいるけれども、それって車を運転できるようになりたいって言っているようなもの。どこにいきたいのか?何をしたいのか?がなければ免許証だけのペーパードライバーになってしまう。
誰に伝えたいのか?何を表現したいのか?何を吸収したいのか?まずは自分の意思を育むことからはじめなければ何も生まれない。もちろんそれは日本語でなくてもよい。いいか悪いかは置いておいて、それならば日本語を捨てて公用語をいっさい英語にするべきだろうと思う。
ただ、共通言語を英語にするという話も言うほど簡単なことじゃない。例えば、日本語には「かわいい」なんて言葉がある。なんとなくわかると思うけれど、これは英語で言う Cute とはちょっと違う。いや、だいぶ違う。この「かわいい」っていう言葉は今や英語でも "KAWAII" と訳されるようだけれど、「かわいい」というのは日本語独特の表現。このかわいいという言葉が共通認識されることで生まれている感性がある。
つまり思想には、日本語だからこそ生まれた思想がある。英語だから生まれた思想がある。ヒンドゥー語だから生まれた思想がある。言語というのはしゃべれればよいというものではなく、乗りこなせなければ意味がない。そしてその言語体系はおそらく思想に深い意識下で影響する。
教育という観点からみれば、母国言語そのものも意識的に育てていかなければならない。その責を負えるほどの大人がどれだけいるだろうか?ただ喋れればいいというのは少々無責任であるように思われる。言語を会話のツールとしてだけではなく、意識や感情の創造という観点でみるとだいぶ違った見え方がしてくるのではないか?
多言語教育には意味がない!?
では、多言語教育が意味がないのか?と言われると、そうとも言い切れない。どっちやねん!それはまた別の問題だろうと思う。
繰り返しになるけれど、思想には日本語だから生まれた思想がある。英語だから生まれた思想がある。ヒンドゥー語だから生まれた思想がある。だからこそ、本当の意味で思想や文化や背景を理解したければ、言語体系から入らなければいけない段階が必ずある。何か興味をもったら、その文化や文化背景を学ぶために言語を学ぶというのはとても大切なアプローチになるはず。哲学を学んでいるとそんな風に思うことが多々ある。
言語を習得するプロセスを学んでおくことはきっと役に立つはずだ。
今の日本での英語教育はそういったプロセスよりも、単に意思伝達のツールとして扱われている節が強いように思う。そしてここが最も不可解なのだけれども、英語のできる・できないが人の優劣の評価軸として優遇されすぎている点も見逃せない。これは戦後、アメリカの占領下において植民地としての言語統制の結果だと主張する人もいるし、大学受験制度の弊害だという人もいるようだけれど、ここではあまり深入りはしない。
思い込みを剥がす
自国の言葉を縦横無尽に使えるようになると、その言葉で収まりをつけてしまう、という話があったけれど、これはより哲学的な繊細な領域では返って弊害になるかもしれない。言葉の語彙が増え表現の幅が広がれば、感情の幅はどんどん拡張していく。言葉は感情そのものではない。むしろ唯物的な性質を持っている。つまり語彙には限界があって、語彙が「わたし」という意識そのものを凌駕することは決してない。
わたしたちが普段に何気なく使っている言葉の生むギャップは、より本質的なもので更に顕著になってゆく。
白って、ほんとはどんな色なんだろう。あなたが見ている全ての白色は、光の加減で実はうっすら灰色がかっています。純粋な白なんて現実には存在しない。それでも目の前の白壁をみて白いと表現して誰も疑わない。タージマハールの壁の色を聞かれて「灰色です(大理石には不純物も含まれていて、表面には土埃が付着しているから)」なんて言う方が頭がオカシイと思われてしまう。
言葉も同じ。
言葉を駆使することで、理解したつもりになってしまっていることって結構身の回りに溢れているもの。慣れ親しんだ言語から離れたとたん、あれ?こっちじゃないかも?と気づいたりする。自分の感覚の方を言語に寄せてしまっていることに気づく。そんなとき、何気なく表現していたことを、他の言語に置き換えてみる。すると、あれ?ここでいう○○って言葉は実はとっても曖昧で、はっきりとした定義ができていないことに気付かされる。他言語の習得はそのような気づきを与えてくれるかもしれない。
言葉に頼りすぎると本質がねじ曲がる
語彙力に長けた人は言葉に頼りすぎて、言葉で生活しすぎてしまう。返って問いに意味付けをしてしまう。そして、「私」という本質を捻じ曲げてしまう。みな形は違えど「私は何者か?」という問いを常に抱きながら生きていて、その問いにもっとも簡単に答えてくれるのが言語なのだと思う。
人間の考えは言語。思考には必ず言語が伴う。だからこそ、言語で表現すると安心し、言語で表現できないものは、ともすると感情をその言語に収めようとして心を形作ってしまう。
そうすると、思考や思想は言葉によって定義づけ/縛られてしまう。
「私は何者か?」の答え
思想家が言語に縛られない己の本質をみるときに、瞑想をすすめるのもきっと言葉の思考プロセスから己を意識的に分離させるためではないかと思ったりもする。より深く己を知る段階において、言葉は返って弊害にもなる。
月とは何か?と問われたとき、月の本質は月を見て体感し得ることでしか会得できない。言葉でそれを表現することはできない。だから、黙って月を指差す。ところが、みんな月を見ずにその指をみてああでもないこうでもないと議論をしはじめる。しかし、その本質は空を見上げなければならない。誰しもいつか、指を離れ空を見上げなければならないタイミングがきっと来るのではないか。
指し示す指は己の表現のひとつ。
今日はぼぅっとしながら、言語の習得と、言語からの解脱について、そんなことを思った。
りなる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
