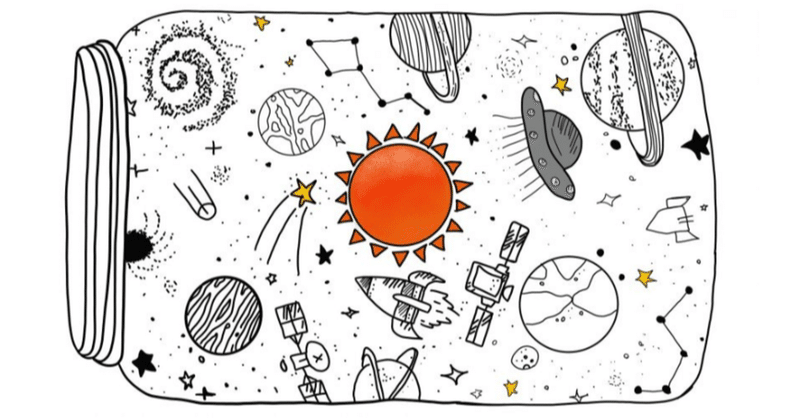
「仕事は楽しい」をあたりまえにする科学
「仕事はつらくてあたりまえ」「お給料をもらっているんだから耐えるもの」なんてよく言われますが、それってホントだろうか?
毎日疲れて、不毛な仕事ばかりに時間を費やしていて、それでも生活のために仕方のないことなのだと、半ばみな諦めている。そもそも労働はつらくてあたりまえだというこの考えは、どこからきているのだろう?そこに根拠はあるのだろうか?もし、根拠のない偏った見方なのだとしたら、わたしたちはそろそろこの仕事に対する考え方自体を見直す必要があるかもしれません。
モチベーションを上げる誤った方法
お金はもらえればもらえるほどモチベーションはあがるし、やりがいも感じられるようになると多くの人は考えがちです。キャリアアナリストのダニエル・ピンク氏によって紹介されていた面白い研究があります。それによると対価としての報酬は仕事の質の向上にはつながらないと言うのです。なぜなら、報酬があると意識がタスクそのものよりも「報酬」に向けられるようになるからです。報酬が見込めないことには意欲がなくなってしまうし、報酬を最大化するためには不正を働いたり、仲間と協力しなくなったりもする。そして、最も大きな問題は意識が無意識のうちに創造性が阻害されてしまうこと。つまり、わたしたちの常識に反して、報酬のないタスクのほうが成果がでるというのです。これは報酬の大小に関わらず100円だろうが1,000万円だろうが起こる。「報酬」によって仕事から意識がそれ、意欲だけでなく品質や創造性までもが失われてしまうのです。
補足しておきますが、報酬がまったく意味がないといえばウソになる。例えば単純にネジ1本10円で締めるとか、頭を使わない単純作業には報酬は効果的なようです。ネジを100本締めれば1,000円。1,000本で1万円!このような場合は報酬が高ければ高いほど仕事の成果や品質は上がる。ただ、いまの社会で頭を全く使わない仕事なんてほぼないし、あったとしても近い将来、AIやロボットに代替されていくことでしょう。
以前わたしは社員会議で何でもいいから社長に質問しなさいなどと、むちゃぶりをされたことがあり、とっさにこんな質問をしたことがあります。
「会社にとって社員の幸せってなんですか?」
それに対する社長の回答はこうだったと記憶しています。「会社には多種多様な人がいて、それぞれに幸せの定義は異なる。だから一概に社員の幸せはこれだ、っていうことはできないけれど、どんな社員もお金は必要だし、お金によって生活の質が上がる。だから、会社にとって社員の幸せを定義するなら、より高い給料を目指すこと。その原資を稼ぐためにみなさんにはいっそうの努力をしてもらいたい。」多くの社員はうなずいていたけれど、これを聞いてわたしはどうも納得感を得られなかった。いま思えばこのどの会社にとっても模範的な考えこそがモチベーションの低下を招いている。
何かに没頭する喜びは作り出せる
自分の好きなことをしているとき、時間が経つことも体が疲れることも忘れてしまうほどに、没頭する体験をしたことはないだろうか?こういう体験からこそ永続的な喜びが生まれる。「ハマってる」ものがある時期は、それ自体が楽しく四六時中そのことを考えてたりもする。恋愛であれゲームやスポーツであれ、そこに「どハマりする」という体験が生活を大きく変える。この「どハマりする」状態を作り出すことはできるものなのだろうか?
心理学者のミハイ・チクセントミハイ氏は、この「どハマり」状態を「フロー」と呼んでいる。彼によるといくつかの条件がそろうことでフロー状態に入りやすくなることがわかっている。その条件を人工的に作り出すことができれば、どハマりする体験の手前までお膳立てできるだろう。趣味趣向の個体差はあるにせよ、その条件がいったいどれだけ難易度が高いものなのか目を通してみてほしい。それは次のようなものだ。
1. 何をすべきか、どうやってすべきか理解している
2. 日頃の現実から離れたような、忘我を感じている
3. ただちにフィードバックが得られる
4. 活動が易しすぎず、難しすぎない(能力と難易度のバランスが適切)
5. その場を支配している感覚(自分が有能であるという自覚)
6. 活動に本質的な価値がある(だから活動が苦にならない)
7. 自分はもっと大きな何かの一部であると感じる
正直どの条件も状況を適切に管理する程度のことであることに、わたしは驚いています。モチベーションコントロールなどにやっきになっている管理職にこそ、このリストをじっくり吟味してもらいたい。仕事を没頭できるほどにやりがいのあるアクティビティーへと変えたいなら、タスクそのものの成果や報酬に目を向けさせるよりも、個人と仕事との関係性についての「適切なバランス」に目を向けていくほうがよほど重要だということです。このバランス調整をこなすコーディネーターが現れれば、仕事はどんどん喜びを伴った活動に変わっていくかもしれない。
フローになりやすい活動
さて、彼の研究で驚く主張がもうひとつあります。ここでみなさんにひとつ質問をしてみたい。現代社会において「フロー」に最も到達しやすい環境はどこにあると思われるだろう?旅行先の歓楽街だろうか?ゲームだろうか?スポーツ観戦だろうか?または競馬場やパチンコなどギャンブルだろうか?
わたしたちの身の回りで「娯楽や趣味などより遥かにフロー状態に達しやすい環境がある」とミハイ・チクセントミハイ氏は言う。勘のいい人はもう気づいたかもしれませんが、それはなんと「職場」なんです。 明確な目標、即座に得られるフィードバック、手の届く能力で充分に対応できる課題など。職場こそ、これらの条件が最も揃いやすい環境なのです。
条件さえ揃えば楽しみ没頭できるだけでなく、うまくこなせさえもする。「仕事はつらくてあたりまえ」は科学的に言えばなんの根拠もない。むしろその逆のことが言える。そうだとするなら、わたしたちがいま経験している「忌々しい職場環境」は、まったくもって謎めいた現象ですらあります。
仕事とは関連性のない『遊び』だけを楽しめて、人生で取り組む真剣な仕事を耐え難い重荷として耐えなくてはならない、と信じる理由はもはや存在しない。仕事と遊びの境界が人為的なものだと気づけば、問題の本質を掌握し、もっと生きがいのある人生の創造という難題に取り掛かれる。
フローを生み出す条件についてもっと詳しく知りたければ、次の動画もおすすめです。
仕事はしなければならない、という ”非常識”
仕事をしなければならない、という常識を捨て、自分の生きがいや、やりがいを追求すること、好きなことを追求し続けるだけでも生きていける、ということが実感できること。ここ数年そんな風潮が芽吹き始めている。SNSを眺めていると、phaさん、プロ奢さん、レンタルなにもしないさんなどの「ただ生きる」という当たり前のことが当たり前にできない世の中への挑戦が目立つようになってきたように感じています。(本人たちからすると挑戦ですらないのだろうけれど)レールの上を歩くことしかできないわたしには、生きる安心を与えてくれる挑戦のようにも映る。この安心こそが、クリエイティビティーの源であり、次の大きな潮流を生み出す源泉だとわたしは思うのです。
ただ、こういった行動はまだ現代の作られた常識に対するアンチテーゼにしかなっておらず、より能動的な潮流を生み出す活動にまでまだ到達できていません。こういった風潮が社会に浸透するには更に次のようなステップを進む必要があるようにわたしは思います。(1)「不毛」なことはやらなくていい。(2)個々に「やりがい」を見出し生き生きと活動できる。(3)このような活動を能動的に「組織」だてて作り上げる。この3つのステップを経てはじめて「場」としての喜びのあり方が完結するのではないでしょうか。今はまだ、1と2を行ったり来たり、3についてはその重要性すら語られていない。まだまだ道半ばです。

死ぬほど残業していたわたしにとって、「時短の推奨」「サービス残業の廃止」などの施策は非常にありがたいし意味があることだと思います。ただ、一方で「仕事は耐え難いつらいものだ」という固定観念が前提になったアプローチでしかないのも事実です。社会にとって大勢の人がワクワクできる舞台は、むしろ職場であり仕事なのです。そのエンターテーメント性やクリエイティビティーに満ちたフロー体験の場を、常識という名の非常識で殺してしまうのはとてももったいない。
より根源的な問題として、仕事がなぜ楽しくあってはいけないのか?8時間労働?オフィス常駐?昼寝はしてはいけない?私語もだめ?それはなぜなのか。繰り返しますが、そこに科学的な根拠はないんです。むしろ科学的には仕事は本来楽しいもの。そして、それを選ぶことはそんなにむずかしいことではないのです。
りなる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
