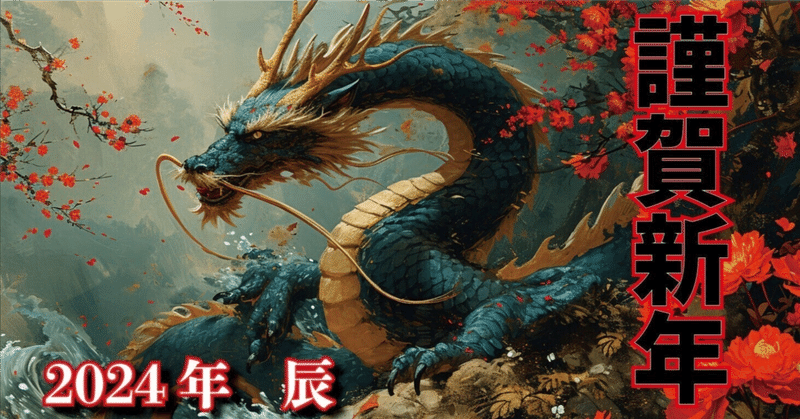
あすなろ荘のこれから(2)
画像はSUGUHARA様のものを使わせていただきました。ありがとうございます
新年あけましておめでとうございます。
また北陸での震災におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
約三か月ぶりの投稿になります。
こんにちはLet's be tomorrowです。
あすなろ荘のクラウドファンディングはおかげさまで、目標金額を大幅に超えるご支援をいただきました。
本当にありがとうございます。
#あすなろ荘 #こどもギフト #READYFOR #クラウドファンディング
このクラウドファンディングは老朽化した建物を建て替えるための資金集めでした。
ただ建て替えるだけでしたら、何とかなるのですが、せっかく建て替えるのであれば、あすなろ荘でこれまでできなかったところもやれたらと考え、「入居者支援×退居者支援×地域の青年支援」をコンセプトに設計を検討しております。
前回は入居者の支援について書かせていただきました。
本日はその二回目。
退居者の支援についてお話していきたいと思います
あすなろ荘の「これからの退居者支援」
あすなろ荘の退居者支援
あすなろ荘の退居者支援は基本的に入居者の支援と変わりはありません。
それでも違うところがあるとすれば、目の前ですぐに支援ができるか、そうではないかの違いでしょうか。
基本的に、卒園生から「やり方がわからない」「話を聞いてほしい」等の連絡が入らないと私たちは特にこちらから定期的に連絡をとったりなどはしていません。
連絡が来た場合は、あすなろ荘に来てもらうか、私たちが退居者のもとへ会いに行くかで対応しています。
自立援助ホームは基本的に6名定員で職員が3名配置が基準となっているため、宿直の入の日や明けの日の前後の空いている時間でしか対応することが困難だったのです。
退居者も遠慮していた
十数年前、あすなろ荘の職員で宿直業務がむずかしくなり、日勤業務のみで働いていたスタッフがいました。
日勤業務のみのため、宿直職員が別にいたこともあり、それまで以上に退居者からの相談にのって、必要とあれば会いに行くことができるようになりました。
するとそれまで行っていた退居者支援以上に「実はこれも困っている」「ここに一緒にきてくれないか」とリクエストがどんどん増えてきました。
彼らの話を聞いていると、やはり職員が宿直の合間に相談にのっていることを知っているため、これ以上お願いするのは難しいと思っていたようです。
そこで、そのスタッフを退居者支援中心の業務に切り替えると、そのスタッフほとんどあすなろ荘にいることがなくなってしまいました(苦笑)
自立援助ホームの退居者支援
本来自立援助ホームにはアフターケアという概念がありません。
入居中も退居中も支援の中身は変わっていないと考えています。
なので、アフターケアではなく、「退居者支援」なのです。
はじめにも述べましたが、入居中も本人の意思を尊重し、それに対して相談にのったり、お手伝いしたりするのが自立援助ホームの支援です。当然退居後も同様に本人の意思を尊重する中で、必要に応じて相談にのったり、必要に応じてお手伝いしていくのです。
しかし、入居者のようにいつも目の前にいるわけではありません。
そこで私たちはつながることを意識した支援をしています
つながり続けるための支援
あすなろ荘が退居者とつながり続けるために行っていることは下記のとおりです。
①あすなろ荘への来宅・電話相談
あすなろ荘には時々退居者も遊びに来たり、電話かかってきます。
入居者が生活している場所ではありますが、そこに特に用事がなく遊びに来ている姿を見て、こういう風に利用をしていいんだと感じてもらっています。電話相談も本人の承諾は得ますが、よほどの相談ではない限り、調理をしながら話すこともあります。これは、深刻な相談ではなくても電話をしたり、遊びに来てもいいんだという入居者へのメッセージでもあります。
②誕生日カードの送付
あすなろ荘では退居者にたいして誕生日カードを送っています。この誕生日カードには入居中にいたスタッフはもちろん、その時にかかわっていないスタッフにもメッセージを書いてもらっています。
私たちスタッフはいずれあすなろ荘から離れてしまいます。
しかし、退居者からすればあすなろ荘はいつまでも自分が生活した場所ですし、何かあったときに頼ることができる場所の一つであると思っています。
だからこそ個人でかかわるのではなく、あすなろ荘として退居者支援を行っているということのメッセージでもあります。
もちろん誰に相談するかは退居者自身が決めることですが、相談したいスタッフがいつもあすなろ荘にいるわけではないので、その人がいないときでもカードの名前が書いてあれば、じゃあ聞いてくださいということにもなるのです。
実際に私もあすなろ荘で働く前にここで生活していた方たちとつながって支援を継続したということもあります。
③食料品の送付
これは新型コロナウイルスが流行した3年前から始めました。
スタッフもなかなか対面で会うことができなくなった状況で、少しでも退居者とつながろうという目的でそれまであすなろ荘の機関紙を送っていた7月と年末に食品を送るようにしました。
メッセージと一緒にあすなろ荘のLINEのQRコードをつけて送ったところ、それまで電話番号しかわからなかった退居者ともLINEでつながることができました。電話だとなかなか連絡をしてきませんが、LINEをつけたことで届いたことへの感謝のメッセージが多く寄せられ、やはりコロナ禍で仕事がなかったりして困っているという話も聞き、何人かの支援につながりました。はじめは一人暮らしをしている人たちのみでしたが、今は家に帰った人たちにも送っています。
親御さんからも連絡をいただくこともあり、そこで相談にのったりすることもあります。親御さんも話を聞いてほしいということもわかりました。
退居者が困った状態になるのはいつになるのかわかりません。
あすなろ荘ではない別の場所に相談ができる場所があるかもしれません。それでも様々な形で、あすなろ荘はあなたとつながっているんだよというメッセージを送り続けることで、本人が困ったときにあすなろ荘に連絡できるようにしています。
とにかく本人からつながりを断つことがあっても、私たちから断たないようにしています。
これからの退居者支援
一昨年改正された児童福祉法で退居者支援を行うための拠点事業が制度化されました。これまでもあすなろ荘と同じ法人の事業でアフターケア相談所ゆずりは等、全国にいくつかの退居者支援の事業がありましたが、それが児童福祉法によって制度化されたことでより退居者支援に特化したことができるようになります。
国で自立支援担当職員が配置され、退居者支援が少しずつ手厚くできるようになる一方、やはりあすなろ荘に来るには入居者の都合なども考えなければなりませんでした。
今年の夏以降あすなろ荘は建て替えを予定しています。新しいあすなろ荘ではこの拠点事業を行うための部屋も作る計画です。そこの部屋は今のあすなろ荘のLDKをなるべく再現したいと考えています。
自分の生活していた場所がなくなることはやはりさみしいものがあるかと思いますが、そこの場所だけはこれまでとなるべく変わらない雰囲気を残せればと思っており、今使っている家具もそこにもっていこうと考えています。
何かあっても、別に何もなくてもちょっとあすなろ荘に行こうと思ってもらうことが、退居者支援の肝だと考えています。
あすなろ荘に興味を持たれた方はぜひホームページもご覧ください
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
