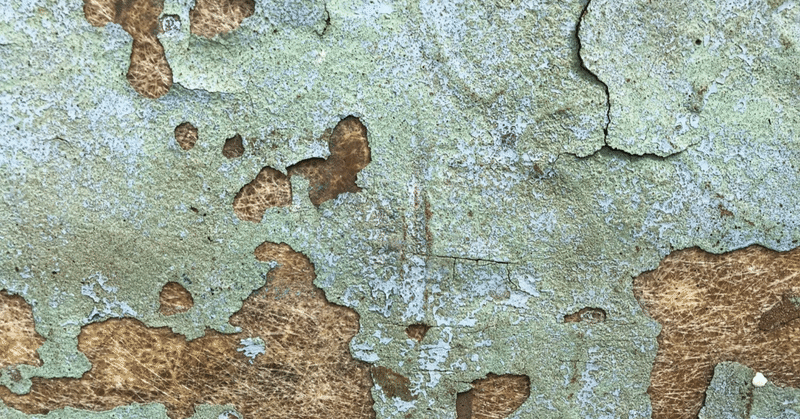
3月のカタルシス 【エッセイ】
新年が始まってから、断片の寄せ集め本しか読めない、断片的な詩文しか書けないといった日々が続いていたが、3月はそれよりはまとまった時間が取れたように思う。仏像を観に行ったり、中編小説を読んだりして、そのことを散文にしたためることもできた。
生活のわずかな違いを体感したことで、ますます「人間には物語の力が必要だよな」という認識を強くした。つまり、断片は確かに大事だが、その組み合わせや並べ方次第でいかようにも変化する。大事なのは流れの方ではないか、ということ。
「構成」が大事だ。義務教育で習うレベルの話であり、アマチュアでも口酸っぱく言われ、プロならばこれを重視しない人はいないだろう。断片──たとえば美文とか、素晴らしい場面描写とか、細やかな心情描写、こういったものも流れを損ねる場合には物語のゴミになりかねない。
そういえば今月は久々に物語の投稿ができた月でもあった。主宰する神話創作文芸部ストーリアに寄せたものだ。《投稿する》をタップした時、久方ぶりのカタルシスが得られた。書けない書けないで思い悩んでいたため(定期)、投稿できたことは単純に嬉しい。
文学の意義のひとつに、読者がカタルシスを得るというものがあるのは言うまでもない。一方で作者がカタルシスを得るという側面もあり、その動機も結実も決して侮れるものではない。
吉行淳之介は自らをカタルシス型の作家と称していたようだ。想像にすぎないが、現代に生み出されている作品にも著者のカタルシスが透けて見えることがある。
物語をざっくりとハッピーエンド/バッドエンドに分けた際、果たしてどちらがカタルシスを得やすいのか。このことは昔からよく考えていたのだが、暫定的な解としては、ハッピーエンドでは短期的で表層的な浄化、バッドエンドには長期的で深層の浄化作用を期待する、と言えそうな気がする。
だからアンパンマンにしても水戸黄門にしても、勧善懲悪ハッピーエンドは連載して益々の強さを発揮する。バッドエンドの映画なんかはいつまでも心に居座り、微かに心を照らし温めるような余韻を残す。
(フツウは)思い通りにいかないのが人生。だから創作内では、思い通りにいくように舵を切るか、思い通りにいかないまま描く方に舵を切るかで文学の態度はだいぶ異なってくる。もちろんクリアカットに分かれるものではないが。
芸術とは、先ず第一に、不幸の意識であって、不幸に対する埋め合わせではない。
この言葉を見たとき、心に貼り付けた幾重ものクロスを素手で引き裂かれたような心地がした。「埋め合わせ」も、作品の流れを滞らせないために、作品を完結させるために必要な要素だと思う。しかし終のところで不幸そのものを見つめられているか。安易なカタルシスに雪崩れ込んでいないか。ましてや心の深層まで降りてゆくべき詩において、緩んだ自己解決を求めたりしていないか。そんなことを自問させられたのだった。
◇
書き殴っただけの乱文にて失礼しました。
ご支援頂いたお気持ちの分、作品に昇華したいと思います!
