11月に聴いたもの
これから毎月聴いた音楽で印象に残ったものを新譜・旧譜関係なくざっくばらんに紹介するノートを始めていきます。
では早速11月から。
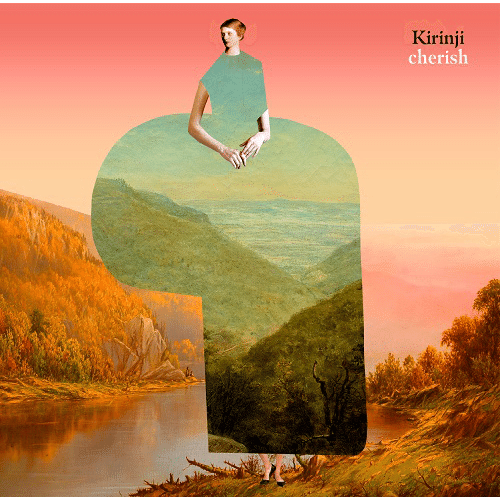
KIRINJI 『cherish』
キリンジのアルバムは発表されるたびに都度話題になるが、今作は特に普段そこまで聞かないという人にまで波及して話題になっていた印象がある。そしてどれも絶賛の声。
自分が聴いた第一印象はというと、「なんか同じような雰囲気の曲が多いな」という、一見ポジティブではないものだった。コトリンゴの脱退以後の前作「愛をあるだけ、すべて」から、今作への方向性を模索していたように感じていて(個人的には前作はバチッとハマる楽曲がなくそこまで聴き込めていないのだが)、その過渡期を経て今作で完全に新たなサウンドを会得していて驚いた。
音色を間引く(曲単体、アルバム通して)、低音を強調するアレンジやミックス、マシンドラムの多用、マイナー調の楽曲の多さなど、2018・2019年以降の流行を緻密に抽出して楽曲に落とし込んだのが感じられる。結果として「堀米高樹という絶対的なフロントマン+個性豊かなメンバー」という図式が良い意味で薄まったように感じる。
「楽器(音色)の固定」という意味ではある意味ジャズっぽくなったとも言える気がする。アコースティックらしさ、というか。「雑務」と「善人の反省」と「Pizza VS Hamburger」がお気に入り。

Terri Lyne Carrington 『Waiting Game』
恥ずかしながら大物だったのを存じ上げなくて、参加してるエスペランサやアーロン・パークスの名前を見ててっきりそれと同世代のイケてる兄ちゃんを想像していた。それほどに音作りが今っぽく、所謂大御所っぽいオーラも良い意味でなく、勢いで押し通す大味なプレイなどもなく、キレも繊細さもある作品と感じた。
内容はラップなどもありストレートアヘッドなジャズ感は薄いが、アーロン・パークスのタッチやスケール使いが絶妙な塩梅でジャズらしさを担保している。アーロンのコンポーズである『Bells』は彼のリーダーアルバム『Little Big』でも演奏されており、リリックが乗ることでより奥行を増している。
2枚組の後半はエスペランサやストリングスを迎えた組曲で、こちらもベクトルこそ違うがシャープな印象。
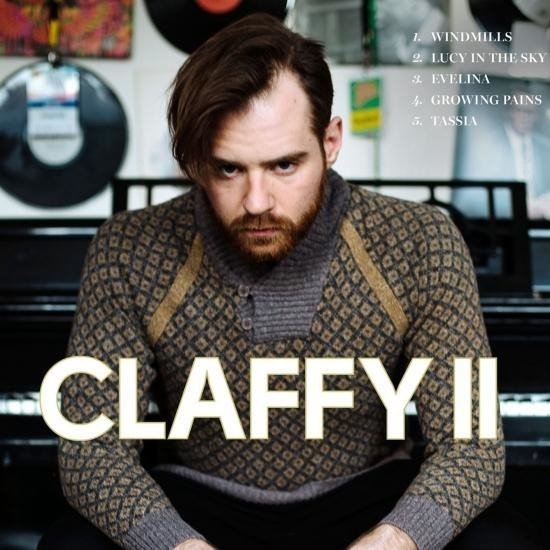
Alexander Claffy 『CLAFFY Ⅱ』
Bandcampやサブスクから消えてしまった一枚目『Claffy』にはカミラ・メサなどが参加しており、また『I'll Be Seeing You』や『With A Song In My Heart』などのスタンダードを小気味良いアレンジに仕上げていてよく聴き込んだが、実質のデビュー作となった前作『Standards: What Are You Doing the Rest of Your Life?』ではカート・ローゼンウィンケルを呼んでかなりストレートアヘッドに舵を切った印象で個人的にはあまり引っ掛からなかった。
その後に今作が発表されたわけだが、タイトルからも分かるように一枚目の流れを汲むキャッチー路線のジャズとなっている。バランス良く歌ものを配しており、ソロのバランスもちょうどよくアルバム通して聴きやすい。
そうするとやはり一枚目を手に入れておくべきだったと思うが、現在国内では流通していないようである。

Coletivo ANA 『ANA』
レオノラ・ヴェイスマンやイレーニ・ベルタチーニらミナスの女性8人の声楽を中心にしたアルバム。そしてディレクターにハファエル・マルチニ、その他レアンドロ・セザールやジョアナ・ケイロスなども参加している。
レアンドロのガラスのマリンバなどの創作楽器が入ることで、主役となる声がより強調されている点が面白い。良い意味での手作り感というか、儀式的な空気を感じることができる。

Joana Queiroz 『Tempo Sem Tempo』
本祭には参加できなかったが、『Festival de Frue 2019』のアフターパーティにて彼女のソロアクトを観ることができて、その感動のまま購入。
そのライブでは基本的に多重録音のこのアルバムの内容を再現するためにルーパーや各種エフェクター(およそクラリネット奏者とは思えないほどの数の)を駆使するものだったのだがその組み立て方が新鮮だった。様々なアンサンブル出身の彼女だけあって、分かりやすいサイクルのリフでループを組み立てるのではなく、長尺で時にはルバートなセクションも挟みながらループを構築して展開していた。聴き手ははじめループポイントを容易に予測できないためループミュージックならではの没入感に達するのが難しいのだが、2回目3回目とオーバーダブを重ねるごとに曲の輪郭を掴み始め、その複雑なハーモニーとループ構築の妙にハマっていく。
そんなライブならではの体験を先にしてしまったのだが、アルバムの方はより静寂や音響に拘った作りになっており、ライブとの対比が楽しめた。ほぼクラリネットとバスクラリネットのみを使用して抽象的かつここまで奥行のある音楽を作れるとは、ぜひまた生で観たい。

Satoshi & Makoto 『CZ-5000 Sounds & Sequences』
日本人の双子のシンセサイザーユニットとのこと。タイトルのCZ-5000はカシオのシンセのようでその音を中心に作られている。
テクノ感ある音色なのだが、楽曲の方向性としてはエレクトロニカ的なノスタルジーを感じるものが多い。

Sam Wilkes 『Live On The Green』
2018年に一気にブレイクしたルイス・コールの動画でほんわかした顔でエッジの効いたベースを弾いているお兄さん。
前作はスタジオ盤だったが今作はライブ盤。メンバーはサム・ゲンデル、ジェイコブ・マンなど同じく界隈のお兄さんたち。ルイス・コール周りでは基本的にビートが効いたプレイを披露している彼だが、自身のリーダーではよりメロウなサウンドを志向している。サム・ゲンデル(こちらも昨年に続いて今年もFRUEにて来日)もサックスを多様にモジュレーションしてほぼシンセのように扱っているし、この二人はほぼセットのようだ。
構成的にあまり展開しないが垂れ流しにならず、どこかのパートがヌルヌルと何かしら微細な動きをしているので、チル要素の強いアンビエントのような体で聴ける。

Trio Curupira 『Curupira』
エルメート・パスコアールのバンド出身のピアニスト、アンドレ・マルケスの率いるトリオ。
エルメート門下らしく賑やかでバラエティに富んでいるが、アンドレはパティトゥッチやブレイドとも共演していることもありよりジャズ色が強い。
昔マンフレッド・フェストというピアニストのジョビントリビュート(『Just Jobim』)をよく聴き込んだが、このような古き良きジャズサンバの香りも仄かに感じるあたりが好感。
ジャケットがウルトラマンに出てくる怪獣みたいなのだけ謎だと思っていたら、タイトルにある『クルピラ』とは、「ブラジルの民間伝承の神話上の生き物。このクリーチャーは、西アフリカとヨーロッパの妖精の多くの特徴を融合していますが、通常は悪魔のような人物と見なされていました。 」(Wikipediaより)とのことで、それをイメージしてるのだろう。

Yes! Trio 『Yes! Trio: Groove du Jour』
アーロン・ゴールドバーグ、オマー・アビタル、アリ・ジャクソンによるトリオ名義。2019年でこういうスウィング至上主義みたいなピアノトリオは彼らとベニー・グリーンくらいしか知りません。あとケニー・バロンとかでしょうか。
個人的にこういうピアノトリオ聞くと「丸の内コットン来そう」って思うんですが、それは私だけではないはず。基本的に真新しいことは無く、ただただ美味しい曲と上手いプレイが並んでいる。
なんだかんだジャズ研出身だと、定期的にこういうアルバムも聴きたくなっちゃうものですね。

石若駿 『Songbook4』
石若駿のソングブックプロジェクトの4作目。毎年1枚、しっかりリリースを重ねてきている。
角銅真実(vo)と西田修大(gt)をほぼ固定メンバーとして、石若本人はドラムは勿論ピアノもバリバリ弾く。このピアノのヴォイシングとタッチの繊細さとドラムのギャップ。なんというかもう二重人格ですかレベル。
ソングライティングについても独特で一聴しただけでも相当アクロバティックなコード進行が続くことが分かる。所謂モード的なスケールのスイッチングではなく、あくまでコーダルにコード単位で細かな転調を繰り返してるという印象。その為トーナリティも長短もはっきりせず、楽譜臨時記号だらけなんだろうなあと勝手に想像している。
なんにせよ、プレイもコンポーズも4作も重ねれば完全に(ピアニストとしての)『石若節』が確固たるものとなっていて素晴らしい。

白と枝 『さみどりの眠り』
確かTwitterでぽろっと見かけて知った女性SSW。フォーク基調だが、ところどころちょっと不思議なコードやメロディセンスで印象に残っていた。
この方はライブで観ると心打たれるだろうな。

長谷川白紙 『エアにに』
前作EPは昨年の12月発売だったようで、それからほぼ1年ぶりの新作でフルアルバム。アルバムタイトルもソングタイトルも一癖あるものが多く身構えながら聞くと、そこに叩き付けるような音数。しかし前作の乱暴にグチャッと投げ付けられたような楽曲群より、気持ちまろやかになった印象もあった。
音楽理論オタクであろうことは一聴すれば分かるのだが、前述の石若駿のコンポーズとは思想が全く違うと思っていて。石若駿はおそらくメロディとハーモニーが同時に生み出されている気がしていて、長谷川白紙はもとになるメロディを作った後細かく切り刻んでリハモ(もはやクラスターのようなものまで含む)して作っている気がする。なんとなく後者はメロディの普遍さを担保として、その器の上にギリギリ溢れないで載せられるだけの具を載せてやろうみたいな信条を感じられる。あのアンサンブルが最初から頭の中に鳴ってたら正直疲れそうというか。ともあれ、これだけリズム的にもハーモニー的にもごつ盛りの危ういトラックを成立させることができるメロディセンスと歌声は凄いと思った。
今の時代「本人が歌う」という自作自演が一番作品に筋を通せるなと。

松井優子 『アンティークレース編み』
冨田恵一プロデュースのオーディションで選ばれた方のようで2009年の作品。その『一角獣と処女』が出色の出来で、特にドラムの訛りが完全にサンバのそれで、これがステップ入力で作られていると考えるとどれだけ当時からクオンタイズに造詣が深かったのかと思ってしまう。
それ以外の曲のプロデュースは冨田さんでは無いようだが、全体的に安藤裕子のドリーミーな感じをより強調したポップで小洒落た楽曲が並ぶ。
久々に「J-POP」にときめいてしまった。
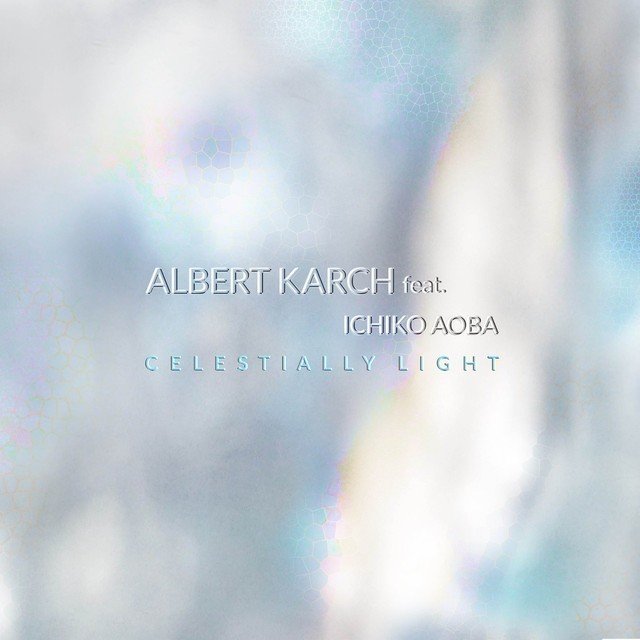
Albert Karch feat. 青葉市子 『Celestially Light』
ポーランドのアルベルト・カルフ(pf、ドラマーでもある?)と青葉市子がコペンハーゲンで録音したという作品。アルベルト・カルフについて検索したがドラマーで来日してるという情報を目にして、多分同一人物だと思うが、詳細が分からず。
アンビエント的な音響のピアノの散文的なリフレインとひそやかな金物の響きを中心に成り立つ音楽に、時折青葉市子の少女性と女神性の両方を感じさせるような声が横切っていく。彼女は色々と引っ張りだこの印象だが、このような少々ジャズの香りがするピアノ作品への参加というのはまだ聞いたことがなくて新鮮だった。声色を大きく変えていないのに様々な雰囲気の曲に妖精のようにふわっと溶け込んで存在してしまうキャラクターは本当に凄い。

Andrew Pekler 『Sounds From Phantom Islands』
アンビエントがアンビエントであるほどに、音楽的要素よりも哲学的要素の方が増す気がして、前者を武器にしている自分がコメントするのがなかなか難しくなるのだが。こちらはどちらかというとIDMに近い感じのアンビエントで、ひんやりとした耳に気持ち良い音が集まっている。クリック、グリッチ系からIDM、エレクトロニカ、そしてアンビエントへと聴き進めて来た自分としては、それぞれの音がバランスよく詰め込まれている気がして心地が良い。

FINAL SPANK HAPPY 『mint exorcist』
リアルタイムでスパンクハッピーを聞いておらず(なんならいまだに聞けていない)、菊地成孔のポップス的な活躍は『普通の恋』くらいしか知らなくて、この作品の文脈などほとんど把握できていないのだが、単純に音だけの話をするとめちゃくちゃ良かったです。
菊池氏のことをちゃんと知ったのは確かDub Sextetがファーストアルバムを出したときで、これにハマり一時期ずっと聴いておりました。それから過去作を一通り聴き、東京ザヴィヌルバッハを聴き、という感じで今に至るのですが、その間は基本的にはジャズのフィールドでの活躍しかリアルタイムで見ていなかったのでした。
そして今作ですが、それまで細かくインスタなどを追っていたわけではないので音源をちゃんと聴くの自体これが初めてで、楽曲の骨組みだけ見ると王道的なところが多いが、音作りと声色のアレンジで最初から最後まであっという間に聴き通してしまった。capusule的なキッチュさに、コードをより複雑化して、最後に今風のミックスにグッと持ち上げた印象。
「聴ける」と「揺れる」と「踊れる」のちょうど重なるスイートスポットを狙い撃ちしてくるようなズルいアルバム。
なかなかこれだけの枚数に真面目に対して文章を書くのは普段慣れていないので、自身の修行も兼ねています。継続できるように頑張ります。
以下各アルバムからの個人的好みによるプレイリスト。ジョアナ・ケイロスのみサブスク無しなので、ぜひ購入を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
