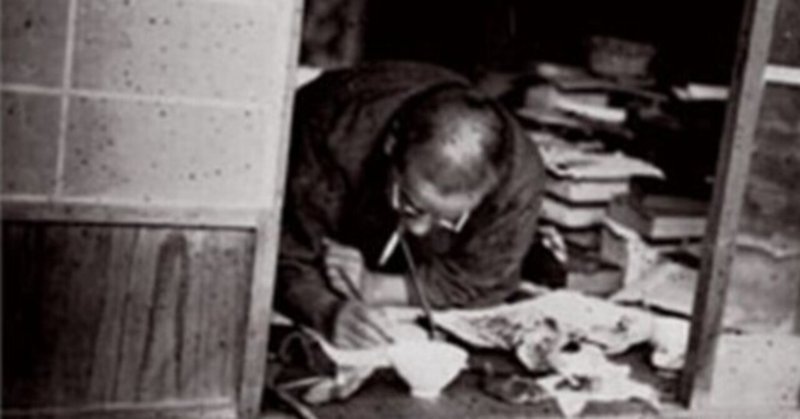
曖昧なボーダー:南方熊楠とわたし(前編)
2年以上前に読書メモの流れで書いたものの、後半の内容が濃すぎて公開できずにいました。ようやく時がきたのかも?
熊楠から、インナーチャイルドの話に繋がっていきます。全2回。
「南方熊楠の見た夢 パサージュに立つ者」
夢、やりあて、南方曼荼羅については中公新書「南方熊楠 ー日本人の可能性の極限」よりも先に読んだ「南方熊楠の見た夢 パサージュに立つ者」(勉誠出版)に詳しい。著者は同じく唐澤太輔さん。
推薦文は、こちらの大御所!
中沢新一 氏 推薦
この研究は、南方熊楠の創造的な思考が、外的な現実と心の内的祖型とをつなぐ中間的な「通路(パサージュ)」でおこなわれたことを明らかにする。
その通路を開くのが夢であり、粘菌であり、仏教であり、熊楠は未来の学問のためにいくつもの創造的な通路を発見してくれたのである。
南方熊楠研究は本書をもって、新しい段階に入った。
いくつか読んだ中で、こちらの書評は簡潔で良かった◉
ちなみに中公新書の読書メモはこちら、「南方熊楠ゼミ」カテゴリに。
熊楠とわたしの共通点/相違点
「南方熊楠の見た夢」は、ボリュームが相当あった。2週間近くかかって読んだ感想を、無理を承知で簡単にまとめると
①自分自身と近い部分のある熊楠に親近感を持った
②言語化しにくい現象や心理状態、行動の動機をあえて言語化すると、こうなるのか・・・という驚き
①は、夢と現実の区別が曖昧なほど抜け出せなくなってしまったり、この世とあの世の境目を行き来してしまったり、自己と他者の境界が曖昧になる体験などのこと。わたしは夢見タイプではない点で熊楠と決定的に違うけれど、それ以外は身に覚えがある。ここで言っているのはHSP的な敏感さとはちょっと違う(それも持ち合わせているけれど)。
こういう不思議体験をする性質(能力)は、必ずしも生まれつき「現れる」わけではない。幼い頃は、その性質を持っていたとしても意識するレベルではなかったり、後天的に発達することも多々ある。その逆もある(おそらくそのケースが多い)。要は「全ての人間が本来は持っていて、スイッチを入れれば使えるようになっている」類のもの。これは、よく言われるけれど本当のこと。
スイッチは勝手に入る場合と、意図的に入れる場合がある。勝手に入る代表例は事故(頭を打つ)、死にかけるなど。後者の代表例は・・・瞑想かな? わたしは両方やったけれど、決して霊能力を得たかったわけではなかった。頭を打って死にかける事故のあと、療養の過程で様々なヒーリングや治療を経験していくうちにスイッチが入っていった。瞑想をするようになってしばらく経ったある日、とつぜん頭頂から開通してエネルギーが入り込むのを感じた。集団瞑想だったので、他の人たちがいつも言っていること(感覚)が、ようやく理解できた。それから徐々に通信感度は強くなった。
ラジオにも例えられるけど、周波数をキャッチする感度のレベルに個人差はもちろんある。でもラジオはみんな持っている。受信できる状態かどうか、アンテナが立ってるか?という違いがあるだけ。
熊楠は、知人の死を予知することが何度かあり、こんなふうに書いていたらしい。(P188、熊楠の記録から筆者が現代語訳した部分)
人がまさに死のうとするとき、 その人は覚悟を決めて、日頃のことや昔の交友などのことを思い出す。その際の強い思いは、池に石を投げたとき渦紋が生ずるように、あるいはラジオの電波が四方八方に発信されるように広がるという。しかし、熊楠は、それを「受信」できるのは、そのような力を受けるに適した脳の持ち主だけだと言う。(唐澤太輔)
熊楠は、個々の脳の能力次第だと言っていて、ある意味そうなのだが・・・それが「生まれつき鋭い感覚を持った、特別な人だけ」という意味であれば、厳密には違う。現代においては、この能力を使っている多くの人が「本来は人間がみんな持っている能力で、それを使うか使わないかの違い」として捉えているはず。「わたしは特別である」と言ってのける人がいたら、ちょっと怪しんだほうがいい。ただ、それが「できる人」が少数派であることは今のところ間違いない。地域差はあると思うけれど、現代日本では少ないだろう。自分は違うけど友達にいるよ!という人は、いるんじゃないだろうか。類は友・・・なので、わたしは周囲にそういう人が比較的多い。でも、こういうことを話す相手は選ぶ。
選ぶといえば、受信するものや程度を選択したり、場合によってOFFにしたりという調整ができると、生きやすい。逆に、できないと非常に苦労する。本を読んでいても、熊楠が苦労していたことが見受けられる。那智山に籠る生活を終えたのも、このままだと自我を喪失する危機を感じたためではないかという。
見たくないものや聞きたくないものが常に入ってきたら、もはや魔界だ。発狂すると思う。わたしは(完全にできているわけではないけれど)不用意にスイッチONにはしない。必要なレベルだけ受信しておく。自分に危険なものと有益なものが区別できる程度に察知できればいい。それ以上キャッチしたければ集中して感度を上げる。ここがコントロールしきれたらプロだと思うけど、わたしはそこまで達していない。だけど、初期に比べたら随分うまく受信できるようになっていると思う。
実際、この性質というか体質のせいで、やりたかったはずのことが出来なくなったり、もうやりたくなくなった、ということは幾つかある。近年は化学物質(特に香り)への拒絶反応が増したことも加わって、逃げ場がない閉鎖的な空間で不特定多数の人に対応する接客業ができなくなった。今は「特定」多数の人とコミュニケーションをとる仕事で、接客は業務全体の3割以下なので、続けられている。そんな感じで自分の性質と折り合いをつけられるよう微調整しながら生きている。
受信能力を全開バリバリにすると、ほかの意識と一体化してしまって戻れないこともあった。状態としては、幽体離脱に近いのかなと思う。体を抜け出して自分を上から見たりはしないけど、自分にしっかり戻れない時は、声が出せなかったり体が動かせなかったりしている。半分抜けているみたいな、ふわふわの危ない時、戻るために現世の添加物モリモリで「人間が加工したぜ!」という(普段わりと避ける)食べ物をコンビニであえて買って食べたりする。一緒にいる人に頼む時は、もし呼び掛けても反応がなくなったら体を揺すって、何か音を出して。手をパチンと叩くとか!等と言いおく(相手はもちろん選ぶけど、慣れない人は困るだろう)。そんな感じで戻る。
わたしは20代くらいまでは、第6感は敏感な方かな?というくらいで、霊感など全くないと思っていた。幼少期にそういった経験もない。30過ぎてから強くなっていき、へろへろにくたばるくらいまでやられる体験もして、これじゃあ生きていけない、と思ったりもした。今はずいぶん落ち着いた。
だいぶ脱線したけれど、本の著者自身には、このような不思議な体験はないとのこと。しかし熊楠の体験や考えを否定せずそのまま受け入れ、熊楠のことを想い、あらゆる方面から資料を読み、分析し、考察している。このような研究者の情熱は、愛に等しいと思う。
②の「言語化しにくい現象や心理状態、行動の動機をあえて言語化する」ことについて・・・この投稿でも、ある程度は言語化を試みたつもり。さらに特殊な体験については、後編に。同じ体験をした人に出会ってみたいと、長年思っているけど見つからない。
よろしければサポートをお願いします。クリエイティブな活動をしていくための費用とさせていただきます。
