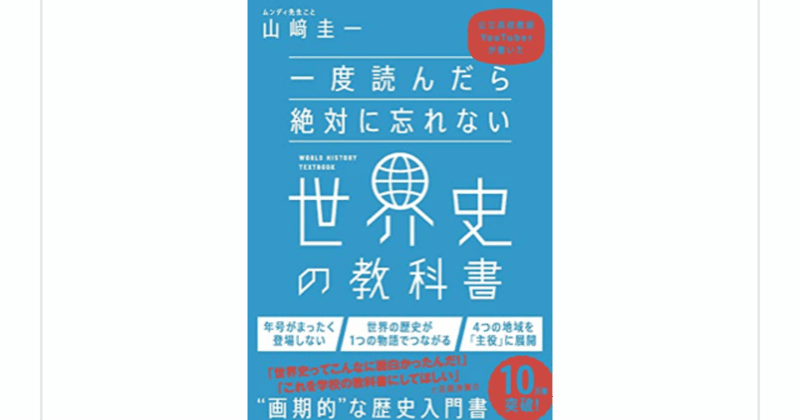
『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書』を読んで
むずかしい本あるある。
*いまどこを読んでいるかがわからない
*「誰が」言っているのか見失いがち
たとえば泉鏡花の『草迷宮』は意図的に主語を曖昧にさせてあるのて苦労して読みました。
歴史の教科書も言われてみれば構造的にわかりにくかったかもしれません。公立高校教師の著者は、その課題感から、
①なるべく一直線で語る
②主役はぶらさず固定する
③年号は後で覚える
といった工夫を施します。
実際、その授業は好評を博します。リクエストを受けてYoutube動画で紹介したところ大ヒット。ついに本書の出版にいたったということです。
色の使い方はじめとして細やかな目線が行き届いている、ていねいな本です。
出口治明さんは「あえて分けず」に一緒くたにして語ることで世界史のダイナミックさを掴めるようにしています。
松岡正剛さんはかつて『情報の歴史』でそれぞれの歴史を年代順に「並列で置く」ことで、同時代に世界で何が起こったのか一目でわかるようにしました。
ようするに、いろんな工夫があっていいと思います。
たしかに大航海時代までは、ヨーロッパ・中東・インド・中国、それぞれを一気に語ってしまった方が理解しやすい気がします。年号は前後すると混乱するのでひとまず置いて、巻末付録にしてしまうのもよい工夫です。
「受験生でなくてもおもしろい!」とおすすめを受けて手にとってみました。全体をバーって読むと、やはり大航海時代からグッとおもしろくなりますね。ふむふむと感じたところをかんたんにメモします。
*命を狙われたルター
カトリック教会にガチ切れして「九十五か条の論題」を叩きつけたルター。「免罪符を金で買えるようにするって、ありえねーだろ!」と。このあたり好きなお話です。
「聖書にそんなこと書いてないから!」を証明するために新約聖書をドイツ語訳し、聖書の民主化を推進したルター。当然、命を狙われていた。で、ザクセン選帝侯フリードリヒがルターをかくまった。このあたりの事情はもっと知りたくなります。
*英語が話せないイギリス王
ステュアート朝が断絶した後、ドイツのハノーヴァー家からジョージ1世を迎えます。もともと議会のつよいイギリスだからこそ「王はいるけれど、国政は議会任せ」が成立しました。
ふと小室直樹が「日本の総理をゴルバチョフにやってもらえばいい」と言ってたのを思い出しました。ちなみに金で平和を買ったのは中国・宋。
他にもいろいろ発見がありました。
歴史に関する本は、既知の整理ができるし未知の発見もあるのでいつ読んでもいいなあ、というわけで以上です!
最後までお読みいただきありがとうございます...!本に関することを発信しております。
