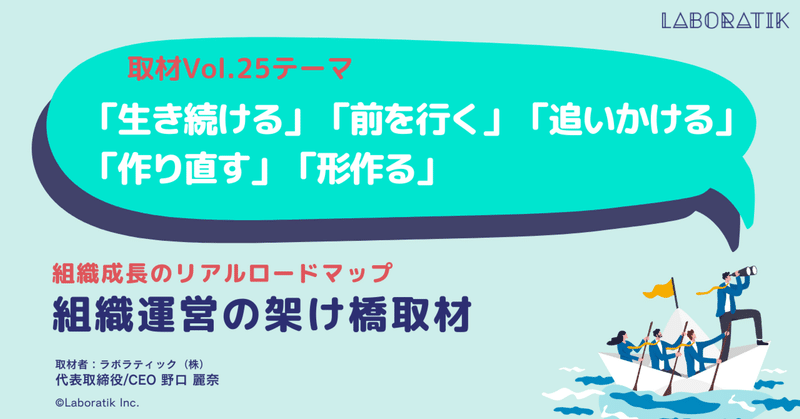
Vol.25「生き続ける」「前を行く」「追いかける」「作り直す」「形作る」
企業向けITプロダクトとサービスを提供する会社を起業してから8年が経過した、岩崎さん。
岩崎さんの会社は、起業当初は自己資金のみで事業運営をされていましたが、現在はベンチャーキャピタルからのサポートを受けながら、着実に事業を前進させています。「スタートアップとしては、比較的時間をかけて、
じっくりと事業を作ってきたと思うんです」と語られた岩崎さんですが、
実は、この言葉には深い意味が込められていました。
事業のステージを進めるためには【生き続ける】ことが重要
岩崎さんは、会社の成長に時間をかける理由を「扱う製品やサービスがヘビーウェイトであるため」と話されます。
バックエンドクラウドサービスという分野は、単に製品を作って販売するだけではなく、技術を結集して開発したソフトウェアを市場に投入し、それを利用する企業からのフィードバックを受けて製品を改善していくプロセスを経て、利用が定着していくものです。
このような事業を軌道にのせるためには、時間をかけることへの覚悟が必要なのは言うまでもありません。だからこそ「まずは会社が生き続けていくことが重要」とおっしゃいます。そのためには、財務面のみならず、組織自体への目配せも必須でしょう。
「起業当初のステージは、自信のある自分(創業者)のアイデアを形にするための組織が必要です。その次に、製品やサービスの品質を意識した組織が必要となり、ステージが進むと顧客の要望に応える組織が必要になっていきます。この流れに伴って、組織も、組織を構成する人員のスキルも市場の要請に適応させていかねば、と強く感じています」
まさに、ビジネスの成長と組織の成長がしっかり同期しなければ、事業成長自体が停滞してしまうということ。更に詳しくお話を伺いました。
【前を行く】事業を【追いかける】ために、組織を【作り直す】
事業と組織成長の同期について、改めて岩崎さんにお話を伺っていきました。
「事業の成長のステージが組織のレベルを追い越し、『前を行く』事業を、組織が『追いかけて』いるような状態が理想だと考えています。また、組織が事業を追いかけるためには、個々人の成長もさることながら、組織を作り直すことも重要です」
理想的な状態は、事業が組織をリードし、組織がそれに追いつく状態。そのためには、個々人の成長だけでなく、組織全体の再構築も必要ということですね。
このような岩崎さんの考えは、ご自身の経験から生まれていると話されます。例えば、小さな組織で大きな顧客に対応したり、市場や顧客の要求レベルと自分たちの組織のポテンシャルやケーパビリティが追いついていなかったり、さらには、ベンチャーキャピタルを通じて資金調達をした直後、事業拡大に向けて組織の拡大を試みたにも関わらず、ビジネス成長が想定していたスピード感で進まなかったり…と、経営者としては様々な歯がゆい経験に根ざした見解だと話されます。
これまでの経験から、事業成長が組織成長を追い越す場合や、逆に組織が過剰に成長する場合、組織の再構築が不可欠であるとの認識をもたれている岩崎さんですが、実際に組織を構築(再構築も含めて)のポイントについても伺いました。
「現時点の事業を支えるために必須の能力を持つ人が、これから起こり得るビジネスの変化についていけるかどうか判断をすること」だそうです。
さらに、事業の変化が予想され、組織構成の条件が明確になった時点で採用を決める場合には「その人が将来の自分たちのチームでどんな活躍の仕方をするのかをイメージすることができるか」を大事にされているそうです。常に、今ではなく、これからを見据えた人との対峙を前提とされているのですね。
「起業当初は、実は楽しければいい、みんなで一緒に成長する意識で運営したこともありました。ただ、事業成長のために、ベンチャーキャピタルからの出資を得て、株主の期待に応えて事業を前に進めるとか、事業のために組織を作り変えることも選択せねばと考えも変わりました」
事業の成長と共に、会社と岩崎さんの向き合い方も変化していることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
重なる部分と重ならない部分の総和で組織を【形作る】
さて、岩崎さんが率いる組織との向き合い方について、さらに掘り下げて伺っていきました。
「組織は、構成する社員の能力が、ベン図として重なる部分と重ならない部分の総和だと考えています。会社の器を広げるためには、チームで全くケーパビリティが重ならない人たちが、互いを認識して認め合っていくことも大事ですし、こういった意識自体が、今後の事業の柔軟性やイノベーションを支えることになる」
岩崎さんの考える組織には、組織というと、ひとまず、価値観を共有できるところに意識が向きがちですが、さらにそのさきにある状態が含まれているのが印象的です。
見据えているイノベーションや柔軟性を実現させるために、さらに岩崎さんはこう話されます。
「組織を構成する社員の数は、単純に、増やせばいい、減らせばいい、少数精鋭ならいいという話でもないですよね。確かに、社長の言うことを聞く人たちだけが集まった組織は管理しやすいかもしれません。一方で、社長以上には成長しない組織になってしまいます。その時点の事業をしっかり見つめつつ、近づく将来の変化に対応できるような、ずば抜けた能力を持っている人がチームに何人かいないとイノベーションが起きません」
社長の器という表現はよく聞かれると思いますが、社長ではなく、社長も含めた組織の器を広げ、さらにイノベーティブになるためには? という信念が伝わるお話でもあります。
では、岩崎さんの理想の組織とは?と伺うと、次のようなお答えをいただきました。その1つのキーワードは、「コンフリクト=衝突」にあるようです。
岩崎さんが理想とされているのは、予め、社員たちの能力が対立して、コンフリクトが起きる可能性を受け入れる前提で運営する組織だそうです。
イノベーションのような組織の化学反応は、メンバー同士のポジティブなコンフリクトの先にあるもので、「中庸」にあるものではないーそんな前提に立った運営だと話されます。
「組織や社員のケーパビリティを全部引き出して、ベン図で重複していない部分の総和で形作るものをチームの価値観としていくという企業文化にしたい」
まさに、岩崎さんのこの言葉こそが、今の組織を「形作って」いるのです。
今回の取材で、岩崎さんが冒頭に使われた「ヘビーウェイト」という言葉には「市場の信頼を得るための組織、イノベーションを実現する組織、変化に耐える柔軟な組織、障害を乗り越える組織」という意図が全て含まれているのかもしれません。
事業ステージの変化を見極め、柔軟に組織を組み替えていくために、未来では何が求められるのだろうか?
不確実性の高い時代だと言われて久しい現在。今後の組織運営においても、多くの不確実性があることは明らかです。
だからこそ、このような岩崎さんの意識や取り組みは、改めて組織や事業との向き合い方についての振り返りの契機となるお話になりました。
今後も、岩崎さんの組織の発展を心から応援しています!
【取材協力】
株式会社 Hexabase 代表取締役
岩崎 英俊様
《この記事に関するお問い合わせ》
ラボラティック株式会社 広報担当
info@laboratik.com
