
1年弱チームをリードして得た「チームの課題解決」の気づきと学び
こんにちは、VoicyでiOSエンジニアをしている立花(@kzytcbn315)です。
今年の2月にフィーチャーチームのリードを任されました。
チームをリードする経験がない中で、色々と試行錯誤して今となっては遠回りをしたなという気づきがありました。
1年前の私と同じような、チームのリード経験がない方達に少しでも参考になるのではないかと思ったので、まとめておこうと思います。
結論
さくっと内容だけ知りたい方向けに、要点をまとめたツイートを先日おこなったので貼っておきます。
当たり前だけど、全体像を見通して戦略を立てるって大切
— Kazuya Tachibana (@kzytcbn315) December 23, 2022
開発プロセスの改善をしていると、次から次へとモグラ叩きのように課題が顔を覗かせてくる感覚になる
実際は地面をならす作業に近くて、相対的にボコッとしてるところが気になっちゃうんだけど、手当たり次第に手をつけちゃうと遠回りになる
何かを改善する時のプロセスとして、
全体像を見通す
優先度を付ける
優先度をもとに改善をおこなっていく
当たり前なことですが、上記のプロセスを踏むことが大切なんだなと実感しました。
全体像を見通す
何かを改善したいと思った際に、何も考えず手当たり次第に手を付けることは、多くの方はしないと思います。
少なくとも、今ある課題を洗い出してみたりするのではないでしょうか。
私もチームを任されてから1ヶ月ほど経ったタイミングで、今ある課題を洗い出して、優先度を付けて対応するということを行いました。
ですが、これは今となってはあまり良くなかったなと思っています。
よくないと思う理由は2つあって、
チームをリードする経験がない中で、自分の見える範囲の課題の洗い出ししかできていない
課題を解決する目的が明確ではない
主に上記2点の問題があったなと思います。
チームをリードする経験がない中で、自分の見える範囲の課題の洗い出ししかできていない
全体像=自分の見える範囲になってしまうのです。
経験が豊富であれば過去の経験から見えてくる世界もあると思うので、これでも問題はないかもしれませんが、経験が無い私の見える範囲で洗い出した課題なんてたかが知れています。
上長との1on1などは行なっていましたし、都度課題の共有などは行なっていましたが、チームの状況を100%伝えるのは不可能ですし、何か問題が起こった時の対応が後手に回ってしまいます。
課題を解決する目的が明確ではない
自分の見える範囲で自分の思う課題を洗い出したとして、それを解決する目的はなんでしょうか?
もっとアウトプットを早くするんだ!
もっと働きやすくするんだ!
もっとアウトカムを出すぞ!
上記はそれっぽいことを言ってるように見えるかも知れませんが、なぜそうするのかが明確では無いです。
Leadという英語の意味に「導く」という意味がありますが、どこへ導くのでしょうか?
恥ずかしながら、チームを任された初期の頃は自分の中でその答えがありませんでした。答えがないどころか、考えてすらいなかったのです。
リードする立場の人間が、フラフラしていてはチームもまとまらないものです。
経験が無い中で全体像を見通すには
経験が無い中で自分が見える範囲だけではダメ、課題を解決する目的も必要となった場合にどうすればいいでしょうか。
1年チームをリードしての気づきとしては、
「理想像と比較して現実とのギャップを見つける」
ことが大切なのでは無いかと思っています。
自分の見える範囲の課題を場当たり的に解決していくのではなく、理想像をしっかりと考え、それをチームと共有し、現在とのギャップを埋めていく作業が必要なんだなと思います。
理想像すらも自分の考えられる範囲かも知れませんが、そこは上長なり、経験豊富な方なりと話してアップデートしていけばいいと思っています。
理想像を描くことで、理想像とのギャップという今までと違うアプローチで課題を洗い出すことができます。
そしてその課題を解決する目的は、理想像へ近づくためという説明もできるようになります。
優先度
「理想像と比較して現実とのギャップを見つける」ことで課題の洗い出しができた後は、その課題に優先度を付けていかなくてはなりません。
優先度の付け方はよくある、「重要度」と「緊急度」みたいな4象限マトリックスみたいな分類を付けて重要かつ緊急なものから着手するように意識ていました。
重要かつ緊急なものの中でも、
チームで解決できる
チームで解決できない
2つパターンの課題があるのでチームで解決できない課題に関しては私が適宜必要な場に上げて解決するように促すことを行いました。
チームで解決できない課題の解決を、チームで解決するように努力するのは時間の無駄なので、課題がどのパターンなのかの見極めはしっかりと行う必要があると思います。
おまけ
私は課題解決はモグラ叩きのようなものだと感じていました。
1つ課題を解決すると、まと1つ課題が顔を出す。
叩いても叩いてもぴょこぴょこと顔を出して、キリがないなと思っていました。
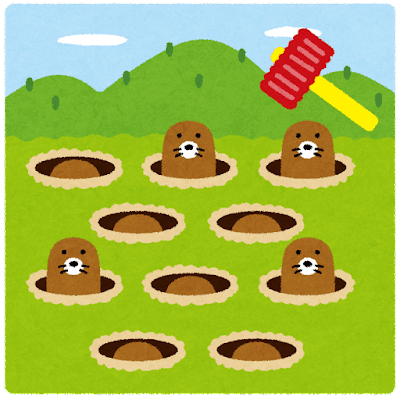
ですが、それは目的のない課題解決をしていただけだと気づきました。
目的を持って課題解決をすると、課題解決は地ならしに近いなと思います。
一つ課題をならして理想に近づいたことで、より理想から遠い課題が気になってしまうだけなんだなと。

さいごに
Voicyについてもっと知りたい、スタートアップで働くことについて興味ある、既にスタートアップで働いてて情報交換したいなどありましたらいつでも歓迎です!
Meetyでカジュアル面談は募集してますのでお気軽に申し込んでください!
(Meetyやってないよって方はTwitterのDMでも大丈夫です!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
