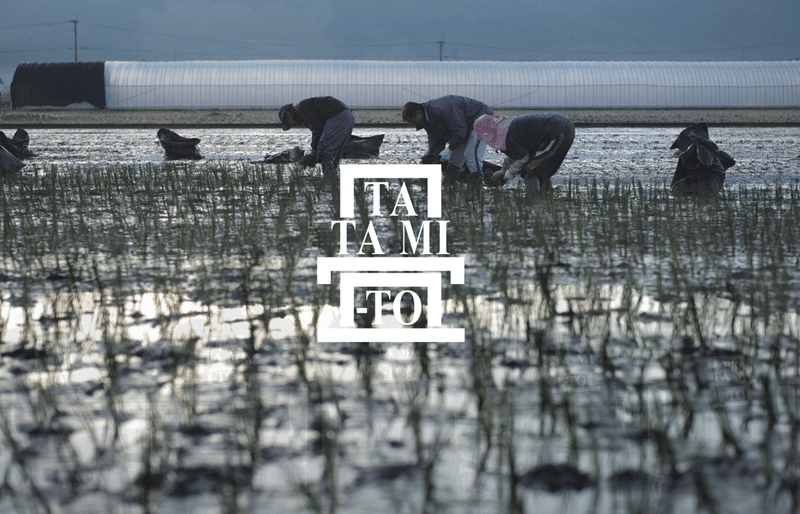消えていく畳の未来。
いぐさ の取引価格は今年は20%以上も下落して、もはや採算に乗らない。
このままでは何年もつのか。
日本のい草の産地である八代を守らなくてはならない。
高齢化と人手不足で農業が成り立たない。
外国産や化学製品が増えている中で、国産畳が消えていく。
そんな、緊張感と危機感が溢れるご挨拶(八代地域農業協同組合長・田代幹雄)からスタートした今年の、第2回九州畳サミットが6月1日(い草の日)に開催されました。

事務局メンバーも合わせると、総勢240名ほどが一堂に会して、畳産業の未来を語り合います。
開催地は、昨年に続いて”いぐさ のふるさと”熊本県八代市です。
いぐさの日本における主な生産地は、ここ熊本県八代地方であり、国産畳表の9割ほどのシェアを誇ります。九州では福岡県、佐賀県、大分県でも生産されていて、「九州全体で考えれば、国産い草の出荷シェアはほぼ九州が担っており、その点では畳産業の未来への責任を九州全体で議論すべきではないのか?」というところが、この九州畳サミットの出発点でした。不肖私(村岡)も副実行委員長としてアドバイザー的に関わらせていただいています。
<昨年(第1回)の様子>

僕自身の畳産業への興味は、CMディレクターの今村直樹さんの「国産畳ってこのままじゃあ無くなってしまうんじゃないの?」という問題提起から始まった様々な取り組みを知って、2016年(?)の夏に一緒にい草農業の視察に行ったことがきっかけでした。
それまでは正直にいって、畳の産業といっても遠い世界の話で、それを「農業」として意識し始めたのは、その時が初めてでした。
<今村直樹さんのプロジェクト:TATAMI-TOの取り組み>
その後、九州の農業団体が一堂に会する協議会のセミナー(福岡)に基調講演講師でお呼びいただいた際に、九州の畳産業のリーディングカンパニーであるイケヒコ・コーポレーションの(当時の)社長さんと名刺交換したことがきっかけで会社をご訪問させていただき、「いぐさ農業って、そんなに切実な状況になっているんですね」「でも八代が全国のいぐさ生産のほとんどを担っているって、九州の人間でも知らないよね」「じゃあ、ONE KYUSHUの理念で括ったら、これってまさしく九州の産業と言えるんじゃないの?」という世間話から関わりが始まりました。
九州畳サミットが、素晴らしい勢いをもってこんなに発展していくとはまさか思わなかったのですが、やはり上位概念でくくる=KYUSHU ISLANDとしての枠組みで物事を考えると、面白い化学反応が起きるのだと実感しています。
ところで、みなさんの家庭に畳の部屋ってありますか?
以下は、い草の栽培面積および、栽培農家戸数の推移をグラフにしたものです。
(参照資料:熊本県いぐさ /畳表活性化連絡協議会)
<いぐさ栽培面積の推移グラフ>

<いぐさ栽培農家戸数の推移グラフ>

これらを見るまでもなく、ずっと右肩下がりの産業。農家の平均年齢も70歳を大きく超えていて、冒頭の組合長の話ではないですが、このままでは数年後には「畳産業は終わる」「国産畳は買えなくなる(?)」のでしょうか。業界の重鎮と話していると、総じて悲観的な話題が支配するのです...。
しかし、僕自身は気になって畳やいぐさ 農業の世界にハマっていくに従って、とても気になる”ムーブメント”の息吹も感じています。
近年の健康志向の高まりやCRAFTED(匠の技)な伝統産業が見直される中で、「畳ーTATAMI」を新たな文脈で見直していこうという機運が盛り上がってきているような気がします。
そんな取り組みを集めて、共有し、業界を内外から盛り上げていこうというのが、この九州畳サミット。今が苦しいということであれば、逆に言えば「ここから上げていくしかない!」のであり、むしろこれまでは閉ざされていた地域産業に、異業種を含めて様々な主体が関わることで可能性のある産業へと転換していきたいと思うのです。
今日は静岡から素敵な方々もプレゼンにきてくれました。老舗畳店からのイノベーションで、面白い雑貨をたくさん作っています。また、地元で畳をテーマとした様々なワークショップも開催されています。
やっぱりイケてる畳屋さんは、ウェブサイトもかっこいいですねー(><)
松葉畳店 : 公式ウェブサイト http://www.matsubatatamiten.jp/
やっぱり「デザイン」って大切な要素。
かつては生活必需品であった「畳」ですが、フローリングに生活様式が変わる中で、限られた生活空間の中に「選ばれる理由」が求められるようになりました。若い世代(20-30代)は何かを購入する際には、まず必ず「検索」します。この検索カルチャーの世代間変化を理解していない方々は、とかくショールームを拡充して「実際に手に取ってもらわなくてはわからない」と言いますが、それ以前の”情報の入り口”のセンスが悪いと、関心を集めることさえできません。
この辺り、八代の畳関連産業の皆さんはよく考える必要があると思います。
(ウェブサイトなど、どれもとにかく見にくくてデザインもダメなので)
株式会社ままこやの山野井恵麻(えみ)さんは、医学療法師としての知見から、昨年、第1回の畳サミットにて「子供の発達における畳との関係性」を発表し、その後「畳アンバサダー」制度を創設して、子育て世代への啓蒙活動をスタートさせていらっしゃいます。<詳しくはこちら>
「選ばれる理由」を子育て世代の最大関心事である、赤ちゃんの発育に紐付けたところが興味深く、各方面から大きな関心を集めています。「床に赤ちゃんを寝かせて、畳の上をゴロゴロ寝返りをしながら遊ばせる」ことで、運動能力の基礎が育まれるという知見は、もっと広く世の中に広がって欲しいと思います。
そして、今年から変更された九州畳サミットの素敵なロゴを作ってくださっているのは、FANFARE Co.,Ltdの梶原さん。
そして梶原さんと言えば、bud brand(バッドブランド)の主宰。若手のデザイナーにスポットを当てて、毎年、ミラノサローネに作品を出品しています。
今年のミラノサローネでは、「角材の中から畳表が出てくる」というユニークなアイデアのピクニックシートを出品。ここから家具や空間にまで展開して、畳の可能性をデザインやIDEAから掘り起こそうという試みです。

梶原さんからは、以下のような提言も。
メーカーというのは、消費者から一番遠いところにいる。実際(現場)のお客様の欲求からずれてしまっていてはモノは売れない。エンドユーザーの「生のニーズ」を生産や製造の現場が知り、商品企画に取り入れることが欠かせない。 大手はハウスメーカーの調査によると、2010〜2016年の6年間で、「畳」の採用率は81.1%→ 74.8% と、6.4%も下落。1/4軒は「畳」がない。尚且つ、6畳以上の畳の間がある家は18%台から16.4%にまで下落。今の家は小さな畳の間が残っているのみ。 要因は、若い世代のデザインに対する考え方、生活スタイルの変化、矮小住宅が増えていることなどがあるが、そういった時代の変化に「畳」が合わせるということをしていない。「畳」の行き場がなくなっている。 しかし、面白い変化がある。 実は、家を建てる年齢が低年齢化する中で、若い年齢ほど畳の採用率が高くなっている。子育て世代にとっては、床に子供を遊ばせられる「畳」は好まれているのではないか。こういった「生のニーズ」に対して、きちんと「畳」産業が敏感になって、使い方をしっかりと提案して、生活に取り入れられるようなデザイン性豊かなプロダクトに昇華させる必要があるのではないかと思います。
最後に、第2回目の「九州畳サミット」に参加して感じたことをいくつか(自身への健忘録的に)、ちょっと辛口に記しておきたいと思います。
ワークショップの中で、既存組合に所属していらっしゃる方々が畳産業やい草農業支援に対する政策批判をしていたが、ここでは一切無駄なことだと思う。そもそも「九州畳サミット」は、そういった話の延長線上で”解決されなかった”ことを、未来志向で語り合い、異業種も受け入れながら地域産業にイノベーションを起こしていこうという「生き残りをかけた強い意思の塊」でなくてはならないはず。
そういった意味では、いわゆる業界人の集まりだけでは面白くないと感じました。第3回を目指す中では、既存組織のしがらみや業界団体が幾重にも重なり合う硬直化したレイヤーの「境界」を溶かして、女性や若い世代(学生含む)、それに異業種のクリエイターの参加も促しながら、「世界があこがれるような、TATAMIのある暮らし」を提言できる先進的な取り組みへと進化させる必要がありそうです。
(国産の)畳産業の存続をかけた戦いにはあまり時間がありません。日本人の精神性の真ん中に当たり前にあった「畳の空間」が今、消えようとしています。今こそオール九州、オールジャパンで取り組む大切な時であり、畳業界の皆さん自らが「ここからはオープンマインドでなんでもやる」「素敵なアイデアには垣根を超えて何でも取り組む」という強い意志を見せてくださればこそ、僕らのような”部外者”が「関わる理由」があるのだと思っています。
事務局メンバーの皆さんにリスペクトを込めて。
前へ進んでいきましょう!!

よろしければサポートお願いいたします。頂いたサポートは、世の中の誰かのためになる活動に使わせていただきます。