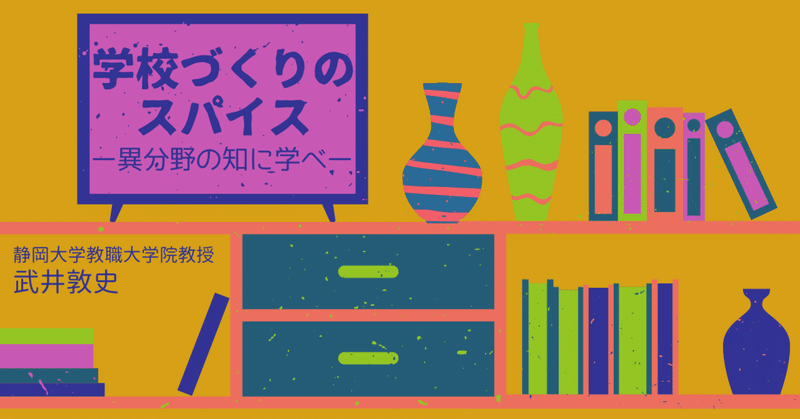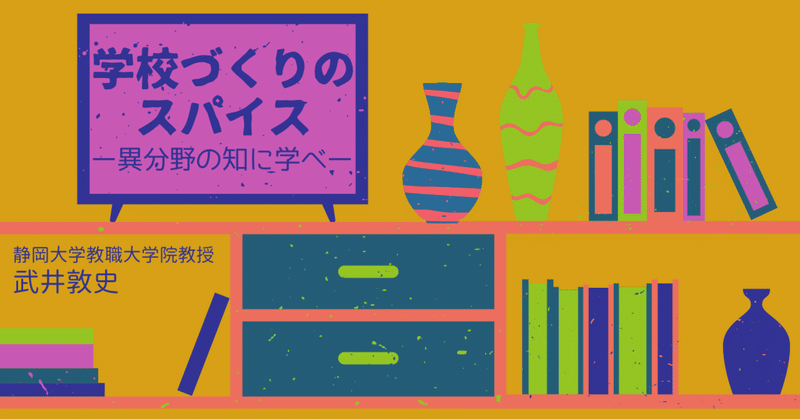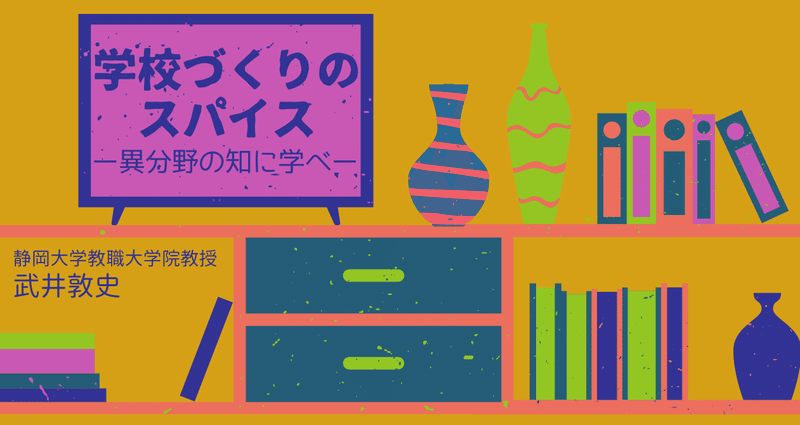
学校のリーダーシップ開発に20年以上携わってきた武井敦史氏が、学校の「当たり前」を疑ってみる手立てとなる本を毎回一冊取り上げ、そこに含まれる考え方から現代の学校づくりへのヒントを…
- 運営しているクリエイター
2022年3月の記事一覧
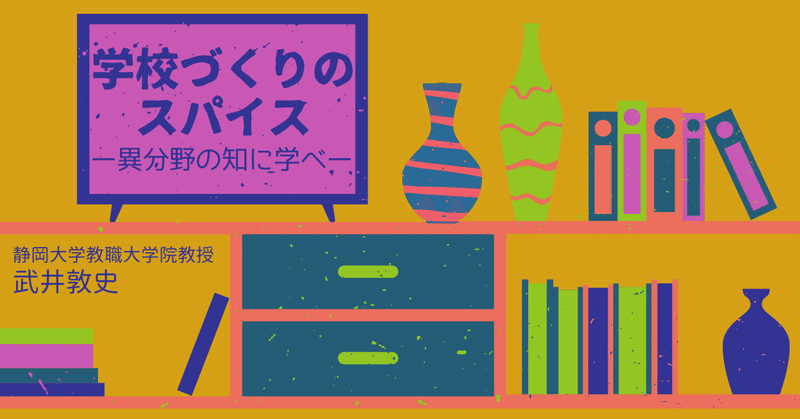
#24 なぜ数値化しないと気がすまないのか?~ ジェリー・Z・ミュラー『測りすぎ――なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?』より~|学校づくりのスパイス
今回はジェリー・Z・ミュラー『測りすぎ――なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?』(みすず書房、2019年)を通して、学校教員を悩ませ続けてきた数値評価について考えてみたいと思います。ミュラー氏はヨーロッパの知性史や資本主義の歴史を研究する歴史学者ですが、医療、警察、軍、ビジネス、慈善事業などのさまざまな領域において、数値測定の圧力が強まった背景と影響について、歴史的な視点も踏まえつつ横断的に迫っているのが、この本の特徴です。 「測定執着」という視点 「学校が子どもの全人