
コーチング?とは
コーチングとは
さて、コーチングと聞くと部下のマネジメント手法であったり、傾聴共感によって自己肯定感を高めるものというイメージが湧く方もいるかと思います。
今日は、コーチングについて、少し説明をしたいと思います。
まず、本気で現状突破をしたい方、自己変容によりさらなる成長をしたい方でないと本当の意味でコーチングの効果はありません。傾聴、共感による人生相談とは別物になります。
私たちは社会性の中で生きており、これまでの人生で、家族、友人、先生等、いろんな価値観に影響され、現在のあなたが形成されています。
そのうち、自分の本音を抑え込み、他者に合わせて、あたかも自分の本音であるかのように行動し、気づいたときには自分がわからないこともしばしば。
あなた自身を今の状態に繋ぎ止めているものは何なのか、あなたのこれまでの人生の謎解きを一緒に行います。
つまり、クライアントとコーチの二人三脚で、クライアントの内的世界のどこに違和感や矛盾点があるのかを探しに行くことです。
内的世界に書き換えが起こると、外的世界での言動に変化が起こります。内的世界の整理を行なった上で、自分の本音のゴール設定を行い、ゴール達成に向けて動いていきます。
未来のゴールを設定し、自分の人生のハンドルをご自身で握って歩んでいくことができることを本気で応援します。

さて、みなさんは、これまでに、「今年はこれをやる」と決めたのに結局やれなかった、続かなかったという経験はないでしょうか。私自身も振り返ってみると、頭で妄想したものの、やれなかったことが数えきれないぐらいあります。
その際、自分は意志が弱い、怠けものだと考えていました(最近までそう思っていました)。
実はこれ、マインドの本能であり、マインドの使い方次第で解決できるんです!!
まずは、言葉の連関性(※)や思考形態について、頭に入れていただく必要がありますので、順番にお話しさせてください。
(※)複数の事象や変数が互いに関連し合っており、これらの要素が相互に影響を及ぼし合っている状態を指しています。
ゴール設定(セッティング)
現状の外のゴール
みなさんが成長したい、変わりたいと決意したときに大切なのは、
「ゴール設定」です。ゴール設定する上で、大切なポイントがあります。
それは「現状の外のゴール」ということです。
現状の外のゴールとは、なんなのか。
まず、現状の定義ですが、「今の状態から予測できる未来」となります。
つまり、達成困難なゴールであっても現状から考えて、予測可能であれば「現状の中」のゴールということになります。
これは一例ですが、
◯勤めている会社で最短で課長になる
◯社内トップセールス取を取り表彰される
◯売上を前年比120%まであげる
などです。
どれも素晴らしい成果であり、達成困難ではありますが現状となります。
(日本語では現状というと現在のことを指す意味合いが強いため、ラテン語のstatus Quoという言葉が本来の言葉です)
現状の外のゴールの心象風景としては、
〇ゴール達成のために必要な道筋もみえないし、何から始めてよいかもわからない
〇未来の自分を想像するとワクワクと同時に恐怖感さえある
〇身近にいる大切な人からは、「やめたら?」「今のままで十分」なんて言われる。
という感じです。
現状の外のゴールなんて妄想で、現実味がないと感じると思います。
そのため、ゴール設定で重要な観点がもう一つあります。
want toであること
それは、本音の欲求「want to」であるということです。
Want toって、どんなものかというと、
〇人生において、身近な大切な人(家族や上司、友人、彼女等)から止められても、止められなかった行動、
〇時間を忘れて没頭してしまうような行動やもの
〇どうしても心が惹かれてしまうもの
です。
みなさんも私も、生まれてからこれまで両親、兄弟、友人、同僚、上司部下、彼氏彼女、夫婦、子供等大切な存在がどんどん増えていきます。
その過程には、大切な人から認められたい、感謝されたいという思いが強く、そのために行動することが多くなります(結果を求めて行動を起こす)。
Want toは、そういった結果を求めて行動していることではなく、気づいたらやってしまっているものになります。
Want toは、勝手にやってしまっていることなので、努力は必要ありません。
Want toはみなさんに必ず一つ以上存在するものです。
本音の欲求であるwant toでゴール設定をするからこそ、現状の外のゴール設定ができるわけです。
(逆に、want to でないもので現状の外のゴールは極めて厳しいです。仮に現状の外のゴール達成した場合は、自分自身や周りがボロボロになってしまうでしょう)
オールライフで考えること
最後にもう一点だけ補足させてください。
私が提供するコーチングにおいては、仕事だけでなくオールライフでゴール設定をしていきます。自分自身の関心の高い領域からで構いませんが、人生は仕事だけではありません。
仕事の他に、趣味、家族、人間関係、知性(仕事とは関係のない生涯かけて取り組むようなもの)、社会貢献(ボランティアや寄付)、
また、それらのゴールが決まってくると、自分自身に要請される
健康・美容やファイナンス(収入)のゴールなんかも変わってきます。
人生において大きく8つの領域がそれぞれ相互に関係しあっています。
複数のゴールを持つことによって、関係し合う領域で相乗効果を生み、ゴール達成の確率がより上がるというわけです。
これら8つの領域をバランスホイールと言います。

「ゴール設定」について、少し解像度があがりましたでしょうか。
エフィカシー:ゴール達成能力の自己評価
次に現状の外のゴール達成のために最も必要なものは、なんでしょうか。
それは、「エフィカシー」です。
エフィカシーとは、ゴール達成能力の自己評価になります。他社からの評価ではなく、自己評価であることがポイントです。このエフィカシーをあげることも、プロコーチの仕事です。
「エフィカシー」とは簡単に言うと、根拠のない自信のことです。
今、話題のワンピースやキングダムの漫画を読んだことはありますか?
あるいは、過去にやったこともない仕事や役割を任されて、まぁ俺ならいけんじゃないと思ったことはありませんか?
自分自身の人生においても、人生でエフィカシーが高かった時代があると思います。
(ワンピースの主人公は「俺は海賊王になる」
キングダムの主人公は、「天下の代将軍になる」)
あの状態のことを、エフィカシーが高い(ゴール達成能力の自己評価)ということですね。
(本人が難易度を把握していることも重要です。難易度を全く知らないのに、俺ならやれるは少しずれています。本気でやりたいものなら、難易度は調べますよね💦)
また、エフィカシーは環境にも左右されます。運動会でクラスや色別対抗戦があった際に、自分には自信がなくても強い仲間がたくさんいると、
「よっしゃー、俺もやったる」と思ったことはないですか?
あれもエフィカシーが、環境要因であがった一例です。
でも、現状の外のゴールを設定して、根拠のない自信(エフィカシー)があっても、道筋も何もみえないのにどうしたらよいのかと疑問がでてきますよね。
それは、我々人間の脳が解決してくれるんです。

RASとスコトーマ
この脳の仕組みで重要なのが、RASとスコトーマです。
RASとは、reticular activating systemと言います。日本語では「脳幹網様体不活系」と言いますが、脳に積極的に情報が入らないようにするシステムです。
ただし、自分自身の心の認知(重要性関数)によって、重要性の高い情報だけは勝手に脳にはいってきます。このとき重要性の低い情報は脳が勝手に遮断しており、我々人間は認識できません。
この認識できないものをスコトーマ(盲点)と言います。つまり、RASがあるからスコトーマがあるということです。
脳はRASによって、積極的に情報を遮断していますね。つまりこのときスコトーマ(盲点)が生まれているわけです。
ただし、一人ひとりのマインドの認知(重要性関数)において重要度の高いものだけを、脳の無意識が勝手に情報として拾ってくる機能を有しています。
あなたの見ている世界と私のみている世界が違うのは、それぞれの認知(重要性関数)によって入力される情報が違うためです。
(「一人ひとりこの世界は違って見えている」私はそんなこと考えたことありませんでした。みんな同じだと思っている。
つまり、見える世界を変えるためには、認知(重要性関数)が変わることで、RASがずれて、スコトーマが外れるということになります。
(認知が書き換わる⇒情報の入力が変わる⇒見えていなかったものが見える
結果、世界が変わるということですね)
そして、この認知を変えるのは、現状の外のゴール設定しかないわけですね。現状の中のゴールでは、認知が現状と変わりませんから、見える世界も変わりません。現状の外のゴールを設定した瞬間、マインドの認知が変わり、RASがずれて、スコトーマが外れる。これにより、今まで見えていなかった道筋が見えるということになります。
ただし、ゴール設定するだけでは、認知は変わりません。
ゴールに対する覚悟や責任感が実装されたときにはじめて、認知が変わり、RASがずれてスコトーマが外れます。
つまり、現状の外のゴールに対する臨場感が必要なのです!!
では、変わりたいのに、なかなか変われないという人はどうなっているかというと、「現状維持する」というゴールが設定されているために、認知が書き換わることもなく、入力と出力にも変化はありません。
私たち人間は、そもそも現状維持する力が強く働くように設計されています。
その原理をこれから説明します。
コンフォートゾーン(CZ)、ホメオスタシス
私たちは慣れ親しんだものを維持しようとします。
一定の安定した状態を維持する機能を有しています。
考えれば当たり前なのですが、身体的なことで考えてみましょう。
例えば、我々の体温、36度から37度に維持されていますよね。たとえ氷点下の中でも、サウナに入っても、皮膚表面の温度に変化はあるものの、体内温度は維持しています。体温を維持する力って命に関わることなので、とてつもなく強い力ですよね。
この恒常性機能のことをホメオスタシスといいます。このホメオスタシスは、人間のマインド(脳)にまで影響があるということが認知科学の観点から証明されています。このマインドにおける安全領域のことを「コンフォートゾーン」といいます。
身体的には、体温や血糖値、血液のPHバランスを正常範囲内で維持しようとしていますが、人間の心(脳)の中では、「コンフォートゾーン」の中を維持しようとしてします。コンフォートですから心地よいゾーンつまり領域ですね。これは、脳の無意識にとって心地よい領域です。
人間はこのコンフォートゾーンの中で現状維持しようとします。当然ですよね、ゾーンから出てしまったら、自分自身の生存に関わることですから、コンフォートゾーンを出ても全力で戻る力が働くと思いませんか?
本来、この戻る力のことをモチベーションと言います。日本ではやる気という意味合いで使われることが多いのですが、本来はコンフォートゾーンに戻る力のことをモチベーションといいます。
ここからは、先ほど出てきた言葉との連関性についてもお話します。
RASとスコトーマとコンフォートゾーンとの関係です。
コンフォートゾーンの外側はすべてスコトーマになっています。
どういった風景かというと、自分の認知(重要性関数)によって、重要と評価している情報やものだけにした領域がコンフォートゾーンであることはわかりますか。
RASの働きによって、重要性の低い情報は積極的に情報遮断するためのシャッターが閉じていきます。つまり自分の見えている世界はすべてコンフォートゾーンの中だけとなるわけです。
コンフォートゾーンの外に飛び出しても人間の生存本能(恒常性維持機能:ホメオスタシス)により、とてつもない強い力でコンフォートゾーンに引き戻されてしまいます(この力をモチベーションと言いましたね)。
じゃあ、コンフォートゾーンから出られないじゃないか。そうです。出られないのです。それが人間本来の機能であり、我々を守ってくれているのです。(冒頭説明した、やると決断したのに結局やれない状況はこの人間の有している機能によってやれない状況をつくっていたわけです。)
どうやったら、外の世界にいけるのか、最初に説明した現状の外のゴール設定です。現状の外のゴールを設定することで、ゴール側のコンフォートゾーンが情報空間に存在することになります。
ゴール側のコンフォートゾーンの臨場感が高まれば、コンフォートゾーンがずれ、スコトーマが外れ、新たな世界を見ることができるのです。プロコーチはコンフォートゾーンがずれるよう徹底的にプッシュしていきます。
少しずつ言葉の意味と関連性が見えてきたでしょうか。
コンフォートゾーンの覚えておいてほしい二つのポイントがあります。
コンフォートゾーンは同時に二つ取れない
一つ目は、コンフォートゾーンは同時に二つ取れないということです。
現状の外のゴールを設定したとき、
未来の自分のコンフォートゾーンと現状の自分のコンフォートゾーン、二つ存在しますよね。先ほど言ったように、このとき、未来の自分のコンフォートゾーンは情報空間にしかありません。
対して、現状のコンフォートゾーンは、現実世界に存在しているように思えます。(なぜ、同時に二つ取れないかを考えたときに、体温を思い出していただければ理解できると思います。同時に体温二つ持てないですよね笑)
ゴール設定したときに、どちらのコンフォートゾーンを選択するかというと、心(脳)については、臨場感の高い方を選択します。そうなると、多くのみなさんは現実世界に臨場感がありますから、現状のコンフォートゾーンを選択します。
結局ゴールを設定しても、現状維持の力が強く働くために、自分自身を変えることができないのです。
現状の外の本音のゴールを設定して、そこに自分の覚悟や責任感が実装されたとき、初めて、未来の自分のコンフォートゾーンを選択することができます。未来のコンフォートゾーンを選択することができれば、RASがずれて、スコトーマが外れ、ゴール達成の道筋も少しずつ見えてくるのです。
セルフトークの重要性
二つ目は、未来のコンフォートゾーンを作り上げるために必要なセルフトークについてです。
現状の外のゴールを設定すると同時に必須となるのが、自分のアイデンティティの更新とセルフトークです。現状の外のゴールにおいて、自分自身のアイデンティティはどのように更新されているのか、アイデンティティが更新されるとともにセルフトークもどのように変わっているのか。
未来の自分について、妄想して映像を出しても、セルフトーク(自己内対話)が変わっていなければ変わることはできません。人間は自己内対話を一日3万回以上していると言われています。臨場感の高さというのは、セルフトークの回数できまります。
先ほどコンフォートゾーンは二つ同時に取れないという話がありました。臨場感が高い方を脳は選択します。ゴール側(情報空間)のコンフォートゾーンが現実のコンフォートゾーンに打ち勝つ、唯一の技がセルフトークです。
人間の感情は、言葉⇒映像⇒感情の順番ででてきます。つまり感情は後からついてきます。
なんか失敗したときに「あぁ、しまった」と言葉がでると、しまった映像、しまった感情、”ネガティブ”チーンみたいな感じですね。
我々の臨場感は情報空間にも作れるということは、証明されています。
小説を読んで涙を流すことができるのは、言語を利用して物理的に触れてない仮想敵な空間に対してリアリティをあげることができている証ですよね。
セルフトークは、あるべき未来のコンフォートゾーンをよりリアルにしていくための極めて有効な技術です。
自分が日頃、どんな言葉を吐いているかというと、意外に親や上司から言われた言葉をそのまま使っていることが多いのです。ここは、ゴール達成のために必要なセルフトークのみを入れていく必要があります。

最後に
コーチングの言葉の定義や連関性が少し見えたでしょうか。
現状の外のゴールであるということ、want to領域であるということ、オールライフでゴール設定していくこと、ゴール達成においてはエフィカシーを上げること、現状の外のゴール設定ができると、コンフォートゾーンが未来側にずれることによって、RASの仕組みによりスコトーマ(盲点)が外れ、ゴール達成に必要なプロセスが少しずつ見えてくること、コンフォートゾーンを未来側にずらすための唯一の技がセルフトークであるということ。
今回は、「コーチングとは」という題材で、なるべく伝わりやすい言葉で書いてみました。
人間の深層心理について興味がある方には是非おススメします。
一人一人が、コーチングマインドを獲得して、人生をさらに充実したものにしていきたいですね!
引き続き、自分自身のゴールに向けて、どんどん多動していきます。
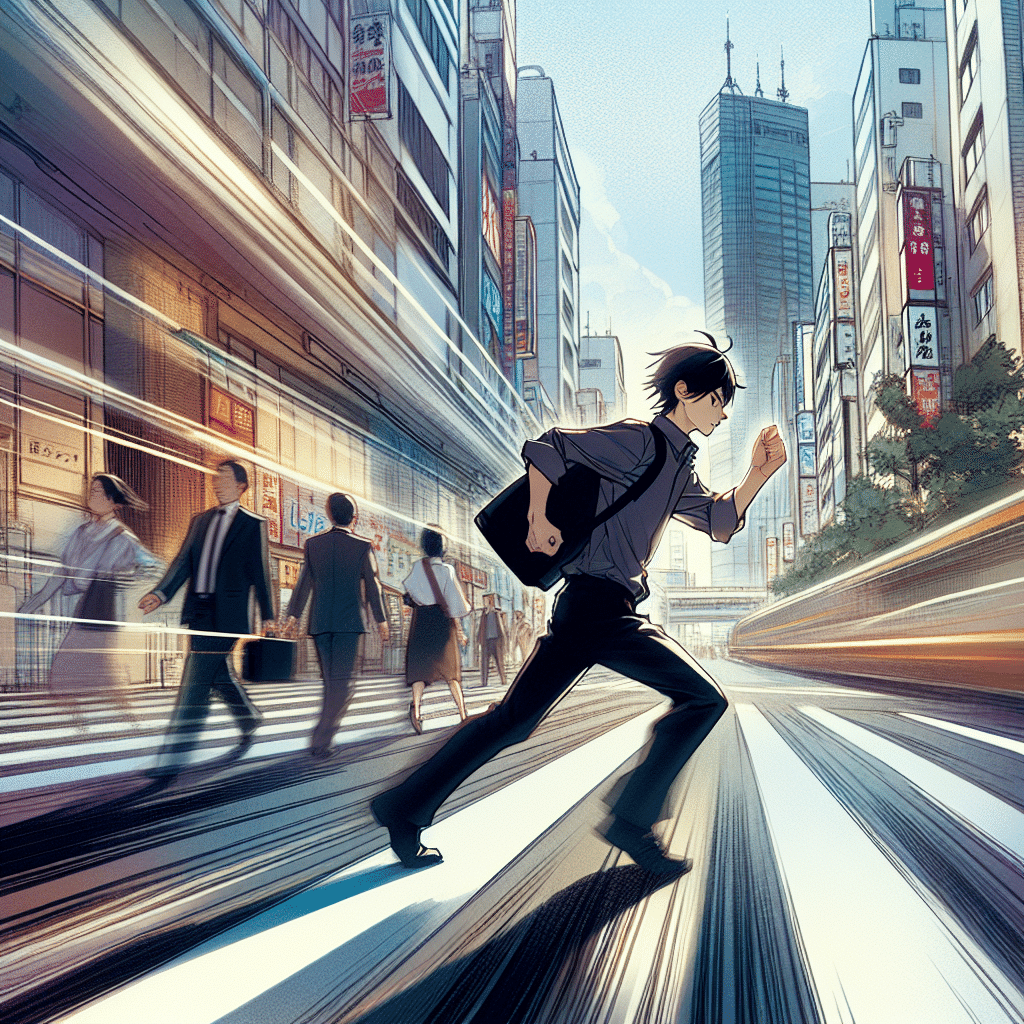
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
