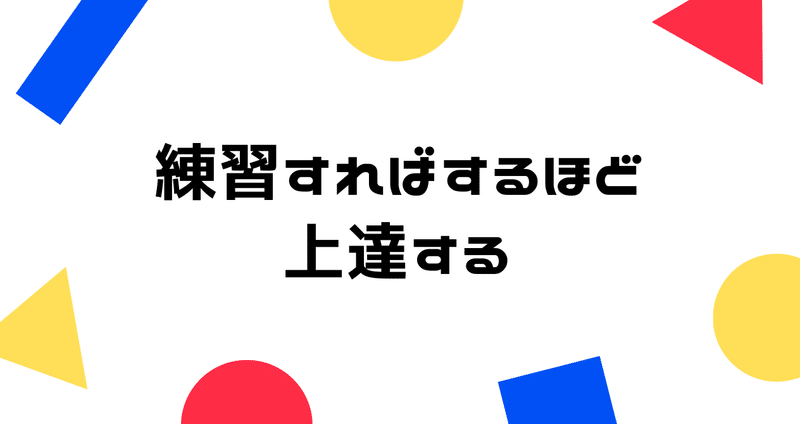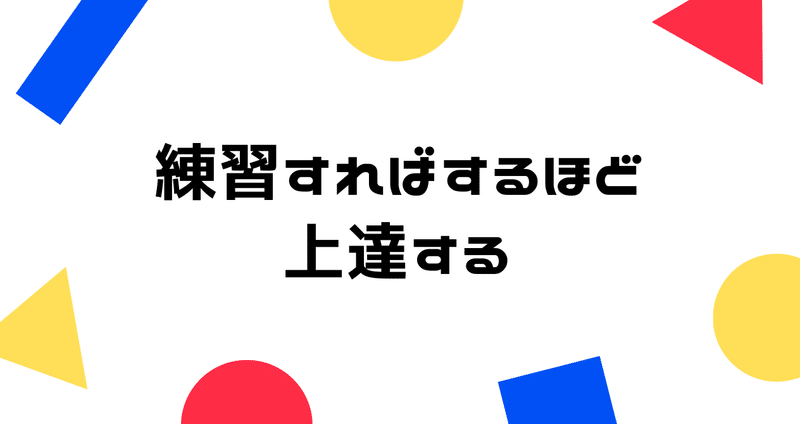Vol.10 足の骨ってどうなっているの?
外反母趾、偏平足、浮指、開帳足など
足の不調や外科的不調に悩まされている方はとても多く、
足つぼセラピスト(セルフも含む)たちも骨格の成り立ちや
ただ足を揉むということだけではなく、
そもそもの根本原因だったり、現状の足の状態を知っておく方が
足に向き合う上でとても有利だし、有効的だと思っています。
反射区がどうのこうのという前に、
足の形そのものが歪んでいると、当然疲れやすかったり、傷めやすかったりするのは理屈では理解ができると思うんですね。
足の骨って、
カラダの1/