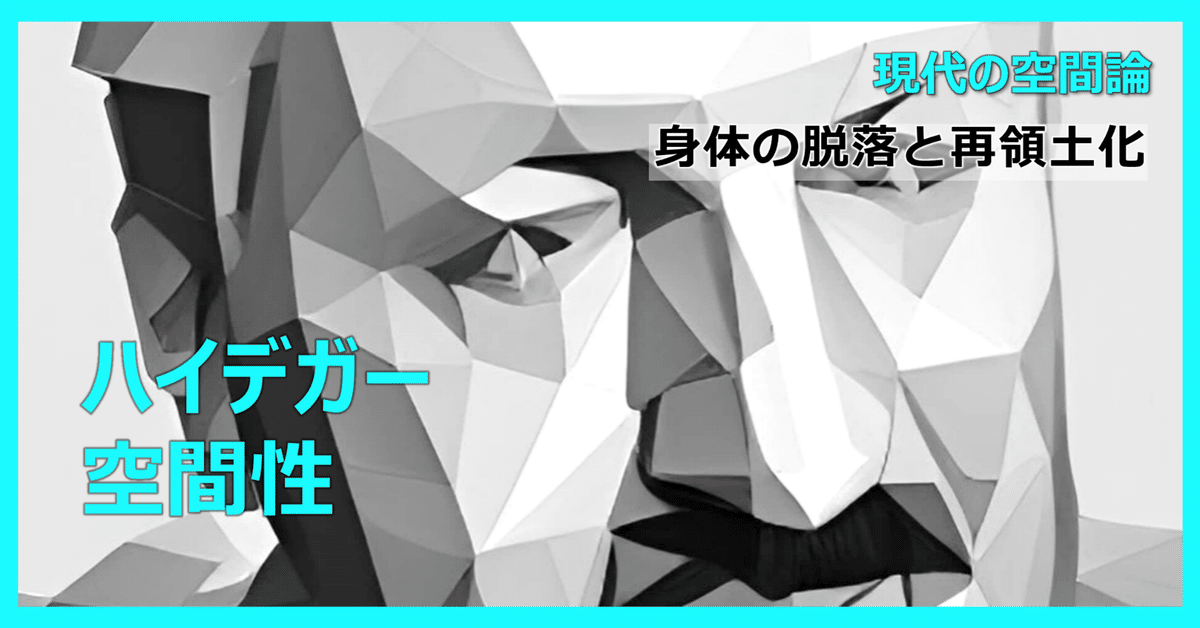
【現代空間論2】ハイデガー「空間性」
映画をみて「後づさり」する。電話しているとき「お辞儀」する。ハイデガーの「存在論的空間」を借用すると、説明つかないメディア利用の振る舞いを上手く説明してくれます。
他人とは独立した「主体」という自分。ハイデガーは、これとは別に「現存在」という別の人間存在を提示しました。「現存在」が生きる「存在論的空間」はなんとも不思議な空間で、そこでの他人やモノとの出会い方は独特です。
現存在というもう一つの人間
ドイツの哲学者ハイデガーは、『存在と時間(SEIN UNT ZEIT)』で、「現存在(Da-sein)」という人間存在を提示します。
「現存在」とは、「世界=内=存在」と説明されます。「内=存在」は、「Being-in」あるいは「~にあること」を意味する空間的な表現ですが、ある物体が、ある空間のなかに存在するというように、単なる空間的な包含関係を表しているのではありません。
それは、世界に対して常に存在が開かれている関係を示しています。「世界=内=存在」という時の「世界」とは、モノ(存在者)の総体でなく、他の存在者とつながった意味連関の全体というべきものです。つまり「現存在」は、内部に閉じたあり方とは反対に、他の存在者に関心を持ち、配慮するという外部に開かれたあり方を示しています。

「現存在」は、常に世界にある存在者と開かれた関係を保っています。その関係は、「配視」「開離」「布置」「間開け」といった聞き慣れない言葉で表されるように、特別な空間性が見られます。
我々が知っている一般的な人間は「主体」と呼ばれます。「主体」が世界で出会うのは、認識の対象としてのモノ。これに対して「現存在」が、世界で出会うのは「用具的 存在者」、つまり道具のことです。道具同士は互いに連関して、道具立ての全体ネットワークが作られています。
この中で、道具の近さや遠さを決めていくのは「配視的な配慮」です。この一種の目配せは、自分と道具の間隔を測るのではなく、道具の使い方といった道具的性格を配慮して行われます。遠くでも道具としての関心が高ければ近くに位置づけ、近くでも関心が低ければ、遠くに追いやります。
こうして「現存在」は、道具に配慮して空間を開き(開離)、その場所柄に目を止め空間を与える(布置)。これを「間開け」といいます。間開けにより、「現存在」は自分のいる「ここ」を、道具のある「あそこ」をもとに了解し、「現」(いまここ)が与えられます。
このように、主体が主観的に世界をあたかも空間のなかにある「かのように」観察するのでもなく、また、カントのように空間は主観のなかに存在していると考えるのではなく、そもそも「現存在」が空間的なのです。
「現存在」が、世界のなかでいつでも道具に出会えるのは、「現存在」自身も空間的であり、「間開け」の契機があるから。そして、「現存在」が空間的であるがゆえに、空間がアプリオリな原理として現れるのです。
空間と空間性
ハイデガーは、「空間」と「空間性」とを区別します。
「空間」とは、「主体」が生きる認識論的カテゴリーにあり、対象としてモノや他者を客観的に認識する、我々がふだん慣れ親しんでいる空間です。
一方、「空間性」とは、「現存在」が生きる存在論的カテゴリーにあり、配慮空間、あるいは関心空間というべきものです。道具の配置関係や、その周縁にある他者関係にその存在が埋め込まれながら、その中で「現」が与えられます。それが世界=内=存在という姿です。ちなみに、前者は「認識論的空間」、後者は「存在論的空間」と呼ばれます。
そして、存在論的空間での距たりは「配慮」や「関心」によって決まり、認識論的空間での客観的で幾何学的な距たりとは異なっています。距たりを縮めるというメディアの働きも、両空間では違った結果をもたらします。
なお、時間についても『存在と時間』では、「現存在」の本質規定としての「時間性」と、過去・現在・未来という客観的な経過としての「時間」とを明確に区別しています。
ところで、「空間」と「空間性」の区別は、情報技術を考える上でも有効です。テレビ、インターネット、携帯電話などメディアの発達で、モノや他者との距たりが縮まり、それに伴って環境世界が急速に変質しています。こうした変化は、私たち「主体」が生きる認識論的空間にだけでなく、「現存在」として生きる存在論的空間にも影響を与えます。
世界初映画での後づさり
映画やテレビといったメディアが運んでくる映像は、過剰な現前性を持っています。
1895年、パリにあるグラン・カフェの地下室「インドの間」で、世界で初めての有料映画リュミエール兄弟の『ラ・シオタ駅への列車の到着』が上映されました。

これを観た当時の観客は、近づいてくる列車の映像に、座席から腰をうかせるほどの恐怖を覚えて、「後ずさり」した話しは有名です。遠方から自らの身体に到来した映像は、もともと「ここ」になかったものだが、「後ずさり」は、到来したその映像を「ここ」から追い出すことに失敗した緊急事態と考えられます。
私たちは今、映画を観て「後ずさり」することはめったにありませんが、ライブ映像を観たり、インタラクティブに電話を利用したりするときには「後ずさり」に似た経験をしています。電話の着信音が鳴って必要以上に驚き、また、電話しながら見えない相手に向かってお辞儀する光景がそれです。
電話利用者を例にとると、彼は、通話中はもちろん、通話していない(ただし、電源は入っている)状態であっても、いつ着信音が鳴り出してもおかしくない世界へ投げ出されています。彼は、遠方とあらかじめ配視的につながった世界=内=存在といえます。この存在論的な了解のために、単なる電信音を、着信音として理解できるので、受話器を手にとるのです。
現在ではメディアが発達して、「現存在」による「間開け」はメディアに依存するようになっています。そして、「後ずさり」のように、これまで体験したことのないヴーチャルな「間開け」によって、意味連関の世界が広がる一方、存在論的な「不安」を感じるようになりました。
音声・映像の領土化と身体脱落
「現存在」は、メディアを通じて遠方の道具を配慮するとともに、「そこ」から遡及的に自分がいる「ここ」を間開けし、そのなかで自己の存在を保持しています。遠方を満遍なく配慮することで自己が維持されている以上、配慮を一点集中することは許されず、それらとの距たりは維持されなければなりません。
しかし、メディアを利用することで道具との距離が極端に縮まり、映像や音声が突然、眼前に到来したらどうなるでしょうか。
電話利用の場合、「現存在」は、到来した音声との距たりが維持できなくなるので、しかたなく玉突きのように自己の身体は「ここ」を脱落しながら(脱領土化)、束の間だけ「ここ」に現前する音声という幽霊的な対象を自らの支持体とすることで(音声の領土化)、かろうじて「現存在」を保ちます。そして、通話が終わると、「現存在」はもとの身体へと舞い戻ります。
このように、私たちは「ここ」にいながら「ここ」から自分自身を追い出すという分裂に生き耐え抜かねばなりません。

存在論的メディア論の限界
このように、ハイデガーの「現存在」の図式を活用することで、映画の「後づさり」や電話の「お辞儀」のように、メディア利用で起こる不可解な事態をうまく説明することが可能です。
メディア利用している私たちが、「主体」としてのみならず、「現存在」としても生きているといえます。そして、メディア利用が行われるデジタル空間は、「主体」が生きる認識論的空間であり、「現存在」が生きる存在論的空間でもある、二つの性格を合わせ持っているといえそうです。
デジタル空間は、現実空間と同様に存在論的な空間として、「居場所」、あるいは「生きられた空間」という役割を持っています。デジタル空間が現実空間に匹敵する活動空間といわれる由縁です。
しかし、この枠組みでは説明できないこともあるので注意が必要です。たとえば「監視カメラ」の問題です。
監視カメラは、犯罪防止等のために用立てられた道具であり、私たちは日常的に駅やコンビニなどに設置されている監視カメラに曝されています。しかし、24時間回り続けるカメラには、一体何を撮るものなのかわからない不気味さがついてまわります。
というのも、情報技術には犯罪防止といった用立てだけでは使い切れない膨大な残余があるからです。カメラが作動中なのに監視される人も、監視する人も不在という状況が少なからず存在しています。
道具から零れた残余部分の意味がわからないまま、我々は「現存在」として監視カメラ世界に自らを投企し、それを引き受けるという不可解な「間開け」に立ち、耐え抜いていく必要があります。それ以上に、これはそもそも「現存在」不在の事態といえるでしょう。
また、メディア利用における説明範囲が限定されているという問題もあります。映画や電話といった旧メディアを対象に、映像・音声による領土化や、玉突きによる身体脱落といった状態は説明できるのですが、メールやSNSなどの振る舞いを上手く説明できません。
映像や音声の突然の襲来による身体脱落は、主に通信技術による「同期」による”空間距離”の縮減によるものです。一方、メールやSNSなど新しいコミュニケーションツールは、主に複製技術による「同位」による”時間”の縮減で成立しており、そのことで、少し前に送ったメールが今に現前するという事態がおこります。これについては別の論考で説明します。
書きおえて
『存在と時間』を読んだのは40歳代になってからですが、迷宮に入った感覚を今でも思い出します。
デジタル社会において他人との距離感は、物理的な距たりでも、時間的な距たりでもなく、「配慮」や「関心」によって決まります。その点で、デジタル空間は、「現存在」が生きる存在論的空間と同じということができます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
(丸田一如)
〈参考〉
マルティン・ハイデッガー『存在と時間〈上〉〈下〉』 ちくま学芸文庫
和田 伸一郎『存在論的メディア論―ハイデガーとヴィリリオ』新曜社
丸田一『場所論』NTT出版
