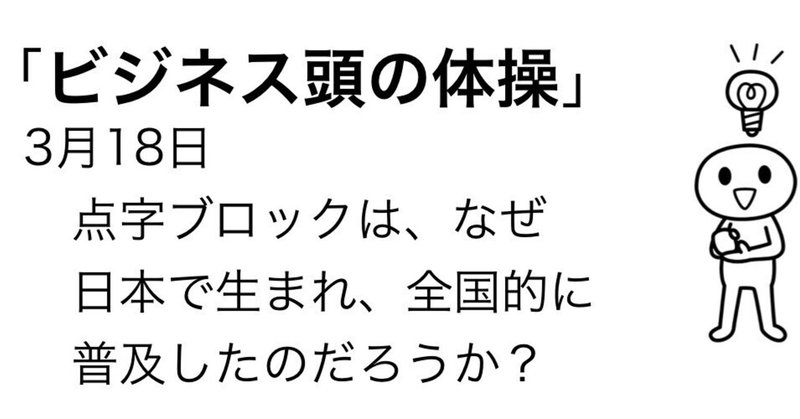
3月18日 点字ブロックはなぜ日本で生まれ、全国的に普及したのだろうか?
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→点字ブロックが日本で生まれ、普及したのには、どんな理由が考えられるだろうか?
岡山県視覚障害者協会が2010年に制定した「点字ブロックの日」です。
1967年のこの日、岡山県岡山市の岡山盲学校の近くの国道2号・原尾島交差点に世界初の点字ブロックが敷設されたそうです。
点字ブロック。
誕生から50年以上経つんですね。しかも日本生まれだそうで、それも驚きました。
点字ブロック、正確には「視覚障害者誘導用ブロック」といいます。
全国に広がる過程で、様々なブロックが製造され視覚障害者から統一を望む声が上がったことから、日本工業規格(JIS)が2001(平成13)年に点字ブロックの規格を決めました。
点字ブロックには、2種類あります。
☑️ 誘導ブロック(線状ブロック)

進行方向を示すブロックです。視覚障害者がブロックの突起を足裏、あるいは白杖で確認しながら突起の方向に従って進むことができるように設置されるものです。
☑️ 警告ブロック(点状ブロック)

危険箇所や誘導対象施設等の位置を示すブロックです。階段前、横断歩道前、誘導ブロックが交差する分岐点、案内板の前、駅のホームの端等に設置されるものです。
(以上、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合HPより)
様々なところに設置されている点字ブロックですが、今回は駅についてみていきます。
その理由ですが、駅のホームでの転落・電車との接触事故が絶えないためです。
例えば、2019年には63名の方が転落・接触事故にあい、うち4名の方がお亡くなりになっています。以下のデータを見ても、毎年のようにお亡くなりになる方がいることが分かります(出典:NHK解説委員室HP)。

最も有効な対策はホームドアですが、コストも時間もかかります。
現場の進捗率は全国では9%にあたる855駅に、優先的に設置するとした1日10万人以上の駅に限ると54%にあたる153駅に設置されているそうです。

もう1つの対策が、先程の点字ブロックの3つ目の種類、「内方線つき点字ブロック」の設置で、これは1万人以上の駅にはほぼ設置が完了しています。

この3つ目の点字ブロックは、これまで、駅のホームの端には警告ブロックが設置されていました。しかし、視覚障害者の方にとっては、警告ブロックのどちら側が線路なのかがはっきりしなくなってしまう場合があり、結果、ホーム側と思って進んだところ、線路側に進んでしまい、転落してしまった、というケースがあることを受けて改良されたものです。
さらに、最近では新しい技術で解決しようという試みもされていて、AIカメラによるホーム縁端歩行注意喚起システムや、白杖にセンサーを、ホーム端などの危険な箇所に発信機を埋め込むことで、白杖の振動などで危険を知らせるシステム、などの活用が検討されています(以下の国土交通省のHPで具体的な説明がご覧になれます)。
なお、こうした点字ブロック、車椅子の方にとっては、車輪の方向が変わることで操作が難しくなったり、高齢者にとってはつまづく原因になったり、という面もあり、立場が変わると難しい問題であることも触れておきます。
最後に、ちょっとそれますが、駅のホームドアを整備する理由は視覚障害者に限らず、ホームからの転落事故が多いことがあります。国土交通省の資料によると2019年のホームからの転落件数は2,887件にもなります(下図)。

この原因ですが、最も多いのは「酔客」つまり酔っ払って、なのです(下図)。

まぁ、コロナ禍でこういった事故は減少傾向にあるようですが…
→点字ブロック。なぜ日本で生まれ、これだけ普及したのだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
過去分は以下にまとめていますので、ご興味があればご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
